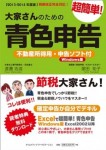「所得」を含むコラム・事例
3,928件が該当しました
3,928件中 1051~1100件目
20年後、競争力のある賃貸住宅を造るには
 相続税対策で賃貸住宅経営が有利なのは解っています。
心配なのは、「家賃下落リスク」「空室リスク」「管理手間負担」などリスクや負担が年を追う毎に増える事です。
「管理手間負担」対策には一括管理委託の「サブリース」や規模の小さいアパートをお勧めします。
「家賃下落リスク」「空室リスク」対策には資産継続に多少重きを置き、競争力のある物件を造る事をお勧めします。
費用対効果もあるので予算を限って、...(続きを読む)
相続税対策で賃貸住宅経営が有利なのは解っています。
心配なのは、「家賃下落リスク」「空室リスク」「管理手間負担」などリスクや負担が年を追う毎に増える事です。
「管理手間負担」対策には一括管理委託の「サブリース」や規模の小さいアパートをお勧めします。
「家賃下落リスク」「空室リスク」対策には資産継続に多少重きを置き、競争力のある物件を造る事をお勧めします。
費用対効果もあるので予算を限って、...(続きを読む)

- 伴場 吉之
- (建築家)
【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】
【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】 平成25年9月2日の日本経済新聞の記事で 東京国税局が管内の不動産所得の申告書について、『お尋ね』を送付したという 報道がありました。 東京国税局管内で不動産所得の申告者は110万人。その中から選んで『お尋ね』 を郵送しているようです。これは任意の『お尋ね』であって税務調査とは 異なります。 しかし、先日国税庁から公表された24年度の所得税の税務調査状況...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養に...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
扶養に関して、103万円、130万円の壁 この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用 NISAよりも税の節減効果が大きな制度は確定拠出年金です
ところで、税制メリットの大きい制度として「確定拠出年金」があることを知っている読者も多いと思います。大半は企業単位で導入していますが、個人にも門戸は開かれています。税の軽減効果は個人型確定拠出年金がNISAに優る場合があります。 NISA専用口座は日本に居住する20歳以上の方です。一方、個人が掛け金を設定する個人型確定拠出年金の加入資格がある人は約3,600万人と推計されています。 対象者は20...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税に備える家計費見直しの考え方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「消費税増税に備える家計費見直しの考え方」 についてお伝えいたします。 消費税8%が目の前に迫ってきました。 実際に消費税が5%⇒8%の負担増額分と年収に対する負担率は、 ・年収300~400万円世帯:年間約7.1万円増(負担率5.4%) ・年収400~500万円世帯:年間約7.9万...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表
【国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表】 国税庁はHPで24年度事務年度(24年7月~25年6月)の所得税と 消費税の税務調査の状況を公表しました。 詳細につきましては下記URLでご覧下さい http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf この報告を読むと国税庁の個人に対...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
会社員や公務員も節税できる!?
最近よくチラシや広告で「会社員や公務員の給与所得者の所得税住民税が安くなる、節税ができますよ」とアプローチがあります。 こんな美味しい話があるのでしょうか? 現実的には可能です(不動産所得や事業所得の赤字と通算すればいいのです) しかし不動産所得も事業所得も「経営」だから上手くやらないと節税どころか資産の取り崩しになり本末転倒も・・・・ だから結局節税は難しいのです。簡単にできるならみんなや...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員や公務員も節税できる!?
最近よくチラシや広告で「会社員や公務員の給与所得者の所得税住民税が安くなる、節税ができますよ」とアプローチがあります。 こんな美味しい話があるのでしょうか? 現実的には可能です(不動産所得や事業所得の赤字と通算すればいいのです) しかし不動産所得も事業所得も「経営」だから上手くやらないと節税どころか資産の取り崩しになり本末転倒も・・・・ だから結局節税は難しいのです。簡単にできるならみんなやっ...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
組合により扶養の認定条件は異なる
この時期になると「扶養の範囲」についてよく質問があります。 いわゆる「103万円の壁・130万円の壁」ですね。 今回は130万円の扶養についてお伝えします。 配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れて本人が年金や健康保険を自身で入り手取り収入が減るので 働き損ではあります。その「年収130万円」についてですが、所属する組合により基準が異なるので注意が必要です。 一般的には前年の...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
組合により扶養の認定条件は異なる
この時期になると「扶養の範囲」についてよく質問があります。 いわゆる「103万円の壁・130万円の壁」ですね。 今回は130万円の扶養についてお伝えします。 配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れて本人が年金や健康保険を自身で入り手取り収入が減るので 働き損ではあります。その「年収130万円」についてですが、所属する組合により基準が異なるので注意が必要です。 一般的には前年の年収...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
●●にも税金がかかるんです。
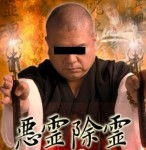 これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中!
『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』
「あの人は今」ってテレビ番組、結構観てます。
こんにちは、1日3分マネーレッスン!
神戸のお金の専門家、霊感ゼロのファイナンシャルプランナー藤原です。
メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約
●●にも税金がかかるんです。
じんせい~50年~~
下天...(続きを読む)
これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中!
『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』
「あの人は今」ってテレビ番組、結構観てます。
こんにちは、1日3分マネーレッスン!
神戸のお金の専門家、霊感ゼロのファイナンシャルプランナー藤原です。
メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約
●●にも税金がかかるんです。
じんせい~50年~~
下天...(続きを読む)

- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)

- 能瀬 敏文
- (弁護士)
Blog201310
Blog201310 今月(2013年10月)は、従業員の採用に関する労働法の論点、著作権法、司法試験、景表法、交通事故と保険、過払い金返還請求、M&A労務に関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 ・ビジネス法務2010年8月号、M&A労務 「M&A労務成功の秘訣」と題して特集が組まれている。 ・不当景品類及び不当...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
来年の夏は起業してる? 何、考えてる?
2014年4月1日の消費税増税が視野に入ってきて、わくわくした気持ちです。現在は、増税を前にした駆け込み需要が活発で、住宅建設や高額商品の販売が盛り上がっています。この需要も、精々来年1、2月までで、その後は駆け込みの反動で、一気に消費の冷え込みが予想されます。 政府は増税を前に、落ち込みを補うための5兆円補正予算を組むと言っています。過去の経験でも、この種の予算は言い訳のように組んではみる...(続きを読む)

- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
司法試験の選択科目の傾向
司法試験の選択科目の傾向 ・旧司法試験 旧司法試験に法律選択科目があった当時では、以下の科目であった。 行政法、破産法、労働法、国際私法、国際公法、 (なお、それ以外に、刑事政策があったが、新司法試験では廃止) ・行政法は必須科目となった。 ・倒産法 旧試験では、ほぼ破産法だけが出題され、条文数も少なく、合格しやすい科目と言われていた。 新司法試...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
含み益の株式は年内売却が必ず良いのか?
 税率10%の内に売却したほうが得なのか?
株式の譲渡益や配当金に対しての課税が
来年NISAが始まることもあり、現行の10%(10.147%)から
本則の20%(20.315%)へ来年から戻る。
※以下復興所得税は記載せず、10%と20%と記載。
気になることは「今の含み益」の取り扱いだろう。
アベノミクス相場もあり、多くの方の株式が含み益状態に
なっているのが通常だ。
...(続きを読む)
税率10%の内に売却したほうが得なのか?
株式の譲渡益や配当金に対しての課税が
来年NISAが始まることもあり、現行の10%(10.147%)から
本則の20%(20.315%)へ来年から戻る。
※以下復興所得税は記載せず、10%と20%と記載。
気になることは「今の含み益」の取り扱いだろう。
アベノミクス相場もあり、多くの方の株式が含み益状態に
なっているのが通常だ。
...(続きを読む)

- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
アメリカの債務不履行がわが国でも起こったら
日本国民の誰もが心配している政府の財政破綻問題。アメリカの債務不履行騒動を見ていて、わが国においてもどのようなことが起こるのか、イメージできるようになりました。マスコミは、オバマ大統領と共和党による意地の張り合いと言ったスタンスで見ていますが、そんな単純な動機とは思えません。 債務不履行の背景は、米国政府があらかじめ設定している、国債発行の上限額を今年10月1日以降は超えることです。オバマケ...(続きを読む)

- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に買った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の現...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に勝った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない
10月に入り、消費増税が予定通り決定しました。 来年4月以降は、消費税率は8%になります。 住宅業界では、注文住宅の経過措置により、9月末には早くも消費増税前の「駆け込み需要」が発生しました。 これは、住宅購入時における消費税は、基本的に「引き渡し時点の税率」が適用となりますが、 注文住宅の場合には、経過措置として2013年9月30日までに請負契約をすれば、 引き渡しが201...(続きを読む)

- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
介護保険の負担も医療費控除
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の還...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
介護保険の負担も医療費控除。
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】
【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】 1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の ための税制改正大綱」を公表したことは、前回のMLでご案内したとおりです 詳細につきましては下記URLでご確認ください https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf ...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
【政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました】
1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の ための税制改正大綱」を公表しました。 詳細につきましては下記URLで自民党のHPへアクセスしてください https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf これは、平成26年4月からの消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化 の...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
お金に愛される人になろう
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です 2014年4月には消費税が5%から8% 2015年には10%ですね・・ そのほかにも 復興特別所得税 退職金の住民税控除の廃止 株式等の配当・譲渡金税率の変更 復興臨時住民税の導入 相続税の基礎控除額を引き下げ 税金以外もあります 社会保険料も増...(続きを読む)

- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
【シニア起業コラム】第六回 「起業の際のお金の話 ライフプランニング編2」
 こんにちは。当社は50~60代という、定年前後での起業をソフトとハードの両輪で支援している会社です。
ソフト面においては起業・経営の事務をサポートしているほか、さらには事業拡大の支援もしているため、
毎月100名規模の起業家交流会『銀座アントレ交流会』を開催し、交流・マッチングを行っております。
また、法律面、法令や官公庁への対応などを含む情報発信、経営のサポートもしています。
...(続きを読む)
こんにちは。当社は50~60代という、定年前後での起業をソフトとハードの両輪で支援している会社です。
ソフト面においては起業・経営の事務をサポートしているほか、さらには事業拡大の支援もしているため、
毎月100名規模の起業家交流会『銀座アントレ交流会』を開催し、交流・マッチングを行っております。
また、法律面、法令や官公庁への対応などを含む情報発信、経営のサポートもしています。
...(続きを読む)

- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
民間投資活性化等のための税制改正大綱(1)基本的な考え方
安倍総理は、10月1日に、消費税率引き上げを決断されましたが、 消費税率引き上げによる景気への悪影響に対応するため、 5兆円規模の経済対策を行うことも明言していました。 その内容として想定されるのが、同日、自民・公明両党が公表した 「民間投資活性化等のための税制改正大綱」ということでしょうか。 「わが国の直面する最重要課題は、 デフレからの早期脱却と経済再生の実現である。 ...(続きを読む)

- 平 仁
- (税理士)
消費税UPには「セレブ☆節約術」で!
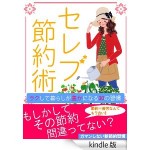 10月1日、安倍総理は、来年4月から
消費税を3%引き上げ、8%にすることを表明し、
同日、午後6時から記者会見を行いました。
消費税は、2015年10月には10%に引き上げられる予定です。
10%への引き上げの決断の時期や条件などは
会見では明らかにされませんでしたが、
10%に引き上げられれば、さらに家計への負担は重くなります。
負担増といえば、今年の1月から「復興特...(続きを読む)
10月1日、安倍総理は、来年4月から
消費税を3%引き上げ、8%にすることを表明し、
同日、午後6時から記者会見を行いました。
消費税は、2015年10月には10%に引き上げられる予定です。
10%への引き上げの決断の時期や条件などは
会見では明らかにされませんでしたが、
10%に引き上げられれば、さらに家計への負担は重くなります。
負担増といえば、今年の1月から「復興特...(続きを読む)

- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」 法学教室145号 条文の規定が複雑すぎて難解な例として相続税法20条がある。 逆に条文の規定は難解ではないが、解釈が難解である例として、相続税法11条の2や、法人税法20条1項2項を挙げられている。 相続税法の課税価格は時価である。しかし、時価を具体的に計算するためには、財産評価基本通達によらなければならない。 法人税法20条...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
今月と先月のブログ記事の内容について
2013年8月は、解雇・退職をはじめとする労働法、平成24年に改正された労働者派遣法・高年齢者雇用安定法・労働契約法、 2013年9月は、知的財産権法、会社法、「月刊ビジネス法務」ノバックナンバーの雑誌記事、金融商品取引法、金融法、独禁法、M&A、M&A買収防衛策、M&A企業結合審査、増井良啓「租税法入門(所得税法)」(法学教室連載)、相続税法、離婚・養育費、 などについて、アメブロとAllA...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」 法学教室連載 所得税法36条 税と時間―課税繰延べ 実現原則(実現主義) みなし譲渡、個人⇒法人への贈与、限定承認(所得税法59条1項、取得費につき60条) 最高裁昭和43・10・31「旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)第五条の二の規定は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし、それを右資産の他への移転の時...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(7) 所得税法のしくみ」
増井良啓「租税法入門(7) 所得税法のしくみ」 法学教室連載 所得税法の法律の外観と基本的な立法趣旨について、解説している。直接に解釈論に結びつくものではないが、参考になる。 (続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
3,928件中 1051~1100 件目

専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。