「所得税」を含むコラム・事例
2,222件が該当しました
2,222件中 951~1000件目
資金繰り改善セミナー
先週末の中国視察旅行の疲れもまだまだ残り、仕事が停滞気味です・・・ そんな状態ですが、今月は沢山セミナーに参加する予定です。 早速今日13日15時~日本生命のセミナーに参加してきます。 「所得税を原資とした恒常的な資金繰りの改善」をテーマに、 元プルデンシャル生命で株式会社リスクマネジメントラボラトリー 清水英孝社長の講演です。 資金繰りが苦しい中小企業の社長さんにお伝えできるス...(続きを読む)

- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除 延長へ!?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 住宅ローン控除は、住宅ローン残高の一定割合にあたる金額を、税額から控除できる制度です。 現在の仕組みは、2013年の12月末までの入居が期限になっています。 詳細...(続きを読む)

- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税!依頼時期に注意!
─────────────────────────────────────────────── 【政府、消費税に配慮?】 ─────────────────────────────────────────────── 昨日、新聞によると、「2013年12月末に期限切れとなる住宅ローン減税を延長し拡充する検討に入った。」とあり、所得の少ない人でも住宅ローン控除を使いきれるようにするようだ。...(続きを読む)

- 森川 稔
- (建築家)
贈与をしても贈与税が課税されない場合って?
<事例> A(母)とB(娘)は、X(Aの亡夫)から土地甲を1/2づつ相続しました。 その後、Bが事業に失敗し多額の負債を負うことになりました。 ABがそれぞれXから相続した土地甲を売却しても負債の全額返済には 足りませんが、それでも土地甲を有効活用して少しでも返済したいと 考えています。 そこで、Aが甲土地の持分を売却する方法・Aが甲土地持分を放棄する 方法が考えれらえますが、それぞれの場合の...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
住宅ローン減税今後どうなる <続編>
今日の日経新聞の一面に、現在適用中の住宅ローン減税について 今後の政府の対策についての記事が出ていました。 具体的には、衆院で可決された消費税増税に配慮して、 平成25年末に期限切れとなるこの制度を延長、拡大する方向で 検討に入ったという内容です。 注目すべき点としては、住民税での控除枠を拡大する方向で 検討していることです。 先日の私のコラムでは、現在の住宅ローン減税の課題として、 住...(続きを読む)

- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
復興特別所得税【平成25年1月以降から】
今日『消費税増税法案』が衆院可決されました。 私自身は実は今たちまちの『消費税増税法案』には反対の意見を 持っています。 なぜかというと根拠が示されないまま『煙に巻いてやれ』のごとく 突っ走られているようにしか思えないからです。 既に以前のコラムでも書きましたが、 社会保険料〈健康保険料・年金保険料〉も段階的に引き上げられています。 実質の増税は既に実行...(続きを読む)

- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
従業員の食事代を会社が負担する場合の限度額は?
【法人税:従業員の食事代を会社が負担する場合の限度額は???】 従業員の昼食代あるいは残業食事代を、会社が一部(あるいは全額)を 負担こともあると思います。 このような場合に、会社が負担することの限度額について法人税では 明確な規定は定められていませんが、所得税では一定の限度額が 定められているため、注意が必要です つまり、一定の限度額以上の従業員の食事代を会社が負担する場合 給与と同...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
給与表示と手取り給与
企業側からの給与表示は 年棒であろうが 年収であろうが 月給であろうが 日給であろうが 手取りではありません。額面といわれるものです。 社会保険完備の会社の手取り給料は、引かれる額が一番多くなります。 給与表示の8割~8.5割がだいたいの手取り額だと予想されます。 社会保険の完備されていない会社なら、引かれる額が少なくて済みます。 引かれるのは ほぼ所得税や市民税だけです。 とにかく...(続きを読む)

- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
確定拠出年金の加入者と内容について
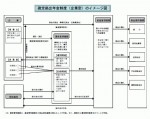 拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を「確定拠出年金」と言います。従来の企業年金は、加入期間などで金額が決まるタイプのものでしたが、運用によって年金額が変わるタイプの確定拠出年金に移行する企業が増えています。確定拠出型は米国の401Kにならって導入されました。
その運用は
1.運用商品の中から、加入者等自身が運用指図を行います。
2.運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株...(続きを読む)
拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を「確定拠出年金」と言います。従来の企業年金は、加入期間などで金額が決まるタイプのものでしたが、運用によって年金額が変わるタイプの確定拠出年金に移行する企業が増えています。確定拠出型は米国の401Kにならって導入されました。
その運用は
1.運用商品の中から、加入者等自身が運用指図を行います。
2.運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
公売とは?競売とは?
競売については一般的ですから ある程度ご存知の方も多いかもしれませんが、 公売についてはあまり知られていません。 公売とは? 所得税・市県民税・健康保険税など その他自治体や税務署などの税金を滞納した場合に 他自治体や税務署など の公的機関が 滞納している人の不動産などの財産を差押して 裁判所の競売と同じように入札方式により 強制的に売却して滞納税の回収を はかる制度のことを公売といいます...(続きを読む)

- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
新児童手当(旧子ども手当)
ねじれ国会だなんだと言っていますが、大事な日本の社会保障制度が政争の具として使われているのは本当に悲しいことです。その最たるものが有名な「子ども手当」です。 民主党が政権公約で全ての子供に一人当たり月26,000円と約束したのが、23年9月まで半額の13,000円となり、今は「児童手当」と呼ばれ、3歳未満15,000円、3歳以上小学校卒業までの第1,2子10,000円、第3子15,000円、中...(続きを読む)

- 西内 純
- (ファイナンシャルプランナー)
年金給付の手続きについて
種々の年金とその給付について、述べてまいりました。 では、それら年金を受け取るにはどのように手続きすれば良いかを、紹介いたします。 公的年金は、受給権が発生しましたら、受給権者が国に対して受給権の確認(=「裁定」)と年金の給付請求を行います。 手続き先は お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。 事務所を探すには、下記年金機構のHPが便利です。 http://www.nenki...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
源泉所得税の納期限が改正されます
 給与を支払う場合、一定金額を超えると源泉所得税が給与から天引きされます。
天引きされた源泉所得税について、給与の支払者は原則として翌月10日までに納付する必要があります。
つまり、毎月納付しなければならないということです。
ただし、給与等の支払人員が常時10人未満の一定の事務所等で、予め届出書を提出した者は年2回にまとめて納付することができます。
これを「源泉徴収に係る所...(続きを読む)
給与を支払う場合、一定金額を超えると源泉所得税が給与から天引きされます。
天引きされた源泉所得税について、給与の支払者は原則として翌月10日までに納付する必要があります。
つまり、毎月納付しなければならないということです。
ただし、給与等の支払人員が常時10人未満の一定の事務所等で、予め届出書を提出した者は年2回にまとめて納付することができます。
これを「源泉徴収に係る所...(続きを読む)

- 菅原 茂夫
- (税理士)
非上場株式を相続して会社に譲渡した場合のみなし配当課税
【相続税質疑応答編-21 非上場株式を相続して会社に譲渡した場合のみなし配当課税について 】 <事例> 今回は、国税庁HPより東京国税局での実際にあった相談事例を 紹介いたします。 詳細については下記URLより国税庁HPでご確認ください http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm ...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
健康保険の被扶養者になれる人の要件 2012更新
先日扶養の条件の内、所得税の配偶者控除、健康保険の扶養の要件で、配偶者の方が税や社会保険を支払わないで済む収入について、説明を行いました。 本日は、健康保険の被扶養者の要件について、説明致します。 健康保険では、被保険者が病気になったり、けがをされた時やお亡くなりに為られた場合に、または出産した場合に保険給付が行われます。その被扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われま...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が受領した被相続人の入院に係る給付金の課税関係
【相続税質疑応答編-20 相続開始後に被相続人の配偶者が受領した被相続人の入院に係る給付金の課税関係 】 <事例> 被相続人の配偶者が、被相続人に係る入院給付金(生命保険契約に基づく給付金) を相続開始後に受取った。 なお、配偶者は、当該保険契約における死亡保険金及び入院給付金の受取人と なっていた。この場合、配偶者が受取った入院給付金に係る課税関係はどうなるか <解説> 配偶者が受取っ...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
任意売却・競売物件の購入
任意売却推進センターは任売客専門業者ですから 当然、任意売却される不動産の販売もしています。 任意売却物件と一般の不動産の購入については、 ほとんど変わりません。 もちろん「フラット35」や民間銀行の住宅ローンも普通の不動産と同じように借りられます。 そして、 競売物件などと違い内覧もできますし、 重要事項の説明や契約書も 一般的なものとなんら変わりません。通常の契約と違う点があるとすれ...(続きを読む)

- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
個人型401Kの活用
401Kというのは確定拠出年金のことで、企業型と個人型の2種類があります。 401Kを導入している企業にお勤めの方には馴染みがあるかも知れませんが、それ以外の方にはあまりよく知られていないのではと思い個人型について少し説明しようと思います。 個人型401Kを行えるのは、国民年金加入者で未納あるいは免除等にはなっていない方達です。国民年金の上乗せ制度として国民年金基金というのは昔からあり401K...(続きを読む)

- 西内 純
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税は今後どうなる?
現在適用中の住宅ローン減税は、平成25年までとなっており、平成26年以降は未定となっています。 これについて、政府では平成26年以降の減税の延長と拡充を検討していることがわかりました。 これは、消費税が平成26年4月より8%に増税されることから、これを住宅ローン減税で緩和しようという狙いがあると推測されます。 ただ、現状の住宅ローン減税制度は、基本的に所得税が対象となっているため、借入額によ...(続きを読む)

- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
土地は代償分割と換価分割どっちが得?
<事例> Aさんの相続人は、長男Bと長女Cです。Aさんの相続財産は 駐車場経営をしている土地Xだけでした。 この土地Xは、路線価評価8000万円(時価1億円)です 長男B長女CともにAさんの住む関西から遠く離れた街で生活を してるため、土地Xを相続して駐車場経営を継続する予定は 全くありません。 そこで、BCが相談した結果以下のように遺産分割が成立しました。 土地XをBが相続し、売却代金1...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
国民年金の付加年金は、日本で一番お得な年金です!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 国民年金の付加年金とは、付加保険料を国民年金の保険料に 上乗せして支払えば、老齢基礎年金に上乗せした年金が終身で 受取れるというものです。 付加年金は、国民年金のみを支払っている第1号被保険者が、 60歳までの期間に、「月々400円」納めれば、老齢基礎年金に終身で 「200円×付加年金保険料納付月数」分の年金額が上乗せされる...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
TOEIC(R)テーマ別語彙「保険・年金」③
みなさん、こんにちは! 「TOEIC(R)テーマ別語彙」第190回目は、「保険・年金」③です(頻出単語のみに焦点を絞っています) <免税措置、年金> spouse:「配偶者」 dependent [dependant]:「扶養家族」 cf. depend on ~(~にたよる) deduction:「控除」cf. deductible(控除できる) income tax:「所得税」 pen...(続きを読む)

- 伊東 なおみ
- (英語講師)
税理士試験 所得税法と法人税法
そろそろ税理士の試験が近くなってきました。ということで今日は税理士試験について語らせてください。ご興味のない方すみません。 やっぱり中小企業のトータルサポートには税理士の資格が欲しいということで、今年も所得税法と法人税法、あと消費税法にチャレンジします。 「所得税法に比べ、法人税法のテキストは約1.5倍。法人税法の方が大変そう。」と最初は思っていました。確かに学習内容も法人税法の方が多い。 ...(続きを読む)

- 渋田 貴正
- (組織コンサルタント)
オーナー社長が土地を自社に安く土地を譲渡した場合の課税
【譲渡所得質疑応答 オーナー社長が土地を自社に安く土地を譲渡した場合の課税】 <事例> オーナー社長であるX氏は、自らが代表取締である甲社の経営基盤を強化するため X氏所有の土地を、売却することにしました。 そこで甲氏は、できるだけ安く売却することを考えた結果 時価が5000万円の土地を2600万円で売却することに決めました。 この場合の課税関係について教えてください なお、甲社の株主構成は...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)
![]() ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。
この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入...(続きを読む)
ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。
この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金 保険契約は、誰が保険料を払って、誰に補償がついていて、誰が保険金を受け取るかでかかる大きく税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 1 課税の種類 ア 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 イ 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 相続税の対象 ウ 契約者:夫...(続きを読む)

- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
【法人税:役員給与に関するQ&Aを国税庁が更新しました】
先週は、国税庁HPで法人税の質疑応答事例集が更新された情報を ご案内しましたが、今日は役員給与と源泉所得税に関する情報の更新を ご案内いたします まず、役員給与に関するQ&Aの更新です。 役員給与は、原則として毎月同額でなければなりません しかし、会社の業績の悪化等に伴って事業年度の途中でも 役員給与の引下げ等を検討しなければならないのは よくあることです。 このような昨今の社会情勢を反映し...(続きを読む)

- 近江 清秀
- (税理士)
2,222件中 951~1000 件目

専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。


















