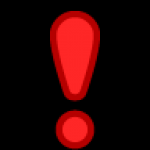「遺族厚生年金」を含むコラム・事例
79件が該当しました
79件中 1~50件目
- 1
- 2

【遺族年金】万一の時に家族には…
![]() 一家の大黒柱に万一のことがあった際、遺族の生活保障として遺族年金(遺族給付)という公的保障があります。加入している公的年金制度によって、国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」、共済年金の「遺族共済年金」があります。職業や収入や家族構成によって、支給額や支給期間等は異なります。私的な保障(民間の保険)に加入する前に、まずは公的な保障を理解しておくべきだと思います。この機会に、ご自身や...(続きを読む)
一家の大黒柱に万一のことがあった際、遺族の生活保障として遺族年金(遺族給付)という公的保障があります。加入している公的年金制度によって、国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」、共済年金の「遺族共済年金」があります。職業や収入や家族構成によって、支給額や支給期間等は異なります。私的な保障(民間の保険)に加入する前に、まずは公的な保障を理解しておくべきだと思います。この機会に、ご自身や...(続きを読む)

- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
保険の見直しはなぜ必要?
 ライフプランの変更や自分自身の経済状況の変化などによって、必要保障額は増減するものです。このため、定期的に保険の見直しをすることが大切です。主なライフプランの変化は以下です。
結婚したとき
配偶者に対する責任から、ある程度の死亡保障が必要となりますが、共働きか専業主婦(主夫)なのか、夫婦の価値観などによって保険の入り方は異なります。まずは、お互いに独身の頃から加入している保険の保障内容や保障額...(続きを読む)
ライフプランの変更や自分自身の経済状況の変化などによって、必要保障額は増減するものです。このため、定期的に保険の見直しをすることが大切です。主なライフプランの変化は以下です。
結婚したとき
配偶者に対する責任から、ある程度の死亡保障が必要となりますが、共働きか専業主婦(主夫)なのか、夫婦の価値観などによって保険の入り方は異なります。まずは、お互いに独身の頃から加入している保険の保障内容や保障額...(続きを読む)

- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
公的年金制度について
 昭和36(1961)年に「国民皆年金」の体制が整い、20歳以上60歳未満の人が加入しています。現役世代の人が保険料を払うことによって、高齢者・障害者・遺族などに生活費を補う“賦課方式”が取られています。職業や年齢によって加入する制度は異なっていて、現在、会社員は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入するこ...(続きを読む)
昭和36(1961)年に「国民皆年金」の体制が整い、20歳以上60歳未満の人が加入しています。現役世代の人が保険料を払うことによって、高齢者・障害者・遺族などに生活費を補う“賦課方式”が取られています。職業や年齢によって加入する制度は異なっていて、現在、会社員は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入するこ...(続きを読む)

- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
亡くなったときの公的保障は?
 家族の経済的担い手である大黒柱が亡くなったとき、公的年金制度の加入者であった場合もしくは年金受給者であった場合、遺族の生活保障として遺族給付という公的保障があります。遺族給付には、国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」、共済年金の「遺族共済年金」があります。職業や収入、家族構成などによってその額や支給期間は異なりますが、まずは子どもがいる家庭で大黒柱が亡くなった場合の遺族年金につい...(続きを読む)
家族の経済的担い手である大黒柱が亡くなったとき、公的年金制度の加入者であった場合もしくは年金受給者であった場合、遺族の生活保障として遺族給付という公的保障があります。遺族給付には、国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」、共済年金の「遺族共済年金」があります。職業や収入、家族構成などによってその額や支給期間は異なりますが、まずは子どもがいる家庭で大黒柱が亡くなった場合の遺族年金につい...(続きを読む)

- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
保険の見直し(2)(山下FP企画・西宮)
一家の大黒柱に万一のことがあっても、残された家族が無収入になることはありません。 公的年金には遺族年金という制度があり、一定の要件を満たした遺族には年金が支給されます。 妻子ある会社員の男性がなくなった場合、妻は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類の年金を受けることができます。 遺族基礎年金は子供が高校生以下(18歳に到達した年度の3月末日まで)である場合などに限られるため、...(続きを読む)

- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
皆の夢や希望を聞いて、ファミリー一族のイベント表を作成しよう
下図は私たちファイナンシャル・プランナーがライフプラン作成時に使う、ライフイベント表をファミリー一族用に拡大したものです。このコラムを読み、ご自身で作成してみようお考えの方は、メールでシート所望とお申し込みください。お名前と、年齢、お住いの市区町村を記載ください。そのメールアドレスに、シートを添付して返信いたします。シートは、マイクロソフト オフィス 2013エクセル「互換モード」で作成しています...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201403、交通事故
Blog201403、交通事故 自動車損害賠償保障法 労災保険法・厚生年金法の保険給付と損害賠償の調整まとめ 自動車損害賠償保障法 今月は、自動車損害賠償保障法の条文を読みました。 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年七月二十九日法律第九十七号) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 自動車損害賠償責任(第三条・第四条) 第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201403、交通事故と社会保険等からの給付
Blog201403、交通事故と損益相殺 使用者災害・第三者行為災害(交通事故)と社会保険給付等からの受給との控除の可否・過失相殺(要約) 労災保険法・厚生年金法の保険給付と損害賠償の調整まとめ 以下、労働者災害補償保険法を労災保険法、厚生年金保険法を厚生年金法、自動車損害賠償保障法を自賠法と略す。 労働基準法(他の法律との関係) 第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者災害・第三者行為災害(交通事故)と社会保険給付等からの受給との控除の可否・過失相殺
使用者災害・第三者行為災害(交通事故)と社会保険給付等からの受給との控除の可否・過失相殺(要約) 労災保険法・厚生年金法の保険給付と損害賠償の調整まとめ 以下、労働者災害補償保険法を労災保険法、厚生年金保険法を厚生年金法、自動車損害賠償保障法を自賠法と略す。 労働基準法(他の法律との関係) 第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法 又は厚生労働省令で指...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と社会保険給付等からの受給との控除の可否・過失相殺(要約)
交通事故と社会保険給付等からの受給との控除の可否・過失相殺(要約) 労災保険法・厚生年金法の保険給付と損害賠償の調整まとめ 以下、労働者災害補償保険法を労災保険法、厚生年金保険法を厚生年金法、自動車損害賠償保障法を自賠法と略す。 労働基準法(他の法律との関係) 第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法 又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201402、社会保障法
Blog201402、社会保障法 今月は、 社会保障法の内容、 労働者災害補償保険法に関する最高裁判例 『社会保障法判例百選』の労働者災害補償保険法の部分 『ハイレベルテキスト労災法』 国民年金法の最高裁判例 厚生年金保険法、 厚生年金保険法に関する最高裁判決 『ハイレベルテキスト厚生年金保険法』 介護保険法、 高齢者の医療の確保に関する法律、 老人福祉法、 障害者基本...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」
◎近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」 原則として、近親婚にあたる内縁関係にある者は、遺族年金の受給権者に該当しない。 最高裁昭和60・2・14訟務月報31巻9号2204頁(『社会保障法判例百選』№41参照)は、被保険者と1親等直系卑属にある者との近親婚で、内縁関係にある場合には、民法の近親婚禁止の趣旨からして、遺族年金の受給権者たる「配偶者」に...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除2
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除の要否2 最高裁判決昭和和62年7月10日 、損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 民集41巻5号1202頁 、判例タイムズ658号81頁 【判決要旨】 労働者災害補償保険法による休業補償給付・傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和和60年法律第34号改正前のもの)による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その2)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要な争点となる。 第7章 国土整備法(不動産に関する行政法) 「道路法、河川法、海岸法」 公共用物である道路と河川を対比しつつ、管理者(国家賠償法参照)、使...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 交通事故によって加害者が被害者に支払うべき損害賠償額を算定するにあたって、同じ損害項目(例えば、治療費、休業補償、逸失利益など)が労災、年金、他の保険から支払われる場合に、それを控除すべきかが問題となる。 ・損害賠償額から控除すべきではないもの ・最高裁平成7年1月30日・判例時報1524号48頁 搭乗者傷害保険金 ・最高裁昭和39年9月25日・民集18...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と遺族厚生年金
交通事故と遺族厚生年金 支給を受けることが確定していない厚生年金については、受給権(受給資格)は受給者の死亡により喪失するので、最高裁平成12年11月14日・民集 第54巻9号2683頁が、「 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。」と判示している。 これに対して、被相続人(交通事故の...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決 それ以前の交通事故の主な最高裁判決は、下記で取り上げています。 http://www.murata-law.jp/jiko/hanrei.html 平成13年3月13日 ・民集 第55巻2号328頁 1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有す...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」
ナンバーワン社労士 必修テキスト 2013年度 (TAC社労士ナンバーワンシリーズ)/TAC出版 ¥3,360 Amazon.co.jp 「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完
「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で必要なものです。 休憩・休日 みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。 年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、1...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
老後生活資金はいくらあれば足りるのか?
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 事務所にお越しになられる方々の相談で、最近割合が増えてきて いるのが、リタイアメントプランニングです。 FP相談も「高齢化」の影響なのでしょうか。 老後生活費がどれだけ必要で、今の資産状況で足りるのかどうか? もし足りないのであれば、事前に対策を打つことができるのか? 自分たちだけで判断するのではなく、専門家に見てもらいた...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
65歳以上の妻遺族年金と離婚の際年金保険料納付記録の分割
昨日は障害年金について述べさせていただきました。本日は、御主人の定年後、65歳以降でお無くなりになった際に、65歳以上の妻が得られる年金について、紹介いたします。 ところで、公的年金には「1人1年金」という原則があります。支給事由の異なる年金の受給権を得た時には、どちらか一方を選択することになり、これを「1人1年金の原則」といいます。 例えば昨日挙げた、障害給付と老齢給付を同時に受けられるとき...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族厚生年金を受給できる方達と年金額の算式
前回は遺族基礎年金を紹介しました。今回は遺族厚生年金につい内容を説明します。 遺族厚生年金の受給要件は 1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(在職中の死亡)。 2. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のあるけがや病気で、初診日から5年以内に死亡したとき(初診日から)5年以内の死亡) 3. 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。 4. 老齢厚生年金の受給権者または厚生老齢年...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族給付を受ける要件について (若齢の)遺族基礎年金
FPの教科書に遺族給付は、貰える人がだれかを確り把握することとされています。例えば、奥様が無くなられた際に、ご主人は遺族給付を受けられるのか等が家計にとって重要なポイントになります。しっかりご確認下さい。 遺族年金には、遺族期さ年金と遺族厚生年金があります。 どちらも遺族給付は年金加入者または年金受給権者が死亡した際に、生計維持関係がある「一定の要件を満たす」遺族に遺族年金が支給されます。 ...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険②必要保障額を正確に計算して見ましょう。
前回は、必要保障額を概算で出しました。 細かくなりすぎると、イメージしずらくなるので。 ただ、ご興味がある方のために、より正確に計算してみましょう。 お子様が大学卒業するまでを親の責任と考えて、ほんとうに必要な保障額を一度、考えて見ましょう。 1.残された奥さまとお子さんとで3人で暮らす生活費 (月○○万円×12ヶ月×上のお子さんが大学卒業するまでの年数) 2.上のお子さん大卒後、したのお子...(続きを読む)

- 佐野 明
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険①お子様がいらっしゃるご夫婦
お子様がいらっしゃるご家庭の場合、死亡保険金って、いくら必要なんでしょうか? 必要保障額と遺族年金についてザックリと、概算で考えて見ましょう。 お子様がいらっしゃれば、遺族年金がご家族に支払われます。 妻79万円+第一子22万円=101万円 (第二子+22万円、第三子以降+7.5万円) つまり、お子様がおひとりいらっしゃれば、月額8.4万円は受け取れます。 ただし、子の加算は子が18歳になる...(続きを読む)

- 佐野 明
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または、被保険者であった方が、下記の要件に当てはまる場合に支給されます。 厚生年金保険の被保険者が死亡された場合、または、その間に初診日があった病気やけがで、初診日から5年以内に死亡された場合。 1級、2級の障害がある方で障害厚生年金を受けていた方が死亡した場合、そして老齢厚生年金の受給権者や受けるために必要な加入期間を満たしている方が死亡した場合に、受給...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族基礎年金について
ご主人にもしもの際に支給される遺族年金の概要をご紹介します。 遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。 遺族基礎年金は概ね国民年金に加入されている方が死亡された場合と老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に支給されます。 受給者は 「子のある妻」か「子」だけに支給されます。過去は男性が働いて、専業主婦が居ることを強く意識して制度化したので、男性配偶者が残されるケースは想定してい...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険①お子様がいらっしゃるご夫婦
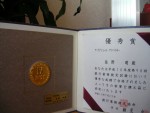

- 佐野 明
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険に加入する前にすること
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 一家の大黒柱に万一のことがあったとき、残された家族にはどんな備えがあればいいでしょうか。 生命保険の加入や増額を考えがちですが、社会には遺族をささえる制度があり、代表が公...(続きを読む)

- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
賢い生命保険の見直し方(その3)
もうひとつの必要保障額 生命保険の必要保障額の考え方は、もう少し簡単な考え方もあります。 それは、毎月のお給料を保障するという考え方です。 例えば、月収30万円のご家庭で、ご主人に万が一のことがあり、残された家族は生活費が20万円必要だとしましょう。 遺族年金が月に10万円支給されるとすると、毎月10万円が不足します。 この不足する10万円を生命保険で保障してもらおうという考え方です。 ...(続きを読む)

- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
賢い生命保険の見直し方(その2)
必要保障額 生命保険を見直す際に、まず考えることは「どれだけの保障」が「どれだけの期間」必要なのか?ということです。 これが必要保障額になります。 この必要保障額の考え方には、大きく2とおりの考え方があります。 はじめに基本的な考え方を書きましょう。 まず、ご主人に万が一のことがあった場合、残された家族が生活していくためにはどれだけの金額が必要なのかを考えます。 例えば、基本的な生活費が...(続きを読む)

- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
79件中 1~50 件目
- 1
- 2

「確定拠出年金」に関するまとめ
-
確定拠出年金(401k)の運用方法を学んで自分の力で年金額を増やしましょう!
最近多くの企業で導入されている確定拠出年金(401k)。いきなり確定拠出年金の導入が決まって、慌しく運用を始めてしまった方いませんか?せっかく確定拠出年金の運用をすることになったのですから、運用時の注意点や確定拠出年金のメリット、節税方法方法を理解して年金額を増やしましょう。 多くの専門家がオススメしている確定拠出年金(401k)。自分で資産を増やせるチャンスです!

専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。