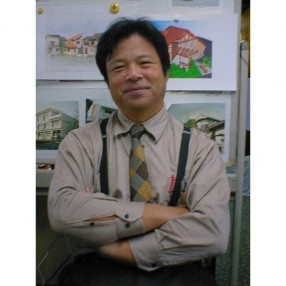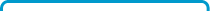●デザイナーズ住宅をよりローコストに のコラム一覧
96件中 1~10件目![]() RSS
RSS
コンクリート打ち放しの家は住み良いか?
 しっかりとした施工をすれば、漏水の心配はないかと思います。コンクリート打ち放しと云っても、屋上(屋根)はしっかりと防水工事を行いますし、窓等の開口部廻りに気を配っていれば雨水が浸入することはありません。壁の鉄筋の間隔がバラバラで歪な応力が壁に発生しない限り、コンクリートを貫通するようなクラックは発生しません。
汚れも、汚れることを見越してデザインしていれば、年月を経るに従って深みのあるものとなる...(続きを読む)
しっかりとした施工をすれば、漏水の心配はないかと思います。コンクリート打ち放しと云っても、屋上(屋根)はしっかりと防水工事を行いますし、窓等の開口部廻りに気を配っていれば雨水が浸入することはありません。壁の鉄筋の間隔がバラバラで歪な応力が壁に発生しない限り、コンクリートを貫通するようなクラックは発生しません。
汚れも、汚れることを見越してデザインしていれば、年月を経るに従って深みのあるものとなる...(続きを読む)
☆工期短縮
住宅建設の場合、工程の管理は監督者の長年の感と経験によりなされてきた。しかし、工程表を作成して計画的に工程管理を行う事により、集約的に工事管理が行え、請負業者の経費削減につながる。 ●バーチャート工程表 工種を縦軸に時間経過を横軸にした工程表。時間軸毎に工事の流れがつかめ、素人にも見易いが、狂いが発生しやすく、各工種の出来高がつかめない。 ●出来高工程表 工種を縦軸に出来...(続きを読む)
☆土地の集団購入
コーポラティブハウスの発想を戸建住宅に活用する。数人で共同組合を組織して、資金調達から土地の購入・建設までを共同で行う。 一人では大きすぎる土地も共同購入すれば無駄なく利用出来る。 又、変形敷地は土地利用が難しく土地値が相場よりかなり安い。 自分達の活用しやすい様に土地利用計画を立て、共同購入すればローコストで優良な環境が手に入る。(続きを読む)
☆スケールメリット
多品種を少量ずつ購入するより、少品種を大量に購入する方が安くなる。内装を統一して、品種を減らし数量を多くする。 工種を減らして一工種当たりの仕事量を増やし間接経費を減らす等が考えられる。(続きを読む)
☆個人輸入
材料支給のひとつの方法。インターネット等を活用すれば海外の魅力的な材料が、驚くほど安価に輸入できる。中小の施工者では、知識的に弱い分野の為、建築主がサポートする事により、良いものが安価に出来る可能性がある。リスクとして、調達期間や支払い方法等を緻密に行わなければ工程順序が逆になったり、為替差損が発生したりする。(続きを読む)
☆完成保証制度
建設工事途中で施工者が倒産してしまえば、建築主の被害は大きい。 途中で工事が止まるのは当たり前で、施工者に過払いでもしていればそのお金は返ってこない。過払いしていなくても、管財人から出来高分の支払いは要求されるが、工事が止まった事による損害は保証されない。 引き継いで工事をしてくれる施工者を選ぶにも、同等の金額で引き継いでくれる保証はない。その為、工事請負契約の際に施工者に保証人を立...(続きを読む)
☆材料支給
住設機器や住宅建材には、定価を公表しているものが多くある。施工者から見積り書が上がってきたら、定価を公表している材料を確認し、それらの中で建築主自身が資材調達した方が安いものを選び。それらを見積書から分離して、建築主が施工者に材料支給して工事を進めるもの。但し建築主から支給した材料は施工者の瑕疵担保から除外されるので注意が必要。(続きを読む)
☆分築
ライフサイクルに応じ、必要なスペースを順次建設していく方法。 小額を短期で借りれば、利子返済が少なくて済む。返済完了後すぐに新たな融資をうけて、増築に取り掛かり、ライフサイクルにマッチした家をいつまでも綺麗に住む方法として、注目されている。 筆者も分築の経験者で、減価償却と共に減少する建物の不動産価値を落とす事なく、高額での売却を経験している。(続きを読む)
☆フラット35
最近住宅金融公庫が推奨している住宅証券の一種。 銀行ローンに比べ長期固定で、低利の融資が受けられる。 変動金利より割高ではあるが、今後金利の上昇が予想され、長期に渡っての返済計画を考えた場合、検討の余地は充分にある。(続きを読む)
96件中 1~10件目