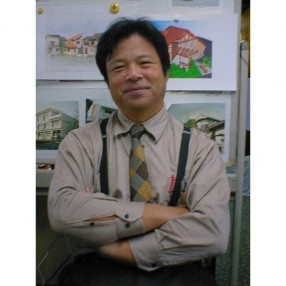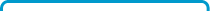●デザイナーズ住宅をよりローコストに - ☆発注システムを見直す のコラム一覧
10件中 1~10件目![]() RSS
RSS
☆個人輸入
材料支給のひとつの方法。インターネット等を活用すれば海外の魅力的な材料が、驚くほど安価に輸入できる。中小の施工者では、知識的に弱い分野の為、建築主がサポートする事により、良いものが安価に出来る可能性がある。リスクとして、調達期間や支払い方法等を緻密に行わなければ工程順序が逆になったり、為替差損が発生したりする。(続きを読む)
☆完成保証制度
建設工事途中で施工者が倒産してしまえば、建築主の被害は大きい。 途中で工事が止まるのは当たり前で、施工者に過払いでもしていればそのお金は返ってこない。過払いしていなくても、管財人から出来高分の支払いは要求されるが、工事が止まった事による損害は保証されない。 引き継いで工事をしてくれる施工者を選ぶにも、同等の金額で引き継いでくれる保証はない。その為、工事請負契約の際に施工者に保証人を立...(続きを読む)
☆材料支給
住設機器や住宅建材には、定価を公表しているものが多くある。施工者から見積り書が上がってきたら、定価を公表している材料を確認し、それらの中で建築主自身が資材調達した方が安いものを選び。それらを見積書から分離して、建築主が施工者に材料支給して工事を進めるもの。但し建築主から支給した材料は施工者の瑕疵担保から除外されるので注意が必要。(続きを読む)
☆性能保証制度
性能表示制度と同時に発足した制度。性能表示制度の様に任意法ではなく強制法の為、一般的に認知されている。性能保証の範囲は10年間に渡り主要構造部の瑕疵、漏水等の瑕疵保証を行うものであり、建物全般に渡るものではない。(続きを読む)
☆性能表示制度
売買契約が購入の条件であれば、性能表示制度の導入を検討する必要がある。 平成12年に発足したこの制度は、住宅の性能を9項目に渡り等級別に性能を評価する制度である。http://www.jin.ne.jp/oado/sinouhyouji1.html これで、自分の要求する性能が第三者の目で客観的に評価される事により安心して住宅を購入することができる。等級は全て高等級を取得する必要はな...(続きを読む)
☆請負契約
建物を取得する方法として、施工者と請負契約を交わし工事を請負わせる方法とマンションや分譲住宅の様に現物を見て買う売買契約がある。 売買契約は原則的に現物を見て購入する方法であるが、現物が完成していなくても、契約しなければ買主を拘束する事はできる。 他の人に売る権利を放棄する事を条件に手付金を取る事が出来るのである。建物が完成すると手付金は契約金の一部に充当され売買契約が完了する。分譲...(続きを読む)
☆分離発注
知人に建築工事に関与している人がいれば、その工種だけ、施工者から分離して、工事を発注する方法。設備工事等の分離発注は日常的に行われておりメンテナンス等にも素早く対応してくれる。(続きを読む)
☆オープンシステム
設計事務所がサポートする事により、建築主自信が発注者となり、各工種ごとに個別に直接契約を結ぶシステム。施工者の経費が必要なくなり注目されている。 欠点として、各工種の連携が悪く施工範囲の曖昧な分野(設備業者と住設業者間で、器具の取付けを誰が行うか等々)はトラブルが発生しやすい。 各工種ごとに請求書が上がってくるので、経理事務が煩わしい。 施工者が不在の為、施工ミスによる瑕疵担保...(続きを読む)
☆競争見積り
設計事務所に設計図書の作成を依頼する事によって、同一条件で複数施工者に見積り発注が可能となる。建設場所や施工条件によって施工者に得手不得手が発生し、同一条件でも入札価格に1〜2割の価格差が発生する。 2000万円の建物だと200万円〜400万円の差となり、コストダウンする上に於いてもっとも重要な方法である。見積り依頼する施工者数は2〜3社が平均的で多くとも5社以内が望ましい。(続きを読む)
10件中 1~10件目
- 1