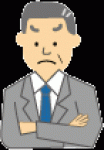「内部統制」を含むコラム・事例
100件が該当しました
100件中 1~50件目
- 1
- 2

戸村智憲の公開セミナーご案内@2015年8月時点
日本マネジメント総合研究所合同会社の理事長の戸村智憲による登壇 ・2015年8月27日(木) (一社)企業研究会 東京開催 監査チェックリスト改訂と監査戦略講座(仮題)・・・ パンフレットPDF 詳細・お申込: https://www.bri.or.jp/seminar/34193 ・2015年8月27日(木) (一社)企業研究会 東京開催 監査チェックリスト改訂と監査戦略講座(仮題)...(続きを読む)

- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント)
情報が多すぎる時は野生の勘を鍛えよう
 憲法9条への新たな問題定義
が盛り上がり
情報の流れが政治的に傾くと
経団連では
・企業統治
・内部統制
・法令遵守
と「利益追求」が矛盾しないように
経営するのが
この夏のテーマと
きなくささに備えているが、
4文字熟語を多くして、
経営者以外には
なじみにくくして情報を流す。
経営者以外に
情報の翻訳者が
いない場合は、
情報過多ストレスが
たまっていく。
この情報過多のストレ...(続きを読む)
憲法9条への新たな問題定義
が盛り上がり
情報の流れが政治的に傾くと
経団連では
・企業統治
・内部統制
・法令遵守
と「利益追求」が矛盾しないように
経営するのが
この夏のテーマと
きなくささに備えているが、
4文字熟語を多くして、
経営者以外には
なじみにくくして情報を流す。
経営者以外に
情報の翻訳者が
いない場合は、
情報過多ストレスが
たまっていく。
この情報過多のストレ...(続きを読む)

- 村本 睦戸
- (ITコンサルタント)
技術者はもういらない。
攻めのIT。 IT経営。 IT営業。 技術者が必要だと 思われているし、 技術者が足りないと 報道されている。 とんでもない 技術者はいらないです。 よく報道される技術者は いわゆる 理系のプログラムができて、 わけのわからない カタカナ言葉を話す 人間ではありませんか? むしろ、必要な技術者の イメージに近いのは 外資系の経営コンサルタントです。 というのは、 ITにする前の 現...(続きを読む)

- 村本 睦戸
- (ITコンサルタント)
東芝-不適切会計 ニュース・事例で見つけるコンプライアンスのネタ(0003)
東芝が不適切会計の問題で揺れています。 【事例】 東芝の不適切会計問題は、第三者委員会による調査・原因究明とともに経営責任をどう取るのかが今後の焦点となる。 田中久雄社長は29日の記者会見で9月開催予定の臨時株主総会までに経営責任について判断し、必要に応じて役員の顔ぶれを見直す考えを示した。 (中略) 企業統治のあり方も問われる。田中社長は「内部統制が十分でなかった」と認めた。 経営陣から予算達...(続きを読む)

- 中沢 努
- (経営コンサルタント)
Blog201405、会社法
Blog201405、会社法 ・『実務に効く M&A・組織再編判例精選』有斐閣 ・『アメリカ法判例百選』有斐閣 ・ビジネス法務2010年9月号「特集 自社・子会社・事業部門の売却型M&A―戦略と手法―」 ・ビジネス法務2013年11月号「特集 親会社に知ってほしい子会社が抱える悩み」 『実務に効く M&A・組織再編判例精選』有斐閣 256頁、 2013年 M&Aに関して、下級審...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年11月号「親会社に知ってほしい子会社が抱える悩み」と題する特集
ビジネス法務2013年11月号「親会社に知ってほしい子会社が抱える悩み」と題する特集 「子会社はどんなことで悩んでいる?」 1、子会社の定義で問題となるのは、以下の法律等である。 ・会社法 ・財務諸表規則、連結財務諸表規則 ・金融商品取引法 ・法人税法の完全支配子会社(本稿では指摘されていない。なお、連結税務申告の対象は任意であるが、100%グループ法人の場合の税務申告...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
金融法の読んだ本(その2)
金融法の読んだ本(その2) ◎証券取引法 河本一郎教授は、証券取引法が改正されて金融商品取引法という名称に代わる前から、『証券取引法読本』という概説書を出されていた権威である。 『証券取引法読本』は、私は弁護士になってから、筑波大学院のときに、「証券取引法」の講義を受講した際に、テキストとして指定されていたので、読んだ。 証券取引法については、例えば、当時、野村証券が東京大学に同法の寄付...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
なぜ、中小企業のパソコンはセキュリティが弱いのか? その4
 利便性と機密性のバランスを取る
これまで、業務利用パソコンにおけるセキュティ対策について説明をしてきましたが、これらの脅威に対して過敏に対応するだけでなく、それらがもたらす利便性についてのバランスを取り、遂行していくことがIT部門ではカバー出来ない総務部門の役割なのではないかと思います。
過去に情報漏洩を起こした企業、あるいは過剰にセキュティ対策をしている企業などでは、情報漏洩を過剰に気にする...(続きを読む)
利便性と機密性のバランスを取る
これまで、業務利用パソコンにおけるセキュティ対策について説明をしてきましたが、これらの脅威に対して過敏に対応するだけでなく、それらがもたらす利便性についてのバランスを取り、遂行していくことがIT部門ではカバー出来ない総務部門の役割なのではないかと思います。
過去に情報漏洩を起こした企業、あるいは過剰にセキュティ対策をしている企業などでは、情報漏洩を過剰に気にする...(続きを読む)

- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
Blog201403-5、金融商品取引法(読んだ本など)
Blog201403-5、金融商品取引法(読んだ本など) ・ジュリスト2012年8月号「特集 金融商品取引法 施行5年の軌跡と展望」 ・『金融商品取引法判例百選』有斐閣 ・松尾直彦『金融商品取引法』商事法務、2011年刊 ・川村正幸『金融商品取引法(第4版)』中央経済社、2012年刊 ・松尾直彦『実務論点 金融商品取引法』 ・有価証券報告書等の虚偽記載等を理由とする損害賠償請求訴訟...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
金融法の内容(金融商品取引法を含む)
金融法の内容(金融商品取引法を含む) 金融法は、司法試験の科目とされていない。 法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。 司法試験の選択科目の場合、合格に必要な勉強時間としては、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。 司法試験の選択科目とすべ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201401、金融商品取引法
Blog201401、金融商品取引法 今月(2014年1月)は、保険法、独占禁止法、借地借家法、宅地建物取引業法、労働法、金融商品取引法、金融法、電子記録債権法、会社法、会社非訟、知的財産法、商標法、意匠法、不正競争防止法、信託法、破産法、倒産法、土壌汚染対策法、行政法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(専門家プロファイル)に掲...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
川東憲治『図説 金融商品取引法(第1次改訂版)』学陽書房 2007年
川東憲治『図説 金融商品取引法(第1次改訂版)』学陽書房 2007年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 タイトルに反して、あまり図解されていない。 第1章 定義 1 金融商品 2 有価証券 3 デリバティブ取引 4 集団投資スキーム(ファンド) 5 金融商品取引業 6 開示に関する用語 募集 ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201401、会社法
Blog201401、会社法 今月(2014年1月)は、保険法、独占禁止法、借地借家法、宅地建物取引業法、労働法、金融法、金融商品取引法、電子記録債権法、会社法、会社非訟、知的財産法、商標法、意匠法、不正競争防止法、信託法、破産法、倒産法、土壌汚染対策法、行政法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(専門家プロファイル)に掲載...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-2、会社法、金融商品取引法など
今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 ビジネス法務2013年9月号、民法改正 遠藤「事例でわかる民法改正 契約実務編」 民法改正中間試案に即して、具体的に、契約の条項について、下記の点を論じている。 ・解除 ・危険負担 (注)試案では危険負担を廃...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、金融商品取引法
 ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2013年9月号、金融商品取引法
林「会社法改正、COSOフレームワーク改訂で議論再燃! 内部統制を合理化するキーコントロール」
会社法改正案で内部統制が重視されている。
また、企業会計審議会が不正リスクについて、金融商品取引法による内部統制の報告の強化が重視されている。
...(続きを読む)
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2013年9月号、金融商品取引法
林「会社法改正、COSOフレームワーク改訂で議論再燃! 内部統制を合理化するキーコントロール」
会社法改正案で内部統制が重視されている。
また、企業会計審議会が不正リスクについて、金融商品取引法による内部統制の報告の強化が重視されている。
...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
トピックスの法律問題
トピックスの法律問題 いま何がトピックスとなっているか、「月刊ビジネス法務」(中央経済社)、「月刊ジュリスト」(有斐閣)を調べてみました。 ただし、主な読者は、「ビジネス法務」は企業法務部・総務部、「ジュリスト」は学者、弁護士などの法律実務家向けです。 したがって、上記の両雑誌は、税務・会計(公認会計士、税理士)、社会保障(社会保険労務士)、行政法(行政書士)などの分野は、若干手...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 4
 スマートフォンで見積り、請求書が1分で作成出来る
外出の多い営業担当者によって、見積書の作成は、会社に戻ってパソコンでエクセルを使って作成することが多いかと思いますが、当社では、これも、スマートフォンがあれば、少ない商品数の見積書などは、1分で発行出来るようになりました。
これは、Zoho Invoiceというクラウドサービスとスマートフォンを組み合わせるのですが、一度、このZoho In...(続きを読む)
スマートフォンで見積り、請求書が1分で作成出来る
外出の多い営業担当者によって、見積書の作成は、会社に戻ってパソコンでエクセルを使って作成することが多いかと思いますが、当社では、これも、スマートフォンがあれば、少ない商品数の見積書などは、1分で発行出来るようになりました。
これは、Zoho Invoiceというクラウドサービスとスマートフォンを組み合わせるのですが、一度、このZoho In...(続きを読む)

- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
事業承継と株式公開(IPO)
事業承継と株式公開(IPO) 1 株式公開とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において不特定多数の株主により所有され、株式市場において自由に売買が行われることを可能にすることです。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれます。 かつて、東京などの証券取引所に公開することを上場と呼び、日本証券業協会の...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
日本経済ウオッチング
企業における日本証券市場の魅力が失われていないか? MBOが証券市場を賑わしている 御存じの方が多いと思うが、MBOとは、経営陣による買収を意味している。 最近のMBOを行う旨の発表を行った企業は、幻冬舎・ワークスアプリケーション・ エノテカ・CCC・アートコーポレーション等があげられる。 上場している企業が、なぜ、自らの手でMBOを実施し上場廃止を目指すのか、私なりの見解を述べてみたい...(続きを読む)

- 宮田 幸治
- (経営コンサルタント)
IFRSって何だろう
昨今、上場企業の経理関係者の関心事は、IFRSなのではないでしょうか。 いままで、内部統制対応に右往左往してきて、今度はIFRSかと嘆きの声が聞こえてきそうです。 2000年ごろから会計ビックバーンといわれ、さまざまな会計制度が、国際会計基準(IAS)や、米国会計基準をベースに導入されてきましたが、IFRSは、今まで以上の対応を求められそうです。 IFRSは、Interna...(続きを読む)

- 松原 寛樹
- (経営コンサルタント)
新会計ルールを知り国際基準に対応する【IFRS】
![]() 世界110カ国以上で採用されている国際会計基準、IFRS(International Financial Reporting
Standards)に関する話題が盛り上がっています。主要ビジネス雑誌で特集が組まれたり臨時増刊号が発行されているほか、関連書籍がいくつもの書店の店頭に並べられています。
では、なぜIFRSに関する話題が高まっているのでしょうか?
<IFRS適用は世界的ト...(続きを読む)
世界110カ国以上で採用されている国際会計基準、IFRS(International Financial Reporting
Standards)に関する話題が盛り上がっています。主要ビジネス雑誌で特集が組まれたり臨時増刊号が発行されているほか、関連書籍がいくつもの書店の店頭に並べられています。
では、なぜIFRSに関する話題が高まっているのでしょうか?
<IFRS適用は世界的ト...(続きを読む)

- 澤田経営研究所 澤田和明
- (経営コンサルタント)
内部統制の文書化をめぐる大きな誤解(5)
「IT統制の不備は重要な欠陥につながる」? 前回は、財務報告リスクに関する誤解として ・なんでもかんでもリスクとすべきではない ・財務報告の観点から「全体感」による重要なリスクを識別することで コントロールの設計もポイントを押さえて進めることができる という内容をお伝えしました。 本シリーズの最終回は、IT統制の文書化に関する誤解についてお伝えします。(以...(続きを読む)

- 原 幹
- (公認会計士)
「情報」の作成・流通・利用を効率化する【XBRL】
![]() 現在、国際会計基準が急ピッチで整備されていますが、財務諸表を中心とする財務情報の作成・流通・利用をXMLで可能にするのは、全世界でもXBRLをおいて他にはなく、世界中の関心が確実に高まっています。日本でのXBRLは、2008年4月、金融庁の「EDINET」で、有価証券報告書のうち、財務諸表の本表部分のXBRLでの提出、さらに2008年7月、東京証券取引所の「TDnet」で、決算短信の決算情報の要約...(続きを読む)
現在、国際会計基準が急ピッチで整備されていますが、財務諸表を中心とする財務情報の作成・流通・利用をXMLで可能にするのは、全世界でもXBRLをおいて他にはなく、世界中の関心が確実に高まっています。日本でのXBRLは、2008年4月、金融庁の「EDINET」で、有価証券報告書のうち、財務諸表の本表部分のXBRLでの提出、さらに2008年7月、東京証券取引所の「TDnet」で、決算短信の決算情報の要約...(続きを読む)

- 澤田経営研究所 澤田和明
- (経営コンサルタント)
内部統制の文書化をめぐる大きな誤解(4)
前回は、内部統制導入にめぐる誤解(および方向性)として 「業務記述書に現状業務をそのまま記述するより、業務フローをまず表現してそこから改善機会を検討するのが効果的」 という内容をお伝えした。 今回は「業務において識別すべきリスク」にまつわる誤解についてお伝えしたい。 「なんでもかんでもリスク」の誤解 内部統制報告制度は 「財務報告リスクを合理的に低減させるため...(続きを読む)

- 原 幹
- (公認会計士)
内部統制の文書化をめぐる大きな誤解(3)
「まず業務記述書から書き始める」の誤解 前回は、内部統制導入にめぐる誤解として ・3点セットの文書化が強制されている(そんなことはない) ・とにかく文書化からはじめればよい(そんなことはない) について書かせていただいた。 今回は「まず文書化すべき文書はどれなのか」に関した誤解、またはそれをきっかけとした内部統制構築の方向性についてお伝えしたい。 内部統...(続きを読む)

- 原 幹
- (公認会計士)
内部統制の文書化をめぐる大きな誤解(2)
制度導入当初の大きな誤解に、いわゆる3点セット(業務フロー・業務記述書・リスクコントロールマトリクス(RCM)にまつわるものがあった。特に多かったのが 「内部統制制度では3点セットの文書化が強制されているので、とにかく今の業務を文書することからスタートしよう」 という誤解だ。 まず「文書化が強制されている」について半分は当たっているが、必ずしも正確な理解ではない。「内部統制基準」...(続きを読む)

- 原 幹
- (公認会計士)
内部統制の文書化をめぐる大きな誤解(1)
内部統制といえば文書化、と脊髄反射で言う人が多い時期があった。 内部統制対応の本番年度を迎えるにあたり、いろいろなところで尋ねられる。 「内部統制でほんとに文書化って必要だったんでしょうかねえ」 私の答えは今のところこうだ。 「実務上は文書を作ることは避けられない。でもそれを目的にしてはダメ」 確かに内部統制監査を行ううえでは文書化は実質的に避けて通れないし、内部統...(続きを読む)

- 原 幹
- (公認会計士)
100件中 1~50 件目
- 1
- 2


専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。