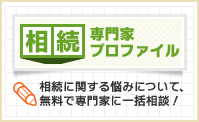おはようございます、今日は苗字の日です。
日本で成立してまだ140年ほどの制度です。
遺言書についてお話をしています。
分割方法についてなるべく具体的に書き、故人が生きていたときの諸事情を反映させたものが好ましいことを確認しました。
もう一つ、実務的な観点から。
これは実際に税理士をしていてよく思うことですが、不動産等について共有での分割をすることはあまりオススメしません。
例えば土地や建物を半分ずつ共有で相続したとします。
何年かして、その処分を検討することになりました。
そういうとき、共有になっていると大概苦労します。
一人は売りたい、でも一人は売りたくない。
意見が合わない、処分ができない…。
仲が良ければ良いのですが、人間関係なんてものはわからないものです。
将来的なことを考えると、不動産を共有にしておくことは色々と問題を産むことがあるのは覚えておいて損のないことです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
 このコラムの執筆専門家
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
 「経営」のコラム
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
現預金や保険の活用 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/11 07:00)
「遺言執行の実務」研修を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/31 17:01)
遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実 芦川 京之助 - 司法書士(2012/09/30 00:39)
【法律事務所のコラム:相続の身近なお悩み】第2回 松野 絵里子 - 弁護士(2011/11/16 14:19)
法定相続情報証明制度はじまる 大黒たかのり - 税理士(2017/06/02 14:23)