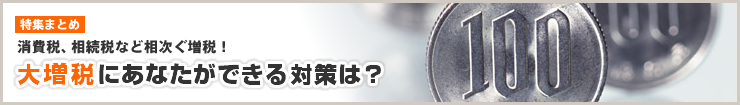対象:住宅設備
回答:4件
扉の下に排水を設けます
横浜の設計事務所の小松原といいます。
やり方はいくつか考えられますが、もっともオーソドックスなやり方は排水口を扉の下に
設けるように設計する方法です。(歩けるようにその上にはグレーチングを敷く)
この時に大事なのは、主排水口は洗い場近くに設置して扉の方はあくまで水上にして、
扉の下の排水口は補助にする事です。
こうしたものは製品でもあります。TOTOからバスドアとセットになった
製品も出ていますし、ユニットバスならばバスルームごとバリアフリー仕様に
なったものもあります。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
富士北山の木で家を建てませんか
富士の裾野で育った産地直送の天然乾燥無垢材を使って、エコで健康的な家造りをしませんか。無垢材対応金物工法・特殊ビスによる5倍耐力壁で、耐震等級3でありながら風と光が通る大開口をもつパッシブデザインの家がリーズナブルに建てられます。
小松原 敬が提供する商品・サービス

今野 樹
建築家
-
![]()
鍵は排水位置(グレーチング)かと思います。
お風呂と脱衣所の床が段差なく、フラットなものは近年のバリアフリー対策の建物ではよくつかわれている物かと思います、ユニットバスでしたら各メーカーさんのサイトで詳細は確認可能かと思います。在来構法の場合は、排水位置(グレーチング)が鍵かと思います。浴室の洗い場の排水とは別に、洗面所と浴室の入口部分に排水口(グレーチング)を設けることで可能かと思います。その際、防水層とのからみがありますので一概にはいえませんが、排水口の深さは、50mm程度の深さでいいと思います。

藤原 浩
工務店
-
![]()
段差を無くし、フラットにする意味
構造としては、シンプルな物は、洗い場の排水で受けきれない物を、出入り口付近をカバーする形で、浅めの、蓋付きの溝(SUSカバーが多い)をもうけ、排水します。開口部までリフォームできるなら、サッシュ溝にたまった水を、排水できる製品もありますので、出来ればこれを採用したです。発売当初のメーカー製品は、上記の形で作られていました。現在殆どのユニットバスは、一度に排水しきれなかった水を、出入り口扉でブロックし、残った水をサッシュ下に設けた小さな溝で排水しています。
メリットは、お年寄りや足に軽い障害を持つ人等が、段差でつまずきにくくするためです。
デメリットとして、サッシュ部の掃除を怠ると、場合によっては、排水の流れが悪くなり、脱衣室床に水が、浸みる事がありますので、注意が必要です。(私の顧客で、過去に数件有りました。)

長谷川 高士
住宅設備コーディネーター
-
![]()
段差がなくても、心配ありません。
こんにんちは、水まわりアドバイザーの長谷川高士です。
段差はない方がいいですね。
つまづいて転ぶ、という危険が少なくなります。
だから家の中にある段差は、
「本当はない方がいいのだけれど、やむを得ずあるもの」
と考えています。
そのやむを得ない理由のひとつが、ご質問にある
「水がたまりにくいのでは?」
ということですね。
ご安心ください。
そのご心配は、解決されています。
お風呂の出入り口から脱衣場に水が出ていかないための工夫が、上手くできるようになってきました。
具体的には、排水口で解決します。
出て行きそうになる水を床下のパイプへ流します。
また、出入り口のドアのスキ間にも、水が出ていかない工夫があります。
ゴム製のパッキンなど。
詳しい構造は、図解などで説明した方がわかりやすいので、別の機会にゆずるとして、
私の結論は、
・お風呂と脱衣所の段差はフラットにできます
・水のたまりは心配ありません
ということです。
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング










 専門家
専門家