対象:遺産相続
祖父は昭和18年ころに死亡しました。
祖母は祖父の実家(曾祖母、祖父の妹)と折り合いが悪く、祖父の死後、県外の実家に戻りました。長男、次男、長女、三男の直系卑属がいますが、幼かったため家督相続などはしていません。
亡祖父名義の不動産には祖父の妹が居住していました。
祖父の妹が離婚して戻ってきてそのまま居住していたようで、土地使用貸借契約等はありません。
祖父が亡くなって以後の固定資産税は祖父の妹が払っていたようです。
祖父の妹が亡くなり、その相続人から電話があり、登記簿を取り寄せて、はじめてその土地が亡祖父名義のままになっていることが判明しました。
この場合、
?1)亡祖父の生存している直系卑属(長男、亡次男の妻と子、三男(妻は死亡、次女は死亡しており子なし))で遺産分割協議書を作成し相続登記することが可能か
?2)亡祖父は旧民法の時期に死亡しているので、長男が家督相続の届出をなし、家督相続の登記をすることは可能か
?3)亡くなった祖父の妹の相続人が、当該不動産は亡祖父の妹のものであると主張(固定資産税の支払実績が亡祖父の直系卑属らの不当利得であると主張)することは可能か
この三点についてお伺いしたいです。
今は、遺産分割協議が可能な場合を想定して、戸籍(除籍)謄本類を取り寄せています。
いろいろ勉強していますが、専門家の方のご意見を伺いたく思います。
よろしくお願いいたします。
補足
2011/12/01 15:43なお、不動産については、直系卑属らは使用する意志はなく、長男に単独相続させ、その相続登記が無事に済めば市町村か公益法人に寄附することを検討しています。
なるべく穏便に済ませたいです。
よろしくお願いいたします。
bakanetさん ( 石川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
相続における登記等
親しい司法書士にも確認しましたが、以下の様にお考え頂ければと思います。
ご質問の件、昭和18年ごろ相続が開始しているとのことですので、旧民法の時代の相続関係となります。
戸主が祖父でありましたらば、第一順位である、いわゆる第一種法定家督相続人であります、直系卑属、すなわちご長男様が家督相続人となります。
よって、家督相続人であるご長男様名義で相続登記をすることは可能と考えられます。
ちなみに戸籍はご覧になられましたでしょうか。ご覧になられたとして家督相続の旨の記載がないのでしょうか?
司法書士の方も同様の戸籍は時折見るそうですが、家督相続の旨入っていない戸籍は見たことがないとの事です。
ただし、ご懸念されている通り、妹の相続人様が、20年以上の土地占有に基づく時効取得を主張してくることは、事実関係如何によっては可能と考えられます。
この点については、このあたりのことについて詳しい弁護士の先生にご相談されたほうがよろしいかと思います。
ただ、文脈からはその様な状態ではないと察しますが…
評価・お礼
bakanetさん
2011/12/02 17:17回答ありがとうございます。
まず戸籍謄本を確認します。
私は三男の娘で相続分はないのですが、三男(父)が軽い認知症、三男が該当不動産の比較的近くに居住し外の共同相続人が遠方で、なりゆきで窓口にされてしまい困惑していました。
順序としては相続登記後に処分でいいと思うのですが、祖父の妹の相続人の動きによっては慌てて相続登記しないのも手かなと考えました。
居住実績は、直近20年は祖父の妹は病院に入っており実質空き家状態とのこと、固定資産税の支払実績のみで所有権を認めるか迷いましたが、直系卑属らは相続や所有を避けたいらしく、認める方向で検討しています。
ありがとうございました。
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
(現在のポイント:1pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング





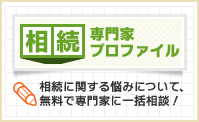





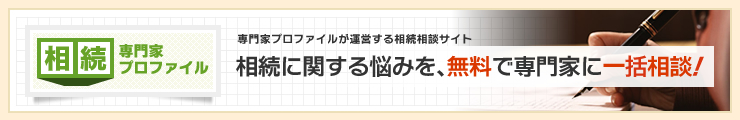
 専門家
専門家




