対象:遺産相続
2月に母が亡くなりました。質問しようとしている私は長男です。
長女(妹)が居ます。父と母はすでに離婚しており父も他界しています。
母が残した不動産(土地建物)はごく普通の一軒家。ただ、まだ詳しく
調べていませんが私との共同名義になっているようです。
不動産を処分(更地化して売却)して妹と分けようかと思っていましたが
借りたい人が出てきた場合(たまたま話が出てきている)、妹と共同名義に
するのがよいのでしょうか?
この場合相続との関係はどうなるんでしょうか?
手の付け所が分から無いと行ったところです。
EzoTanukiさん ( 北海道 / 男性 / 52歳 )
回答:2件
お母様の不動産持分の相続手続きが必要です。
行政書士の加藤です。
まずは、法務局にて不動産の土地及び建物の謄本(全部事項証明)を取得し所有権者を確認する必要があります。ご質問のようにお母様と質問者の共有とされていれば、お母様の持分に関する相続手続きが必要となります。
まずは法定相続人が質問書にあるように2人だけなのか、お母様に関する除籍・原戸籍等を取得して確定する作業も併せて必要です。
法定相続人が2人だと仮定すれば、お母様の持分に対し質問者と妹様が各2分の1に割合で権利を持つことになります。その持分を質問者が単独相続するのかあるいは法定相続分どおり相続するのかは、お二人で協議のうえ決定することになります。
不動産の固定資産税評価証明及び路線価をお調べのうえ、お二人で協議する必要があります。不動産を処分するについても前提としてこの相続の手続きは必要です。この場合は、換価分割となります。
詳細については、お近くの行政書士あるいは司法書士事務所にて有料相談をされることをお勧めします。
回答専門家

- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
1
![]()
共同名義の不動産相続並びに賃貸の件につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
お母様には、負債がなく、資産については、不動産(土地建物)の持ち分のみであるという前提にて、以下、参考までに回答させていただきます。
【ご質問の件につきまして】
相続の結果、お母様の持ち分については、長男(ご質問者様)及び長女(妹様)が、この持ち分を共有するにいたります。
今のところ、妹様と遺産分割の協議はなされていないと思いますので、まずは、妹様と話し合いを行う必要がございます。
つまり、お母様の持ち分を相続するのか、また、相続をするにしても、どのくらいの割合で相続するのかを、それとも、相続放棄をするのかを、きちんと、話し合われる必要がございます。
その話し合いがまとまった結果、決めた持ち分にて、改めて不動産登記(相続登記)をすることになります。
なお、不動産を売却するのか、賃貸に出すのかが、はっきりとされていないかと思いますが、第三者に対して、権利関係を明確に示すためには、相続に関する不動産登記は、早めになされたほうがよろしいかと存じます。
相続登記に関しては、法務局へ出向き、ご自身で行うことができますが、もし、お時間がなく、また、手間がわずらわしいというのでありましたら、最寄りの司法書士もしくはお知り合いの司法書士に登記手続きの依頼を行えば、簡単に済ませることが可能です。
【売却の想定】
相続登記が完了した結果、不動産の売却を希望するのでしたら、普通に売却活動を行えば、特に問題はないかと存じます。
補足
【賃貸の想定】
相続登記が完了した結果、賃貸にすることを想定する場合、所有形態が共有名義になります。この場合、貸主の名義がどのようになるのかが、今回のご質問の主たる内容であるかと存じます。
つまり、ご質問者様及び妹様の連名で貸せばよいのか、それとも、ご質問者様だけの名義で貸せばよいのかと…。
結論から申し上げれば、基本的には、どちらでも構わないと思います。
賃貸の実務上で、所有形態が共有の場合、共有の一人が、貸主となって、賃貸借契約を行うことはよくあることです。(家賃をそれぞれの貸主に支払うのは、借主にとって、手間暇がかかることとも考えられます。)
民法上では、共有に関するものとして、管理(収益)行為を行う場合、持ち分割合が過半必要という規定もありますけども、現実には、これとは異なる形で、賃貸借契約がなされているのが一般です。(※当事者間で合意のうえなら、問題ないということです。)
どのような名義にされるのかについては、借主様の意向を尊重し、賃貸の事務手続きなど踏まえ、また、賃貸仲介業者が入るのであれば、業者様の意見を参考にして、お決めいただければと存じます。
なお、今回、法定相続分に応じた登記をした場合には、ご質問者様が相続前から保有していた持ち分割合を含めますと、過半数の持ち分を有することになりますので、この点、特に問題は発生しないとも考えます。
【総括】
上記の手続きの大前提は、妹様とトラブルにならないような取り決めがあってこそ成り立ちます。
何よりも大切な妹様との話し合い(1.相続に関する分割協議、2.賃貸を想定した場合、家賃の分配協議)を最優先にして、今後の手続きをお決めいただければと存じます。
回答になりましたでしょうか?精神的に辛い状況かと存じますが、円満な手続きを進めてくださいね。
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却|初めての相談はファイア・ワーカーズ ⇒ http://fireworkers.jp/
(現在のポイント:2pt)
![]()
「相続登記」に関するまとめ
-
相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!
相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング





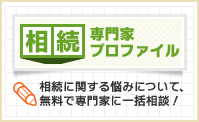





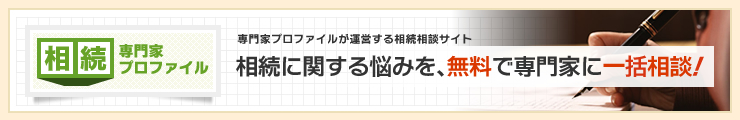
 専門家
専門家




