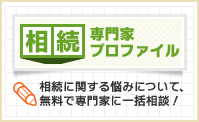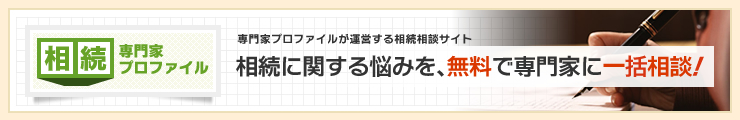対象:遺産相続
はじめまして、色々悩むことが多くご相談させていただきます。
家族構成は父・母・私(長女)私の子・妹(次女)の5人で暮らしています
私の子は結婚離婚後に親権を得て一緒に生活しています。
(土地・家ともに父と母半分ずつの名義です)
父母共に病気持ちです
私の親の理想は、自分たち両親が亡くなったら家を取り壊し姉妹それぞれ個別の家を建てて
生活して欲しいとの希望があります
しかしそれをあえて文書で(遺言)などには残すつもりは無いようです。
問題点
私(長女)の理想
・妹とは一緒に暮らしたくない(妹の生活が派手すぎてやりくりに困るため)
・今の土地で家を建て直すことに賛成
・今の家の資産の金額の半分を妹に渡して生活を別にしても良いが(妹に家を譲ってもらう)子どもと二人で住むには大きすぎるのでそれは嫌(固定資産など色々な面で小さい家でも十分)
妹(次女)の理想
・親が残してくれた家に居座りたい(と言うか居座る!と言っています)
・今の土地を半分にして家を建てるのは面倒だし建て直す貯金がない
・家を出ていくつもりはない
・財産分与はしっかり半分欲しい
財産分与でもめたときに調停で話合いをすると聞きました
話がもめた時には家を売って出来たお金を姉妹で均等に分けるときいたことがあるのですが
そうなる前に出来ることはないでしょうか?
また今私の手取り12万円で子どもを扶養していますが、妹は手取り20万円です
私は家に6万、妹は「お金がない」と2万円しか入れずによく遊びに行きます。
ここの点も財産分与に考慮して欲しいのですが
(今私は生活がカツカツ、扶養出来る条件にある妹に扶養しようとする行為がない、父の病院通いに協力しない)
など最近ちょっと精神的にも疲れていて
将来の不安もあり事前の対策が出来ればと思うのでアドバイスお願い致します
両親健在のことでこんな質問はと思いますが
勝手な行動に母は私と子どもが一番良い形になるようにと思ってくれています
(だからと言って遺言書を書くほどの行動は起こしてくれないようです)
親の扶養は当たり前だと思う私の考えと遊びに使いたいと思う妹の意見の食い違い
出来れば財産分与でもその辺りを少しでも融通して頂けたらと思うのですが無理でしょうか
アドバイスお願い致します
aiaiai32000さん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
1
![]()
審判での解決になるかもしれません
弁護士の松野絵里子です。
簡単にポイントを回答しますね。
仮にご両親がなくなった場合、お二人でその不動産を相続する状態になるとおもわれますが、遺言がなければ互いに半分が法定相続分になります。なにもしないと単に土地建物が共有になってしまうだけです。財産を分割するには合意して遺産分割協議書を作成するか、その合意ができないなら遺産分割調停をすることになります。調停は、たとえば貴方が妹さんを相手にして申し立てます。弁護士に依頼すれば貴方の利益を保護して調停に一緒に行ってくれますので安心ですが、費用がかかってしまいます。調停では、調停委員が事情を聞き、必要に応じて資料等を提出し裁判官がそれを見たり、必要なら鑑定をして不動産価格などを明らかにしていきます。各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかを明確にして、みんなが合意できる解決案をだしてくれ、話合いでまとめようとします。これでも話合いがまとまらないと、調停不成立となります。そして、審判手続というものになり(遅くともこの時点では通常は弁護士はつけています。)、裁判官が、遺産となっている財産や、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判と呼ばれる判断をします。そこで例えば貴方が妹さんの相続分に相当する現金を払うという主張をすればそれが通る可能性はあります。もちろんその現金がそこで用意できないといけませんが。そして、単独の所有になった土地を分筆して半分売って残りに家を建てるなども可能かもしれませんね。もっとも、相続税がありうるのでそれには注意してください。
なお、貴方が多くの金額を家に入れているという点は、寄与分という制度で考慮されます。相続された人の財産の維持、増加に特別の寄与をしたひとが相続人にいる場合で、その人が通常の家族間の相互扶助の域を超えた特別の行為をしていた場合です。これにもいろいろなパターンがありますが、給料などの収入などから亡くなった人の支出を減少させた結果として相続財産の維持・増加に貢献したような場合もあります。あなたの場合、6万円が貴方と子の食費程度であるともいえ、相続財産の維持・増加に寄与したといえるかは、具体的にはわからない気がいたしますが、主張することはできますので、記録をきちんととっておくとよいでしょう。
補足
当事務所では、相続のご相談も受け付けています。
事務所のHPはこちらです。 http://ben5.jp
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング