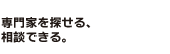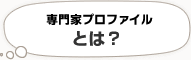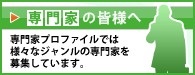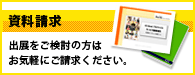- 大澤 眞知子
- Super World Club 代表
- カナダ留学・クリティカルシンキング専門家
PodCast[『迷子になった日本の教育』日本の子供を救いたい]で日本の教育環境の異常さを話しました。
クリティカルシンキング思考法を見事に育てるカナダの教育を覗き見出来るStoryシリーズの3編目。
#1 The Best Part about School
#2 The Dance
さぁ「カナダの教育を覗いてみましょう」ストーリー。
地球温暖化による異常気象が目に見えるような大自然のカナダで、毎年激しくなるWildfire.
カナダに住むみんな、もちろん留学生にも大きな影響があります。
そして、学校制度にも。
州を越えると外国ほど違う高校教育制度を全く知ることもなし、興味もなしでカナダにやって来る日本人高校生。
また、なぜ友達が出来ないのかと葛藤し孤独に泣く日本人高校生。
今後の留学には、絶対知識として学ぶ必要のある、異常事態を舞台にしたカナダの現実が見えてくるストーリーです。
準備がもうすぐ完了する「カナダ式教育を日本で育ち日本の学校で学ぶ子供たちに(仮題)」のカリキュラムにも、どうしても取り入れたい瞬間をストーリーにしました。著者は、Robert McMillan。日本の生徒へのエッセイ指導の達人です。
_______________________________
The Wildfire
by Robert McMillan
(日本語訳は下にあります)
They arrived in the middle of the night. A drive of 700 kilometers, crossing a time zone, entering a new province. It had taken most of the day.
Rachel was wide awake until the last hour. Now her mom was reaching back, gently shaking her. “Wake up, Ray. We’re here.”
The house they faced had the porch light on, and a squadron of prairie insects buzzed about as if everything were normal. The other houses on the block were as dark as death.
The four travellers stepped quietly from the SUV. Their ears hummed in the silence of the night. It felt like their bones did, too. The steady noise and vibration from their vehicle would not let them go. The late August night was cool and comfortable, but they hardly noticed. They were dazed. The house would have looked comfortingly familiar had the circumstances been different.
Rachel yawned. She was tired but felt a pent-up energy in her young legs. She had been confined in a tight space for too long, they all had been, and she wanted to run into the dark of night and unleash a wild scream. Then the front door swung open and out streamed her aunt, uncle and two cousins.
Rachel’s cousin and childhood friend Abby rushed straight to her and wrapped her arms around her tightly. Abby was more full-bodied than last they met, and Rachel felt she was hugging a grown woman. Then Rachel did what she did not want to – she cried. In the warmth of Abby’s embrace. Abby patted her back and soothingly repeated, “Hey, hey. Hey, hey…” Meaningless words full of meaning.
Abby’s brother Liam looked on. He wondered whether he too would cry if he were about to lose his home. He was pretty sure he wouldn’t, he decided, after observing his cousin Rachel.
Abby caught him staring and glared as only a sibling does. “Get the bags, Liam,” she ordered. Liam’s eyes darted about as if he had been looking for them the whole time.
Then Abby greeted the slim Asian girl with shiny black hair, “Hi! I’ve heard about you. I’m Abby.”
“Hi, I’m Rin,” said the girl.
“Dean?”
“No, no. Rin.”
Abby looked at Rachel once and back at Rin, “Reene as in Irene?”
“Rin” said Rin, a slight exasperation flashing across her face.
Abby threw a loving arm over her shoulder. “Welcome, Reene. I’ll have to practice that name now that you are here. I love your hair, by the way.”
The adults were off to the side, speaking in murmurs.
“So you made it ok? We were watching the news and…”
“Yeah, yeah… slow going.. everyone getting out… musta past three fires.”
“I can’t imagine.”
“Push forward… all you can do.” Rachel’s father spoke tersely, as though saving his family from a wildfire had punched the words out of him.
“Well, you know we don’t have a big place, but our house is yours. Stay as long as you want.”
Rachel’s mom teared up, “Thank you. We don’t want to burden…”
“Don’t be silly. You’d do the same. Come on in, the rooms are ready. Are you hungry?”
The Mulligans lived in an old, two story home, with the kids’ bedrooms upstairs. Abby had the bigger room; the older child’s privilege. It was rectangular and had high ceilings. The walls were a pretty eggshell blue. The only eyesore was the huge dark brown knot pillow on the floor between Abby’s bed and study desk. It was so comfy that its jarring colour was forgiven.
Liam lugged Rin’s suitcases up the narrow stairway one at a time, depositing them in Abby’s room. When he returned with Rachel’s bag, the three girls were already settled – Abby and Rin sprawled on the huge knot pillow, and Rachel lying on her tummy on Abby’s bed, her chin in her hands, legs bent up at the knees. Unlike his sister’s long blonde hair, Rachel’s was brownish and short, and she looked more athletic than Liam remembered. He somehow thought of a wild animal.
When Rachel saw her bag, her lips began to quiver. “We were only allowed one bag, and I couldn’t fit Beanie in…” she said, wiping her eyes on the sleeve of her hoodie.
Abby was touched. Rachel had won the stuffed doll at a rodeo midway years ago when visiting Abby. It was a dog with a funky beanie – thus the name “Beanie” – and when they were kids, they worked out their differences by speaking to the dog instead of directly to each other.
“Ray, the important thing is that you are here. Beanie is us, he always will be,” Abby said, and was shocked at how much she sounded like her mother.
Then she caught Liam staring again. “Thank you Liam, you can go now.”
“No, let him stay, Ab,” Rachel said, “I don’t get to see him much. Come here, Liam, give us a hug,” she said, propping herself up off the bed and stretching out her arms.
Liam didn’t like hugging his cousins and aunts, but he wanted to stay and listen to the older kids and knew that was the price of admission. Rachel picked him up, squeezed him tight, then swung him round, growling like a bear, which made him giggle.
“Lucky you, Reene. You’ve got two bags,” observed Abby.
“She just arrived from Japan two days ago, poor thing, and that’s all she’s got,” Rachel explained, plopping down Liam and mussing up his hair.
Then Abby asked Rin what it’s like in Japan, and Rin said, “Good,” and Abby said that she would like to go to Japan someday, where would Rin recommend, and Rin thought for a moment and said, “Kyoto,” and Abby asked why, so Rin said, “Temples,” and Abby said she was more into manga than temples, and Rin said, “Yeah,” and laughed, and their conversation ended.
“So Abby,” said Rachel, “I heard you were working at the grocery store this summer?” Rachel was back on the bed again while Liam hunkered down in Abby’s chair by the desk.
“Yeah, that’s right. I worked the cash register. How would you like to pay?” she asked in her firm-but-friendly grocery-store voice, and Rachel laughed.
“That’s dope. You heard I was a lifeguard?”
“Ye~ah, that’s hella cool. I’m packing rhubarb into bags and you’re at the lake. We don’t even have a river here.”
“Yeah, but that’s all gone now,” Rachel lamented. “What am I going to do if our house burns down, Ab?”
“Then you are going to live here. With me. And Liam the freak.”
Liam stuck out his tongue and blew her a raspberry.
Rin looked at Abby and thought, “What about me?” but couldn’t vocalize it.
Abby seemed to notice. “You come, too, Reene,” she said, and immediately feared she had spoken too soon. Rachel and her parents alone would pretty much fill their home. She looked back to Rachel and said, “But your house will be fine. It’s made to last. So what are you taking this semester anyway?” The girls were all entering grade 10 in a week, and Abby wanted to get Rachel’s mind off of her house.
“English, biology, PE and…, ew, math” Rachel answered.
“Ha ha. Are you doing dash one? Dash two?”
“What do you mean?”
The cousins were surprised to discover this difference in their schools. Abby had to decide in grade 10 whether or not to go to university, and if so, needed to take “dash one” courses. English 10-1, for instance. But Rachel did not have such a choice. She would simply take English 10.
The girls were unaware that these were provincial requirements. In a sprawling country like Canada, each province has its own education system suited to its people, history and geography. At times the provinces are more like countries.
Since Abby had good grades, she was aiming at university. Rachel was unsure.
Abby suddenly looked at Rin, “Hey, you want to be careful about your courses, Reene. There was a Japanese boy in our school named Daiki who took dash-two courses, and two months before graduation, found out he couldn’t get into university. He graduated. But he couldn’t go to university. Was he ever pissed off.”
Rin’s eyes widened with fear.
“Where is he now?” asked Rachel.
“Last I heard he was headed to college to take grade 12 dash-one courses. But it’ll probably set him back a year.”
Rin pulled her schedule up on her smartphone and showed it to Abby and Rachel. “I take English, PE, home ec, science.”
“Hey I know those courses,” Rachel said. “You said you came to Canada to speak English with Canadians, right Rin?”
Rin nodded emphatically, “Yes.”
“That English and science are for international students. There aren’t any Canadians in them.”
“Eh?!”
“Last year there were a lot of Chinese and Indians. A bunch of Korean kids. A few Japanese. I had science in the same classroom after theirs and used to see them come out.”
Rin looked shocked.
“But you can meet Canadians in PE and home ec, right? And you’ll see them in the halls,” Abby said in consolation.
“Maybe in PE,” Rachel added. “But home ec is full of international students. I heard it’s an easy credit while they build up their English.”
Rin now had conflicted feelings. She wondered if she should have chosen a different school and if it were too late to change. Her host sister Rachel’s emotions were sometimes exhausting, but her host family seemed nice, so maybe she should stay. But now their home may be lost to wildfire.
And she was struggling to understand these two cousins who had known each other all their lives and had so many things to talk about. Rin had thought her English was better. It was her best subject at school back in Japan. Now she had serious concerns about her ability to communicate with Canadians.
It was all very stressful. While the wildfires roared, her destiny was intertwined with that of her hosts. She decided there was nothing to do but go with the flow. The way she jumped into the SUV when they told her, took the harrowing drive past burning hills, breathed in smoky air, travelled hours and hours through forests and mountains, finally arriving on a flat prairie where she had yet to see the daylight, and in a different home, waiting. There was nothing she could do but wait.
Then they heard the adults speaking downstairs. “The vent!” remembered Rachel.
In this old home, there was a large, square vent in Abby’s bedroom floor that allowed the heat to circulate between floors. It was large enough for the kids to crouch near and eavesdrop on their parents. Rachel and Abby had enjoyed “spying” for years, since they were little children.
The four kids gathered around the vent, lying on the floor looking down, careful not to make a noise.
“The fire broke over the ridge to the west… we could feel the heat… that’s when we got the call… had to leave in 30 minutes… good thing we had bags packed… no idea if it will reach our home… there’s a chance we’ll get lucky…” said Rachel’s father Raymond.
“We’ve got insurance,” added Rachel’s mother, Olivia, “but everything is so expensive now. I don’t even know if we can afford to rebuild.”
“We gotta keep paying mortgage… but rent costs an arm and a leg…,” Raymond looked at Olivia, “maybe we could borrow an RV… stay on our property… save costs.”
“Where would Rin stay? I think a homestay family needs a home.”
“Well,” said Jeff, Abby’s father, “you know you can stay here as long as you want. The school in town is understanding. They’d let Rachel in if we explained. Not sure about Rin, though,” he added, looking at his wife.
Becky nodded in agreement. “They’re pretty good. They take international students. We can always ask. I suppose you’ll need to talk to Rin’s parents and see what they want.”
“Not much we can decide now… till we know more about the house,” said Raymond. “It’s a waiting game.”
Rachel pulled away from the vent with a glazed look in her eyes. And Rin asked Abby, “I go to school here?”
“... No, we don’t know yet, Reene. It all depends on what happens. We’ve gotta wait.”
The girls did not sleep much that night. Abby and Rachel shared the bed while Rin slept on a foamie on the floor; a common occurrence at a Canadian home full of guests. The foamie was comfortable enough, but Rin found it ironic to sleep on the floor when she did not do so in Japan where it was tradition. Now here she was, far from home, sleeping on the floor in a house full of strangers, wondering if she would have a home to return to.
At one point, she thought she heard Rachel sob quite loudly, and then Abby’s voice, “Shh, shh, …”. Once she got up for the washroom and saw Abby with her arms wrapped tightly around Rachel. They were both asleep, and this struck her as rather odd. “I couldn’t hug my homestay sister like that,” she thought.
The call came in around 9:00 a.m. The winds had changed direction. Their house was spared. They were not yet allowed back, but their home was no longer in danger.
The wind had shifted so suddenly, however, that they couldn’t save the school. It burned to the ground.
Now the entire house is awake. Olivia, Rachel’s mom, has been calling her neighbours to check on their safety and inquire about schooling. She can’t reach the school board – she gets a recorded message confirming the loss: “We are doing everything we can to make alternative arrangements.”
There are rumours that the children will be bused to a nearby school 30 minutes away. But that school is nearly full, and with little room for local students, may not accept international ones. “Portable classrooms,” says one of her friends, referring to the one-room classes notorious for poor ventilation, bad smells and tight spaces. “Our kids will all be crammed into portable classrooms.”
Raymond, Rachel’s father, is searching the internet for news and ideas.
Rin has informed her mother but can’t reach her agent. She has left him three messages and is starting to worry. His homepage says nothing about the fire.
Abby is on social media to see if Rachel and Rin could attend her school, just in case. After all, it is only a week until school begins.
Their online activity has put a stain on the rural wifi, and everyone is struggling to get information.
It was all too much for Rachel. She went for a jog an hour ago and hasn’t returned.
_________________________________________________
The Wildfire
(translated by Machiko Osawa)
着いたのは真夜中だった。700キロを車で走り、異なるタイムゾーンに入り(*カナダには6つのタイムゾーンがあります)新しい州に来た。ほぼ一日かかったドライブ。
最終の1時間前までRachelは目が冴えていた。とうとう眠ってしまったRachelを母親が腕を伸ばし、やさしく揺り起こした。「着いたよ。」
着いた家には明かりの灯ったポーチがあり、大平原に住む虫の戦隊がまるで何事もなかったかのようにブイブイ、コロコロ、ヒリヒリと鳴いていた。同じブロックにある他の家はまだ死んだように暗かった。
4人の旅人はSUVからそぉ〜っと降り立った。夜の静寂がうるさく感じられた。骨までが静寂に反応していた。ほぼ一日続いた車中での絶え間ない音と振動が身体中から離れなかった。8月終わりの夜は涼しく心地よかったが、それに気づくことさえ出来なかった。放心状態でぼ〜っとしていた。もし、全く違う目的でここに来たとしたら、その着いた家からはほっとするような親しみを感じたはずだけど。
Rachelはあくびをした。疲れ切っていたが、若い足にはエネルギーが鬱積しているように感じた。狭い車に長い間閉じ込められた後は、夜の暗闇の中に走り込み動物のように吠えてみたいと思った。
Rachelのいとこでもあり、子供時代からの友達でもあるAbbyがまっすぐRachelに走りより、きつくRachelを抱きしめた。Abbyは、前に会ったときより、大人になり肉付きがよくなったと、Rachelは感じた。大人の女性を抱いているようだった。そして、Rachelは絶対したくなかったことをやってしまった。泣いた。Abbyの抱擁の暖かさの中で。AbbyはRachelの背中をなで、なだめるように何度も言った。「ほら、ほらね、ほらほら、ほら。」意味のない言葉だけど実は意味がいっぱい。
Abbyの弟Liamが側で見ていた。もし自分も家を失いかけたとしたら泣くかなと思った。いやぁ、泣かないなと自信があった、いや、そう決心した。いとこのRachelが泣くのを見て。
Liamが見つめているのに気がついたAbbyは兄弟特有の睨みをきかせ、指示した。「荷物持って行って、Liam」実はずっと荷物を探していたんだよと言うように、Liamの目は泳ぐように周りをキョロキョロ見た。
それからAbbyは黒髪でほっそりしたアジア人の少女に挨拶した。「Hi! あなたのこと聞いてるわよ。私はAbby.」
「Hi. 私はRin.」とその少女。
「Dean?」
「違う違う、Rin。」
Abbyは一度Rachelに目をやり、もう一度Rinに聞いた。「Ireneの発音に近いReene?」
(*日本人の名前は英語で発音すると全く違うものになることが多いです。ローマ字読みでは通じないことも知っておいてください。)
AbbyはRinの肩にやさしく腕を回した。「ようこそ、Reene. あなたの名前の言い方を練習しなくちゃね。ところで、きれいな髪ね。」
大人たちは横の方に固まり、何やらボソボソ話していた。
「で、無事に来れてよかったね。ニュースをずっと見ていて。。。。」
「いやぁそうそう。。。なかなか進めなくて。。。みんな逃げようとしていたから。。。途中で3箇所燃えていたし。」
「想像も出来ない。」
「とにかく進むこと。。。これしかなかった。」Rachelの父親がそっけなく言った。火事の中を家族を連れて逃げるストレスから、言葉の使い方を忘れてしまったかのように。
「ねぇ、この家は大きくはないけど、自分の家と思って。必要な限りここにいてもいいからね。」、
Rachelの母親は目に涙をためて、「ありがとう。面倒かけたくないけど。。。」
「馬鹿なこと言わないで。境遇が逆なら同じことするでしょう?さぁ、入って、部屋の用意は出来てるから。お腹すいてる?」
Mulligan家は古い2階建ての家に住み、子供の部屋は2階にあった。Abbyは大きな方の部屋、それは年上の特権。その部屋は長方形で天井が高い。壁はおしゃれにくすんだ水色。ちょっとだけ場違いなのはAbbyのベッドと勉強机の間に置かれた超デカのこげ茶色のknot pillow(結び目クッション)。ものすごく座り心地がいいので、その不快な色もまぁ許せる。
Liamは狭い階段を苦労しながらRinのスーツケースを1つづつ運び、それをAbbyの部屋に入れた。Rachelのかばんを運んで部屋に戻ると、3人の少女はすでに自分の場所を見つけていた。AbbyとRinは超デカのknot pillowの上に寝そべり、RachelはAbbyのベッドの上で、手であごを抱え、膝を曲げて腹ばいになっていた。Abbyの長い金髪とは異なり、Rachelのは茶色で短く、Liamが覚えているより運動選手っぽく見えた。何か野生動物のことを思い出した。
自分のかばんを見たRachelの唇が震えた。「たったひとつのカバンしか持ち出せなかったの。だからBeanieを入れられなかった。。。」と言い、パーカーの袖で涙をぬぐった。
Abbyはジーンとした。数年前、Abbyの所に来ていたRachelはロデオ大会の出店でぬいぐるみを当てた。いけてるニット帽をかぶった犬のぬいぐるみだったので、名前をBeanieにした。2人が子供だった頃、お互いの違いをそのまま相手にぶつけるのではなく、代わりにその犬に話すことで解決したものだった。
「Ray、あなたがここにたどり着いたことが大切なこと。Beanieは私達そのもの、そして彼はいつまでも私達」とAbby が言った。自分の母親とすごく似た口調を使っていることにショックを受けながら。
そして、Liamがまた見つめているのに気がついた。「ありがとうLiam。もう行っていいよ。」
「いえいえ、ここにいさせてあげて、Ab。」とRachel。「Liamに会うことってそんなにないから。Liam、ここにおいでよ。みんなをハグして。」ベッドから起き上がり、腕を前に伸ばしながらRachelが言った。
Liamはいとこや大人たちをハグすることは好きではなかったけど、そこにいてみんなが言うことを聞いていたかったし、我慢してハグすることでそれが許可されるんだと思った。RachelはLiamを抱き上げ、きつく抱きしめ、ゆらゆら振り回し、熊みたいな唸り声を出し、Liamをクスクス笑わせた。
「良かったね、Reene。2つもカバンを持って来れた。」カバンを見てAbbyが言った。
「2日前に日本から来たところで、可哀想に、その2つのカバンが彼女の持ち物すべて。」Rachelはポンと降ろしたLiamの髪をグチャグチャにしながら説明した。
AbbyはRinに日本てどんな所かと聞き、Rinはこう言った、「いい。」そして、Abbyはいつか日本に行きたいと思っているので、どこがお勧めかと聞いた。Rinはちょっと考えて言った。
「京都。」Abbyはなぜかと聞き、Rinは「お寺。」そしてAbbyは自分はお寺より漫画向きだと言い、Rinは「Yeah.」答え、笑った。そこで2人の会話は終わった。
(*これが日本人留学生の典型的な英語の話し方です。話す内容がなく、文章で話すわけでもなく、単に単語を発するだけ。困るとなぜか『笑う』ことが多いです。)
「で、Abby。」とRachel。「この夏休み、食料品店で働いたって聞いたけど?」Rachelはベッドに戻り、Liamは机の側のAbbyの椅子にうずくまっていた。
「ええ、そうなのよね。レジの仕事をしてたの。『お支払い方法は?』」型にはまっているけど親しみを込めた食料品店用の声で聞き、Rachelが笑った。
「やばいね、それ。私がライフガードをしてたの聞いた?」
「聞いたよ〜、めっちゃかっこいい。私がルバーブを袋に詰めている時に、あなたは湖にいたんだ!ここには川さえないからね。」
「そうだけど、全部なくなってしまった。」とRachelが嘆いた。「もし家が焼け落ちてしまったらどうしたらいい、Ab?」
「そしたらあなたはここに住むのよ。私と一緒に。そして変わり者のLiamともね。」
Liamは舌を突き出し、べ〜と口を鳴らした。
RinはAbbyを見て思った、「私はどうなるの?」でも声には出せなかった。
Abbyは気がついたように、「あなたも来ていいよ、Reene。」と言ったすぐさま、せっかちに誘いすぎかなと心配になった。Rachelとその両親だけでも家はいっぱいになるのに。後ろを向いてRachelを見て言った、「でも、あなたの家は大丈夫。長持ちするように作られているから。で、今学期は何を取るの?」少女たちはみなGrade10になる、一週間後に。AbbyはRachelに家のことから気持ちを逸してほしかった。
「English, 生物、PEと。。。ええっと、数学。」Rachelが答えた。
「はは、−1それとも、−2?」
「どういう意味?」
「いとこたちは学校の違いを発見し驚いた。AbbyはGrade10で大学に行くのか行かないのかを決めないといけなかった。もし大学に行くなら『−1』を取る必要がある。例えばEN10−1。でも、Rachelにはそんな選択はなかった。ただ単にEnglish10を取るだけ。
少女たちは、カナダでは州により規定が違うことを知らなかった。カナダのように広大に広がる国では、各州ごとにその地域に住む人や歴史、地理的要因に適した教育制度を持っている。時には各州はまるで外国ほど異なる。
Abbyは成績が良かったので大学を目指している。Rachelはまだよくわからない。
突然、AbbyがRinを見た、「ねぇ、コース決める時には気をつけてね、Reene. 私の学校にDaikiという名の日本人の男の子がいて、『−2』のコースを取ってた。そして、卒業の2ヶ月前になってそれでは大学には行けないことがわかった。卒業はしたけど、大学進学資格のないコースだけで。ものすごく怒ってたよ。」
Rinの目が恐怖で大きくなった。
「そのDaikiって子、今どこにいるの?」Rachelが聞いた。
「最後に聞いた時には、確かGrade12の『−1』コースを取るためにカレッジに行こうとしているって。でも1年はかかってしまうね、うまく行ったとしても。」
Rinはスマホから学校の時間割を出し、AbbyとRachelに見せた。「English,PE,Home Ec, Science取る。」
(*このように、間違った文法を使う日本人留学生が非常に多いです。この場合は、現在形は間違いです。常に習慣として取っているという意味になり、これから取るという意味にはなりません。周りのNative Speakerは理解はしてくれますが、英語レベルはかなり低いとみなされます。)
「ねぇ、このコースが何か知ってるよ。」とRachelが言った。「カナダ人と英語が話したいからカナダに来たって言ったよね、そうだよね、Rin?」
熱烈に頷いたRinが「はい。」
「あなたの取ってる英語とサイエンスは留学生用のだね。カナダ人生徒はいないよ、そのクラスには。」
「え〜?!」
「去年は中国人とインド人が多かったね。韓国人生徒も。日本人はそれほど多くなかったかな。その留学生だけのサイエンスコースの後、カナダの生徒が取ってる授業が同じ教室であったから知ってるよ。その教室から留学生がぞろぞろ出てきたからね。」
Rinは衝撃を受けたように見えた。
「でも、PEとHome Ec(家庭科)のクラスではカナダ人生徒と会えるかもよ、ね?学校の廊下でも。」慰めようとしてAbbyが言った。
「PEなら多分ね。」とRachelが付け加えた。「でも、Home Ecは留学生でいっぱい。英語が出来ないので、Home Ecのような簡単な単位を取るためだと聞いたよ。」
Rinは混乱した。違う学校を選んだほうがよかったのかも、そしてもしコースを変えるのに間に合わなかったらと、迷い始めた。ホストシスターのRachelは感情的で時には一緒にいてつかれる、でもホストファミリーはいい人みたいだし、だから、多分その学校にいたほうがいいし。でも、今そのホストの家は火事でなくなるかも知れないし。
そして、Rinはこの2人のいとこと話すことに大苦労していた。彼女たちは小さな時からずっとよくお互いを知っているし、たくさんの共通の話題もある。Rinは自分の英語力はもっと高いと思っていた。日本の学校では一番英語の成績が良かったから。でも、今は自分のコミュニケーション能力を深刻に心配していた。
すべてがストレスになった。火災が荒れ狂っている間、留学生であるRinの運命はホストの運命でもあった。何も自分にはできることがないと、流れに任せることにした。言われるままSUVに飛び乗って、悲惨に燃え盛る丘を超え、もうもうと立ち込める煙を吸い込み、何時間も何時間も森や山を抜け、やっと真っ平らな大平原に着き、夜が終わり、朝の陽を見て、違う家で、待っているだけ。待つ以外、何もできることはない。
それから、子供たちは大人が階下で話しているのを聞いた。「換気口!」とRachelが思い出した。
古い家には、大きくて四角い換気口がある。Abbyの部屋の床にも。床を通して暖気が還流するのを助けるためにの換気口。大きいので、子供がうずくまって大人の話に聞き耳を立てることができる。RachelとAbbyは小さな時から何年もこうやって「スパイ」して来た。
4人の子供は換気口の周りに集まり、床に腹ばいになり、見下ろした。音を立てないように気をつけながら。
「西への尾根で火事が起こり。。。熱を感じた。。。その時だよ、電話が来たのは。。。30分で避難するようにと。。。荷物を詰めておいえよかった。。。自分の家にまで火が回るなんて思いもしなかった。。。もしかしたらチャンスはあるかも。。。」と、Rachelの父親のRaymond。
「保険があるから。」とRachelの母親のOliviaが付け加えた。「でも、今何でもものすごく高いから。再建するのに十分かどうかもわからない。」
「住宅ローンは払い続けないといけないし。。。賃貸は高すぎる。。。」RaymondはOliviaを見た。「RVでも借りて。。。燃えてしまった家の跡において。。。費用を抑えて。」
「Rinはどこにステイするの? 家のないホストファミリーなんてないよね。」
「そうだね。」とAbbyの父親のJeffが言った。「あのね、いつまででもここにいていいよ。この町の学校も理解してくれるはず。説明したらRachelは入れてくれると思う。Rinのことはわからないけど。」と妻を見ながら付け加えた。
Beckyは賛同して頷いた。「ここの学校は結構いいわよ。留学生もいるしね。聞いてみないとわからない。まずはRinの両親と話して、何がしたいか聞くことが必要だと思うわ。」
「今ここで決めれることはないね。。。家の運命がわかるまでは。」とRaymond.「待つだけだね。」
Rachelはとろんとした目で換気口から起き上がった。そしてRinはAbbyに聞いた。「私、ここの学校に行ってるですか?」
(*またしても間違った現在形ですので、このような意味になります。)
「。。。いや、まだわからない、Reene. 何がこれから起こるかにかかってる。待つしかない。」
少女たちはその夜余り眠れなかった。AbbyとRachelは一緒のベッドで、Rinは床に敷いたマットレスで。客が多い時には、カナダの家でよく見られる光景。マットレスは寝心地はいいけど、皮肉だなと思った。日本は床で寝るのが伝統だったけど、自分は日本では床では寝たことがないから。今、このカナダで床で寝てる、故郷から遠く離れて、知らない人だらけの家の床で、帰る家があるかどうかもわからないままで。
「ある時点で、RinはRachelがかなり大きな泣き声を出しているのを聞いた気がした。そして、Abbyの声も。「大丈夫、大丈夫。。。」 一度トイレに起きた時には、Abby がRachelを腕できつく包み込んでいるのを見た。2人とも眠っていた、そして何か不思議な気がした。「私はホストシスターをあんな風にはハグ出来ないな。」とRinは思った。
電話が午前9時ごろに来た。風向きが変わったと。家は救われた。まだ帰るのは許可されていないけど、家はもう火事の危機から逃れたと。
風は突然変化した、しかし、学校を救うことは出来なかった。学校は消失した。
さぁ、家中が起きてきた。Rachelの母親のOlliviaはずっと電話をかけ続け、隣人たちの安否を尋ね、学校のことを聞いていた。地区の教育委員会には通じなかった。消失したとの確認メッセージが流れるだけ。「代替の段取りをするために出来うるすべてのことをやっています。」と。
「30分離れた近くの町の学校までバスで通うという噂も出ていた。しかし、その学校もほぼ満員で、地元の生徒にもほとんど席がないので、留学生は受入れないだろう。「ポータブル教室」と、電話口でOliviaの友達が口走った。一部屋だけの間に合わせ教室、換気が悪いことで悪名高く、悪臭がし、狭い。「子どもたちはみんなポータブルに押し込まれるか。」
Rachelの父親のRaymondは、ニュースや新しいアイディアをネットで探していた。
Rinは日本の親に何が起こっているかを知らせたが、カナダに来るのを手伝ったエージェントには連絡がつかなかった。3つもメッセージを残したけど何も返って来ないので、心配になり始めた。エージェントのホームページには、火事のことなど何も書いていなかった。
AbbyはSocial Mediaで調べてみた。RachelとRinが自分の学校に入れるかどうか、もしもの場合に。新学期があと1週間で始まるから。
田舎の遅いWiFiのせいで、みんなのネット検索が滞った。みんな情報を求めてもがいている。
全部もうどうでもいい、耐えきれないと、Rachelは思い、1時間前にジョギングに出かけ、まだ帰って来ていない。
______________________
このストーリーは、何も知らずにカナダ高校留学してしまった日本人高校生を見事に表現しています。
英語で満足にコミュニケーションも取れない、自分のいる高校の制度すら知らない、カナダの同年代の話には絶対入って行けない、「迷子」そのものが日本人高校留学生です。
Watch Out!
カナダをよく知ってから カナダにいらっしゃい!
_____________________
Canada News for You (留学に必須の最新カナダ情報)
「カナダ大学留学への特訓方法」eBook
カナダからの特別オンラインレッスン Canada Club
「カナダ高校留学実態総集編」eBook
カナダから日本人のための本格的英語学習サイト UX English
Podcast [カナダにいらっしゃい!]
 このコラムの執筆専門家
このコラムの執筆専門家

- 大澤 眞知子
- (カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
- Super World Club 代表
カナダにいらっしゃい!
カナダ 在住。パンデミック後のNew Normal 留学をサポート。変わってしまった留学への強力な準備として UX English主催。[Essay Basics] [Critical Thinking] など。カナダから日本に向けての本格的オンライン留学準備レッスン・カナダクラブ運営。
 「迷子になった日本の教育」のコラム
「迷子になった日本の教育」のコラム
Bilingual Education for「日本で育つ子供へ」Trial report - Canada News for You(2024/03/31 04:03)
日本で育つ子供をBilingualに:Trialレポート(3-29-2024)(2024/03/30 06:03)
Bilingual Education fm Canada : Trial 参加者募集(2024/02/24 14:02)
日本の中学受験狂乱と英語イマージョンの大罪(2024/02/21 11:02)
日本で育つ子供へのバイリンガル教育: Trial 参加者募集(2024/02/18 04:02)
このコラムに類似したコラム
My Cabin Life Canada 7/25/2023 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/07/26 06:19)
The Best Part about School: カナダの教育を覗いてみましょう 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/06/23 08:19)
Bilingual Education for「日本で育つ子供へ」Trial report - Canada News for You 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2024/03/31 04:13)
Bilingual Education fm Canada : Trial 参加者募集 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2024/02/24 14:44)
Creative Thinkingを日本の子供に:迷子になった日本の教育 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/12/30 05:51)