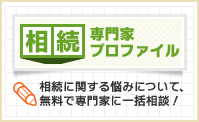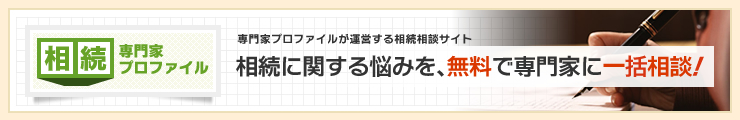対象:遺産相続
遺産相続の事で教えて頂きたい事があります。
認知症の伯母(独身)が亡くなり、相続人は直系の兄弟姉妹3人と代襲相続人が3人です。 伯母は一人暮らしでしたが、認知症が出てきたため、母(伯母の妹)と母の娘の私とで、週1回、伯母の家に介護しに、通っていました。後の日はヘルパーに来てもらっていました。伯母が亡くなるまでの4年間、2人で介護しました。
遺言書はありませんが、遺産の事で代襲相続人に連絡すると、家裁に申し立てたので、すべて弁護士に任せてあると、言われました。
1回目の調停は終わったのですが、伯母から、生前、私に介護してもらっているお礼にと、300万円、もらい受けたお金の事で、代襲相続人の弁護士から、伯母は認知だたので、意思能力があったのか聞いてきました
伯母は、私が介護に行き欠けた頃から、何回も介護のお金を取っておいて、と言ってくれていたので、亡くなる1年前に伯母の承諾を得てATMから、お金を引き出しました。
その時に母や兄弟姉妹には、承諾は得ています。
生前、認知症があった伯母から、もらい受けたお金は、代襲相続人が認めなければ、
返さないといけないのでしょうか。
伯母は、貯金通帳にすごく執着があり、亡くなる1か月前まで、自分で持っていました、確かに認知はありましたが、まだ意思能力はありました。
代襲相続人が希望している、法定相続分での分割は承知しています
私達側は、弁護士をたてていないので、不安です
お手数ですが、ご回答、宜しくお願い致します。
banana45さん ( 大阪府 / 女性 / 53歳 )
回答:1件

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
![]()
認知症患者が全て判断能力がないとは言えません
banana45さん 初めまして、
結論から申しますと、「認知症」を患っていると判断能力がないとは言い切れません。現になくなる1ヵ月前まで、預金通帳をご自分で管理されていたようですので、決して財産管理能力が損なわれていたとは考えられません。
また、300万円を引き出す際に、ご兄弟たちの承諾を得ているとのこと。ただ、今回の問題のように、そのご兄弟がなくなりお孫さんたちが問題提起している点ですね。
整理してみますと、1)認知症の程度がどうだったか(医師の診断があり判断能力を否定されていたかどうか等) 2)300万円をいただく時にご兄弟の承諾を得ているが、これが証明できるものがあるかどうか
認知症になった人あるいは判断能力が失われた人の財産管理等については、成年後見制度があります。判断能力の程度により、補助・保佐・後見というように3段階に分かれます。
判断能力がどこまでありどの段階になるかは、医師による診断書が必要になり、診断書に基づき家庭裁判所うが決定します。
つまり、認知症患者が全て判断能力がないわけではありません。第1回目の調停が終了したようですが、認知症の症状については、あくまで1ヶ月前までご自分で管理されていたことを強調し、財産管理能力が十分あったことを伝えることが大事です。
また、ご兄弟の承諾については、多分なんの証拠もないと思いますので、事実を訴えるしかないと思います。お母さんも同席していたようですので、お母さんに助け舟を借りるしかないですね。いずれにしても、先方の弁護士さんも、伯母が既になくなっているため認知症の診断はできません。医師の協力を得て状況を証明してもらうことになるかと思いますが、裁判所の判断が気になりますが、特に不安になることはありません。ご自分が経験したことをそのまま伝えれば良いことです。
300万円については「贈与税」の対象になるため、税務署に申告しておくこともひとつの手かもしれませんね。
評価・お礼
banana45さん
2013/05/10 15:10早々、のご回答ありがとうございました。
参考になり、少し不安も和らぎました
また、近い内に調停があります。
調停はお互いの話し合いの場所と聞きましたが、弁護士さんと、私達の話を聞いて、
調停委員の方が、認めるか、認めないを、決めるのですか
調停は弁護士さんより、調停委員の方のほうが、権限をもっているのでしょうか
すいません、もう一度、お願いします。
藤本 厚二
2013/05/10 20:28ご質問の通りです。
弁護士さんの役割は、法的な見地から依頼者に変わって返答する役割です。ですから調停委員がすべてのリーダーシップをとります。
しかし、決定はしません。いくつかの論点を指摘し、それを当事者がじっくり考え、お互いが納得のいく考え方になるところまで話し合いを通じ導くのが、調停委員の役目です。弁護士さんを立てないから不利になるということはありません。ただ、弁護士さんはそれを職業としているため、専門的に色々な手法を心得ております。依頼主を良くしようとするために依頼されたわけですから、当たり前ですよね。こちらの主張に対し、専門的な点をついて反論してきます。それにはビックリしなくて結構です。こちらとして主張することを堂々とすればよいことです。
調停委員さんは、できるだけお互いが冷静になって、話し合いができるような場を作ることが本来の役目です。調停委員の立場から判断を出すことはしません。話がうまくいかなければ、日を変えてもう一度開くことになるでしょう。それを繰り返し、どうしても合意を得られなければ、裁判ということになります。頑張ってくださいね。
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング