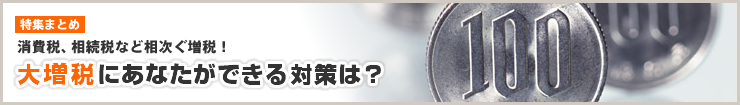対象:借金・債務整理
父と私で親子ローンを組んでいます。
私は昭和49年生まれの36歳会社員、父は昭和18年生まれ68歳自営業です。
平成11年に家を新築し、平成46年までの35年ローンで2900万円を借り入れたそうです。そうです・・・・というのは、完全なる私の未熟さゆえの汚点であることを認めた上で説明させていただくと、借入れ当時は私は25歳で父の言われるがままに契約書のようなものにサインをし実印を押印しました。当時の父からは、キャッシュで支払うことも可能だが、税金対策のために住宅ローンを組むと説明を受け、父が借り入れたものの保証人に私がなるということでした。当時は私は独身でしたのでその新築の家に住んでいました。
月日が流れ平成13年に結婚し、両親との同居を始めました。が、いわゆる嫁姑の問題等諸々があり、別居をすることになりました。別居したところ当然、いづれは自分たちの家を建てようとうことになりました。
前段が長くなりましたが、そのような状況で自分で住宅ローンを組もうと考え始めたところ下記のようなことが分かり、現在の状況では住宅ローンを組めないことが判明しました。分かったと言っても、両親は現在の住宅ローンについてはお前には金銭的な迷惑はかけないからと一切説明してくれません。
分かったこと
1.私は父の保証人になったのではなく、連帯債務者として、私自身も住宅ローンを組んでいる状態であること。
2.父と私の支払い割合があるらしく、どちらかが死亡した場合でもその死亡した者の割合分しか免除されないということ(団体信用保証?)
私としては、現在、自分で住宅ローンを組めないことはあきらめるとして(何か策があればご教授下さい)、将来父が死亡した際に、この家のローンの一切を引き継ぎたくありません。
いうなれば、この家も要りませんし、両親からの財産も何も一切要りません。(もちろん借金も引き継ぎたくありません。きっと借金しかないと思うので)
こういった場合、相続放棄をすれば良いのでしょうか。(相続放棄のメリットもデメリットもあまりよく分からないで聞いています。)
補足
2011/07/12 19:42長文かつ、的の違う2つの質問ですが、要するにご教授願いたいのは
A.現在の私の状況を確認するために、私ひとりで住宅ローンを組んでいる銀行に行って、上記のようなことを説明しすれば、借入れ状況、残額、借入れ割合、団体信用保証の有無などすべて教えてくれるのか。(父とそろって銀行に行かないと教えてもらえないと言う友人もいます。)
B.私自身が、住宅ローンを組むことは可能か
C.現状A、Bをあきらめて、数年後父が死亡した際、住宅ローンや、父の借金などの一切を私にかからないようにする方法があるか
の3点です。
現状を補足すると、もともと父の名義の土地に今の家を建てたので2900万円のローンの対象は建物のみです。また登記簿で確認したところ、土地は父名義、建物は父と私の50%ずつの登記となっており、土地、家とも銀行の第1抵当権が設定されているようです。また、この家のローンに関して、借り入れ当初より私自身1円たりとも支払ったことはありません。(父が、私の割合分も支払っているということだと思います・・・・・コレって本当はダメ?)
ちなみに私たち夫婦は両親からの別居後、この住宅ローンや父の借金の問題で両親とは絶縁状態で、家を含め、両親の財産なるものは一切要らないから、借金も一切要らないということで一致しています。
チャンプさん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

井手 誠博
行政書士
1
![]()
相続放棄だけでは弁済は免れません。
A.現在の私の状況を確認するために、私ひとりで住宅ローンを組んでいる銀行に行って、上記のようなことを説明しすれば、借入れ状況、残額、借入れ割合、団体信用保証の有無などすべて教えてくれるのか。(父とそろって銀行に行かないと教えてもらえないと言う友人もいます。)
あなた自身が債務者の一人ですから、残債の額や支払い状況などは教えてもらえるでしょう。しかし、父個人としての借入状況(個人信用情報)は開示してもらえないと思います。
あくまでも住宅ローン債権に関する情報のみです。
B.私自身が、住宅ローンを組むことは可能か
結論から申し上げれば不可能ではないと思います。
但し、相当な所得が必要と思われます。
C.現状A、Bをあきらめて、数年後父が死亡した際、住宅ローンや、父の借金などの一切を私にかからないようにする方法があるか
相続放棄をする意思があるようですが、父の権利義務を放棄するだけでは、あなた自身の連帯債務者としての責任は免れません。父の相続とは関係がありませんので。
あなた個人の責任を免れるには、
1.法的手続き(破産)を行う。
但し破産を申し立てるには弁済不能の状態でなくてはなりませんので、あなたが他に借金があったり低収入で生活に支障を来たすような状態でなければ現実的に無理があると思います。
2.遺産分割協議をして代償分割により現金で受領して残債に充てる。但し現金があることが前提。
3.相続開始前後でも構わないが、現在のあなたの共有持分を他の親族(相続人)に売買する。銀行と相談しながら進める必要があります。
2・3は親族の協力なくしては進めることが困難なので、現在の関係を良く検討して下さい。
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A