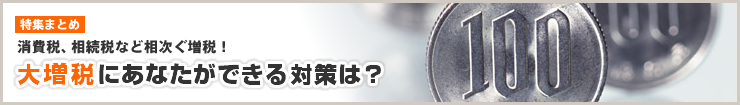対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
昨年11月に自己都合で会社を退職し、実家に住民票を移しました。その際、父の世帯に入ったわけですが、その後に国民年金と国民健康保険の手続きを行ったことで重大な問題に気づかされました。
現在、父は年金を貰いながらたまにシルバーセンターの仕事をする程度で所得が低いため、国民健康保険は7割控除を受けています。しかし、私が父の世帯に入ったことで来年度(4月以降)から7割控除が受けられなくなるそうです。控除を継続するためには、私が住所を移すか、社会保険に加入するかだと、税務課の職員が教えてくださいました。
就職活動の末、私は先月末から新しい職場で働き始めましたが、現在は試用期間中のため社会保険への加入は5月以降になります。そこから社会保険へ移行しても控除の審査が4月1日を基準に行われるため、再来年度まで控除が適用されないそうです。家移りも考えましたが、今年の各納税が所得に対して大きいと思われるため、なかなか決心がつきません。
そんな中「世帯分離」の手段があることを知りました。役所に申請すれば可能らしいですが、世帯分離に伴う影響が十分に把握できておりません。役所に相談しようとも考えましたが、納税を軽減するための相談では話を聞いてもらえないのではないかと不安で踏み出せずにいます。そこで、こちらの専門家の皆さんにご意見を頂戴したく投稿させていただきました。
確認したい内容は以下のとおりです。
1、世帯分離によって父の控除は継続できるか。
2、世帯分離によるデメリットはあるか。
自分にかかる税金は自分で対処するつもりです。兎にも角にも父の控除だけは継続させたいと思っています。ご回答及びご教示のほどよろしくお願いします。
はやてさん ( 鹿児島県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
![]()
「生計を共にしていない」なら世帯分離をして構わないと考えます
はやてさんへ。FPで国民健康保険料コンサルタントの杉浦恵祐です。
世帯分離については専門家の中でも意見が異なりますが、私は「生計を共にしていない」なら「世帯分離」をしても全く構わないと考えます。
(「生計を共にする」というのは生活実態がどうかで、一方「生計を一にする」は税務の扶養等の定義で、両者の意味合いは異なります。
国民健康保険で住民票を一緒にした(世帯を一緒にした)ことで世帯全体の所得が問題となるのは、
・保険料(均等割、平等割)の法定軽減-今回の相談内容
・自己負担限度額(高額療養費)の所得区分
・入院時の食事代自己負担額
・70歳以上の自己負担割合が3割になるか1割になるかの現役並み所得判定 等で
ちなみに介護保険では、
・65歳以上の保険料の所得段階区分
・高額介護サービス費の所得区分
・施設の居住費、食費等の自己負担限度額の所得区分 等です。
(現在の後期高齢者医療制度でも同様の問題があります。)
はやてさんとお父さんの生活実態が「生計を共にしていない」ならば、堂々と世帯分離の届けを出すことによって、上記の所得からはやてさんの所得を抜くことが出来ますので、時間的に間にあえばお父さんの国民健康保険料の法定軽減が受けられるはずです。
一方、デメリットですが、
・高額療養(医療)費、高額介護費は世帯合算でみますので、はやてさんとお父さんが共に高額な医療費等の自己負担をした場合には、世帯が一緒の方が自己負担が少なくなります。
・地域によって異なりますが、町内会費等や町内会等の役員順番等が住民票上の1世帯ごとにかかってくる場合等はその負担が増します。
実際には、市町村役場の窓口で担当者からいろいろ言われる場合もあるようですが、「生計を共にしていない」、「生計が別である」なら堂々と手続すればよいと考えます。
生計を共にしているのかしていないのかは、本人しか正確には判断できないのですから。
評価・お礼
はやてさん
2011/02/11 21:58杉浦様、詳しいご回答ありがとうございました。疑問と不安が解消されて気持ちが少し楽になりました。来週にでも役所へ行って手続きを行いたいと思います。
今まで保険や納税に関しては会社の経理任せだったので、無頓着であったことを今回のことで反省しました。生活や家族に関わることなので、これからは少しずつ勉強したいと思います。
(現在のポイント:4pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A