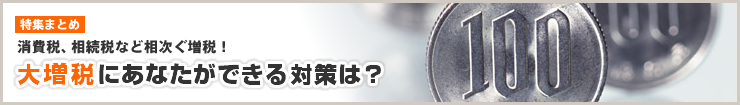被相続人(死亡)甲と、相続人乙が、30年前に共同で出資して購入した土地がありますが、事情により、所有権登記は、甲となっていました。
共同で出資したことについては、資金の流れなどで証明できます。
その10年後に、当該土地の上に、甲と乙が共同で出資して、RC構造のアパートを建築しました。
当初は、建築費用の担保として、土地、建物に抵当権を設定しました(抹消済)。
アパートは、共有の登記(甲が3、乙が7)をして、その収益や管理にかかる費用なども持ち分に応じて按分するとの書面を残しましたが、土地の利用については、記載がありません。
ただ、事実として、乙が、「借地料」の代わりとして、土地の固定資産税を、全額を支払ってきました。ただし、振込用紙によるため、証明困難です(逆に、ほかの不動産は銀行口座引き落としで、当該土地だけは振込用紙を利用していたことは、証拠となりませんか)。
そこで、外形上、借地権(地上権)の設定があったと考えうるとして、「貸宅地」での評価で申告しました。
(甲の建物の持ち分に対応する部分は、「貸家建付け地」と申告)
なお、詳しい相続関係は、土地を共同相続し、乙が土地の持ち分3、そして、共同相続人丙が、建物の持ち分3(甲の持ち分すべて)、および、土地の持ち分7をそれぞれ相続します。
しかし、税務署からは
土地については、共同出資分については、「贈与と推定するとの通達」があるとのことで、贈与とされました(贈与税は時効消滅)
そして、共有の建物(アパート)の相続人乙所有(共有)のための土地の利用の権利は、「使用貸借と見なす」と言われました。
そして、(乙の建物の持ち分に応じて)土地の7割は「自用地」と評価されました。
やはり、乙所有(共有)のための利用部分の土地を、「貸宅地」での評価は、難しいでしょうか。
さらに、疑問に思うのは、自分の所有(共有持ち分)する賃貸建物が建っている部分は、「貸家建付け地」で評価されるのに、家族とはいえ他人の所有(持ち分)する賃貸建物が土地の使用貸借で建っていると「自用地」になってしまう点です。
せめて、「貸家建付地」で評価は、されないのでしょうか。
なにとぞアドバイスをいただけますように、よろしくお願い申し上げます
melemakaniさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件

和田 安弘
税理士
-
![]()
土地の評価について
税理士の和田と申します。質問内容に◆◆の部分にコメントを入れましたので。ご確認ください。
被相続人(死亡)甲と、相続人乙が、30年前に共同で出資して購入した土地がありますが、事情により、所有権登記は、甲となっていました。
共同で出資したことについては、資金の流れなどで証明できます。
◆所有権登記が甲となった事情はわかりませんが、甲だけとなったことにより、資金の流れから、乙から甲への資金提供であるとみなされます。◆
その10年後に、当該土地の上に、甲と乙が共同で出資して、RC構造のアパートを建築しました。
当初は、建築費用の担保として、土地、建物に抵当権を設定しました(抹消済)。
アパートは、共有の登記(甲が3、乙が7)をして、その収益や管理にかかる費用なども持ち分に応じて按分するとの書面を残しましたが、土地の利用については、記載がありません。
ただ、事実として、乙が、「借地料」の代わりとして、土地の固定資産税を、全額を支払ってきました。ただし、振込用紙によるため、証明困難です(逆に、ほかの不動産は銀行口座引き落としで、当該土地だけは振込用紙を利用していたことは、証拠となりませんか)。
◆固定資産税相当額以下のの借地料の支払いですと、その土地の利用は使用貸借であるとみなされるのが通常です。◆
そこで、外形上、借地権(地上権)の設定があったと考えうるとして、「貸宅地」での評価で申告しました。
(甲の建物の持ち分に対応する部分は、「貸家建付け地」と申告)
なお、詳しい相続関係は、土地を共同相続し、乙が土地の持ち分3、そして、共同相続人丙が、建物の持ち分3(甲の持ち分すべて)、および、土地の持ち分7をそれぞれ相続します。
しかし、税務署からは
土地については、共同出資分については、「贈与と推定するとの通達」があるとのことで、贈与とされました(贈与税は時効消滅)
そして、共有の建物(アパート)の相続人乙所有(共有)のための土地の利用の権利は、「使用貸借と見なす」と言われました。
そして、(乙の建物の持ち分に応じて)土地の7割は「自用地」と評価されました。
やはり、乙所有(共有)のための利用部分の土地を、「貸宅地」での評価は、難しいでしょうか。
さらに、疑問に思うのは、自分の所有(共有持ち分)する賃貸建物が建っている部分は、「貸家建付け地」で評価されるのに、家族とはいえ他人の所有(持ち分)する賃貸建物が土地の使用貸借で建っていると「自用地」になってしまう点です。
◆家族間で、しかも乙は固定資産税相当額しか借地料を支払っていませんので、その土地の利用は使用貸借とみなされるのはやむを得ないと思います。使用貸借であればその土地の権利について、借地人乙は借地権の権利を主張できませんので、土地の持ち主である甲はその土地は乙に関係なく甲が自由に処分できることが可能ですので自用地として評価されます◆
せめて、「貸家建付地」で評価は、されないのでしょうか。
◆建物は甲ではなく乙の所有ですから貸家建付評価とは出来ないことになります。◆
補足
土地の評価の減額は、その土地の権利行使にあたって制限されるのか、されないのかによって評価がかわっています。家族間でしかも借地人が第三者であれば支払われる権利金、相当の借地料が支払われないような場合には、借地人には保護されるべき権利はないものと考えられます。なのでその土地の評価は自用地となんらかわらないと判断されます。
評価・お礼
melemakaniさん
2014/06/12 20:59お忙しい中を、回答いただき、誠にありがとうございます
借地人乙が住む家であれば、甲は自由に土地を処分できるというのも分かるのですが、貸家であり、甲は借家人に対して権利主張が制限され、堅固な建物で分割も困難であるのに、土地使用の権利が制限されていないとは、何とも腑に落ちないのですが、きっと判例その他でそのようになっているのですね。
和田 安弘
2014/06/13 06:58甲と乙の関係が親子関係であることがまず検討されます。第三者間の賃貸借ではないので、権利の制限はないであろうと判断されます。相続が発生した場合には乙は甲の財産を取得することが可能です。もし乙が第三者に建物部分を譲渡しようと考えた場合、地主である甲の承諾が必要であり、借地権部分の対価の支払いを取得するであろう第三者に求めることになるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
![]()
「相続税評価額」に関するまとめ
-
相続する不動産の評価額はどう決まるか知っていますか?相続税評価額を知るための基礎知識をまとめました。
お金や株式とは異なり不動産の時価を決めるのは難しいため、不動産の相続税評価額について悩まされている方や提示された相続税評価額を不審に思っている方は沢山いらっしゃると思います。 相続税評価額を決定する方法や税理士、不動産鑑定士によって算出される評価額が違ってくる仕組みなどを知れば対応策を考えることが出来ますね。 専門家プロファイルでは相続税評価に強い専門家の意見やアドバイスをコラムやQ&Aで知ることが出来ます。不動産の相続税評価額に関する基礎知識を見に付けて問題を解決しましょう。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング