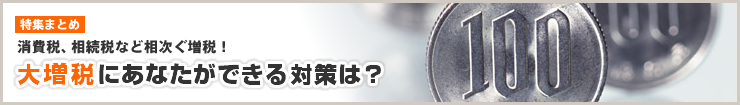今年3月末に結婚退職した妻の市民税と所得税について質問します。
まず市民税について、今年3月まで給与所得者として特別徴収で納めていましたが、結婚退職し私(配偶者)の扶養に入っても、4月以降の市民税を普通徴収にて納めなければならないのでしょうか? 因みに、結婚退職と同時に県外に転居したにもかかわらず前住所の市から納税通知書が届きました。納税通知書には詳しい説明が無く、しかも記載された「年税額」が「何月からの税額?」なのか記載が無く、特別徴収で納めた税額がちゃんと差し引かれているのか疑問です。(ぼったくりはないと思いますが・・・)
次に、所得税ですが、妻の今年度所得については確定申告(年末調整)で所得税を還付できるのでしょうか?または、私の配偶者控除にて申告し年末調整されるものなのでしょうか?因みに、妻の今年度所得は給与所得907,057円(1月~3月)と退職金1,584,100円です。
以上、税金のことがイマイチよく分からないので宜しくお願いします。
サムライ39さん ( 愛知県 / 男性 / 39歳 )
回答:2件

宮原 裕一
税理士
2
![]()
住民税は前年分にかかる税金です
こんにちは。弥生マイスター税理士の宮原です。
住民税は1月1日現在でお住まいの住所地にて課税されますので、
途中で転居されても納める先は変わりません。
また、住民税は前年分の所得に対して課税されますので
奥さまは今年度も例年通りの水準で住民税がかかります。
特別徴収の住民税は、その年の6月から翌年5月までの月割徴収となります。
奥さまは前年度の住民税については4・5月分について納める必要があり、
今年度分については年間分が別に市から送付されるかと思います。
なお、退職時に5月分までの住民税を一括徴収された場合は、
前年度分は会社の特別徴収で終わっています。
奥さまの所得税については、奥さまが確定申告をして還付を受けることになります。
念のため、給与所得と書かれておられるのは給与収入(いわゆる103万)ですよね。
ご主人は今年の年末調整で奥さまにつき配偶者控除を受けることとなります。

舛田 義行
税理士
-
![]()
ご回答いたします
MCS税理士法人立川事務所の税理士舛田です。
以下のご回答いたします。
1.まず市民税について、今年3月まで給与所得者として特別徴収で納めていましたが、結婚退職し私(配偶者)の扶養に入っても、4月以降の市民税を普通徴収にて納めなければならないのでしょうか?⇒住民税を特別徴収されている場合には6月1日から12月31日までに退職した時には原則(本人の申し出がない場合)普通徴収に切り替わりご自身で納付してゆくことになります。また翌年1月1日から4月30日までの間に退職された場合には強制的に最終給与もしくは退職金から残りの住民税を一括徴収されます。(給与等から引ききれなかった場合には普通徴収になります。)。ということで退職時に残りの期間の住民税を一括徴収されているはずですから一度以前お勤めの会社にご確認してみてはいかがでしょうか?会社の方で一括徴収していない可能性もありますが。
2.因みに、結婚退職と同時に県外に転居したにもかかわらず前住所の市から納税通知書が届きました。納税通知書には詳しい説明が無く、しかも記載された「年税額」が「何月からの税額?」なのか記載が無く、特別徴収で納めた税額がちゃんと差し引かれているのか疑問です。(ぼったくりはないと思いますが・・・)⇒住民税は1月1日から12月31日までの所得に対して翌年に課税されます。また課税される年の1月1日現在の住民登録されていた市町村です。住所変更をしても納税先は変わりません。
3.次に、所得税ですが、妻の今年度所得については確定申告(年末調整)で所得税を還付できるのでしょうか?または、私の配偶者控除にて申告し年末調整されるものなのでしょうか?因みに、妻の今年度所得は給与所得907,057円(1月~3月)と退職金1,584,100円です。⇒年末調整は原則としてその年の最後の給与を支払う際に行うこととなっており、年の中途で退職した人の年末調整はできないこととなっています。(例外はありますが)。よって退職した年の翌年に確定申告(還付申告)にて還付を受けることになります。またあくまで奥様の所得ですのでご主人の年末調整に奥様所得を合算することはありません。ただしその年の奥様の給与収入が103万円以下であればご主人の方で配偶者控除を年末調整時に受けられます。
評価・お礼
サムライ39さん
ありがとうございました。市民税については、最終(3月)の給与で3カ月分の住民税が引かれており、これが今年度4・5月分の一括徴収であり、また、市役所から通知のあった税額は本来今年6月~翌年5月まで特別徴収される予定だった前年度の市民税(普通徴収)ということでよろしいでしょうか?所得税については、給与収入が今年度103万円以下であれば扶養対象ということですが、退職金が退職控除額480万円(=40万円×勤続年数12年)より少ないため今回この給与収入に加えず、給与収入907千円≦103万円ということで、配偶者控除を年末調整で受けられるということでよろしいでしょうか?
舛田 義行
ご評価いただきありがとうございました。おっしゃる通り本年に市役所から来た住民税の通知は今年6月から来年5月までの分だと思われます。住民税はその年の1月から12月までの所得に対する税額を翌年に課税されるため奥様が平成21年6月から平成22年5月まで給与から控除された分というのは平成20年分になり、平成22年から平成23年5月まで4期分納(普通徴収)するのは平成21年分になります。
退職金についてですが退職所得の計算はご記入いただきました通り控除額が勤続年数20年までは年40万円×勤続年数になり12年であれば480万円となり退職金額の1,584,100円は所得としては0円となりますのでご主人様の方で奥様を配偶者控除の対象として考える時の奥様の収入は給与収入のみとなります。
(現在のポイント:6pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング