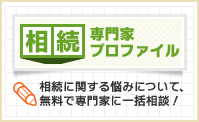昔から、親が相続対策の一環?で生前に子どもなどの名義で預金をしておくことがあります(なお、現在は金融機関での本人確認が厳しくなっているので、親が勝手に新たにこのような預金口座を作るのは以前より難しいと思います。)。
しかし、このような方法を取っていても、その預金が親の相続財産から外れるとは限りません。名義は子どもら名義でも実際には未だ親の財産であると税務署から認定され、相続税の対象財産(相続財産)とされることが度々あるからです。
さて、こういったことにならないようにするためには、きちんと子どもらへの贈与という形を取り、子どもらに預金の存在をきちんと知らせて自分のものとの認識を持っておいてもらうことや(税務署の調査があった場合には、親から贈与を受けていると回答してもらう必要があります。)、預金通帳や印鑑などを子どもらに渡しておくことなど、実態としても親の相続財産から外しておくための措置が必要だと考えられます。
子どもらの贈与税の観点からは、課税を完全に避けたいのであれば、毎年子供らそれぞれに対して贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で贈与(口座への振込)をすることが必要となりますが、あえて多少の贈与税の申告・納付をして公的な証拠を残すという方法も考えられます(将来の相続税の減税という観点からも望ましい場合があります。)。
なお、毎年一定額(たとえば110万円など)の贈与をする場合に注意すべき点としては、最初の年に将来分も含めて贈与があったもので単にその支払いを分割で毎年しているにすぎないというような認定を受けることがないようにしなければなりません。仮にこのような認定を受けると、最初の年に全額の贈与があったものとされるため、税率が高くなってしまいますし、毎年の基礎控除を生かすことができず、子どもらの支払う贈与税が多額になるおそれがあるからです。ですから、毎年毎年、改めて贈与契約を行い、契約書を作成・保存するのが望ましいといわれているわけです。
もっとも、相続開始前3年以内の贈与財産については、法律によって相続財産とみなされて相続税が課されることになっていますので、この場合は、相続税の申告漏れに注意して下さい。なお、相続財産とみなされたものについて以前に支払った贈与税があれば、その分は相続税の額から差し引くことができます。
このコラムに類似したコラム
名義預金と贈与 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/20 00:00)
親から子への学費・生活費の援助は、無条件で贈与税非課税? 近江 清秀 - 税理士(2012/10/29 08:00)
預金と遺産分割 佐々木 保幸 - 税理士(2013/05/09 22:43)
孫への教育資金贈与 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/02/21 21:25)
相続時精算課税適用対象者の範囲の改正 大黒たかのり - 税理士(2013/02/21 09:00)