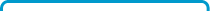服部 明美
ハットリ アケミグループ
任意加入被保険者だったときの未納期間も、受給資格期間に合算できます
-
![]()
年金機能強化法による一連の改正で、国民年金に任意加入していた人の取り扱いも一部変わりました。
昭和61年3月31日までの専業主婦等や、平成3年3月31日までの学生などのなかには、国民年金に加入する義務はなかったけど自由意思で加入していた人たちがいます。
その「任意加入被保険者」であった期間中に保険料を納めなかった期間について、これまでは年金を受け取る権利を得るための「受給資格期間」(原則25年、平成27年10月からは「10年」になる予定)から除外されていました。
未納は未納だから、ということですね。
これが、平成26年4月実施の改正により、受給資格期間に合算できることとなりました。
元々、加入しなくてもよい期間だったからですね。
改正後の取り扱いは、加入義務がないから加入しなかった人たちと同じ、「合算対象期間」(通称「カラ期間」)とされます。
つまり、受給資格期間には合算されるけど、老齢基礎年金の額の計算には反映されない、からっぽの期間です。
任意加入未納期間を受給資格期間に合算することにより年金の受給権が発生する場合、その受給権発生日は平成26年4月1日となります。
ただし、平成26年3月31日までに死亡した人については、その遺族に遺族年金が支給されることはありません。
なお、今回の措置は、昭和61年3月31日までに年金を受け取る権利が発生している「旧法」の受給権者は対象となりません。
《参考》 「合算対象期間」とは、次のような期間です。(日本年金機構HPより)
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254