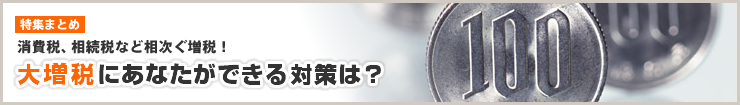納税についてお尋ねいたします。
私は個人事業主ですが、昨年、経営不振によりやむなく亡くなった親から15年ほど前に兄弟で相続した土地建物の自己所有分2分の1を兄弟に買い取ってもらいました。
この際、兄弟に金銭的余裕が無かったため、兄が住宅ローンを組んで、私は自己所有相当額の現金400万円を受け取り、この内、約350万円は借金返済に充て、残りは生活費にして無くなりました。昨年は事業所得が約40万円しかありませんでした。
そこで質問ですが、
住居用の場合は3000万の控除があるから、その位の金額なら申告は特に不要で、普通の確定申告だけでいいはずで、問題があれば税務署から連絡があるんじゃないかな、と知人に言われましたので、不動産売却の金額は記入せずに確定申告を済ませました。が、どうにも気になって念のため税務署に尋ねたところ、分離課税(?)なので申告は必要と思われますとの事でした。おそらく税務署の方が正しい気はしますが、何となく腑に落ちない面もあります。
両親の死後、現在も兄がずっと居住しておりますが、このような場合も申告は必要でしょうか?特例の控除は、自分も兄弟と同居している場合は適用されるが、実際に住んでいないので控除が適用されないという事なのでしょうか?
ネット上で自分なりに検索で調べてみましたが、居住用と共有名義という点で節税できる余地があるのか、控除は適用されるのかどうか、それとも税務署のいう通りなのかよくわかりません。現在は生活費もままならない状況で不安で頭がいっぱいですので、必要なな税金以外も余分に言われるままに納めるのは避けたいので、是非ご助言をお願い致します。
2008MNさん ( 北海道 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
3,000万円控除の対象にはなりません。
2008MNさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おそらく居住用の3,000万円控除があり、税金はかからないので、申告不要と思われていたかと思いますが、そもそもこの3,000万円控除の適用を受けるには確定申告が必要になります。
しかし、2008MNさんの場合、この3,000万円控除の対象とはなりません。
3,000万円控除の原則は自分が住んでいるマイホームを売った場合に適用があります。
従いまして、2008MNさん自身又は生計を一にする親族が住んでいませんので、3,000万円控除の適用はないことになります。
但し、所得計算をして所得がゼロ又はマイナスであれば確定申告の必要はありませんが、所得が出るようですと申告分離課税として確定申告の必要があります。
ちなみに、相続で取得した場合、取得日及び取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
2008MNさん
大変迅速で適切なご助言有難うございました。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス

2008MNさん
Re:3,000万円控除の対象にはなりません。
2008/03/26 22:12お世話になります。
大変迅速なご回答有難うございました。
ご助言により、申告は必要とわかりました。
1点、不明なのですが、
「但し、所得計算をして所得がゼロ又はマイナスであれば確定申告の必要はありませんが、所得が出るようですと申告分離課税として確定申告の必要があります」
上記の部分ですが、
昨年の事業所得は、控除と経費や減価償却分を足し引きしますと200万円ほどの赤字です。
これに対しての確定申告は済ませてありますが、
改めて不動産売却の金額400万円を申告しますと、借金返済で350万は消えましたが、数字上では利益が出たことになり、単純に400万円の2割を納税する事になるのでしょうか?それとも、事業所得の赤字分を差し引き計算されるのでしょうか?
いづれにしましても、現在は支払能力が無いのですが、どのようになるのでしょうか。
また、申告のタイミングとしては、税務署からの連絡を待ってからで良いのか、すぐにでもした方がよいのか悩んでおります。
非常に情けない状況で恥じ入るばかりですが、何卒ご助言下さいます様、よろしくお願い致します。
2008MNさん (北海道/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング










 専門家
専門家