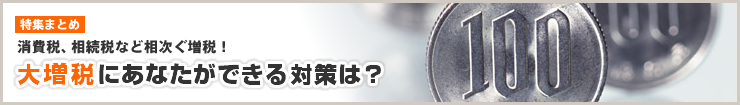対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
回答:1件

後藤 義弘
社会保険労務士
-
![]()
免除申請で負担減にトライしましょう
以前ご相談を受けたことのあるAさんの実例を使って、どの程度の免除が認められるかを見てみましょう。
・前年収入 約350万円 (課税所得約150万円/平成16年)
・準備期間 7ヶ月 (平成17年6月退職〜平成18年2月個人事業開業)
(1) 国民健康保険料
[免除額] ゼロ
この中で一番免除のハードルは高いと言えます。
この保険料の計算基礎はあくまで「前年の所得」であることより、現時点での収入がない(失業等)ことのみをもって「免除」あるいは「減免」の対象とはなりません。やはりポイントは前年の所得、Aさんレベルの所得では基準を満たさず、残念ながら免除・減免いずれも認められませんでした。
(2) 市県民税
[免除額] 7.3万円 (平成17年全期分の免除)
これも市区町村によりますが、Aさんのケースは条例の所得基準をクリアしており、「失業」中であることを理由に「免除」が認められました。(各支払期ごとに免除の申請が必要)
(3) 国民年金保険料
[免除額] 16.4万円 (平成17年7月〜平成18年6月/全額免除適用)
この3つの中では一番要件は緩く、「失業」状態であることが確認できれば〜例えば、退職時に会社から渡される「離職証明書(離職票)」などをお住まいの市区町村に提示〜「免除」が認められます。 ただし、将来の年金額が減額となるデメリットがあるため、資力回復後納付[10年分まで遡れます]し減額をカバーしていきましょう。
以上Aさんは準備期間中計約24万円(月額3.4万円)の負担減を果たしました。 このようにちょっとした予備知識と計画性が少なからずの負担減少につながります。 事業はすでに準備期間から始まっています。 在職中にこうした「原価意識」を持ち開業準備に入ることはとても大切なことです。 こういうときこそ各分野の専門家を有効に活用しましょう。
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング