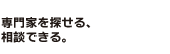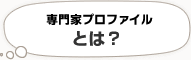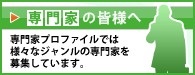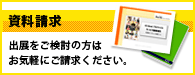- 大澤 眞知子
- Super World Club 代表
- カナダ留学・クリティカルシンキング専門家
PodCast[今の日本で子育てする勇気あるあなたに]で、日本の教育環境の異常さを話しました。
クリティカルシンキング思考法を見事に育てるカナダの教室風景を覗き見出来るStoryの公開し始めました。一回目はこちら。The Best Part about School PodCastでも朗読しながら、カナダの教室で起こっていることを話していますのでぜひ。
さぁ、今日は2回め「カナダの教育を覗いてみましょう」ストーリーです。
世界中から人が集まる多民族のカナダ、舞台になった小さな小さな大平原の町にもこんなダイナミズムがあります。その中で学ぶ子供たち、そして大きなヘルプをする教師たち。これこそ教育と思える風景です。
現在全力で準備を進めている 「カナダ式教育を日本の子供たちに(仮題)」のカリキュラムにも、どうしても取り入れたい瞬間をストーリーにしました。著者は、Robert McMillan。日本の生徒へのエッセイ指導の達人です。(現在彼の指導するEssay Basics夏の半額キャンペーン中です、ぜひ。)
日本の子供たちの持つ折角の考える力を日本の教育に潰されないために、カナダから手を差し伸べる方法が絶対あるはず、そんな思いです。
_________________________
The Dance (by Robert McMillan) (日本語訳は英語版の下にあります)
Mrs. Page sped through the early dawn light to her workplace, a one-building K-12 school where she had taught for the past 21 years. She pried her wakeup coffee from its cup holder embrace, took her first sip, and felt the warmth seep through her body. And she sighed.
City born and raised, Mrs. Page never imagined herself teaching so long in a small prairie town. But she liked the atmosphere of her school. The people here, generally speaking, watched out for one another. And the principal Mr. Adams had an open ear. He listened to the concerns of parents and teachers alike and made changes when he could. He was supportive, excited even, when Mrs. Page offered to start an after-school Debate Club twice a week to guide students through problematic issues and help them solve differences.
But this fine morning Mrs. Page was not thinking about the Debate Club. She would have liked to revel in the fresh green of the fields lining both sides of the road, especially after the long, cold winter. But she couldn’t. She was thinking about her social studies class.
The class had been learning about Ukraine, a country of focus in the grade three provincial curriculum for years. Today the class would see a traditional Ukrainian dance from their newest classmate, Kristina, a girl whose family fled to Canada after losing their home in the war. The students were excited about this, as were many teachers. But Mrs. Page was worried. A lot could go wrong, and she did not want any more distress to fall on this girl who had already experienced too much.
As she pulled into the school parking lot and plopped her thermos back into the cup holder – the most important accessory of a car in Canada – she checked her appearance in the rear view mirror. It reflected a stern face with a hint of softness, a look she had affected to teach elementary school kids. She checked her hair, mid-length and slightly messy with a tinge of grey. Mrs. Page called it “professionally messy” and preferred it this way because it was easy, but also because it looked more dynamic and, she suspected, that resonated with her students.
At the school entrance she bumped into Sam, Samantha MacKenzie, a local mother who volunteered at the crosswalk in front of the school (to socialize, Mrs. Page suspected).
“You’re here early,” said Sam, dressed in the bright yellow vest of a crosswalk volunteer.
Mrs. Page liked to arrive early and enjoy the peaceful hallways before the kids streamed in and shattered the quiet. “You too,” said Mrs. Page with sincerity.
“You know, if you lived in town, you could sleep longer and wouldn’t have to drive.”
It irked Mrs. Page that locals think a teacher should live in the town they teach. The guy with the only gas station in town did not live here, and everyone was just happy to have gas. Why couldn’t they just be happy their kids had a free education? Mrs. Page happened to be more comfortable living in the city, even though it meant a 30-minute drive to work. Teachers, she thought, should not have restrictions on where they live, no one should. But she had a diplomatic reply: “And teach my own kids? No thank you.”
Sam laughed. Mrs. Page’s children attended school in the city – kids here, you see, go to the public school in their area. And it makes sense. The public schools are good, and all of the students grow up together – the academic ones, the non-academic ones, the special needs kids. Here they learn how to deal with children who are different from themselves. That’s good for these kids. But tough for newcomers like Kristina.
Then Sam asked how Mrs. Page’s kids were and Mrs. Page asked how Sam’s family was because that is what Canadians do, talk about family.
When Mrs. Page finally arrived at the staffroom, she restlessly checked her lesson plans. There was a saying amongst her colleagues that you plan lessons meticulously the first year and then teach the same thing for the rest of your career. And there is some truth to that, but class dynamics change, so Mrs. Page pencils memos to herself in the margins with suggestions for the next year. Her note from last year was simple: Visuals. Well, she had a visual this year, a live dance, and she didn’t know why she was so nervous about it.
Mr. Adams did not offer any reprieve. “Lisa!” he cheerfully greeted her by her first name.
“Morning Mike!” she replied.
“About that dance today, I was thinking it’s a good chance to show the whole school.”
Mrs. Page’s face went pale. “I don’t know, Mike. Kristina is still kind of fragile, you know, with the move and all. I worry that’ll be stressful on her.”
“Um…, right, okay. Let’s just do it for the grade threes then. Is it okay to invite a handful of other kids? The good ones? I think they’d get a lot out of it.”
This meant the performance would be in the gymnasium instead of the familiar, cozy atmosphere of the classroom. But it was hard for Mrs. Page to refuse.
When the time came, Mrs. Page found herself on the stage beside a nervous little girl dressed in the colourful, embroidered vyshyvanka outfit of her village in Ukraine. She’d had her hair lovingly braided and wore a flower crown – a head wreath. Her family was clearly proud of her role here. But the pressure on the girl was obvious. Her eyes were fixed on the floor in front of her feet and her thin lips were pressed so tightly together that the colour had drained out of them.
“Look at you! Beautiful!” Mrs. Page said comfortingly. Then she bent down to whisper a secret in Kristina’s ear: “Kids here know nothing about dancing, so anything you do will be special.”
Kristina’s expression didn’t budge, and Mrs. Page wondered if she had understood. The girl had not been in Canada a year and struggled with English. Mrs. Page’s family had moved, too, when she was young, so she knew something about this difficulty: saying the right things, making new friends and always feeling lonely. But Kristina had moved to a place with a different language and customs, a place where everyone grows up together from kindergarten through high school. Mrs. Page suddenly remembered seeing the Japanese and Korean students, high-school aged, walking home alone after school with that despairing look of loneliness. The only two international students here in the middle of nowhere.
The old maroon curtain was drawn from the gym stage to reveal a cheerfully-attired girl staring at her feet. In that moment of silence, Caleb, a class clown of sorts, stood from his chair and barked: “She looks like an Easter egg!” referring to the boiled eggs that children here dye in bright colours each spring to celebrate the holiday.
Laughter burst from a handful of children, and Kristina appeared to shrink. “Mister Wahl,” Mrs. Page called his last name deliberately slow and shot him a blistering glare that could wither paint on gym walls. Mrs. Page was not tall, but she was stocky, and the way she wore her skirts tight and just below the knees suggested an athleticness that meant business. She glared until Caleb sat down and the laughter subsided.
Fortunately, when Kristina looked up she saw Amina in the front row smiling and waving at her. Amina, a war refugee from Syria sponsored by a local church, knew better than anyone what Kristina was going through.
Mrs. Page put on the music, an old CD from Kristina’s grandmother. A fast-paced, frenetic rhythm surged from the stage, and Kristina fell into a trance of intricate foot taps, lively hopping and subtle head movements. She was quite good.
When she was done, Kristina smiled proudly. And the gym broke out in applause, the teachers clapping a little too energetically, as teachers will.
Then it was question time.
Mrs. Page looked at the scatter of raised hands, some stretched high, some half-raised indifferently, searching for a good first question. There. A student from her Debate Club, a thoughtful kid. “Liam,” she said.
Liam amplified his young voice, a technique he learned in the Debate Club: “Does your dance have a meaning? I just wonder when people do it.”
With Mrs. Page’s help, Kristina explained that the dance was for celebrations, especially to welcome people, her grandmother had said. As soon as she said it, Kristina wondered if her grandmother had made up the “welcome people” part to fit the occasion, but she kept that to herself.
Amina then commented that the dance was beautiful and reminded her of the dances she had seen in her native Syria.
Next, Mrs. Page called on Ben.
“My grandparents came from Russia, and my grandmother has a dress like yours. Is this like a Russian dance?”
“NO!” Kristina snapped, her eyes fierce.
This is what had worried Mrs. Page.
Before she could intervene, Ben sensed the problem: “I mean, my grandparents escaped the Soviet Union. Ran away with nothing’. And they came here. And I’m glad you came here, too, Kristina. I hope you stay forever.”
This brought tears, mostly from the teachers, who were encouraged to clap even more energetically.
To wrap it all up, Mrs. Page pulled the kids who asked questions up onto the stage and told them to show Kristina a local dance. Before Liam and Ben could protest that they didn’t have one, Amina began to leap and spin gracefully, nearly crashing into Liam who then began undulating with an imaginary hockey stick while Ben tapped his imagination for what a Soviet dance would look like, prompting Mr. A., a teacher, to call his moves the Constipated Robot Shuffle and dance along, sending the principal Mr. Adams into uncontrollable laughter.
Kristina beamed, laughed out loud, and clapped in time to these hopeful fragments of “dance”.
Mrs. Page never thought of herself as an important cog in the wheel that kept Canada moving along. A multi-ethnic hodgepodge of people from all over the world, people that didn’t always get along, didn’t always like one another. But without the Mrs. Pages, the wheels would fall right off the whole thing.
ダンス (translated by Machiko Osawa)
Mrs. Pageは、早朝の光の中、仕事場である学校に向かい車をブンブン走らせていた。たったひとつの校舎に幼稚園から高校3年生までが通う小さな町の学校は、Mrs. Pageが過去21年間ずっと教えている所。寝ぼけ頭を起こすコーヒーを車のカップホルダーからギュイっと取り、グビッと一飲みし、喉で暖かさをほ〜っと感じた。そして、ため息をついた。
都会で生まれ育ったMrs. Pageは、カナダ大平原の小さな町でこんなに長く教師をするなんて思ってもいなかった。でもMrs. Pageは今の学校の雰囲気が気に入ってる。ここの人たちは、まぁ、お互いを見守りながら思いやりを持って生きているようだから。そして、校長のMr. Adamsは何でも真剣な目で聞いてくれる。親や教師の心配に耳を傾けてくれ、出来ることは変えていってくれる。Mrs. Pageが週に2回放課後のDebate Clubをやりたいと提案した時にも、協力的で一緒に夢中になってくれた。
しかし、このキリッとした朝の空気の中でも、Mrs. PageはDebate Clubのことを考えていたのではない。道路の両側を埋め尽くす新緑を見ても楽しめなかった。特に、カナダの長くて寒い冬を乗り越えた後の大平原では、眩しい緑は大いなる楽しみのはずだったけど。でも、そんな贅沢なひとときは無理。今日教える社会科の授業のことで頭がいっぱいだったから。
授業ではウクライナのことを教えていた。州のカリキュラムではGrade3の生徒にウクライナのことを教えることになっていた。ウクライナ移民の事を学ぶカリキュラムは数年前からこの州が力を入れている。今日の授業では、新しくウクライナから来たKristinaが伝統的なウクライナダンスを見せてくれることになっていた。Kristinaは戦争で家を失い、家族と一緒にカナダに難民として逃げて来た少女。生徒たちはこのダンスをとても楽しみにしていたし、教師たちも同じくらいワクワクと待っていた。でも、Mrs. Pageは気が気でならなかった。ひとつでも何かが起こるとすべてがうまくいかなくなるし、すでに多くの悲惨な体験をして来たKristinaが、これ以上の苦痛を感じることにならないように、と。
コーヒーの入ったサーモスをカップホルダーからポコっと外しながら、学校の駐車場に車を乗り入れ(カナダでは、サーモスの入るカップホルダーはとても重要な車の付属品) – バックミラーで自分の見かけをチェックした。そこにはちょこっと柔らかさもあるけど真剣な顔。小学生を教えることで身についてしまった顔があった。肩にかかるくらいの髪はちょっと見ボサボサで白髪が顔を出していた。Mrs. Page自身はその髪を「職業的ボサボサ」と名付け、なんか気に入っていた。手間がかからないし、ダイナミックに見えるし、小学生たちの落ち着きのないキョロキョロしたダイナミックさとも共鳴すると思っていた。
学校の入り口で、Samと出くわした。 Samantha MacKenzie、地元の母親で、学校前の横断歩道のボランティアをしている。(この町の人たちがボランティアをするのは、地域での存在感を持つため。Mrs. Pageはどそう推察している。)
「今日は早いね。」と、横断歩道ボランティア用の目がくらむほど黄色いベストを着たSamが声をかけた。
Mrs. Pageは、学校には早く着いて、子どもたちがなだれ込み静寂が砕け散ってしまう前の平和な廊下が好きだった。「あなたも早いですね。」とMrs. Pageは簡単な返事をした。
「お節介かも知れないけど、もしあなたがこの町に住んでたらもっと寝坊できるし長い運転もしないですむのに。」と、Sam。
この町の学校の教師ならこの町に住むべきだと、地元の人たちが考えていることにMrs. Pageはうんざりしていた。この町にたったひとつのガソリンスタンドを経営する人も、町には住んでないけど、町の人はガソリンスタンドがあるということだけに満足している。町の学校の教師がどこに住んでいようと、子どもたちは無料で教育を受けられるるんだから、そこに注目出来ないのかなぁ。Mrs. Pageは自分には大きな街に住むのが向いていると思っていた。例え、仕事に来るのに片道30分かかっても。教師がどこに住もうと、それは制限されるべきではないと考えていた。個人の選択権は守るべきだと考えていた。しかし、ここでは如才なく、「ここに住んだら、私の子供も同じ学校に来るから、自分の子供を教えることになるのよね。真っ平ごめんかな。」と返しておいた。
Samはちょっと笑った。Mrs. Pageの子どもたちは街の学校に通っている。ここの子供たちは地元の公立の学校に行く。理にかなっている。公立学校は良いところ、そして生徒みんなが一緒に成長出来る – 学問に向いている子ども、そうでもない子供、特別支援のいる子供もみんな一緒に。ここでは自分と異なる同級生とどう接したらいいのかを学ぶ。それは子どもたちにとっても良いこと。でも、Kristinaのような新入生にはかなり厳しい環境。
そして、SamはMrs. Pageの子供のことを尋ね、Mrs. PageもSamの家族のことを尋ねた。カナダの人のいつもの話題は家族のこと。
Mrs. Pageはやっとスタッフルーム(職員室)に着き、せかせかとレッスンプランをチェックした。教師仲間の間ではこんな言い習わしがある。教師になった最初の年には念入りにレッスンをプランする、そしてその後の教師生活ずっとその同じプランを使う、と。否定出来ない部分もあるけど、クラスの構成やそこで学ぶ生徒たちも目まぐるしく変わる。だから、Mrs. Pageは次の年の授業に役に立つよう、プランの余白に鉛筆でメモを書き込むことにしている。昨年のメモはとても簡単:「目で見る資料」 そう、今年は「目で見る資料」を用意はした、ダンスをライブで。それなのに、Mrs. Pageはなぜ自分がこんなにも神経を尖らせているのかよくわからなかった。
Mr. Adamsは、Mrs. Pageの心配をよそに、「リサ!」と、陽気に彼女のファーストネームを使い挨拶した。
「お早う、マイク!」と、Mrs. Pageもファーストネームで返した。
「今日のダンスだけどね、学校全体に見せたらどうかな。いい機会だと思うんだよ。」
Mrs. Pageは青くなった。「いやぁ、それはどうかな。Kristinaはまだかなり精神的に壊れやすいと思うから、戦争や逃げて来たこととかで。あの子にストレスはかけたくないのよね。」
「ふむ。。。そうだね、わかった。Grade3だけでやろう。少しなら他の生徒を呼んでもいいかな?いい子だけにするから。このダンスから学ぶことはすごく多いと思うからね。」
校長の提案だと、ダンスを見せるのはいつもの居心地のいい空気のある教室ではなく、体育館でやるということ。それを断るのは難しいなとMrs. Pageは思った。
時間になった。Mrs. Pageは舞台の袖でビリビリに緊張しまくっている少女と一緒にいた。故郷ウクライナの村に伝わる繊細な刺繍のある、目の覚めるほど彩り豊かな衣装を来たKristinaと。髪は美しく編まれ、花の冠をかぶっていた。Kristinaがここでやろうとしていることは、彼女の家族にとっても大きな誇りとなるに違いない。しかし、少女にのしかかるプレッシャーは明らか。足元と床だけをじっと凝視し、薄い唇は余りにも固く閉じられ、血の気が失せていた。
「わぁ、綺麗!」Mrs. Pageは元気づけるように言った。そして、腰をかがめ、Kristinaの耳元で秘密を囁いた。「ここの子どもたちはあなたのダンスのことは何にも知らないからね。間違えても、どんな踊りをしても、全部特別だからね。大丈夫よ。」
その言葉にもKristinaの硬い表情は変わらなかった。Mrs. Pageは果たしてKristinaが英語を理解したかどうか不安になった。カナダに難民として逃げて来てから1年も経ってないし、英語でも困っていたから。Mrs. Pageの家族も、彼女が小さい時に引っ越しをしたので、違う場所に慣れることの難しさは知っていた:その地の常識を知り間違ったことを言わないこと、新しい友だちを作ること、いつも一人で寂しいこと、など。でも、Kristinaは違う言葉と習慣を持つ国にやって来た。異国の小さな町に。そこではみな一緒に育ち、幼稚園から高校卒業するまで一緒。中に入るのは想像出来ないほど難しい。Mrs. Pageは、韓国人と日本人の生徒をこの小さな町で見かけたことを突然思い出した。高校生かな、放課後一人で歩いて帰るところ。寂しさで希望を失ったような表情で。何もない大平原のど真ん中のここにたった2人だけの留学生、地元の仲間に入れない孤独な留学生。
えび茶色の古いカーテンが上がると、体育館のステージでは、鮮やかな色彩の衣装に包まれた少女が足元を見つめていた。一瞬の静寂の後、いつもお道化者のCalebが椅子からバン!と立ち上がり叫んだ。「イースターの卵みたいだ!」春のイースターのお祭りには、子どもたちがゆで卵を明るい原色で染める。その卵みたいだと、叫んだ。
何人かの子どもたちから笑い声が上がり、Kristinaはまるで縮んでしまったように見えた。「Mr. Wah!」Mrs. PageはCalebの名字をわざとゆっくり怒りを込めて呼び、火でも吹くんじゃないかと思えるような睨みをきかせた。まるで体育館の壁までが剥がれるようなパワーで。Mrs. Pageは小柄だけど、がっしりして、膝下丈のぴっちりしたスカートをはいている姿は、たくましさを感じさせた。つまり、下手に逆らわない方がいいよという強さ。Mrs. PageはCalebが腰を下ろし、笑い声が消えるまでキッと睨み続けた。
幸い、Kristinaが目を上げると最前列ではAminaが微笑み、手を振っているのが見えた。Aminaも難民。シリアから逃げて来て、この町の教会がスポンサーとなり面倒を見ている。Kristinaがどんな気持ちで過ごしているかを誰よりもよく知っている存在。
Mrs. Pageは、Kristinaのおばあちゃんから借りた古いCDをかけた。早いテンポ、熱狂的なリズムがステージをうねった。Kristinaは恍惚状態で、もつれそうなほど複雑なステップを踏み、激しく飛び跳ね、微妙な頭の動きを見せた。すごい、すごくうまい。
ダンスが終わると、Krsitinaは誇らしげに微笑んだ。体育館中が嵐のような大喝采。教師たちはちょっとだけエネルギッシュな拍手のしすぎだったけど。教師って大体そんなもんだから。
さぁ、質問タイム。
Mrs. Pageはいくつか上がった手を見た。最初には良い質問が必要だと、高く上げている手、半分だけ興味なさそうに上がっている手を順番に見た。あ、あれだ。Debate Clubの生徒、思慮深い生徒。「Liam」とMrs. Pageが指名した。
リアムは少年特有の張りのある声を出した。Debate Clubで学んだテクニック。「このダンスには意味がありますか?このダンスは特別な時のものに見えますね。」
Mrs. Pageの助けを借りて、Kristinaは説明を始めた。ウクライナから来たおばあちゃんによると、このダンスは特に人を歓迎する特別なお祭りのためのものだと説明した。こう言ったものの、Kristinaはもしかして、今日の機会に合わせるために「人を歓迎する」はおばあちゃんの即興創作かも知れないと思った。でも、それは黙っていた。
Aminaは、ダンスは美しく、自分の故郷のシリアのダンスを思い出したとコメントした。
次にMrs. PageはBenを指した。
「僕のおじいちゃんとおばあちゃんはロシアから来て、おばあちゃんも君と同じようなドレスを持ってます。このダンスってロシアのダンスと同じようなものですか?」
「いいえ!」Kirstinaは、燃えるような怒りの目で噛みつくように言い放った。
これが正にMrs. Pageが心配していたこと。
Mrs. Pageが割って入る前に、Benはまずいと感じたのかこう付け加えた。「えぇっと、僕が言いたかったのは、僕のおじいちゃん、おばあちゃんもソビエト連邦から逃げ出したこと。着の身着のままで。そしてカナダのこの町に来た。Kristinaもここに来れて本当に良かったね。ずっとここにいられますように。」
この言葉は涙を誘った、主に教師たちの。そして教師たちはここぞとばかりに、更にエ゙ネルギッシュに拍手した。
最後をうまくまとめるために、Mrs. Pageは質問をした生徒をステージに上げ、Krsitinaにここの地元のダンスを見せたらどうかと提案した。LiamとBenがそんなのないよと抗議する隙さえない間に、Aminaが飛び跳ね優雅に旋回始め、思わずLiamとぶつかるところだった。Liamは想像のホッケースティックをうねうねするふりをし、Benは多分ソビエトダンスはこんな感じかなと足をタップした。刺激されたMr. A(先生)はBenの動きを「便秘ロボットシャッフル」と呼び一緒に踊り始め、校長のMr. Adamsが笑い転げた。
Kristinaは目を輝かせ、大笑いし、この希望に満ちたダンスっぽい動きに合わせ手を叩いた。
Mrs. Pageは、カナダが前に進んで行くための歯車の大事な歯かも知れない。でも、カナダの歯車の歯の役割を自分が担うなんて想像もしたことはなかった。世界中からやって来た人たちの多民族ごった煮がカナダ。この国に集まる人々は必ずしも仲良くやっていくとは限らない、お互いに好印象を持つとも限らない。しかし、Mrs. Pageのような人がいないと、歯車はすぐにバラバラに分解し、崩れてしまう。これがカナダ。
Feedbackなど聞かせていただけると嬉しく思います。
さぁ、こんな教育を日本で試してみたいですか?
Join us, 「カナダ式教育を日本の子供たちに」
そして、脳の準備が出来たら
カナダにいらっしゃい!
______________________
StoryTelling Camp in Canada 2023
「カナダ大学留学への特訓方法」eBook
カナダからのオンライン講座 Canada Club
「カナダ高校留学実態総集編」eBook
カナダ発日本人のための本格的英語学習サイト UX English
わかりやすいクリティカルシンキング講座
Podcast [カナダにいらっしゃい!]
 このコラムの執筆専門家
このコラムの執筆専門家

- 大澤 眞知子
- (カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
- Super World Club 代表
カナダにいらっしゃい!
カナダ 在住。パンデミック後のNew Normal 留学をサポート。変わってしまった留学への強力な準備として UX English主催。[Essay Basics] [Critical Thinking] など。カナダから日本に向けての本格的オンライン留学準備レッスン・カナダクラブ運営。
 「迷子になった日本の教育」のコラム
「迷子になった日本の教育」のコラム
Bilingual Education for「日本で育つ子供へ」Trial report - Canada News for You(2024/03/31 04:03)
日本で育つ子供をBilingualに:Trialレポート(3-29-2024)(2024/03/30 06:03)
Bilingual Education fm Canada : Trial 参加者募集(2024/02/24 14:02)
日本の中学受験狂乱と英語イマージョンの大罪(2024/02/21 11:02)
日本で育つ子供へのバイリンガル教育: Trial 参加者募集(2024/02/18 04:02)
このコラムに類似したコラム
My Cabin Life Canada 7/13/2023 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/07/14 09:38)
[迷子の日本教育から子供を守りたいですか?Join Us!] 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/07/12 09:11)
My Cabin Life Canada 6/29/2023 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/06/30 10:20)
エッセイ特訓しましょう - Essay Basics 夏の半額キャンペーン 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/06/29 06:04)
カナダの優れた教育を日本で育つ子供に 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/06/28 13:51)