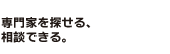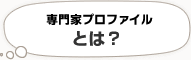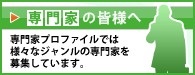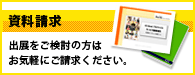- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
本坊事件高裁判決は、税務調査に違法性を認めなかったのみならず、
税理士法1条に触れつつ、
「税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に
規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする職業人であり、
そのような見地からすると、税理士は、税務代理に関する委任契約を締結した
納税義務者が課税庁の質問検査権を行使されるに当たり、納税義務の適正な
実現に資するべく、その現場に立ち会い、検査の対象となっている納税義務者の
すべき主張・陳述について代理・代行することができることは当然であり、
望ましいことでもある。そして、そのような立場に自覚的な税理士であるほど、
課税庁が税理士の立会いなしにする質問検査権の行使に警戒的になることは
容易に想定されるとともに、本件における控訴人もそのような立場から
本件税務署員らに対応したものと認められ、その心情には理解できる」
と、原告税理士の行動に理解を示しながら、
税理士の立会権を認めなかったことに、注意する必要があろう。
ただ、本件において、原告がとった行動は、
同業者として、申し訳ないが、やりすぎの感は否めない。
特に、ビデオカメラを持ち出して、調査内容を撮影しようとすること
については、守秘義務を課税庁側に主張されてもやむを得ない。
もし、撮影を許可して、この撮影された映像が万が一流出してしまった場合、
許可した調査官は公務員法違反で処分されるだけでなく、
原告自身も、税理士法違反に問われ、綱紀監察事例になるものである。
今回の判決は、国家賠償には当たらないだろうと、肯定的に評価はするが、
実務家としては、税理士の立会権の侵害については、
税務調査に対する学術的な意味合いとは異なる判断がなされた
いわゆる事例判決であると信じたいところである。
また、本坊事件は税理士法改正前の平成11年の事件であることを考えれば、
税理士法改正後は、税理士法に税理士の立会権が、
ある程度明確にされたのであるから、(本シリーズ(1)を参照)
税務権限代理証書を添付している権限ある税理士の立会権を侵害する
無理な調査は行われないようになることを期待したい。
本件のように不意打ち調査や税理士の立会権が無視されるような事態が
生じるのには、事務運営指針に基づいた税務行政の実態が一因であろう。
いわゆる通達行政である。
憲法84条が求める租税法律主義が、課税要件の全てを法律で決めなさい、
と明言しているにもかかわらず、税務行政は、
法の世界では法源にも含まれない通達や指針によって運営されているのである。
通達行政については、ある程度は必要悪の部分があると考えるが、
行き過ぎた通達行政が、自分では法の解釈をせず、疑問があれば、
何でも税務署に問い合わせて処理をするような税理士を生んでいるし、
平和事件のように、事例応答集に記載されている事例を模した
租税回避スキームが生まれてしまうのであろう。
話を戻す。
裁判所が判決文でも事務運営指針は、平成13年3月27日付けの
「税務調査の際の事前通知について」であるが、これには、事前通知は、
昭和37年9月6日付の「税務調査の際の納税者及び関与税理士に対する
事前通知について」に基づいて適切に実施することを要求し、
「有りのままの事実実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の
把握が困難であると想定される場合」には事前通知を要さない旨が
規定されている。
本件の場合に、調査が10年近く行われていなかったとはいえ、
優良法人として評されていた法人であったことから、大阪高裁も
「本件両会社は、これまで優良法人との評価を得ていた上、
具体的な問題点を把握した上での調査ではないから、あえて無予告で
調査をしなければならないほどの必要性があったかは、かなり疑問
というべきである。」と指摘しているところである。
ただ、だからといって調査の必要性がないとは判断できないので、
税務調査が違法とはいえないというのが、大阪高裁の判断である。
さて、問題は、この事務運営指針の法律解釈上の意味である。
通達は行政庁内部の業務命令に当たるのだから、税務署員は
通達(本件では事務運営指針)に従って業務を行うのは当然である。
しかし、通達は、法源でない以上、国民を拘束できるルールではない。
つまり、通達や事務運営指針の内容に国民が従う法的根拠はない。
租税裁判全体について言えることであるが、判決文を見ると、
通達どころか、私的著作物と最高裁が認定した質疑応答集や
コンメンタールを判決の根拠として引用する場合が結構多いのである。
弁護士に税法が専門といえる方が少ないことは業界内では
周知の事実であるが、裁判官はそうでないことを信じたいが、
正直、そうとは信じられないのが実情である。
本件も、事前調査の違法性を事務運営指針をもって否定する。
憲法84条は
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める要件を必要とする。」と規定するが、
事務運営指針は、法源に当たらないのであるから、
当然法律の定める要件には該当しない。
そのことを裁判所はどう評価するのか。
また、根拠として引用する事務運営指針は平成13年3月27日付
のものであり、平成11年の事件には適用することは許されない。
それとも、大阪高裁は、事務運営指針は法ではないから、
遡及適用も許されるとでも言うのであろうか。甚だ疑問である。
本件で適用すべき事務運営指針も、昭和37年9月6日付であり、
実に37年間もの長期にわたり、事務運営指針のまま残されている
規定である。ここまで長期に適用するのであれば、せめて個別通達に
昇格させることをしないのか?
まさかとは思うが、通達に昇格させると、税務六法に掲載
されてしまうから、事務運営指針のままにして、専門家である
税理士等にしか出回らないようにしたわけではあるまい。
現在では、国税庁HPで事務運営指針も検索できますが、
当時は、古い事務運営指針を調べるには苦労しましたね。
事務運営指針のみで国民の申告が適正に行われているのかを確認する
唯一の手段でもある税務調査のやり方を決めることに無理があり、
税務調査における無用のトラブルが生じる危険性も孕んでいるのである。
税理士が、税務署員による質問検査権の行使を警戒しなければならない
状況をなくすためにも、ルールの明確化、オープン化が必要なのである。