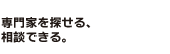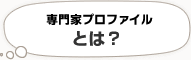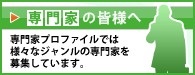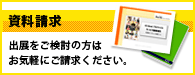- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
¥3,465 Amazon.co.jp
北村喜宣『環境法』弘文堂
2013年、本文600頁。末尾にキーワード解説がある。
環境法の最新テキストである。初版が2011年刊行である。第2版では、その後の法改正が追加されているが、法改正前の部分が現在形の記述となっており、継ぎ足しで書かれたと思われる部分と矛盾がみられる。
また、本文で説明されていない事項が図表の中でしか記載されていないことも多いので、要注意である。
上記書籍を読み終えました。
第1部 総論
「第1章 環境法学の学習にあたって」
環境とは、自然、人工環境、生活環境である。
人口環境とは、歴史的・文化的環境、農村や都市の景観等である。
公害は、生活環境に大きな影響を与えた。
「第2章 環境法政策の目標と基本的考え方」
環境法は、従前、汚染の予防・除去の費用について、受益者(購入者・役務を受ける者)負担原則、または、汚染者(汚染原因者)負担原則を取ってきたが、汚染の元となる物質を生産した製造者等に対して、拡大生産者負担原則に移行してきている。本稿では指摘されていないが、生産・製造→排出→汚染という流れで、より汚染に関して責任のある者に対して、いわば下流から上流に遡って負担を求める原則である。
なお、汚染土地の所有者・占有者等に負担を課す土壌汚染対策法は、上記の原則の例外である。
工場操業等の経済活動を阻害しない範囲での環境法という調和条項の考え方は、経済活動より環境保全を優先する原則に移行した。
ただし、不動産開発法(例えば、都市計画法、道路法等)の中には、不動産開発を優先する考え方があり、環境法とは異なる場合がある。
また、汚染除去の事後処理から、環境基準(排出基準、施設基準)を定めたうえで、排出・汚染を抑制する汚染予防の手法に移行してきている。
また、規制や汚染物等処理の主体が地方自治体の場合には、国の基準を守るだけでなく、地方自治体の対応・条例が問題となる。例えば、一般廃棄物(一般家庭の生活ごみ)の分別・収集・運搬・処理は、地方自治体が対応している。
汚染物質・廃棄物等の排出の抑制から、リサイクルへ移行してきている。
「第3章 環境規制の法的アプローチと規制手法」
強制的手法は、不利益処分となる行政処分(許可取消、命令等)、立入検査、賦課金、行政罰、刑罰等である。
誘導的手法は、補助金、税制優遇、低利融資等である。
任意的手法は、事業者名の公表等である。
行政と事業者との合意による手法は、公害防止協定、環境保全協定、景観協定(景観法)、建築協定(建築基準法)等である。
事業の手法として、生産・製造等の業者によるもの、汚染者、専門の処理事業者、指定法人(各種のリサイクル法)、基金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)等によるものがある。
なお、行政が行政調査、行政計画により、環境法の政策の目標を立て、達成する。
「第4章 個別環境法の基本構造」
環境法の個別法の第1条に目的規定があり、目的がわかる。
規制に関して、規制の対象となる物質・事業者、地域、行為が定めている。
特別法による場合もある。例えば、水俣病救済法、アスベスト救済法等である。
周辺住民参加の手法として、意見表明、公聴会等がある。
「第5章 環境法の実施主体と活動の枠組み」
「第6章 環境法の執行」
「第7章 環境訴訟・環境紛争処理」
損害賠償責任として、民法709条以下、民法717条(工作物責任)の不法行為に基づく損害賠償請求、国家賠償法2条(公営造物等)に基づく国家賠償請求、人格権に基づく差止請求権等である。
損害賠償請求の要件として、汚染者の故意・過失、違法性、結果、行為と結果の因果関係である。
汚染者が複数の場合、民法719条による共同不法行為があり、意思を連絡する主観的共同だけではなく、汚染行為が互いに無関係に行われた場合でも客観的共同不法行為でもよいと解しされている。
例外的に、無過失損害賠償責任として、水質汚濁防止法、大気汚染防止法に特別規定がある。
違法性として、企業の経済活動等の加害行為の性質・内容・態様・有用性、被害を受ける者の不利益、公共の利益、行政の環境基準等が比較衡量される受忍限度論が最高裁の基準である(国道43号線訴訟、小田急高架訴訟)。なお、将来の損害賠償請求については不確実性を理由として、最高裁は認めていない(大阪空港訴訟、横田基地訴訟等)。
因果関係として、資料の偏在や立証の困難性から、立証の負担を軽減するために、高度の蓋然性、疫学的証明でよいとされている。
差止請求の場合、人格権に基づくが、身体生命の健康被害等の重大な場合には認められているが、景観利益・眺望利益のような場合には認められていない。
行政不服審査法、行政事件訴訟法による行政救済法がある。
行政事件訴訟法では、例えば、廃棄物処理業の許可取消の取消訴訟、廃棄物処理業や施設の許可を義務付ける訴訟、または、許可の取消を義務付ける訴訟等がある。
また、損失補償の額に関しては、形式的当事者訴訟もあある。
行政事件訴訟法の場合、計画・告示の段階で、処分性を認められるかどうかに関しては議論がある。
行政の作為・不作為に関して、裁量権収縮説もあるが、最高裁は、裁量権の逸脱・濫用を違法とする立場を取っている。
公害健康被害補償法に基づく給付がある。
公害紛争処理法に基づく公的な裁判外紛争処理手続(ADR)である。国レベルでの重大事件・複数の都道府県にまたがる事件等を扱う公害等調整委員会、都道府県の公害審査会がある。紛争当事者のあっせん、調停、仲裁、裁定を行う。この手続を利用するメリットは、手続費用が低廉で、調査・鑑定費用は公費であり、専門家・行政が関与する公的な裁判外紛争処理手続(ADR)である。具体例では、豊島事件等がある。
第2部 各論
「第8章 環境基本法」
環境法の基本理念、すなわち、環境の保全、ひいては国民の健康で文化的な生活の確保を目的とすること等を定めている。
環境法の基本計画を策定すべきことを定めている。
裁判例は、環境基本法の条文から具体的な法的拘束力がただちに生じることはないと解している。
「第9章 循環基本法」
廃棄物処分より、リサイクルを優先させる考え方を基本理念とする。
拡大生産者責任の考え方が取られている。すなわち、リサイクル・処分の責任を、消費者や自治体から生産者にシフトさせるものである。
これを受けて、個別法として、容器包装リサイクル法、家電製品リサイクル法、自動車リサイクル法などがある。
「第10章 環境影響評価法」
環境アセスメントを定めている法律である。
手続として、事業に内容をよく知る事業者の負担でのアセスメント手続、実体規制として行政による環境配慮審査を定めている。
① 実施方法書の事前手続(「計画段階環境配慮書」で複数の案の比較検討を義務づけている)
② 「実施方法書」手続
③ 「準備書」手続(代替案がある場合には、記載を義務付けている)
④ 「評価書」手続
⑤ 「報告書」手続
⑥ この間、行政庁による審査・報告・公表、地方自治体への求意見、住民の意見の聴取がある。
⑦ その後は、個別法による許認可
なお、同書で、事業者による事業決定が既決事項と表現しているのは、不適当な表現と思われる。環境影響評価法は、いわば個別の環境法の事前手続と位置づけられており、アセスメントを実施していない場合には、そもそも許認可申請できず、申請しても不受理とされる。または、環境アセスメントを実施し、不適切な場合・不適当な方法の場合、再考させたり、最終的には不許可とすることで、事業を開始させないこと、あるいは方法・場所・態様などを変更させたりすることができる。または、事後の司法審査で事業の許可が取消される場合もある(例えば、小田急線高架事業取消訴訟第1審判決。ただし、控訴審で第1審判決は破棄され、上告審でも控訴審の判断は基本的に維持された)。
環境影響評価法が適用されないのは、都市計画法または港湾法が適用される場合である。
第1種事業(2条2項)は、環境アセスメントが当然に必要とされている。一定規模以上の道路、ダム、鉄道、飛行場(空港)、発電所、埋立・干拓、土地区画整理、産業廃棄物処理施設などである。
第2種事業(2条3項)は、第1種事業に準じる規模として、施行令5条で定めている場合(形式要件)、または、環境に影響を与えるおそれがある場合(2条4項、実体要件)。環境アセスメントが必要とされている。
「第11章 水質汚濁防止法」
水質汚濁防止法の対象は、一定規模以上の特定施設である工場・事業場(例えば、旅館業、ガソリンスタンド、畜産業など)の排水等、生活排水の規制である。
命令の名宛人が汚染原因者である。この点が、土壌汚染対策法と異なる。
地下水が汚染された場合、飲料水にもなるため、人への健康被害がより直接的である水質汚濁防止法がまず適用され、土壌汚染対策法も適用される。
無過失損害賠償責任の特別規定がある。
「第12章 大気汚染防止法」
特別法として、ダイオキシン法、アスベスト救済法がある。
大気汚染防止法の対象は、一定規模以上の特定の大気汚染する排出物質(ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん)の施設である工場・事業場、自動車排ガスの規制である。
無過失損害賠償責任の特別規定がある。
自動車道路に対しては、国家賠償法、民法717条が適用される。
「第13章 土壌汚染対策法」
土壌汚染対策法の土地所有者等の汚染除去等の義務が無過失責任であることが厳格にすぎると主張しているが、本法のモデルになったアメリカのスーパーファンド法への言及がない。
不動産登記簿で調べても土地所有者が判明せず、命令を下せないとの記述があるが、行政法の一般原則として、命令の名宛人は登記簿上の所有者に対して下せばよいであろう。ただし、例外的に、土地登記簿上の取引行為につき課税処分の重大性のみ(処分の明白かつ重大性を要件とせずに)を理由として、処分を無効とした最高裁判決がある。
「第14章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の前身は清掃法である。
なお、同法は、産廃法と略されることもあるが、一般廃棄物に関する規定も含んでいるので、正確な略称ではない。通常の略称は、廃掃法である。
原則規定は、一般廃棄物の箇所にあり、産業廃棄物に準用されているので、この法律を読むときは注意が必要である。
廃棄物には、以下の6種類がある。
一般廃棄物、
特別管理一般廃棄物(例えば、廃パソコン、自動二輪車など)、
産業廃棄物、
特別管理産業廃棄物、
事業系一般廃棄物、
事業系特別管理廃棄物
上記のうち、特別管理に該当するのは、爆発性、毒性、感染性がある場合である。
なお、建設残土、気体状物質、放射性物質(原子炉等規制法、放射性物質対策特別措置)については、別の法律が適用される。
一般廃棄物の処理責任は市町村(東京都の場合には特別区)にあり、産業廃棄物と異なる。
産業廃棄物処理業の許可は、収集・運搬や産業廃棄物処理施設を保有していることが前提となっているので、対人許可+対物許可である。行政法でいう警察許可として、羈束裁量と考えるべきとされる。
産業廃棄物処理施設は、基準を守っていることが前提とされているが、現実には種々の弊害(例えば、施設から有毒な水・物質が浸出したことなど)が生じたことから、効果裁量と考えるべきとされる。施設の設置に際しては、ミニ・アセスメントと呼ばれる環境影響評価手続が実施される。
産業廃棄物処理業の許可は義務的取消であり、環境法の中では異例である。ただし、連鎖的取消とならないように法改正で対応された。
特定産業廃棄物除去特別措置法は、除去費用の支援により、過去に不法投棄された産業廃棄物の除去を定めている。
「第15章 容器包装リサイクル法」
リサイクルの対象は、原則として、容器である。
リサイクルを義務づけられるのは、特定容器利用、特定容器製造等、特定包装利用の各事業者(特定事業者)である。特定事業者がリサイクルについて、指定法人に委託して料金を支払ったときは、リサイクル義務を履行したとみなされる。
飲料等のアルミ缶・スチール缶・紙製品、ダンボールは資源ゴミとして、別途、分別収集される。なお、本稿では指摘されていないが、資源ごみとして収集場所に置かれた古紙を持ち去って処罰された刑事事件もある。
本稿では指摘されていないが、レジ袋の有料化が一般的になった。
・建設リサイクル法
従来、建設現場では重機で建物等を取り壊しており、分別していなかった。そのため、産業廃棄物の不法投棄の事例が多数あった。そこで、建設残土等について、分別処理が義務付けられた。
・家電リサイクル法
リサイクルの対象となる特定家庭用電化製品は、エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機等である。リサイクルは、製造業者に義務づけられている。消費者が購入する時点で、リサイクル料金を支払い、それが販売業者を通じて製造業者に還流される。
・自動車リサイクル法
従前、自動車は粉砕処理され、基本的には鉄クズ等とされていた。本稿では指摘されていないが、廃車とされた自動車が放置され、社会問題となったことがあった。
リサイクルは、製造業者に義務づけられている。自動車の購入者が購入する時点で、リサイクル料金を支払い、それが販売業者を通じて製造業者に還流される。
「第16章 自然公園法」
自然公園法については、 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』の中で触れた。
自然公園法では、建物建築等が制限され、不許可とされた場合、損失補償を請求できる。これは、憲法29条に基づく。自然公園法では、もともと建築できないこともあるから、補償金が出ない場合もある。
「第17章 地球温暖化防止法」
二酸化炭素の排出量を規制する法律である。
民間企業どうしの排出権取引は、行政庁の許可により、効力を生じる。なお、排出権取引は、金融商品取引法の対象ともなる。
再生可能エネルギー特別措置法は、太陽光、風力、地熱等の再生可能エネルギーの調達を電気事業者に義務づけている。電気事業者は、その費用負担を電気需要者に転嫁している。