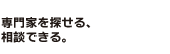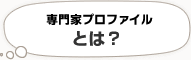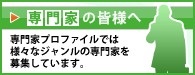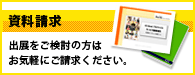- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
Blog201403,金融商品取引法(最高裁判決)
・金商法17条に定める損害賠償責任の責任主体は発行者等に限られない(最判平成20年2月15日,民集62巻2号377頁,損害賠償請求事件)
・最判決平成24年3月13日,ライブドア損害賠償請求事件(民集66巻5号1957頁)
・最判平成24年12月21日,アーバンコーポレイション再生債権査定異議事件(裁判集民事242号91頁,判例タイムズ1386号169頁)
金商法17条に定める損害賠償責任の責任主体は発行者等に限られない
最判平成20年2月15日,民集62巻2号377頁,損害賠償請求事件
【判決要旨】 証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集・売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。
1 本件は,不実の目論見書等の使用者の損害賠償責任について定めた証券取引法17条(平成16年法律第97号による改正前のもの。以下「法」という)の責任主体の範囲が問題となった事案であり,事実関係の概要は次のとおりである。証券取引法は平成18年改正され,法律の名前も金融商品取引法と改められたが,17条の構造は現在の金商法17条でも維持されている。
(1)。Xは,コール資金の貸借又はその媒介等を営む株式会社である。
(2)。Y1は英国法人であるA社を中心とする企業グループであるAグループに属する会社であり,同グループが日本において情報の収集,処理,分析等を行うために設立した会社である。Y2は,現在,Y1会社の代表取締役であり,後記の有価証券取引が行われた平成13年4月当時は,Y1の取締役の地位にあった者である。
(3)。Y2は,Y1の代表取締役であって平成13年当時も取締役であったBと共に,グレナダ法人であるC社を発行者とする,証券取引法上の有価証券である本件証券の募集のため,C社の事業内容等について説明した目論見書(有価証券の募集・売出し等のためにその相手方に提供する当該有価証券の発行者の事業その他の事項を説明する文書)である本件目論見書をXに交付して,本件証券の取得を勧誘し,あっせんした。また,Y2及びBは,Xからの質問に答えるなどして,C社と共にXに対して本件目論見書の内容について説明をした。
(4)。Xは,本件目論見書の記載とY2らの説明を基に本件証券を取得することとし,平成13年4月5日,C社から本件証券を代金30億円で購入した。
(5)。しかし,本件目論見書の記載及びその内容に関するY2らの説明は,投資資金の送金先,資金の運用方法,担保・保証の有無などの多くの重要な点で,実際の資金の流れや管理等の実態と食い違っており,Xは償還期限から4年以上が経過した平成18年6月の時点でも,本件証券の償還を受けることはなかった。
2 上記の事実関係において,Xは,Y2に対しては法17条に基づき,Y1に対しては,その代表者であったBが法17条の責任を負うとして,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)261条3項,78条2項,民法44条1項に基づき,損害賠償の支払を求めた。
3 第1審は,法17条の責任主体について,証券の発行者,募集若しくは売出しをする者又は引受人又は証券会社等といった有価証券の発行から取得に至る過程に介在する者に限られないと解するとしても,Y2及びBは,Xの本件証券の購入に際して,Xの求めに応じて情報を提供したり,書面を作成していたにすぎないこと,Xは大規模に短資業を営む会社であって本件目論見書の分析は十分可能であったことなどからすれば,Y2及びBは法17条にいう「有価証券を取得させた者」には該当しないと判断して,Xの請求をいずれも棄却した。
原審は,第1審とは異なり,Y2らは単なる情報提供にとどまらず,有価証券の取得の勧誘,あっせんをしたという事実を認定した上で,法17条の責任主体は,発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等又はこれと同視できる者(以下,併せて「発行者等」という。)。に限られると解釈した上で,Y2及びAは,法17条にいう「有価証券を取得させた者」に該当しないと判断した。これに対し,Xが上告受理の申立てをしたところ,第二小法廷は原判決を破棄し事件を原審に差し戻した。
4 本件で問題となった法17条は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示(以下「虚偽記載のある目論見書等」という。)。を使用した者の損害賠償責任について定める。この規定の性質について,通説は,不法行為責任の特則であり,ただし書が定めるとおり,故意・過失の立証責任が行為者に転換されている点,すなわち過失が推定される点に特色があると解している
従来,有価証券の取得の勧誘やあっせんに際して虚偽の説明等を行った外務員や証券会社等の責任については一般の不法行為に基づく請求がされる事例が多数を占め,法17条を含む証券取引法の損害賠償責任規定に基づき責任を追及する事例は,公刊された裁判例をみる限りあまり見られなかった。
学説でも,法17条の責任主体について意識的に論じたものは少なく,「募集又は売出しに伴い証券市場における便益を享受することとなる発行会社を念頭に置いたものではなく,当該取引に関して詐欺的な表示を行い,不当な資金配分に直接関与した者が該当するものと思われる。」旨論じた文献が見られる程度であった。
5 本判決は,法17条は虚偽記載等のある「目論見書を使用して有価証券を取得した者」と規定しており,責任主体を発行者等に限定する文言は存在しないこと,証券取引法は目論見書の使用者に法定の記載内容と異なる内容の目論見書等を使用してはならないとの義務を課していること,証券取引法は発行者の責任について別に18条2項に規定を置いていることなどを理由に,法17条の責任主体は,虚偽記載のある目論見書等を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,発行者等に限るとすることはできないと判断して,原審のような限定解釈を採らないことを明らかにした。
原審は,法17条の責任主体を募集又は売出しの場合の目論見書の交付義務について定めた法15条2項(金商法15条2項)。の責任主体に準じて理解したものということができるが,法16条や法18条を見ても分かるように証券取引法(金商法も同じ)は損害賠償責任を定めた条文ごとにその責任主体を書き分けていることから,原審の解釈には無理がある。本判決は,これに加えて,証券取引法・金商法が投資者の保護をその目的の一つとしており,しかも目論見書等の開示書類の虚偽記載について詳細な規定を置いていることなどを考慮して,原審のような限定解釈を採用しなかった。本件は,法17条の「有価証券を取得させた者」の意義について,最高裁が初めて判断した。
最判平成24年3月13日,ライブドア損害賠償請求事件,民集66巻5号1957頁
【判決要旨】
1 検察官は,金商法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる。
2 金商法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」とは,虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにするに足りる基本的事実をいう。
3 金商法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」とは,投資者が虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券を取得するにあたって実際に支払った額と当該取得の時点において当該虚偽記載等がなかった場合に想定される当該有価証券の市場価額との差額に相当する分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりのすべてをいう。
4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき,投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合において,個々の取引ごとの取得と処分との対応関係の特定ならびに取得価額および処分価額の具体的な主張,立証がされていないときは,裁判所は,当該有価証券の取得価額の総額と処分価額の総額との差額をもって金商法21条の2第1項にいう「第19条第1項の規定の例により算出した額」とした上で,当該差額と同法21条の2第2項によって推定される損害額の総額とを比較し,その小さいほうの金額をもって,上記投資者が同条に基づき請求することのできる額とするという算定方法によることができる。
5 金商法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る(民法412条)。
1 事案の概要
本件は,Y(株式会社ライブドア。現商号は株式会社LDH)の株式(ライブドア株)を流通市場で取得したXらが,Yの提出した有価証券報告書(本件有価証券報告書)に約3億円の経常赤字を約50億円の経常黒字と偽った虚偽記載(本件虚偽記載)。があったことにより損害を被ったと主張して,金商法21条の2に基づき,Yに損害賠償を求めた事案である。本件の争点は多岐にわたるが,主な争点は,Xらが同条に基づきYに賠償を請求することのできる損害額である(以下,同条の項を摘示する場合は原則として項番号のみを掲記する)。
2 事実関係
Yは,その代表者Aの指示ないし了承の下,平成16年12月27日,同年9月期の連結会計年度について,実際には約3億1278万円の経常赤字であったのに,売上計上が認められないライブドア株の売却益や架空売上等をそれぞれ売上高に含めるなどして,経常利益を約50億3421万円と記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書(本件有価証券報告書)。を関東財務局長に提出した。平成18年1月16日,東京地方検察庁は,Aを含むYの役員らについて,証券取引法違反の容疑があるとして強制捜査に着手した。東京地検検察官(本件検察官)は,同月18日,司法記者クラブに加盟する報道機関の記者らに対し,Yが平成16年9月期決算(単体)において,Yの傘下にあった企業の預金等を付け替えることで,約14億円の経常黒字と粉飾した有価証券報告書の虚偽記載の容疑がある旨伝達し,その頃その旨の報道がされた(本件開示)。Y株は,強制捜査着手以後その株価が暴落し,同年4月に上場廃止となった。Xらは,機関投資家であり,本件開示以前にY株を取引所市場において取得し,本件開示の日においてこれを保有していたが,本件開示後,Y株を全て売却した。そこで,Xらが,本件虚偽記載によって損害を被ったと主張して,金商法21条の2に基づき,Yに対し,合計約108億円の損害賠償を求めたのが本件である。これに対し,Yは,有価証券報告書の虚偽記載によって投資者に生ずる損害は,取得価額と想定価額(当該虚偽記載がなければ想定された取得時の市場価額)との差額(いわゆる取得時差額)が現実化した分にとどまると解すべきであるところ,本件開示後のY株の値下がりには,Aの逮捕や過熱報道等に起因する値下がり分など,取得時差額を超える値下がり分が含まれているから,これらを4項ないし5項によって減額すべきであるなどと反論した。
3 ライブドア関連の訴訟
Yによる本件虚偽記載を理由として投資者が損害賠償を求める訴訟は,複数提起されており,これまでに①(A事件)。本件1審である東京地判平20.6.13判タ1294号119頁,本件原審である東京高判平21.12.16金判1332号7頁,②(B事件)東京地判平21.5.21判タ1306号124頁,その控訴審である東京高判平23.11.30金判1389号36頁,③(C事件)東京地判平21.6.18判タ1310号198頁,④(D事件)東京地判平21.7.9判タ1338号156頁が言い渡されている。
4 第1,2審の判断
(1)。第1審は,本件開示後のY株の値下がりは,Aらが逮捕されたこと,F社との提携解消方針が報道されたこと,東京証券取引所がY株を監理ポストに割り当てたことなどがその要因となっているなどとして,5項に基づき,2項の推定損害額から3割を減額し,Xらの請求を合計約95億円の限度で認容した。
(2)。これに対し,原審は,1項にいう「損害」とは,民法709条にいう「損害」と同様に虚偽記載等と相当因果関係のある損害をいうものと解すベきであるから,投資者は取得時差額に限られず相当因果関係ある損害についてその賠償を求めることができるとした上で,Aらの逮捕など強制捜査,過熱報道,Y株の監理ポスト割当て等の事情は,本件虚偽記載の発覚によって通常起こり得る事態であるとして,5項に基づく減額割合を1割にとどめて,Xらの請求を合計99億円の限度で認容すべきものとした。
(3)。Yが上告受理申立てをしたところ,第三小法廷は,これを受理し,原審の判断を基本的に是認して,おおむねYの上告を棄却すべきものとした(ただし,原判決における損害額の算定の一部については誤りがあるとして,その部分については破棄自判し,総認容額が約1100万円減額されている)。
5 判示1(公表の主体)及び2(公表の対象)について
(1)。前提
本件では,2項の推定規定による損害額の算定が問題となっていることから,本判決は,まず,2項にいう「公表」があったか否かを検討している。本判決が採り上げたのは,公表の主体(判示1)及び公表の対象(判示2)に関する論点である。
(2)。公表の主体(判示1)
原審は,本件検察官が,報道機関に有価証券報告書の虚偽記載の容疑がある旨を伝達した行為をもって,2項にいう「公表」があったものとしている。2項にいう「公表」の意義については,3項に定義規定が置かれており,「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」が公表の主体とされている。そこで,検察官が「法令に基づく権限を有する者」に含まれるかが問題となる。
学説は,積極説と消極説に分かれている。
積極説は,「法令に基づく権限を有する者」とは,有価証券報告書等の提出者から信頼性のある情報を取得することができる者を意味すると解すべきであるとした上で,検察官が法令上種々の捜査権限を与えられており,その権限を行使して得られた捜査の結果が特に信頼性が高いことを理由に,検察官も「法令に基づく権限を有する者」に含まれるとする(黒沼悦郎・金判1303号6頁,田中亘・ジュリ1405号186頁,河内隆史・セレクト2010-Ⅱ24頁)。立案担当者の解説である三井秀範編『課徴金制度と民事賠償責任』159頁も,警察による捜査結果の発表について,「公表」に当たるとしている。
消極説は,論者によって理由付けは異なるものの,①検察官による捜査結果の発表は法令に基づくものではなく,金融商品取引の適正を実現しようとする趣旨に基づくものでもないこと,②「公表」は2項の推定規定を適用するための要件であるから,明確で客観的な基準が設定される必要があり,厳格な解釈をすべきであること,③2項が公表の主体を「当該書類の提出者」と「法令に基づく権限を有する者」とを並べて列挙していることからすれば,「法令に基づく権限を有する者」は「提出者」に準ずるものと解すべきであることなどを理由に,「法令に基づく権限を有する者」とは,当該企業に対し法令に基づく監督権限ないし処分権限を有する行政官庁(金融庁等)に限られ,検察官は含まれないとする(田中庸介・関学60巻1号16頁,新谷勝・金判1308号4頁,弥永真生「金商法21条の2にいう『公表』の意義」商事1814号5頁,近藤光男・商事1846号13頁)。
裁判例をみると,A~D事件の第1,2審判決は,いずれも検察官が「法令に基づく権限を有する者」に含まれることを認めている。
本判決は,検察官が有価証券報告書等の虚偽記載等の犯罪につき刑事訴訟法に基づく種々の捜査権限を有しており,その権限に基づき正確な情報を入手することができ,その情報には類型的に高い信頼性が認められることを根拠に,検察官が「法令に基づく権限を有する者」に当たるとして,積極説に立つことを明らかにした。
(3)。公表の対象(判示2)について
本判決は,本件検察官が開示した情報が3項にいう「虚偽記載等に係る…事項」に当たるか否かを検討している。この点については,論旨において,3項が当該書類の「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」と定めていることなどから,上記「事項」とは,当該有価証券報告書等に記載すべきであった真実情報(本件でいえばYが約3億円の経常赤字であったこと)。をいうと解すべきであり,このような真実情報が開示されない限りは「公表」があったとはいえないと主張されていたところである。
立案担当者の解説である三井編・前掲159頁は,「虚偽記載については,虚偽部分を指摘すれば足りるし,また,厳密な意味で真実を完全に公表しなければならないわけではなく,当該証券価額への誤った評価を解消するために必要な程度の事実の公表があれば足りる」として,「事項」を広く解釈する見解に立っている(緩和説。黒沼悦郎・商事1872号22頁も参照)。他方,弥永・前掲7頁は,虚偽記載の内容としておおむね正しい情報が開示されない限りは「公表」がされたとはいえず,例えば「金額は不明であるが資産の過大計上があったようである」との発表では足りないとして,「事項」を厳格に解釈する見解に立っている(厳格説)。。なお,「公表」の意義等については,岩原紳作ほか「金融商品取引法セミナー(12)民事責任(2)。」ジュリ1401号76頁以下参照。
裁判例をみると,A~D事件1,2審判決は,いずれも結論としては本件開示が「公表」に当たることを肯定しており,緩和説に立っているものと思われる。
本判決は,取引所市場の評価の誤りを明らかにするに足りる情報が開示され,その結果当該有価証券が大きく値下がりしたにもかかわらず,真実情報が明らかにされないことをもって「公表」がないものとするのは投資者保護に欠けることを理由に,真実情報について開示されることまでは要しないとした。そして,①2項が「公表」を推定の基準時としたのは,「公表」によって当該有価証券に対する取引所市場の評価の誤りが明らかになることが通常期待できるという趣旨によること,②評価が誤っていたかどうかは「公表」時点で既に明らかになっている事実を考慮に入れて判断されるべきことであることから,「虚偽記載等に係る……事項」とは,当該有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにするに足りる基本的事実をいうものと解すべきであるとして,本件開示の内容が上記基本的事実に当たることを肯定し,本件検察官による本件開示が2項にいう「公表」に当たることを肯定した。
本判決は緩和説に位置付けられるものであるが,「評価の誤りを解消するに足りる事実」の開示ではなく,「評価の誤りを明らかにするに足りる基本的事実」の開示で足りるとしているのは,取引所市場の評価の誤りを完全に解消するだけの情報が開示される必要はないという点を,より明確にする趣旨であると思われる。
6 判示3(5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義)
本件では2項が適用されることが肯定されたため,次に本判決は,5項によって減額すべき「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義について検討している。
立案担当者は,2項の趣旨について,虚偽記載等による投資者の損害の額は取得価額と想定価額の差額となるところ,想定価額を立証することは極めて困難であることから,公表日前後1か月間の各平均株価の差額をもって取得時差額の近似値であると考え,2項を設けたものである旨の説明をしている(三井編・前掲37頁)。これを受けて,学説においても,上記「値下り」とは,取得時差額相当分の値下がりを指すという見解がある(取得時差額説)。この見解は,取得時差額を超える値下がりは会社の信用毀損等によって生ずる間接損害にすぎず,これについて特定の株主が会社に対し賠償を請求することを認めれば,他の株主及び会社債権者を害することになるなどとして,取得時差額を超える値下がり分は4項又は5項によって減額されるべきであるとする(田中亘・前掲187頁参照。加藤貴仁「流通市場における不実開示と投資家の損害」新世代法政策学研究11号303頁も結論同旨)。
これに対し,神田秀樹「上場株式の株価の下落と株主の損害」曹時62巻3号619頁は,そもそも虚偽記載等による投資者の損害の額が取得時差額に限られるという前提に疑問を呈し,取得時差額は出発点にすぎないとする。そして,2項についても,取得時差額を推定する規定というより,むしろ,「公表前後の各1か月の株価の差額を損害額ととらえることは,虚偽記載による影響を示す数値である可能性が高いという,その意味で虚偽記載との因果関係が高い数値であるという考え方のうえに成り立って因果関係の推定を認めたものと理解するほうがベターである」とする(相当因果関係説)。この見解に立てば,会社の信用毀損による値下がりなど,取得時差額を超える値下がりであっても,虚偽記載等と相当因果関係があるということができるものであれば,4項又は5項による減額は認められないことになろう(潮見佳男「虚偽記載等による損害」商事1907号15頁,同「不法行為における財産的損害の『理論』」曹時63巻1号1頁も参照)。
裁判例をみると,B~D事件1審は,いずれも取得時差額説に立つことを明らかにして,推定損害額の約3分の2を5項により減額している(本件1審も,強制捜査等による値下がりを理由として減額していることから取得時差額説に立ったものと思われる。)。これに対し,本件原審は,取得時差額説を明確に否定して相当因果関係説に立っていた。
本判決は,1項にいう「損害」が一般不法行為の規定と同様に,虚偽記載等と相当因果関係のある損害を全て含むとの解釈を示した上で,2項にいう「損害」についても,これと同様に虚偽記載等と相当因果関係のある損害を全て含むものと解するのが相当であって,これを取得時差額に限定すべき理由はないとした。そして,5項は2項を前提とする規定であるから,5項にいう「虚偽記載等によって生ずベき当該有価証券の値下り」とは,取得時差額相当分の値下がりに限られず,虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいうとして,取得時差額説を排斥して,相当因果関係説に立つことを明らかにした。あわせて,本判決は,傍論ではあるものの,2項の推定規定を用いずに,一般不法行為の規定に基づき,あるいは1項に基づき請求する場合についても,取得時差額に限らず虚偽記載等と相当因果関係のある損害の全てについて賠償を受けることができることを述べており,一般不法行為の規定と金商法21条の2各項とを整合的に解釈する姿勢がうかがわれる。
なお,本判決は5項による減額について判示したものであるが,4項による減額についてもその射程は及ぶものと思われる。
7 判示4(請求可能額の算定方法)。について
本判決は,虚偽記載等に係る有価証券につき,投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得し,これを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における請求可能額の算定方法について,「個別比較法」と「総額比較法」の当否を検討している。
まず,モデルケースとして,「取得価額120円の有価証券を70円で処分し(取引1),取得価額100円の有価証券を80円で処分した(取引2)。。2項によって推定される損害額(ただし5項による減額後のもの)は30円である。」とのケースを用いて,個別比較法と総額比較法について説明する(以下の説明では,全ての取引につき取得価額が処分価額を上回ることを前提とする)。
取引 取得価額 処分価額 19条1項限度額 推定損害額 請求可能額
1 120 70 50 30 30
2 100 80 20 30 20
合計 220 150 70 60 50
個別比較法とは,個々の取引ごとに,金商法19条1項の規定の例により算出した額(取得価額と処分価額の差額。19条1項限度額)。と推定損害額(4項又は5項によって減額する場合は減額後の額。以下同じ。)。とを算出し,両者を比較して,金商法21条の2に基づく請求可能額を算定するという方法である。上記モデルケースにつき個別比較法で請求可能額を算定すると,取引1については推定損害額(30円)が19条1項限度額(50円)を超えていないから,推定損害額(30円)が請求可能額となる。取引2については推定損害額(30円)が19条1項限度額(20円)を上回っているから,19条1項限度額(20円)。が請求可能額となる。以上により,請求可能額の合計は50円となる。
これに対し,総額比較法とは,取得価額の総額と処分価額の総額との差額をもって19条1項限度額とした上で,これと推定損害額の総額とを比較し,その小さい方の金額をもって請求可能額とするという算定方法である。上記モデルケースにつき総額比較法で請求可能額を算定すると,19条1項限度額の総額は70円,推定損害額の総額は60円であるから,請求可能額は60円となり,個別比較法の場合を上回る。
個別比較法は,個々の取引ごとに19条1項限度額による制限を課し,この額を超過する部分についてはこれを切り捨てていくという算定方法であるため,最終的な請求可能額は総額比較法による場合を超えることはなく,投資者に不利な算定方法といえる(上記モデルケースでも,個別比較法による請求可能額は,総額比較法による場合よりも10円少なく,投資者に不利な結果となっているが,この差額10円は,個別比較法で取引2における19条1項限度額超過分〔10円〕を切り捨てたために生じたものである。)。。原審は総額比較法によったが,Yは論旨で個別比較法が妥当であるとする。
個別比較法と総額比較法のいずれが相当かについては,潘阿憲・ジュリ1419号145頁が,「2項が,公表日現在において保有している株式の全部について,その公表日前後1カ月間の株価の変動につき平均額を推定される損害額として採用している以上,保有株式の一部についての推定損害額が金商法19条1項の上限額を超えても,それは推定損害額の算定において,当然の前提として織り込まれているものと見るべきではなかろうか。」と述べて,総額比較法に親和的な見解を示しているほかは,特段の議論が見られない。
裁判例をみると,B~D事件においては,全ての判決において個別比較法によって請求可能額が算定されているが,投資者が個別比較法によって請求可能額を算定して請求していた事案に関するものであり,かつ,個別比較法の妥当性について明示的に判断はされていない。他方,本判決の1審及び原審は,総額比較法によって請求可能額を算定しているが,Xらの算定方法に従ったにすぎず,その理論的根拠等については何ら触れていない。
本判決は,まず,理念的には個々の取引ごとに損害が生じているとみることができることから,個々の取引ごとの取得と処分との対応関係が特定され,取得価額及び処分価額につき具体的な主張,立証がされているとき(すなわち個別比較法による算定が可能なだけの主張,立証がされているとき)。には,裁判所が個別比較法によって請求可能額を算定することを否定する理由はないとした。しかしながら,①総額比較法によっても19条1項限度額を上限とした趣旨には反しないこと,②個別比較法によらなければならないことをうかがわせる文言が金商法21条の2に存しないこと,③取得と処分との対応関係を特定することが困難なこともあり得ることなどを考慮すると,上記の主張,立証がされていない場合には,裁判所が総額比較法により請求可能額を算定することも許されるとした。これを具体的な訴訟の場面に当てはめてみると,投資者が総額比較法によって請求可能額を算定して請求してきたのに対し,会社側が個別の取得と処分の対応関係を特定し,各取引の取得価額及び処分価額を主張立証した場合には,裁判所は個別比較法によって請求可能額を算定することになろう(なお,この立証は,いわゆる本証であると解されるが,その法的性質を抗弁あるいは間接反証類似のものととらえるべきか,個々の有価証券の個性が失われている株式等振替制度の下で取得と処分の対応関係をどのように特定すべきかなど,なお検討すべき問題があろう。)。。本件では,Yがこのような主張立証を尽くしていなかったため,総額比較法によった原審の判断に違法はないとされた。
ただし,本判決は,原審が,X6の請求につき,X6自身が取引をして被った損害に係る部分と,B社が取引をして被った損害でB社からX6が権利関係を承継したものに係る部分とを区別しないで,あたかもX6が全ての取引を行ったもののように扱って総額比較法を適用した点については,上記承継によってYが賠償すベき損害額が変わるものではないから,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,原判決を破棄し自判した。
8 金商法19条1項と同法21条の2第5項の適用順序
金商法21条の2第2項の規定を用いて損害額を推定する場合,同法19条1項所定の限度額(取得価額と市場価額ないし処分価額との差額。以下「19条1項限度額」という。)。による制限と,同法21条の2第5項による減額の適用順序が争われたので,補足しておきたい。この点については,①2項推定損害額の算出→5項による減額→19条1項限度額による制限という適用順序(以下「19条1項後適用説」という。)。と,②2項推定損害額の算出→19条1項限度額による制限→5項による減額という適用順序(以下「19条1項先適用説」という。)。があり得る。
最高裁は,ライブドア事件において自判するに当たり,19条1項後適用説に立つことを前提にして認容額を算定している。
9 判示5(遅滞時期)。について
金商法21条の2に基づく損害賠償債務の遅滞時期については,同条所定の責任を不法行為責任とは異なる法定責任と捉え(法定責任説)。,民法412条3項により履行請求時から遅滞に陥るとする見解がある(B事件1審判決参照)。
しかしながら,学説上は,金商法21条の2は一般不法行為の規定の特則であると解する見解(不法行為責任説)。が通説であり(神田・前掲621頁,山下友信=神田秀樹編『金融商品取引法概説』178頁〔小出篤〕,川村正幸編『金融商品取引法〔第4版〕』206頁〔芳賀良〕等),立案担当者も不法行為責任説に立っている(三井編・前掲153頁)。。
本判決も,上記通説と同様に不法行為責任説に立って,金商法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥ることを明らかにした。
最判平成24年12月21日,アーバンコーポレイション再生債権査定異議事件
裁判集民事242号91頁 ,判例タイムズ1386号169頁
【判示事項】 株式会社が,臨時報告書及び有価証券報告書の虚偽記載等の事実の公表をするとともに,同日,再生手続開始の申立てをした場合において,虚偽記載等がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載等がなければこれを取得しなかった場合における,上記投資者に生じた当該虚偽記載等と相当因果関係のある損害を,金商法21条の2第2項の規定により損害の額を算定するに当たり,上記投資者が当該虚偽記載等の公表後,上記株式を取引所市場において処分したときは,その取得価額と処分価額との差額を基礎とし,同条4項又は5項の規定により減額をし,経済情勢,市場動向,当該上場株式を発行する会社の業績など当該虚偽記載等に起因しない市場価額の下落分を上記差額から控除して,これを算定すべきである。
1 本件は,東証一部上場企業であった株式会社アーバンコーポレイション(以下「アーバン」という。)。の株式(以下「アーバン株」という。)。を取引所市場で取得した個人投資家らが,アーバンの提出した臨時報告書等に虚偽記載等があったことを理由として,アーバンの再生手続において,金商法(以下「金商法」という。)。21条の2に基づく損害賠償債権につき再生債権として届出をしたところ,アーバンがその全額を認めなかったため,個人投資家らとアーバンとの間で上記債権の存否及び額について争われた査定異議訴訟である。
2 事実関係の概要等
本件の事実関係の概要等は,次のとおりである(なお,月日は全て平成20年である。)。。
(1)。アーバンは,市場の冷え込み等により新たな借入れや借換えが困難となり,資金調達に困難を来すようになっていたことから,6月26日,B社に発行総額300億円の転換社債型新株予約権付社債(以下「本件CB」という。)。を発行する旨の取締役会決議をし,7月11日に払込金の支払を受けた。ところが,アーバンは,これと並行してB社との間でスワップ契約を締結しており,本件CBの発行によってアーバンが得た払込金は即座にB社に還流されることとなっていた。にもかかわらず,アーバンは,6月26日に提出した臨時報告書(以下「本件臨時報告書」という。)。等において,本件CB発行の資金の使途として,債務の返済に使用する予定である旨を記載したのみで,上記資金が上記スワップ契約に基づく支払金に充てられることについて何ら記載しなかった(以下「本件虚偽記載等」という。)。。
(2)。その後,アーバンは,業務・資本提携交渉を進めていた米国大手投資銀行M社からTOBを拒絶され,8月13日,本件虚偽記載等の事実を公表するとともに(以下,この日を「本件公表日」という。)。,再生手続開始の申立てをした(以下「本件再生申立て」という。なお,アーバンは同月18日に再生手続開始の決定を受けている。)。。
(3)。アーバン株は,本件公表日前からほぼ一貫して値下がりを続けていたところ,本件公表日の翌日から大幅に値下がりし,9月14日に上場廃止となった。
(4)。そこで,本件公表日前にアーバン株を取引所市場で取得していた個人投資家であるX1(①事件)。及びX2(②事件)。が,本件虚偽記載等によって損害を被ったと主張して,それぞれ金商法21条の2に基づき損害賠償債権につき再生債権として届出をしたところ,アーバンはその全額を認めなかった。
3 訴訟の経緯
(1)。 ①事件
ア 第1審(東京地判平22.3.9金法1903号102頁)。は,金商法21条の2第2項によって損害額を推定した上,同推定額(以下「2項推定損害額」という。)。には本件虚偽記載等によって生ずべき値下がり以外の事情によるものも含まれているとして,まず2項推定損害額に同法19条1項の制限を適用し,次いで同法21条の2第5項によってその2割を減額して,1株当たりの損害額を約47.98円と査定した。
イ これに対し,原審(東京高判平22.11.24判タ1351号217頁)は,アーバンが6月末には破綻状態にあり,再生手続開始の申立ては必然的であったから,アーバン株の値下がりが本件再生申立てによって生じたものとは認められないなどとして,2項推定損害額からの減額を一切認めず,金商法19条1項の制限内で1株当たりの損害額を約59.97円と査定した。
ウ アーバンが上告受理申立てをしたところ,第二小法廷は,最三小判平24.3.13民集66巻5号1957頁(以下「ライブドア事件判決」という。)。を引用して,金商法21条の2第4項及び5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」とは当該虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりをいうところ,アーバン株の値下がりによってX1が受けた損害の一部には本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がり以外の事情により生じたものが含まれているというべきであるとして,これを否定した原判決を破棄し,本件を原審に差し戻した。
(2)。 ②事件
ア 第1審(東京地判平21.10.28〔公刊物未登載〕)。及び原審(東京高判平22.3.17〔公刊物未登載〕)。は,本件虚偽記載等がなければX2がアーバン株を取得することはなかったものと認定した上,X2に生じた損害は,取得価額と想定価額(アーバン株の取得時において本件虚偽記載等がなかったならば想定される価額)との差額であるなどとして,X2の損害額を2615万円(1株当たり約74.71円)と査定すべきものとした。
イ アーバンが上告受理申立てをしたところ,第二小法廷は,最三小判平23.9.13民集65巻6号2511頁(以下「西武鉄道事件判決」という。)。を引用して,臨時報告書に虚偽記載等がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が,当該虚偽記載等がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,当該虚偽記載等により上記投資者に生じた損害の額,すなわち当該虚偽記載等と相当因果関係のある損害の額は,上記投資者が当該虚偽記載等の公表後,上記株式を取引所市場において処分したときは,その取得価額と処分価額との差額を基礎とし,経済情勢,市場動向,当該上場株式を発行する会社の業績など当該虚偽記載等に起因しない市場価額の下落分を上記差額から控除して,これを算定すべきであるとして,これによらなかった原判決を破棄し,本件を原審に差し戻した。
4 アーバンコーポレイション事件
ア アーバンによる臨時報告書等の虚偽記載等については,個人投資家が金商法21条の2に基づく損害賠償債権の存在を主張した査定異議訴訟が多数提起された。最高裁に係属したものとしては,(A)。東京地判平21.10.28,東京高判平22.3.17(本件②事件)。,(B)。東京地判平22.3.9,東京高判平22.11.24(本件①事件)。,(C)。東京地判平22.1.13(公刊物未登載),東京高判平22.12.24(公刊物未登載),(D)。東京地判平23.2.7判タ1353号219頁,東京高判平23.6.16(公刊物未登載),(E)。東京地判平22.3.26金法1903号102頁,東京高判平23.12.20(公刊物未登載),(F)。東京地判平22.1.12判タ1318号214頁,東京高判平23.12.20(公刊物未登載),(G)。東京地判平23.1.26証券取引被害判例セレクト42号70頁,東京高判平24.3.29消費者法ニュース92号283頁,(H)。東京地判平23.8.29(公刊物未登載),東京高判平24.6.21(公刊物未登載),(I)。東京地判平23.4.11(公刊物未登載),東京高判平24.6.7(公刊物未登載)。がある(以下,上記裁判例を引用する場合は,例えばA事件の1審判決を「A-1」などと表記する。)。。
イ 上記裁判例では,金商法21条の2第2項の損害額推定規定を用いるか否かでまず大きく判断が分かれた。A-1,2では,本件虚偽記載等がなければ個人投資家がアーバン株を取得することはなかったと認定され,同項を用いずに,すなわち同条1項に基づき個人投資家が請求することのできる損害額が認定された。
ウ これに対し,その余の裁判例は,いずれも金商法21条の2第2項を用いて損害額が推定され,同条4項又は5項によって減額することの可否や減額割合が争点となった。
圧倒的多数の裁判例は,2項推定損害額には本件虚偽記載等による値下がり以外の分が含まれているとして,金商法21条の2第5項により,2項推定損害額の一部を減額している。その額については,多くの裁判例は,5割強(C-1,2)ないし約8割(F-1,2)という大幅な減額を認めている。中には取得価格の11.41%を超える額について減額を認めているものもある(H-2,I-2。両判決は,個人投資家らが被った損害がいわゆる高値取得損害〔取得価格と想定価格の差額〕であることを前提に,本件虚偽記載等の影響によって引き上げられた価格は値幅制限〔ストップ安〕の80円を超えないとして,本件臨時報告書の提出日の翌日における想定価格を264円〔=前日の株価344円-80円〕と算定し,これと実際の株価〔298円〕との差額〔34円〕が実際の株価の約11.41%であることなどから,取得価格の11.41%が高値取得損害に当たるとしたものである。)。。
他方で,B-2及びG-2は,アーバン株の値下がりによって生じた個人投資家の損害は全て本件虚偽記載等に起因するものであるとして,2項推定損害額から一切の減額を認めておらず,下級審裁判例の判断が分かれていた。
5 本判決
(1)。 ①事件
ア 本判決はB-2の上告審判決であり,2項推定損害額からの減額の可否が争われた。本判決は,ライブドア事件判決で示された一般論を引用した上,本件公表日前後1箇月間のアーバン株の値下がりについて,本件公表日前と後とに分けて検討している。
まず,本件公表日後の値下がりについて,本判決は,①上記値下がりは,本件虚偽記載等の公表と本件再生申立てとがあいまって生じたものであるところ,本件再生申立ては,かねてから継続していたアーバンの資金繰りの悪化によるものであって,本件虚偽記載等の公表によって資金繰りが悪化したわけではないこと,②アーバンは,M社との業務・資本提携交渉を開始しており,TOBも見込まれていたなど,倒産状態であったとはいえないことなどから,本件再生申立てによる値下がりが本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりということはできないと判断した。
次に,本件公表日前の値下がりについて,本判決は,アーバン株のほぼ一貫した値下がりには,アーバンの経営状態など本件虚偽記載等とは無関係な要因により生じた分が含まれていることは否定できないとして,この値下がりにも本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がり以外の事情により生じた分が含まれていると判断した。
本判決は,アーバンの値下がりによってX1が受けた損害の一部には本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がり以外の事情により生じたものが含まれているとして,金商法21条の2第4項又は5項の規定による減額を一切否定した原審の判断には違法があると判断した(なお,第二小法廷は,G-2についても,本判決と同日,本判決と同旨の理由により原判決を破棄する旨の判決を言い渡している。)。。
イ 原判決と本判決とで判断が分かれたのは,(ア)。本件公表日後に生じた本件再生申立てに起因する値下がりについて,これが本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりといえるか否かについて,その評価が分かれたこと,(イ)。本件公表日前の値下がりについて原判決は何ら考慮しなかったのに対し,本判決はこれを考慮すべきものとしたことによるものである。
(ア)。については,原判決は,本件臨時報告書が提出された時点でアーバンが既に倒産状態にあったという前提に立って,これを積極に解した。これに対し,本判決は,M社によるTOBも見込まれていたなど本件の事情に照らせば,本件臨時報告書の提出時においてアーバンが既に倒産状態であったとはいえないとして,原判決の上記前提自体を否定した(この点につき,単なる経営難と経営破綻とは異なるとして,法廷意見を敷えんする須藤裁判官の補足意見が参考となろう。)。。そして,ほかに本件再生申立てによる値下がりが本件虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりであると評価すべき事情は見当たらないとして,本件再生申立てによる値下がりを2項推定損害額から控除すべきであるとした。本件とは異なり,倒産のおそれのなかった会社が極めて悪質な虚偽記載等を行い,これが明るみに出たことによって会社の信用が失墜して倒産に至った場合や,会社が既に倒産状態であったのに,虚偽記載等のある有価証券報告書等を提出することによってこれを隠蔽し,あたかも倒産のおそれが全くないかのような印象を市場に与えていた場合であれば,会社が倒産し,あるいは倒産状態であることが明らかになったことによる株価の下落分についても,当該虚偽記載等と相当因果関係のある損害という余地もあるように思われるが,本件はこのような事案ではなく,本件再生申立てによる値下がりを本件虚偽記載等による値下がりと評価することには無理があろう。前記の下級審裁判例のほとんどは金商法21条の2第5項による減額を肯定しており,本判決もこうした下級審裁判例の大勢に従ったものである。
また,(イ)。については,本件公表日前の値下がりについては,本件虚偽記載等の事実が公表されていない以上は,同事実が一部関係者に漏えいしていたなど特段の事情のない限り,上記値下がりは本件虚偽記載等に起因して生じたものとはいえないであろう(なお,本件ではそのような漏えいの事実は認定されていない。)。。そして,アーバン株が本件公表日前1月間に本件虚偽記載等とは無関係な要因によって一貫して値下がりしているとすれば,本件公表日前1月間の平均株価をそのまま用いて2項推定額を算出すれば,損害額が過大に算定されることになる(例えば,公表日1月前の株価が200円,公表日直前の株価が100円,公表日前1月間の平均株価が150円である場合,公表日前の値下がりが虚偽記載等とは無関係な要因によって生じたものだとすれば,200円から100円への下落は投資家が甘受すべきものであって,150円を基礎に損害額を計算するのは不当である。)。。本件公表日前1月間の値下がりがさほど大きくないのであれば格別,アーバン株は,本件公表日1月前には200円であったところ,ほぼ一貫して値下がりを続け,本件公表日前日には63円まで値下がりしているのであって,これを無視して損害額を認定することは許されないと思われる。前記下級審裁判例においても,本件公表日前の値下がりを理由に減額を肯定するものが大部分を占めている(B-1,C-1,2,D-1,2,E-1,2,F-2,G-1,H-1,2,I-1,2)。本判決も,こうした下級審裁判例の大勢に従い,本件公表日前1月間の値下がりについても減額すべき分が含まれているものと判断したものである。
(2)。 ②事件
本判決は,A-2事件の上告審判決であり,金商法21条の2第2項の損害額推定規定を用いない場合の損害額の認定が問題となった。
本判決は,本件虚偽記載等がなければX2がアーバン株を取得することはなかったという原審認定を前提に,取得価額と想定価額の差額が損害となるとした原審判断が西武鉄道事件判決で示された法理に反することを理由に,原判決を破棄した。本判決の判断は,西武鉄道事件判決を踏まえれば当然である。虚偽記載等がなければ投資家が当該株式を取得することがなかったといえるか否かは,第一次的には,当該投資家の属性や投資性向,当該株式を取得した動機や経緯,当該取引の内容,当該虚偽記載等の内容など諸般の事情を踏まえた事実認定の問題であることから,法律審である上告審としては原審認定にあえて介入することはしなかったものと思われる。
6 金商法19条1項と同法21条の2第5項の適用順序
なお,アーバンコーポレイション事件では,金商法21条の2第2項の規定を用いて損害額を推定する場合,同法19条1項所定の限度額(取得価額と市場価額ないし処分価額との差額。以下「19条1項限度額」という。)。による制限と,同法21条の2第5項による減額の適用順序が争われたので,補足しておきたい。この点については,①2項推定損害額の算出→5項による減額→19条1項限度額による制限という適用順序(以下「19条1項後適用説」という。)。と,②2項推定損害額の算出→19条1項限度額による制限→5項による減額という適用順序(以下「19条1項先適用説」という。)。があり得るが,アーバンコーポレイション事件における下級審裁判例をみると,1審判決の一部(B-1,C-1,F-1)に19条1項先適用説に立ったものもみられたものの,高裁レベルでこの点について明示的に判断したものをみる限り,19条1項後適用説で統一されている(C-2,D-2,F-2)。なお,アーバンは,19条1項後適用説に立った前記各高裁判決に対し,19条1項先適用説が相当であると主張して上告受理申立てをしたが,不受理に終わっている。