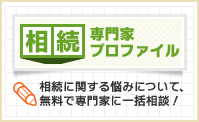よく「相続」ではなく、「争続」という言葉を聞きませんか。それだけ相続人の間でのもめ事が多いのです。これは資産の有無ではありません。居住している自宅のみでも、もめるケースが多いです。
そこで重要になってくるのが意思を残せる遺言です。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。「自筆証書遺言」には法務局に預けられる「遺言書保管制度(※)」というものが2020年からスタートしました。
主な特徴は下記の通りです。
|
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
|
特徴 |
・本人が書く。 ・証人が不要。 ・自分で保管するか、または法務局に預ける。 ・家庭裁判所の検認が必要(法務局に預けなかった場合) |
・公証人が記述する。 ・証人が2人以上必要。 ・公証人役場に預ける。 ・家庭裁判所の検認が不要。 |
・本人が書き、封印する。 ・証人が2人以上必要。 ・公証人役場に預ける。 ・家庭裁判所の検認が必要。 |
|
メリット |
・作成が簡単で書き直しも自由にできる。 ・費用がかからない。 ・法務局に預かってもらうこともできる。 ・内容を秘密にできる。 |
・公証人が作成・保管するために無効になりにくく、紛失偽造の危険がない。 |
・内容を秘密にすることができる。 ・改ざんの危険はない。 |
|
デメリット |
・無効になりやすい。 ・法務局に預けなかった場合には、紛失、偽造の危険がある。 |
・費用がかかり、手続きが煩雑である。 ・遺言の存在、内容を秘密にすることができない。 |
・費用がかかり、手続きが煩雑である。 |
※遺言書保管制度とは
① 自筆証書遺言を法務局で長期間管理します。(原本:遺言者死亡後50年間/画像データ:遺言者死亡 後 150年間。)
② 保管の際には、法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)をします。
③ 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応 します。
④ 家庭裁判所の検認が不要になります。
⑤ 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨を通知します。
 このコラムの執筆専門家
このコラムの執筆専門家

- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
このコラムに類似したコラム
認知症と家族信託 その2 大黒たかのり - 税理士(2017/09/14 12:50)
遺産相続で最初に確認すべきポイントは 大黒たかのり - 税理士(2016/08/22 08:18)
民法、相続ルールの大規模改正へ(4) 高原 誠 - 税理士(2016/02/22 19:23)
遺言は書いてもらった者勝ち 高島 秀行 - 弁護士(2015/10/14 10:18)
子供のいない人は遺言を書いてください 高島 秀行 - 弁護士(2015/09/29 10:09)