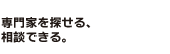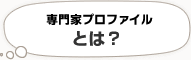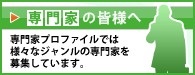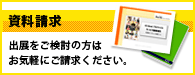- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除の要否2
最高裁判決昭和和62年7月10日 、損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
民集41巻5号1202頁 、判例タイムズ658号81頁
【判決要旨】 労働者災害補償保険法による休業補償給付・傷病補償年金又は厚生年金保険法(昭和和60年法律第34号改正前のもの)による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。
【参照条文】 労働基準法84条2項
労働者災害補償保険法12条の4
労働者災害補償保険法14条
労働者災害補償保険法18条
厚生年金保険法40条
厚生年金保険法(昭和和60年法律第34号改正前のもの)47条
民法709 条、民法710条
一、Y1会社の従業員Xが、就業中、業務に関して他の従業員Y2と口論のあげく暴行を受け、傷害を被ったとして、Y1、Y2に対し、損害賠償(入院雑費、付添看護費、休業補償、慰藉料等)を求めた。
原審は、Xが各費目の損害(合計約1350万円)を被ったことを認めたが、一方でXは労災保険法による休業補償給付、傷病補償年金及び厚生年金法(昭和和60年法律34号改正前のもの)による障害年金の各保険給付を受領しており、その合計額(1400万円余り)が認容すべき前記損害額を上回っていることを認定のうえ、労災保険法及び厚生年金保険法に基づく保険給付は、いかなる給付名義をもってされたものであっても、それが本件事故による身体傷害を原因とする損害の填補の実質を有するものである限り、右損害の填補がされたものとして、入院雑費、付添看護費、慰藉料を含む前記損害の合計額から保険給付の合計額を一括して控除すべきものとし、そうすると、Xの損害はすべて填補されたことになるから、Xの請求は棄却すべきものと判断した。
Xは、原審の認定した損害のうち休業補償に相当する損害から保険給付額を控除することは格別、その余の損害について保険給付による損害の填補を認めることは許されないとして一部上告したところ、本判決は、論旨を容れ、要旨のとおり説示して、該当部分につき原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した。
二、本件のように労災保険法及び厚生年金保険法の保険給付の対象となる事故が発生し、右各法に基づく保険給付がされたときは、Y1、Y2は、その限度でXに対する損害賠償責任を免れる(その法理については、最3小判昭和52・10・25民集31巻6号838頁、最3小判昭和52・5・27民集31巻3号427頁、なお、最2小判昭和52・4・8裁判集民事120号433頁参照)が、それは、民事損害賠償と保険給付の二重填補を排除するためであるから、単純に保険給付の金額の限度で損害賠償責任が減縮するというものではなく、保険給付と「同一の事由」(労基法84条2項、労災保険法12条の4、厚生年金保険法40条)の関係にあるものと認められる損害賠償責任のみが減縮するものと解される。
そして、保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるということは、保険給付の趣旨目的と民法上の損害賠償の趣旨目的とが一致することをいい、単に同一の損害から生じた損害であることを指すものではなく、保険給付の対象となった損害と民法上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であって、民法上の損害賠償を認めることによって二重の填補を与えることになる関係にあることを指称するものと解されている(大阪高判昭和29・9・29高民集7巻10号780頁、通説。労働省労基局労災管理課『新訂版労災保険法』258頁)。
そこで、具体的に保険給付のいかなる給付費目と民法上の損害賠償のいかなる費目が同一の事由の関係にあるとみるべきかであるが、業務災害に関する労災保険給付の各給付(労災保険法12条の8参照)の支給の要件をみると、労災保険法による保険給付は、民法上の損害賠償の項目として挙げられているもののうち、財産的損害に対応する損害の填補を目的としているものであることが明らかであり、物的損害及び精神的損害(慰藉料)の填補を目的とするものではないといえる。この点は学説上異論がなく(前記『新訂版労災保険法』258頁)、物的損害については判例はないが、慰藉料については既に判例がある(最1小判昭和37・4・26民集16巻4号975頁、最1小判昭和41・12・1民集20巻10号2017頁、最3小判昭和58・4・19民集37巻3号321頁)。
そうすると、慰藉料と労災保険給付とは同一の事由の関係にないものというべきであるから、後者をもって、前者の損害の填補があったものとすることは許されないことになる。
次に、民法上の損害賠償中の財産的損害(積極損害及び消極的損害)の各費目と労災保険の各給付項目との関係において同一の事由をどう考えるべきかであるが、労災保険法上の療養補償給付は民事賠償費目中の治療費(積極損害)とほぼ対応しており、同じく葬祭料は民事賠償費目中の葬祭費用(積極損害)と対応するものといえる。
問題はその余の休業補償給付、障害補償給付、傷病補償年金、遺族補償給付である。
これらは全体として民事賠償上の逸失利益(消極損害)に対応するものといえるが、労災保険法上は別個の給付項目とされている。
そこで、民事賠償の費目も、右各給付項目毎に対応関係を細分化することも形式的には考えられないではないが、逸失利益の算定方法は必ずしも労災保険給付の項目に応じて算出されると決まったものではないし、前記各項目は、要するに受傷又は死亡による消極損害の内容を便宜分析したにすぎないものであるから、右のように細分化された項目相互間でしか損害の同質性がないとみることも理論的とはいえない。
そこで、これらの労災保険給付は、その給付の種類にかかわらず、民事賠償上の消極損害と同性質の損害に相当する、すなわち、同一の事由の関係にあるものとして、その給付による損害の填補を肯定するのが適当と思われる(松本久「労災保険給付と損益相殺」民事交通・労働災害訴訟555頁、宝金「各種保険・補償代位の問題点」民事判例実務研究3巻221頁、前記最2小判昭和52・4・8、名古屋高判昭和49・5・13高民集27巻2号208頁)。
昭和和55年改正により設けられた労災保険法67条は、労働者又はその遺族が保険給付の受給権を有し、かつ、同一の事由について事業主から損害賠償を受けることができる場合における当該損害賠償と保険給付との間の調整について定めているが、同条2項が定める労働大臣の定める基準(支払調整基準、昭和和56・6・12発基60号)も、この見解に沿うものといえる。
そうすると、消極損害に対応する休業補償給付及び傷病補償年金は、積極損害に位置付けられる入院雑費や付添看護費を填補するものとして取り扱うことはできないということになろう。
厚生年金法による障害年金も、その給付の性質(厚生年金保険法47条)からみて、消極損害の填補を目的とするものといえるから、以上と同じことが妥当すると思われる。
三、原判決は不法行為に因る損害賠償請求訴訟の訴訟物の個数は1個であるとした最1小判昭和48・4・5民集27巻3号419頁によって従来の判例は維持できないとの見解を採ったものと想像されるが、その後、従来の判例を維持する前記最3小判昭和58・4・19がされたことによって、そのような理解は斥けられ、訴訟物の把握とは関係なく、その給付の実質的性質に応じて損害の填補を考慮するものであることが確認されたものといえる。本判決は、以上のような見解に基づき前記のように判断したものと思われる。
最高裁判決平成8年2月23日、損害賠償請求事件
民集50巻2号249頁 、判例タイムズ904号57頁
【判決要旨】 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号)による特別支給金は、被災労働者の損害額から控除することができない。
【参照条文】 労働基準法84条2項
労働者災害補償保険法12条の4
労働者災害補償保険法(平7法35号改正前)23条1項
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)1条
労働者災害補償保険特別支給金支給規則2条
民法709 条
一 Xは、弁当の製造販売会社Yに勤務していたが、弁当箱洗浄機を使っての作業中、右機械に右手指を挟まれて負傷し、右手示指・中指の用廃等の後遺障害を負った。
Xは、使用者(事業主)Yが機械に事故防止のための装置を設置しなかったこと及び異物を取り出す際には必ず機械を停止させるよう指導を徹底しなかったことに安全配慮義務違反があるとして、休業損害、後遺障害による逸失利益等合計1900万円余の支払を求めた。
Yは、本件事故はXの不注意による自損事故であるとして、安全配慮義務違反を争うとともに、Xが労災保険から受領した休業特別支給金及び障害特別支給金を損益相殺として控除すべきであると主張した。
原判決は、Yの安全配慮義務違反を認め、Xの過失を考慮して4割の過失相殺を行い、Xが受領した労災保険給付(休業補償給付及び障害補償給付の合計)を過失相殺後の損害額から控除して、Xの請求を一部認容した。
Yの前記各特別支給金の控除の主張に対しては、右各特別支給金は災害補償そのものではなく、療養生活援助金等の色彩が濃い性質のものであるとして、控除すべきではないとした。
これに対してYが上告し、特別支給金の損害額からの控除を認めなかった原審の判断の法令違反等を主張したが、本判決は、原審の判断を正当として、Yの上告を棄却した。
二1 労災保険は、業務災害・通勤災害による負傷、死亡等に対して、必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし(労働者災害補償保険法1条)、右目的を達するため、保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる(労働者災害補償保険法2条の2)。
特別支給金は、労働福祉事業のうち、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(労働者災害補償保険法23条1項2号)として、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令30号)に基づいて、被災労働者又はその遺族に対して支給されるものである。
特別支給金の趣旨については、立法担当者は、次のように説明している(労働省労災管理課『労災保険制度の詳解』308頁)。「特別支給金は、法23条に基づき、被災労働者及びその遺族の福祉に必要な施設として行われるものであり、他の保険施設と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の実効を期そうとする趣旨のものである。その性格は、災害補償そのものではなく、休業特別支給金にあっては療養生活援護金の色彩、障害特別支給金にあっては治ゆ後への生活転換援護金の色彩が濃いものということができる。他面、その支給事由、支給額等から明らかなように、保険給付と直接関連、密接不可分の加給金的な関係にあり、その現実的な機能としては、各保険給付と相まってこれを補う所得的効果をもつものということができる。」
2 労災保険給付は、被災労働者の損害の填補の性質を有するものであり、保険給付が行われたときは、使用者行為災害の場合には、使用者は、その限度で民事上の損害賠償債務を免れ(労働基準法84条2項の類推)、第三者行為災害にあっては、政府は給付の限度で第三者に対する損害賠償債権に代位する(労働者災害補償保険法12条の4)として、いずれの場合にも被災労働者の損害のうち逸失利益の額から控除すべきものと解されている(本判決の引用する最3小判昭52・10・25民集31巻6号836頁など)。
これに対し、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金を損害額から控除すべきか否かについては、学説、判例ともに肯定説、否定説の両見解が対立している。
控除否定説(門井節夫「特別支給金の損害額からの控除」判例通覧労災職業病275頁、桑原昌宏「労災・職業病の給付・福祉事業」現代労働法講座12巻142頁など)は、その理由として、(1)特別支給金は、労働福祉事業の一環として行われるものであり、損害の填補を目的とするというよりも、被災労働者及び遺族に対する生活援護金、遺族見舞金的側面が強い、(2)特別支給金については、代位(労働者災害補償保険法12条の4)や年金給付と使用者の損害賠償債務の履行との調整(労働者災害補償保険法64条)の規定の適用が排除されていることからすれば、損害の填補を目的とした制度でないことは明らかである等を挙げる。
一方、控除肯定説(西村健一郎『労災補償と損害賠償』274頁、岩出誠「労災民事賠償における労災保険給付の控除」季刊労働法143号159頁、安西愈『改正労災保険法と民事賠償調整の実務』264頁など)は、(1)特別支給金は、支給事由・額・方法について、保険給付と直接的に関連し、密接不可分の加給金的な関係にあり、保険給付との同一性、類似性が強い、(2)機能的にも、保険給付と相まってこれを補う所得的効果を有し、保険給付の給付率を引き上げたのと同じ役割を果たしている、(3)特別支給金の財源は保険給付と同様、事業主の支払う労災保険料であり、財源面からも同一性が認められる、(4) 特別支給金を控除しないのは、事業主にとって二重払いの不利益になり、被災労働者には損害の二重填補となり不合理である等を理由とする。
下級審の裁判例も肯定、否定の両説に分かれており、従来は控除を否定するものが多数であった(例えば、東京地判昭56・3・19判時1009号131頁)。
これに対し、東京地裁民事交通部は、一時期、肯定説をとることを明らかにし(長久保=森木田「東京地裁民事第27部(民事交通部)における民事交通事件の処理について」司研論集86号50頁)、同部の松尾じん肺訴訟第一審判決(東京地判平2・3・27判例タイムズ722号168頁)は、じん肺に罹患した労働者から使用者に対する損害賠償請求について、休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金を逸失利益から控除すべきであると判断し、注目された(右事件の控訴審判決(東京高判平4・7・17判例タイムズ804号71頁)も控除を認めた一審の判断を是認した。右控訴審判決に対しては、被告日鉄鉱業のみが上告したため、上告審では、この点は審理、判断の対象となっていない。)。
三 本判決は、見解の分かれていた特別支給金の損害額からの控除の可否の問題につき、否定説の見解をとることを明らかにしたものであり、今後の労災事件の処理に影響を与える重要な判例である。
最高裁一小判決平成22年9月13日、損害賠償請求事件
民集64巻6号1626頁、判例タイムズ1337号92頁
【判決要旨】 1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきである。
2 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,不法行為の時から相当な時間が経過した後に現実化する損害をてん補するために労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付の支給がされ,又は支給されることが確定したときには,それぞれの制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,てん補の対象となる損害は,不法行為の時にてん補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整を行うべきである。
【参照条文】 民法709条
労働者災害補償保険法22条、22条の2、22条の3
国民年金法30条
厚生年金保険法47条
民法412条
1(1)本件は,交通事故により傷害を受け,その後に後遺障害が残った被害者から加害者に対する損害賠償請求において,被害者が支給を受けた労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付との間で行う損益相殺的な調整の方法が問題になった事案である。
(2)Xは,平成成14年3月6日,通勤途上,Yが運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭い,右大腿骨開放性骨折等の傷害を負って右足を切断するに至り,後遺障害が残り,合計9873万円余りの損害を被った。
その後,Xは,労災保険法に基づく療養給付や休業給付の支給を受け(以下「本件各保険給付」という。),また,労災保険法に基づく障害年金,国民年金法に基づく障害基礎年金,厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の支給を受け,又はその支給を受けることが確定した(以下「本件各年金給付」という。)。
(3)これらの給付との損益相殺的な調整について,原審は,本件各保険給付については,これによって損害金のうち治療費,休業損害の元本がてん補されたものとし,てん補された損害金元本に対する事故発生の日からてん補の日までの間の遅延損害金は生じていないと解したが,本件各年金給付については,これをまずてん補の日までに生じた遅延損害金に,次いで元本に充当することとし,原告の請求を,4601万円余りの支払を求める限度で認容した。
(4)これに対し,X,Yの双方が上告受理を申し立てた。
2(1)不法行為に基づく人身損害には,治療費等の積極損害,後遺障害による逸失利益や休業損害等の消極損害,慰謝料及び弁護士費用が含まれるが,同一事故による同一利益の侵害(例えば同一の身体障害)によってこれらの損害が生じた場合,全損害についての損害賠償請求権及び訴訟物は1個であり,不法行為時にこれらの全損害につき損害賠償債務が発生するのであって,被害者が現実に治療費や弁護士費用を支払った時点で損害が発生するのではないとするのが判例である(最高裁判決昭和48.4.5民集27巻3号419頁,判タ299号298頁,最高裁判決昭和58.9.6民集37巻7号901頁,判タ509号123頁,最高裁判決平成7.7.14交民28巻4号963頁など)。
また,不法行為に基づく損害賠償債務が遅滞に陥る時期につき,判例は,損害の発生と同時,すなわち不法行為時に何らの催告を要することなく遅滞に陥るとの立場を採っており(最高裁判決昭和37.9.4民集16巻9号1834頁,判タ139号51頁,前掲最高裁判決昭和58.9.6,前掲最高裁判決平成7.7.14),通説もこれを支持している(我妻榮『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』105頁,奥田昌道『債権総論〔増補版〕』132頁など)。
このような考え方によれば,不法行為(自賠法3条を含む)に基づく損害賠償債務の一部に関して弁済がされた場合であっても,事故日から支払日までの間については,上記支払により補てんされたものを含む全損害に対する遅延損害金が発生していることになる。
(2)債務の弁済については,それが元本及び遅延損害金の全部を消滅させるのに足りないときは,遅延損害金,元本の順に充当される(民法491条1項)。当事者の合意によりこれと異なる定めをすることは可能と解されるが(我妻・前掲291頁以下,奥田・前掲522頁),交通事故の被害者が加害者に不法行為に基づく損害賠償請求債務元本及び遅延損害金の支払を求めたのに対し,加害者がその一部を弁済した場合には,特段の合意がなければ,当該弁済は,まず遅延損害金に充当され,残額が損害賠償債務元本に充当されることになる。
(3)以上の考え方を前提とすれば,充当に関する特段の合意があり,弁済が元本に充当されることになったとしても,全損害に対する事故日から弁済等の時点までの間の遅延損害金は既に発生しているから,被害者がこれを請求することを妨げられる理由はないことになる。最高裁判決平成11.10.26交民32巻5号1331頁や,最高裁判決平成12.9.8金法1595号63頁は,自賠責保険金に関し,その旨の判示をしている。
さらに,社会保険給付との損益相殺的な調整が問題となる場合について,最高裁判決平成16.12.20裁判集民事215号987頁,判タ1173号154頁(以下「平成成16年判決」という。)は,交通事故の被害者(死亡)の相続人らが加害者に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,民法491条1項を参照条文として掲げ,相続人らが受けた遺族厚生年金及び労災保険法に基づく遺族補償給付が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるベきであるとした。
(4)これに対し,社会保険給付についても,その額が損害賠償債務元本及び遅延損害金の全部を消滅させるのに足りないときは,民法491条1項の定める充当順序が妥当するとすることについては,
①社会保険給付は各給付の基礎となる法が定める目的のために給付されるものであり,損害賠償の支払とは制度の趣旨,目的を異にする上,損害賠償債務のうち特定の費目(各給付と「同一の事由」の関係にある損害費目)のみをてん補するものであることからすれば,そもそも遅延損害金をてん補する性質を有するとはいえず,民法491条1項に従った処理をする基礎があるとはいい難い(高取真理子「公的年金による損益相殺」判タ1183号70頁,大島眞一「交通損害賠償訴訟における虚構性と精緻性」判タ1197号37頁,高野真人「社会保険給付と損益相殺・代位の問題点」財団法人日弁連交通事故相談センター編『交通賠償論の新次元』215頁,田中敦=新田和憲「交通事故損害賠償実務の未来(2)」法曹時報61巻11号73頁など),
②社会保険給付が損害賠償債務のうち各給付と「同一の事由」の関係にある損害費目のみをてん補するものである以上,その充当関係につき民法491条1項の定める充当順序が妥当するのであれば,遅延損害金についても,各給付と「同一の事由」の関係にある損害費目に対する遅延損害金のみが充当の対象となると解するのが自然であり,そうすると,不法行為による損害賠償債務の一部について弁済や損益相殺的な調整の対象となる給付がされた場合の充当計算が極めて複雑になり,実務的に妥当性を欠く結果になる(高取・前掲70頁,74頁,大島・前掲32頁,44頁,高野・前掲216頁など)
といった問題があるとの指摘がされていた。
また,不法行為日に全損害が発生しそれにつき遅延損害金が発生するというのは法的な擬制にすぎず,例えば治療を受けたことにより治療費が発生するなど現実の損害が発生し,それにつき加害者が遅滞なく支払をした場合には,その損害費目については,不法行為日に遡って支払がされたものと擬制して,遅延損害金は発生しないと考えることにより,社会保障給付が支給されたときはこれを元本に充当し遅延損害金は発生していないと解すべきであるとの見解も述べられていた(大島・前掲37頁)。
3(1)本判決は,①不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った被害者が,労災保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきであり,②このような被害者に社会保険給付の支給がされ,又は支給されることが確定したときには,それぞれの制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,てん補の対象となる損害は,不法行為の時にてん補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整を行うべきであると判示した。
(2)本判決は,上記2(4)のような議論状況を踏まえ,不法行為に基づく損害賠償債務が何らの催告を要することなく損害の発生と同時に遅滞に陥るという理論と民法491条1項の定める法定充当の規定を組み合わせて,事故後に後遺傷害が残った事案において損害と社会保険給付との損益相殺的な調整を行うことが相当ではないことを明らかにしたものである。本判決が平成成16年判決とは事案が異なると判示しているのは,本判決は事故後に後遺障害が残った被害者に対し社会保障給付がされた事案であるのに対し,平成成16年判決は事故当日に被害者が死亡しており,その相続人が支給を受けた遺族厚生年金及び遺族補償給付との損益相殺的な調整が問題になった事案であることによるものと思われる。
(3)なお,本件では,Xが任意保険金や自賠責保険金の支払も受けており,この充当についても争われた。原審は,任意保険金については,損害賠償債務元本に充当し,これによって消滅する損害賠償債務元本に対する遅延損害金の支払債務を免除する旨の黙示の合意があると認定し,自賠責保険金については,まず支払時までに発生した遅延損害金に充当し,その残額を損害賠償債務元本に充当すべきであるとしたが,これらの点についての法令解釈の誤りをいう論旨は受理決定において排除された。
もっとも、任意保険金については,通常,被害者等から治療費,通院交通費,休業損害等の費目につき,関係資料を任意保険会社に提出して請求し,任意保険会社においてそれを検討して,損害費目を示して被害者に支払がされるものであり,支払われた損害金と損害費目との結びつきが明確にされていることが多いことからすれば,当該損害費目につき元本充当の合意を認めることができると考えることができ(大島・前掲37頁),その充当については,仮に民法491条1項の定めによるとしても,少なくとも黙示の合意があったとして原審と同様の処理をすることが可能な事案もあり得ると思われる。
4 不法行為により後遺障害を受けた被害者が社会保険給付を受けた場合の損益相殺的な調整については,本判決の後に第二小法廷が同趣旨の判断を示しており(最高裁二小判決平成22.10.15裁判所時報1517号4頁),この論点についての最高裁の判断は固まったものと思われる。