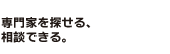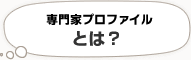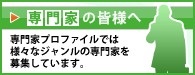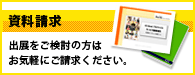- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除の要否
最高裁判決昭和52年4月8日、損害賠償請求事件
裁判集民事120号433頁、金融・商事判例527号26頁
【判決要旨】 労災保険給付の受給権者が政府から休業補償としての保険給付を受けた場合には、受給権者の第三者に対する民法又は自動車損害賠償保障法に基づく休業損害の賠償請求権は、その分だけ減縮する。
【参照条文】 民法709条
自動車損害賠償保障法3条
労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号改正前のもの)20条
道路わきのガソリンスタンドで給油を受けるべく対向車線を横切ろうとした乗用車と右対向車線を直進してきたライトバンとが衝突した事故により、ライトバンを運転していたX(原告・被控訴人・被上告人)は、右膝蓋骨粉砕骨折、胸部打撲の傷害を被った。
Xは、乗用車の運転者であるY1(被告・控訴人・上告人)に対し民法709条に基づき、その保有者であるY2(被告・控訴人・上告人)に対し自賠法3条に基づき、Xが本件事故により被った休業損害、労働能力喪失による逸失利益等の損害額からXが自賠責保険によって支払を受けた金員を控除した残額の賠償を求めた。これに対してY1らは、Xは、本件事故の休業補償として労災保険からの給付を受けているから、これを損益相殺として控除すべきものであると主張したが、原審は、Xが右保険給付を受領したことを認めるに足りる資料はないとして、Y1らの損益相殺の主張を排斥した。
本判決は、原審の右認定は経験則に違反し、理由不備の違法があるとしたうえ、判決要旨記載のとおり判示し、したがって、原判決の右違法は、原判決中Y1らに右保険給付額に相当する54万円余についても賠償を命じた部分に関し結論に影響を及ぼすことになるとして、これを破棄し、差し戻したものである。
労災保険法による補償の原因たる事故が第三者の行為によって生じた場合において、同法に基づく国に対する保険給付請求権と民法・自賠法に基づく第三者に対する損害賠償請求権とが競合関係に立つものであることは学説、判例上争いがない。その場合においても、保険受給権者(被害者)が重複して損害の填補を受けることができると解するのはもとより相当でなく、損害が同質、同一である限り、両者は相互に補完しあい、労災保険給付による補償がされた場合には、第三者はその限度で損害賠償責任を免れ、第三者が損害賠償した場合には政府はその限度で補償義務を免れるとしなければならない。また政府の行う補償は、その実質において他人の損害賠償義務の履行であるから、賠償をした国は、保険受給権者(被害者)の第三者に対する損害賠償請求権に代位することができると考えるべきものであろう。
このような法理を根拠に、労災保険法(昭和48年法律第八五号改正前のもの)20条(現12条の4)は、労働者が保険関係外の第三者の不法行為によって業務災害を被った場合、政府が同法に基づいて保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、政府は保険受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し(同条1項)、また保険受給権者が第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、政府はその限度で補償義務を免れると規定する(同条2項)。
このように、第三者の民法、自賠法上の賠償責任と労災保険法上の政府の労災補償責任とが相互補完の関係にあることに徴すると、同一事由に基づく同質、同一の損害の二重填補は排除されなければならないから、保険受給権者が政府から休業補償として保険給付を受ければ、保険受給権者の第三者に対する休業損害の賠償請求権はその限度において減縮されなければならないことは明らかであり、学説、判例上異論をみない。
右減縮の根拠として、損益相殺法理を用いて説明するか、保険者の代位の理論を用いて説明するかについては議論がある。労災補償により、被害者・遺族の損害賠償請求権が減縮されるのは、政府によって損害の填補がされたからであって、加害者の不法行為が被害者自身に損失と利得とを生じさせた場合に損害額そのものを利益を受けた限度で減縮する損益相殺とはその性質を異にし、したがって、損害賠償者の代位、保険者の代位と根拠を同じくする労災保険法12条の4(改正前の20条)の代位法理で説明するのが相当であるとするものが多い(篠原『注釈民法(19)』五八頁、下森・別冊ジュリスト48号一三三頁、西井・民商七五巻二号三二四頁、門井・労働法律旬報九一三号六一頁、谷水・判例タイムズ二六八号二〇六頁)。
本判決は-多数説の立場をとることを明らかにしている。
最高裁判決昭和52年5月27日、損害賠償請求控訴同附帯控訴事件
民集31巻3号427頁、判例タイムズ350号269頁
【判決要旨】 厚生年金保険法・労働者災害補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の第三者に対する損害賠償請権額から控除することを要しない。
【参照条文】 厚生年金保険法40条
労働者災害補償保険法(昭和48年法第85号改正前のもの)20条
民法709条
本件は、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、労災保険及び厚生年金保険から第三者行為災害の被害者本人に対し将来にわたって支給されることが決定している障害補償給付額を休業損害及び労働能力低下による逸失利益額から控除することの可否が問題となったものである。
被告(上告人)は、中古自動車のエンジンを試動するに際し、過失により右自動車を暴進させ、原告(被上告人)に右自動車を衝突させ、同人に重傷を負わせた。
原告は被告に対し民法709条により休業損害、労働能力低下による逸失利益等の損害賠償を求めたところ、被告は、原告が労災保険及び厚生年金保険から障害補償として支給された額のみならず、将来にわたって支払われる障害補償給付額も控除すべきであると主張した。
原審は将来の給付額については、損害から控除すべきではないとし、本件上告審判決も原審の右判断を是認したものである。
この問題は、労働者災害補償保険法(昭和48年法第85号改正前のもの)20条(現行法の12条の4)、厚生年金保険法40条の解釈と関連する。
従来の下級審判例は、
(a)既に現実に受領した分についてのみ控除を認め、将来受給する補償給付額については控除すべきでないとするもの(例えば、福岡高判昭46・6・21判時653号111頁)と、
(b)既に受領した分のみならず、将来の給付額も現在価額を算定し控除すべきであるとするもの(例えば、札幌高判昭46・1・18判時624号44頁)
とに分かれていた。
本件と同様に第三者行為災害の事案につき、最高判昭46・12・2判時656号90頁は、原審である前掲福岡高判の立場を支持した。本件は、右最高裁判決と同じ立場をとり、さらにその理由を示しているので、実務に及ぼす影響も大きい。
最高裁判決昭和52年10月25日、損害賠償事件
民集31巻6号836頁、判例タイムズ357号218頁
【判決要旨】 労働者災害補償保険法・厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。
【参照条文】 民法709条
労働基準法84条2項
労働者災害補償保険法12条の4
厚生年金保険法40条
一、本件は、就労中に労働災害を被った労働者から使用者に対し民法717条による損害賠償を求めた訴訟において、労働者に対し将来にわたって支給されることになっている労災保険からの長期傷病補償給付金及び厚生年金保険からの障害年金を損害賠償債権額(逸失利益)から控除することの可否が争われたものであり、災害の原因が使用者にあるいわゆる使用者行為災害の事案につき、最高裁判所が最初の判断を示したもので、実務上重要な意義を有する。
二、本件の事案は、次のとおりである。
上告人は、特殊自動車等の分解整備を業とする被上告会社に整備工として雇用されていたものであるが、昭和42年6月7日被上告会社の工場において、トラックターシヨベル車の点検修理作業に従事中、シヨベル車のバケット(重量約1.5トン)を吊っていたワイヤーロープが突然切断し、バケットが上告人の頭上に落下し、その下敷きとなった上告人が脳挫傷等の重傷を負い全く労働能力を喪失するという事故が発生したが、これは右ワイヤーロープに瑕疵があったために発生したものであった。
そこで、上告人は、民法717条に基づき被上告人に対し、損害賠償を求めた。
これに対し被上告人は、上告人が既に支給を受け、又は今後支給を受けるべき労災保険法に基づく長期傷病補償給付金及び厚生年金保険の障害年金は、逸失利益から当然控除されるべきであると主張した。
原審(高松高裁)は、上告人が労災保険及び厚生年金保険から既に支給を受けた保険給付については勿論、将来支給を受くべき保険給付額についても、その現在価額を算出して、これを上告人の逸失利益から控除すべきであるとした。
三、労働者が業務上の災害により負傷・死傷した場合、その原因がその労働者の使用者にある場合及び災害の原因が使用者でない第三者にある場合を問わず、被労働者・遺族は労災保険から休業補償や障害補償年金等の給付を受けることができるが、これとは別に被災労働者は災害の原因をもたらした使用者あるいは第三者に対して民法上の損害賠償を請求することができる(最高三小判昭和38・6・4民集17巻5号716頁)。
ところで、右の相互関係につき、将来受給することが確定した保険給付を損害賠償債権額から控除すべきか否かについては、かねてから控除説と非控除説が対立していたところであるが、第三者行為災害の事案につき、最高三小判昭和52・5・27(民集31巻3号427頁)は、非控除説に立つことを明らかにした。
しかしながら、本件のように使用者行為災害の場合については、労災保険法12条の4、厚生年金保険法40条のような明文の規定がないため、解釈上、より問題を含む。
下級審の裁判例も、控除説、非控除説とに分かれていた。
本判決は、使用者行為災害の場合においても、第三者行為災害の場合におけると同様、労災保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から控除すべきでないことを明らかにしたものである。
最高裁判決昭和52年12月22日、損害賠償請求事件
裁判集民事122号559頁、金融・商事判例548号48頁
【判決要旨】 労働者災害補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、受給権者が使用者に対し自動車損害賠償保障法3条に基づいて請求しうる損害賠償の額から将来の給付額を控除すべきではない。
【参照条文】 自動車損害賠償保障法3条
労働基準法84条2項
労働者災害補償保険法12条の4
労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の自動車運転上の不法行為によって生じ、かつ、被災労働者の使用者が右事故につき自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償の責に任すべき場合において、保険給付により受給者が第三者及び使用者に対する損害賠償請求権を失うのは、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られるのであって、いまだ現実の給付がない以上、たとい将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者が第三者及び使用者に対して請求することのできる損害賠償の額を算定するにあたり、このような将来の給付額を損害額から控除すべきではないと解するのが相当である(最高裁昭和五二年五月二七日第三小法廷判決・民集三一巻三号四二七頁、最高裁昭和五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号参照)。
最高裁判決昭和58年4月19日、損害賠償請求事件
民集37巻3号321頁、判例タイムズ497号89頁
【判決要旨】 労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく(労災保険法に基づく保険給付には慰謝料が含まれていない)、これを被災労働者の慰藉料から控除すべきではない。
【参照条文】 労働基準法84条
労働者災害補償保険法14条、15条
民法709条、民法710条
一、本件は、観光・バス会社Yの補助運転手Xがその乗務中のバスを、運転手Aの指示によって方向転換のため誘導中、運転手の過失ある運転により惹起された事故により、バスに左足踵部を轢過される傷害を受けたとして、運転手の使用者であるYに対して、民法715条に基づく損害賠償を請求したものである。
主たる争点は、過失相殺と損害の填補による残損害額の算定の点にあった。
第1審、控訴審では異なる算定方法を採っており、上告理由の論旨も、原判決が、その認定による過失相殺をしたのちの慰藉料の金額から、本訴において請求していない休業損害等に対する既払分に過失割合を乗じて算出された金額及び原告Xにおいて当初から労災保険支払を受けたとして差引請求をしている障害補償一時金の金額を控除するなどして請求認容額を算定したことの是非にある。
二、(1)原告Xは、本件事故によって被った損害として、(1)逸失利益、(2)慰藉料、(3)弁護士費用の合計額から、後遺症につき労災保険から既に受給ずみの障害補償一時金14万0100円を控除した残額577万7900円を請求した。
(2)被告Yは、Xの後遺症に起因する逸失利益は皆無であると争うとともに、Xは(イ)障害補償一時金の他に、(ロ)労災保険からの休業補償金、(ハ)Y共済会から15万8815円、(ハ)Yからの昭和和48年賞与として10万2000円、(ニ)Yからの見舞金5万円、(ホ)Aからの見舞金7万円の金員を受領しており合計金額分だけ損害の填補がされている、と主張した。
三、裁判所は、(1)第1審、控訴審とも、本件事故は、運転手の過失行為に惹起されたものであり、Yは被害者Aの選任・監督につき相当な注意をなしたとは認め難いから、Xが本件事故によって被った損害の賠償責任を負うべきであると判断し、(2)損害額の算定については、(イ)第1審、控訴審とも後遺症による稼動能力の減少による損害については、本件事故後後遺症の存在により現実に原告の実収入が減少したとは認められないとして、X主張の後遺症による逸失損害は存しないものと判断したが、(ロ)慰藉料の額は、一審は160万円、原審は200万円と認め(いずれも障害補償一時金の受給、後遺症等を斟酌)、(ハ)過失相殺については第1審はXの過失を認めず、原審はXにも過失ありとして2割の過失相殺を認めた。
(3)損害の填補と損害残額(=認容額)については、第1審、控訴審で相当異なる算定の仕方をした。
(i)第1審は、認定した慰藉料からAからの見舞金を控除したうえ、これに弁護士費用を加算し、Yの支払うべき損害残額=認容額を212万円であるとした(X、Yともに主張する労災保険からの障害補償一時金の受給は慰藉料算定につき斟酌したが、Y主張の労災保険及びYの共済会からの休業補償金、Yから支払われた賞与、見舞金については、Xが本訴で請求していない休業損害及び付添費用として充当されたものであるから、Xの本訴請求にかかわる損害から控除すべきではない、と判断した)。
(ⅱ)原審は、第1審が充当を認めなかった前記休業補償金、賞与金、Yからの見舞金は、Xが本訴で請求していない休業損害及び付添費用に充てて支払われたものであると認めながらも、本件口頭弁論の全趣旨によれば、休業損害及び付添費用の損害は、右休業補償金、賞与金、Yからの見舞金の支払により填補されたとしたうえ、右各支払金の合計金の2割(Xの過失割合)を、過失相殺をしたのちの慰藉料から控除し、更に前記労災保険から支給ずみの障害補償一時金及びAからの見舞金を控除すると、損害填補分を差引いた残損害額と弁護士費用を加算した金額がYの賠償すべき額(=認容額)となると判断した。
第1審判決に対してはYが控訴し、原判決に対してはXが上告した。
(ⅲ)本判決は、
(イ)「労働者に対する災害補償は、労働者の被った財産上の損害の填補のためにのみなされるものであって、精神上の損害の填補の目的を含むものではない」とする判例の見解(最高1小判昭和37・4・26民集16巻4号975頁、最高1小判昭和41・12・1民集20巻10号2017頁)に従った判断のもとに、Xが受領した労災保険からの障害補償一時金及び休業補償金は、上告人の財産上の損害の賠償請求にのみ充てられるべき性質のものであって、Xの慰藉料請求権には及ばないというべきであるから、Xが各補償金を受領してもその全部又は一部がXの慰藉料から控除することは許されないと判示し、更に、
(ロ)Xが受領したその余の費目の金員についても、原判決がその一部又は全部を慰藉料から控除しているが、右費目の名称からみて、Xに生じた損害を填補するものか、また、いかなる性質の損害を填補するものか、はっきりしないものがあり、原判決の説示する理由だけからは慰藉料から控除する理由が明らかではない、と判示し、結局、原判決には、(イ)の点につき、労働者災害による損害賠償に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、かつ(ロ)の点につき、審理不尽、理由不備の違法がある、として原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した。
四、訴訟物の個数と過失相殺について、(1)同一事故により生じた身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権及び訴訟物については、学説の分かれるところであるが、これを1個であると解するのが判例の見解である(最高1小判昭和48・4・5民集27巻3号419頁)。
また、(2)同一事故から生じた全損害に対する1個の賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に過失相殺をする方法については学説上見解の分れるところであるが、判例は、いわゆる外側説を採り、まず損害の全額を算定し、右全損害額から過失割合による減額をし、その残額が請求額を超えないときは右残額が、請求額を超えるときは請求の全額を認容することができるものと解する立場をとる(前掲昭和48年最高裁1小判決)。
(3)しかし、原告が全損害のうちの一部を限定し、特定して損害賠償の請求をしてきた場合には、右請求にかかる損害の賠償請求権及び訴訟物が1個であることになり、裁判所は狭義の弁論主義に違反しない範囲で損害の存否につき判断するべきことになるのは民訴法上当然の理であろう。
本訴のように、原告Xからの請求にかかる損害が後遺症による逸失利益、慰藉料及び弁護士費用に限定されており、その他の損害については全てが填補されているとは主張しているわけではなく後遺症による逸失利益の損害から支給ずみの障害一時補償金だけを差引いた残額を請求したのにすぎない。
そうすると、本件の場合にも訴訟物1個説を採り外側説による過失相殺の仕方が適当かどうか、もしこの方法を採るのであっても原告、被告の主張から、本件事故による総損害が出されて、その立証がされていない限り無理であろう。
本件は、治療費、休業損害等明らかに生じたであろうと推測できる損害についても主張されていない。
この点、原審の認定した総損害は、弁論の全趣旨によるとはいえ、かなりラフなものであり、必ずしも原判決に掲記された損害費用の合計額だけが損害であるとは考えにくい。
(4)ところで、被災労働者が労働基準法、労働者災害保険法等による災害補償金の給付を受けた場合に、右補償金の支給によって労働者の被った損害が填補されるか、については学説上争いがある。
判例は、これを肯定しながらも、右補償金により填補されうる損害は財産上の損害に限られるとの見解を採り、被災労働者がかかる補償金の支給を受けたとしても使用者に対して別途慰藉料を請求できるものと解し、また、その反対に、加害者である第三者から被害者に慰藉料が支払われたからといって被災労働者が受給しうる労災保険法に基づく災害補償の額に影響を及ぼさないものと解している(最高1小判昭和37・4・26民集16巻4号975頁、最高1小判昭和41・12・1民集20巻10号2017頁)。
したがって、判例の立場からすると、被災労働者が労働者災害保険法に基づく補償金の支給を受けたからといって、使用者の慰藉料支払義務が免責されることを否定すべきである。
なお、慰藉料の算定にあたり、斟酌しうる事情があるという下級審裁判例もある(大阪高判昭和29・9・29高民集7巻780頁、東京高判昭和30・11・9下民集6巻2350頁)。
右判例の立場に従う限り、原判決のようにその認定した慰藉料200万円からその2割の過失相殺をしたのちの慰藉料160万円から労災保険から支給された障害補償一時金及び休業補償金の全部ないし一部を控除したのは明らかに誤りということになろうし、その他の名目で支払われた支給金についてもはっきりした性質、目的が分らないようであり、本判決はこの点も審理を尽くさせるべし、としたのは無理からぬように思われる。