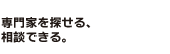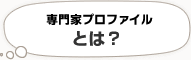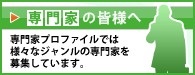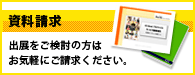- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
¥4,095 Amazon.co.jp
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
商事法務、2012年、本文450頁。
著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。
本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。
今日までに、上記書籍を読み終えました。
以下、私が感じたなりの法的な疑問点について、多々書いたが、各業界(広告、映画、音楽など)の実情・慣習・慣行について、よくも網羅していると感心した。
『太陽風交点』に対する著者の批評については疑問がある。同事件は、明示の出版権設定がない場合、初版出版社に3年間の独占的出版権を認めなかった判決として、昭和61年当時、出版業界では、話題をよんだ。
著者は、「プロデューサー=資金出損者」という独自の観点から、同判決はプロデューサーが不当に軽んじられているとして、批判している。
また、同事件では、出版権設定契約か出版利用許諾契約かという論点もあるが、「疑わしきは契約起案者の不利益に解釈すべき」という契約解釈の一般的原則が適用されたに過ぎないと考えることもできる。
しかし、同事件が教訓となって、現在では、出版社は常に出版前に出版権設定契約を求める傾向がある。
そもそも、著作権法では、著作者を保護することから出発しているのであって、資金出損者を優位にするのは、
① 使用者が著作者・著作権者となる職務著作物、
② その性質上特別規定の多いプログラムの著作物、
③ 映画製作者を著作権者とする映画の著作物、
④ 広汎な著作隣接権を認められている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者くらいであろう。
⑤ なお、ゲームは判例上、音と映像の点から映画の著作物として、あるいは、プログラムの著作物として、取り扱われている。
これらの類型では、資金出損者は、コンテンツができる以前から、人件費・器材などの多額の経費を負担し、独自の配給・流通のシステムがあるからである。経費はかけたが回収できない「リスク・マネー」という著者独自のネーミングにも意味がありそうである(学問としての著作権法では、このような発想はあまりしない)。この著者は、上記のような特殊なビッグ・ビジネス(まさに「エンタテイメント」ビジネス)にのみ妥当しそうな考え方を、他の伝統的な著作権にまで無理に拡張・一般化しているような印象を受ける。
そして、小説・論文のような言語の著作物のコンテンツであれば、出版社が事前に多額の資金出損しているとはいえないと思われる。むしろ言語の著作物では、著作者が先行して自己投資して、コンテンツを創造するのが通例である。
なお、『太陽風交点』事件のような短編小説集であれば、タイトル及び収録されている短編小説を入れ替えるなどにより、出版権設定契約がある場合であっても、同一著者は、別の短編小説集を出版できることを指摘しておく(この点について触れている論者はいないようである。)。
疑問に感じた箇所
・「書籍の印税方式より買取り方式のほうが著作者にとって有利。」
印税と譲渡対価の金額の大小を言わずに一概には断定できない。そもそも著作権を買う側にしても、売れそうもない場合には、譲渡対価を安くするはずだから、「印税方式より買取り方式のほうが著作者にとって有利(高い)」などという経験則なるものは、最初から存在しないのである。普通のビジネスは「安く仕入れて、より高く売る」のが普遍的である。したがって、「売れた分しか印税が発生しない」印税方式のほうが、安く買い叩かれるより、著者にとっては、むしろ合理的である。
・音楽の著作物の場合
最初に著作権管理団体にコンテンツを信託的に譲渡する音楽の著作物の場合は、書籍の場合とは異なる。ただし、音楽の著作物の場合でも、買取りではなく、著作権管理を目的とする「信託的譲渡」であって、「真正売買」ではない。音楽の著作物のビジネスモデルでは、利用されるたびに、印税が支払われる。例えば、1曲ダウンロードされるたびに数円の印税が歌手(作詞家兼作曲家)に支払われるそうである。
・「譲渡対価が安いから譲渡の合意は存在しない」。
これは、売買の一般原則であって、売買代金が安いから売らないというのは当然である。あるいは極端に言えば、買い手の人柄品性が気に入らないから売らない、というのも自由である。売り手には、そもそも売る義務など、法律上、存在しないからである。
・第7章 映画業界
映画が製作され、監督、脚本家、俳優などにギャラなどが払われるが、二次的利用(ビデオ化、テレビ放送、有線放送、航空機・ホテルなどの施設での放映、インターネット配信、海外ライセンス、商品化)に対して、俳優などの実演家には二次的利用の対価が払われないのは当然だと著者は考えているようだが、現在では、事情が違うようである。
例えば、実演家には、公衆送信権(例えばインターネット配信)・放送権・有線放送権があるから、その際には、当然、報酬請求できる。少なくとも俳優協会に加入している主な俳優について、二次利用について全くの無報酬ということは、現在ではないようである。
また、アメリカでは、俳優や歌手・録音技師などのユニオン(職業別組合)の力が強い国では、日本などより、昔から、権利意識が非常に強かったとされている。
商品化事業には、多様なものがあるが、肖像・似顔絵を無断で使われた場合には、実演家は、肖像権・パブリシティ権に基づいて、差止請求や損害賠償請求ができる。
・第8章 レコード音楽業界
レコード会社は、タレント所属事務所に印税・出演料などを支払うが、所属事務所は何かと理由をつけてタレント本人に支払いをしようとしないし、タレントを長時間働かせるという構造になっているようにみえる。
そして、著者は、上記の構造について、何ら疑問も感じていないようである。
しかし、リスクマネーを投じるプロデューサーだからこそ、リターンを得るという著者独自の持論は、この個所では何も役に立っていないし、矛盾を感じる。
また、本書によれば、通常の意味でのプロデューサーまたはマネージメントという側面でも、所属事務所は、マネージャー・付き人をつける、運転手付きの自動車で送迎する、ヘアメイクをするといった程度であるという。
所属事務所の仕事で一番大事なのは、仕事を獲得する、スケジュールを含めて管理をするという気がするのだが、なぜか本書では、その点について、突っ込んだ検討はされていない。
・第9章 出版業界
著者は、例えば、ある雑誌の連載漫画については、当該出版社は独占的出版権があるかのような記述をされている。
しかし、これは疑問である。出版権設定契約・利用許諾契約をしていない限り、出版社が独占権うんぬんする方法は、著作権法にはないからである。
業界慣行として、ある雑誌連載漫画を他の雑誌が掲載することが事実上ほとんどないのは、法律的な意味はなく、いわば「礼儀」としての意味合いでしかないと解される。
なお、上記のような、ある雑誌連載漫画を他の雑誌が掲載する実例は、我が国でも過去にもあった。漫画家が希望しても雑誌が掲載してくれない場合には、そのように対処するしか方法がないからである。
・第10章 ゲーム業界
「職務著作のゲームについて、ゲームがヒットした場合、従業員に対する追加の印税が払われることがある」旨の記述がある。
しかし、職務著作の場合、著作権は使用者にあるので、従業員に対する追加報酬の支払いの法的性質は、名目はどうあれ、成果主義的な賞与やインセンティブ、対価の後払いであろうと解される。
実際のゲーム製作会社の従業員でも、ヒット作品のゲーム製作担当者と、そうではないゲーム製作担当者とでは、年収に大きく開きが出る場合があるようである。
・第12章 ライブパフォーマンス業界
音楽、演劇について、論じている。
・第13章 テレビ業界
著者は、テレビ番組の二次利用については、無理に拡大させなくともよいとする。
アニメと特撮番組については、近時、二次利用の需要が拡大している。
しかし、多額の費用を投下した新規の映画が興行的に失敗する場合があるのに対して、例えば、昔、高視聴率を取ったテレビ番組のビデオ化・公衆送信権・放送・有線放送などの二次利用は魅力的ではないだろうか。
・第14章 モバイルコンテンツ業界
著者は、「作家や音楽クリエイターを育ててきた出版社やレコード会社の機能を、アップルやグーグル、携帯電話会社が担うのか」という問題提起している。
音楽業界については、確かに、アーティストを売れるように育てるという側面もあるかもしれない。
しかし、現在の出版業界では、素人をプロの作家や漫画家に育てるというシステムは存在しないと思われる。