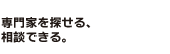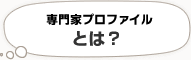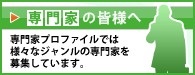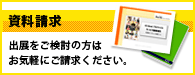- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
Blog201402、会社法
弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2)
東京弁護士会『会社法の法的論点と実務』弁護士専門研修講座、ぎょうせい、平成19年
東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格
弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ)
初版は2006年刊行。第2版が2010年刊行。
法学教室連載の単行本化。
会社法の制定にいち早く対応した学者による演習書
旧商法での判例・学説との違いを重点的に論じている。これは司法試験での出題可能性が高いことによるものであろう。ただし、旧商法を勉強した実務家にとっても有意義である。そして、会社法での解釈は未だ定まっているとはいえない。会社法の立法担当者とは違う説が学説上の多数説になったり、最高裁判例になっているからである。
今日までに、上記書籍(初版)のうち、以下の部分を読みました。
設問2 株主代表訴訟
設問3 財産引受、開業準備行為
設問4 見せ金、出資の有効・無効
見せ金は出資として、最高裁は無効と解している。それが、その後の会社法改正につながった。
設問17 競業取引に対する会社の介入権の規定が廃止されたことの意義・効果
設問18 取締役の報酬等(取締役会設置会社、委員会設置会社)
設問27 債務超過会社との合併などの可否
弥永教授は実質債務超過会社の株式の価値は通常プラスであると解しているが、その理由付けは不明である。実質債務超過会社の株式であれば、株式の時価はゼロ以下のはずである。そして、実質評価がプラスの会社と実質評価がマイナスの会社が合併すれば、実質評価がプラスの会社から見れば、資産が減少するはずである。
設問28 会社分割の分割比率が不公正な場合の株主の救済方法
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
判例タイムズ社、2012年
今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
「6 株式の持ち合い」
株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。
株主であれば、少なくとも年1回開催される株主総会に出席して、主要株主や経営陣の動向(ガバナンス)を把握し、決算書を入手できる。
バブル崩壊前のメインバンクであれば、非上場会社であっても主要な融資先について、独占禁止法・銀行法に規定されている相手先企業の株式割合が5%以下という制限があっても、株式を保有していたのは、上記のようなメリットがあったからである。
昨今、銀行の財務体質改善のために、銀行が保有株式を放出して、株式の相互保有が崩れたが、それとともに、取引先企業に対するモニタリング機能が低下している。
そして、そのような歴史を知らない世代の銀行員がいとも簡単に取引企業の財務書類が入手できるとか融資先のガバナンスの情報を取得できるとか錯覚しているのは、上記のような「実務上の智恵」を知らないからである。
考えてみればわかるであろうが、年1回だけでも、役員全員や主要株主の人間関係を観察し、その動向を把握する機会があるというのは、実務的には意義が大きい。株主でもない外部の人間に「我が社の内情」をわざわざ見せるはずもない。
また、旧独占禁止法9条の改正により、銀行・保険会社以外の事業会社について、株式の保有制限がなくなった。事業会社であれば、安定株主対策目的や取引先と商売上の付き合いだけでなく、株式を相互保有することによって、少なくとも年1回開催される株主総会に出席して、主要株主や経営陣の動向などの企業統治(ガバナンス)を把握し、決算書を入手できる。それによって、取引先の情報を確実に入手できるツールの1つであり、また、今後の商売上の付き合いを継続すべきか・拡大縮小すべきか、あるいは平常時からの債権保全の手段の1つでもあるからである。
「8 共同研究開発契約」
本稿は、民法上の組合、有限責任事業組合契約に関する法律の有限責任事業組合契約に関して検討している。
しかし、共同研究開発契約には、合弁会社、委託契約、商法上の匿名組合、事業者団体、中小企業等協同組合法に基づく協同組合、ライセンス契約、出資や資金貸与などを行う形式などのさまざまな法的形式が考え得る。これらの論点について、本稿は検討していない。
なお、本稿では「ライセンス」を独占的実施権のみを指す用語に理解しているが、適切ではない。また、実施権がある場合、特許権の準共有者に対して影響を与えないかのごとき記述があったが、大きな誤解であろう。
特許法改正により、特許権が移転等した場合にも、移転前に設定された通常実施権は、登録なくして、特許権の譲受人に対して対抗できる(特許法99条)点の指摘が抜けている。
また、職務発明(特許法35条)について、対価の点の検討が抜けていた。職務発明の対価についての分担などをどのようにするかは1つの問題である。
また、本稿では、独占禁止法上の取扱いの検討がされていない。
一方的に知的財産の成果物を委託者に帰属させるのは、優越的地位の濫用に該当する(優越的地位濫用ガイドライン)。
また、公正取引委員会によれば、下請代金支払遅延等防止法にも違反する場合があると解されている。
また、情報交換が独占禁止法(不当な取引制限または、不公正な取引方法)に該当するかが問題となる場合がある。
有限責任事業組合契約に関する法律についての記述は、おおむね妥当であろう。
本稿では検討されていないが、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律も問題となる。
「9 企業間提携契約と継続的契約」
本稿は、平井宣雄教授、内田貴教授の学説を検討している。しかし、中田裕康教授に依拠しているとしつつ、中田教授の見解を紹介していないのは、学説上のプライオリティを遵守していない。
無償契約について補償を要するとの見解は、やや違和感を覚える。例えば、有償委任の場合の解除の損害賠償、役員の解任の場合の損害賠償のような事例は、いずれも、有償契約が前提だからである。もっとも、例えば、無償使用貸借契約のように、事前に予告期間を置くべきとするのは、賛同したい。ただし、企業間で、全くの無賞という事例は想定するのは困難だが。
履行利益と信頼利益の区別がよくできていないようである。ただし、平井宣雄教授、内田貴教授ともに、両者の利益を峻別する通説に批判的である。そして、裁判例も、必ずしも、両者の利益の名称にとらわれずに、具体的事案に応じて、相当因果関係のある損害の場合に限って、損害賠償を認めているのではないかという一部の学説の指摘もある。
資生堂事件、花王事件の最高裁判決においては、継続的契約の打ち切りについて、「やむを得ない理由」は必要ないが、「正当な理由」は必要であると解されている。
某週刊誌が鉄道会社を批判する記事を掲載したところ、当該掲載号から、鉄道会社での売店での当該週刊誌の販売打ち切りをしたため、雑誌会社が鉄道会社に継続的契約の地位にあるという仮処分を起こして、結局、契約を継続する和解で終了した事件があるが、そのような指摘が抜けていた。
下請代金支払遅延等防止法が関係する場合には、下請代金支払遅延等防止法を遵守すべきである。この点の指摘が抜けていた。
また、継続的契約について、企業間であれば独占禁止法、(事業者と消費者間では特定商取引法、消費者契約法なども)が問題となる。この点の検討も弱いようである。
「11 企業提携交渉をめぐる法的諸問題」
信義則に基づいて情報提供義務が認められている。
契約の相手方の救済万円手段として、
契約の相手方の虚偽の情報提供・不告知(秘匿)による詐欺に基づく契約の取消、
錯誤による契約の無効、
不法行為に基づく損害賠償請求、
契約締結上の過失に基づく損害賠償請求、
が考えられる。
なお、詐欺に至らない程度の不実告知などについて、民法改正で問題とされている。
情報提供義務の対象が何についてかは、問題となるが、契約類型・契約を締結しなかった理由などによって異なる。
もっとも、上場企業の場合、情報は企業自ら収集すべきとして、相手方企業は積極的情報提供義務を負わないとされた裁判例もある。また、提供義務があるかどうかは、情報の内容にもよるであろう。そのため、M&Aなどでは、デューディリジェンスが重要とされている。
契約を締結しなかった理由として、何が正当な理由に該当するかが問題となるが、当初予想できなかった事情が判明したなど、事案によって異なるであろう。経済的な不況が深刻化したという程度では、正当な理由ではないと解した裁判例もあるが、他方、家賃保証システムで保証すべき家賃が契約交渉中1年間に変更になったことが正当な理由とされた裁判例もある。
損害賠償の内容については、履行利益ではなく、信頼利益にとどまると解されている。
中間合意のうち、レターオブインテント(M&Aの基本合意書)の独占的交渉条項について、最高裁のUFJ事件の仮処分事件は法的拘束力を認めたが、近時のM&Aは、いきなり基本合意だけではなく、段階的に中間合意を積み上げていく方式がとられているようである。もっとも、同事件の本案訴訟では、信頼利益しか認められず、東京高等裁判所で和解で終了している。
M&Aでは、表明保証条項が必要であるが、第三者に保有株式を売却するような事例では有効であろうが、合併・会社分割などでは相手方が自社に吸収されたり、事業譲渡では相手方が清算してしまうなどによって、義務を履行する相手方が存在しない場合も多いので、実効性については、悩ましい問題である。
東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2)青林書院
東京地方裁判所商事部(民事第8部)に所属したことのある裁判官らによる商事関係訴訟の裁判実務についての「基本書」である。
判例タイムズ社で、同じ東京地方裁判所商事研究会が執筆した、記述がさらに詳細で発行年が新しい『類型別会社訴訟Ⅰ・Ⅱ(第3版)』が刊行されている。
第1章 商事関係訴訟の特徴
第2章 株主権をめぐる訴訟
第3章 株主総会決議に関する訴訟
第4章 取締役の地位に関する訴訟
第5章 取締役の報酬・退職慰労金に関する訴訟
第6章 会社の取締役に対する責任追及訴訟
第7章 株主代表訴訟
第8章 第三者の取締役に対する責任追及訴訟
第9章 新株発行差止め、新株発行無効・不存在確認の訴え
第10章 計算書類・会計帳簿等・株主名簿の閲覧等請求訴訟
第11章 会社の解散の訴え
東京弁護士会『会社法の法的論点と実務』弁護士専門研修講座、ぎょうせい、平成19年
会社法施行に際して刊行された。弁護士会による研修講義録である。
私は弁護士会でほぼ同じ内容の研修講義を受講している。
図表、書式などを用いて、わかりやすく解説されている。
ただし、会社法施行直後の講演のため、現時点での会社法の最新の基本書のほうが最新で実務的であろう。
1 新会社法と企業の実務動向
2 新会社法における会社訴訟、会社非訟
3 株式会社の設立手続
4 新会社法下における会社運営
5 組織再編
6 上場企業等大会社における会社法上の実務問題
7 中小企業の機関構成と実務
8 中小企業における株式制度
東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格
金融法務事情1920号100頁
1 本件は、Y1を新設分割会社、Y2を新設分割設立会社とする本件会社分割について、Y2に承継されなかったY1の債務に係る債権者であるXが、当該債務について履行の見込みがないことから、本件会社分割は無効であると主張して、会社法828条2項10号に基づく本件会社分割を無効とする訴えを提起した事案である。
2 会社法は、会社分割の態様として、吸収分割(会社法757条以下)および新設分割(会社法762条以下)について規定するが、会社分割の無効は、吸収分割でも、新設分割でも、訴えをもってのみ主張することができると規定し(会社法828条1項柱書き)、その出訴期間を制限している(前者につき、同項9号、後者につき、同項10号)。会社分割以外の会社の組織に関する行為と同様の法規制に服することになるが、会社法は、分割無効の訴えの原告適格についても制限している。会社法828条2項9号・10号の規定するところであって、これによれば、吸収分割(9号)についても、新設分割(10号)についても、当該会社分割について「承認をしなかった債権者」が原告適格を有することになる。
この点につき、Yらは、承認をしなかった債権者とは、承認をし得る立場にあったのに、承認をしなかった債権者をいうのであって、そもそも承認をし得る立場になかった債権者は承認をしなかった債権者に該当しないと主張する。
新設分割の無効の訴えの原告適格について規定する会社法828条2項10号の文理解釈としても、Yらの主張のとおりに解釈されるべきものである。
本件第1審、2審の判断も同旨であって、これを新設分割が問題となっている本件事案に即していえば、『新設分割の無効の訴えを提起することができる会社法828条2項10号にいう「新設分割について承認をしなかった債権者」とは、新設分割について異議を述べることができる者として同法810条1項2号に規定する債権者をいう』ということになる。
3 Xは、そのような解釈では、濫用的な会社分割を活発に行う者たちの隠れ蓑や温床となるので、新設分割会社が債務超過で、会社分割後も新設分割会社のみが債務を負い、新設分割設立会社が債務を承継しない場合は、このような会社分割に同意しない債権者は、「新設分割について承認をしなかった債権者」に該当する者として新設分割の無効の訴えを提起できるとすベきであると主張しているが、Xの主張するところは、会社分割の無効の訴えの原告適格を認める理由になり得ないとしても、現行の会社分割制度が抱えている病理現象ともいうべき問題点を指摘するものとして受け止める必要がある。
それというのも、例えば、会社分割が事業の再生のために吸収分割会社あるいは新設分割会社の事業を採算部門と不採算部門とに分けてその一方を吸収分割承継会社あるいは新設分割設立会社に承継させ、他方を吸収分割会社あるいは新設分割会社に存続させるとすると、採算部門を引き継いだ会社と、不採算部門を引き継いだ会社とで、それぞれの債権者に対する債務の履行ないしその見込みに違いが生ずることが避けられないところ、その違いが形式的に否定される場合、例えば、会社分割に伴うそれぞれの会社の積極財産と消極財産とが計数的にみて増減がない場合であっても、実質的に肯定される場合、例えば、それぞれの会社の積極財産と消極財産とが価値的にみて均衡を欠く場合には、債務の履行ないしその見込みが減少する会社の債権者から会社分割に不満・不服が述べられることは必至であるからである。会社法は、債権者の保護手続(吸収分割につき、759条2項・3項、761条2項・3項、新設分割につき、764条2項・3項、766条2項・3項)を規定しているが、以上のような債権者の不満を解消し得るものではなく、それは、近時の会社分割をめぐる裁判例をみても否定し得ない。