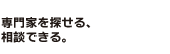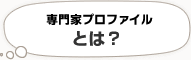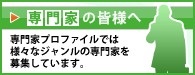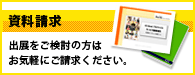- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
傘下の高等学校の校長を退職し、傘下の大学の学長に就任したことに伴い、
支給された退職金の退職所得性が認められた
大阪地裁平成20年2月29日判決を紹介します。
事件の概要は次の通りです。
原告である学校法人の設置するB高校及びC中学の校長であった甲が、
校長を退職した後、同じ学校法人の設置するD大学の学長に就任した。
そこで、原告は、甲に対し、B高校の就業規則及び退職金規定に基づいて、
退職金4800万円余りを支払い、この金員に係る所得は所得税法30条1項に
規定する退職所得に該当するとして、甲の所得税を源泉徴収し、国に納付した。
ところが、被告税務署長は、本件所得は所得税法28条1項に規定する給与所得に
該当するとして、原告に対して納税告知及び不納付加算税付加決定処分
(以下、本件各処分)をしたことから、原告が本件各処分の取消を求め、
訴訟を提起したものである。
裁判所は次のように判断している。
確かに、甲は、本件校長の職を退く前後を通じて学校法人である原告の
理事及び理事長の地位にとどまっていた。
本件校長からの退職及び本件学長への就任という勤務関係の異動は、
同一の学校法人の設置する内部組織としての教育機関の代表者、
最終責任者の職間の移動にすぎないとみられなくもない。
しかしながら、そもそも、同一の学校法人の設置する教育機関であっても、
高等学校と大学とでは、その教育機関としての目的、性格が基本的に異なるものであり、
その差異に応じて学校教育法その他の関係法令によりその組織及び運営の
両面にわたって種々の規制がされているのであって、同一の学校法人との間に
雇用等の法律関係にある者であっても、少なくとも教員については、
その設置する高等学校及び大学相互間の異動は一般的に考え難く、
原告においても、このような観点から、本件高校及び本件大学について
それぞれ別個とした上勤続年数に関する通算規定等を設けていないものと解される。
甲の平成14年3月31日までの原告における職務のうち主要なものは、
常時勤務を要する本件校長としての職務であったということができ、
その余の理事長としての職務及び園長としての職務は、いずれも常時勤務を
要しないものである上、丁若しくは戊又は副園長にその職務の一部又は大部分を
ゆだねていたというのであるから、これらの職務は、甲の原告における
職務のうちのごく一部にすぎなかったというべきである。
平成14年4月1日以降については、本件学長としての職務が
主要なものであったということができるものの、甲が本件大学に出勤するのは
1週間に2,3回という頻度であって、理事長としての職務、園長としての
職務と同様、常時勤務を要するものではなく、さらにその多くを副学長である丁や
学長補佐である戊にゆだねていたというのである。
以上によれば、甲の本件学長就任後の職務は、本件校長在職時の職務に比べ、
その量において相当軽減されたものであるだけでなく、勤務形態自体が
異なるとともに、その内容、性質においても、学校の代表者、
最終責任者としての職務という点では本質的な相違はないものの、
具体的な職務内容や自らのかかわり方については相当程度異なるところがある
というべきである。
甲の本件学長就任時の給与月額は、本件校長退職時に比べ、約21%減少しており、
本件学長としての職務に対する給与は、本件校長としての職務に対する給与に比べて、
約30%減少したというのであり、給与面にも前記のような職務の量、内容、性質の
変動が一応反映されているということができる。
以上に認定、説示したところからすれば、甲の本件校長からの退職、
本件学長への就任という勤務関係の異動は、社会通念に照らし、
単に同一法人内における相当業務の変更といった程度のものにとどまらず、
これにより、甲の勤務関係は、その性質、内容、処遇等に重大な変更があった
といわなければならない。
以上のような判断に基づいて、本件退職金を退職所得とする源泉所得税の納付を
容認したのである。
本件は、甲の年齢的な事情を含め、非常に特殊なケースであるため、
いわゆる事例判決として評価すべき事例かもしれない。
しかし、本件における裁判所の判断のポイントである、
就業規則および退職金規定の存在を過小評価すべきではなかろう。
つまり、みなし退職による退職金の支給を考えるためには、
長期的な視点から、就業規則および退職金規定を整備しておくことが重要であり、
また、その就業規則等に基づいて、親族以外の他の従業員にも、
規則通りの支給がなされていることは、傍証として重要である。
本件では、通達がおおむね50%以下の減少とする報酬の減少について、
職務給では約30%、給与全体でも約21%の減少に過ぎないにもかかわらず、
裁判所は、職務の激変に伴う給与の減少として是認したことには、
注目してもよいのではなかろうか。
この点の、今後の税務行政に与える影響を考えると、
課税庁がなぜ控訴しなかったのか、不思議でならない。
つまり、職務の激変に伴う給与の減少額は、通達基準にいう半額以下、を
裁判所は判断基準とはしていないということだからである。
この点の明確な基準は、今後の判例の積み重ねを待つしかなかろうが、
いかに通達のみに従うことが納税者に不利な、
無用の税額の支払をお願いする行為となるかを、我々税理士は肝に銘ずる必要があろう。