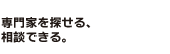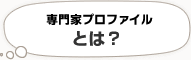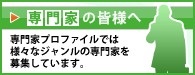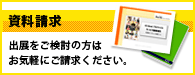- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
最高裁平成19年3月13日判決を紹介したい。
本件の概要は、以下のようなものであった。
染色業を営んできた原告X社は、創業者であるAが平成3年まで
代表取締役を務め、Aの息子であるBが2代目を引き継いでいた。
しかし、平成11年以降、繊維業界不況の影響から赤字に転落し、
平成11年6月から事業整理を開始するに伴い、
役員報酬を代表取締役Bは150万円から75万円、
取締役Aは80万円から20万円と大幅に引き下げた。
平成13年11月までに工場の従業員を解雇して工場を閉鎖するとともに、
Aら役員および従業員を被保険者とした簡易保険および団体生命保険の
満期保険金として、約1億5614万円の支払いを受けた。
平成13年10月に給与の改訂を行い、Bは75万円から95万円に増額をし、
平成14年1月にBの妻であるCが取締役に就任したのに伴い、
新事業形態への転換を企図した。
平成14年3月31日に臨時株主総会、取締役会を開催し、
代表取締役Bの退任、取締役Aの取締役退任を決議し、これに伴い、
Aに対し1560万円、Bに対し4000万円の退職慰労金(本件金員)を
支払うことを決議した。また、後任の代表取締役にはCが就任し、
Bは取締役として残り、Aは監査役に就任することを決議した。
この役員分掌変更に伴い、各々の役員報酬は、Bは95万円から45万円に、
Aは20万円から8万円に減額し、Cは20万円から45万円に増額された。
被告Y税務署長は、本件退職慰労金の支払いについて、
A、Bに退職の事実がないから役員賞与にあたるとして、
本件更正処分を行ったところ、原告X社が本件更正処分の取り消しを求めて
提訴したものが本件である。
判決内容は地裁、高裁はほぼ同じ、
最高裁は、実質的に事実誤認又は単なる法令違反を主張するのみの
上告理由に対して、上告不受理決定をし、納税者敗訴が確定した。
判決内容は、京都地裁平成18年2月10日判決の文章から紹介する。
原告は、本件事業年度までに、取引先の倒産、廃業、事業縮小などにより
売上高が減少し、自社工場を閉鎖し、従業員を解雇しており、
外注を主とするようになっており、原告の業務の実態、内容は、
本件事業年度において大きく変わっていることはうかがえる。
しかし、原告は、同年4月1日以降も従前の取引先との取引を継続され、
その取引による売上げが同日以降も、従前の取引先との取引が
原告の業務の主要部分を占めること、主要な取引先との実質的な対応は、
引き続きBが担当していたこと、Cが企画制作及び販売している
商品の売上高が原告の売上高に占める割合は小さいこと、
同日以降のBの報酬は減額されたとはいえ、なお代表取締役であるCと
同額であることなどの事情を考慮すると、Bは、同日以降も、
原告で常勤しており、原告の売上げの相当程度を占める主要な活動について
重要な地位を占めていたというべきである
(原告自身も,本件事業年度の後の法人税の確定申告の際には,
Aが常勤の取締役であるとの認識を有していたこともその表れである。)。
この点、原告は、同日以降、Bに替わってCが代表者として
原告の経営上主要な地位を占めていたという趣旨の主張をし、
証人B及び原告代表者も同趣旨の供述をするが,
Cのそれまでの原告における経験は豊かであったとはいえない上、
Cの創作小物についての経験についても、縮小したとはいえ
原告の営業の主軸となり得るものといえるものではないことに照らし、
両者の供述は不合理というべきであり、採用することはできない。
そうすると、Bが平成14年3月31日をもって、
「常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても
代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上
主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと」
(本件通達(1))との事実はなく、その他、原告を実質的に退職したのと
同様な事情があったとは認められない。
確かに、本件事業年度までの工場の閉鎖、従業員の解雇などの経過からすれば、
原告の元従業員などの関係者との関係では、少なくとも形式的には、
Aら役員が退任する意味があることは理解できるものの、そのことは、
実質的にも退職することまでも必要とした事情とまではいうことができない。
また、原告は、Cを代表者として、それまでの染色業から創作小物品の小売へと
業務を転換し、それに伴い、A及びBは、原告を実質的に退職した旨主張するが、
平成14年4月1日以降の原告の売上げの大部分は、従前の取引の継続によるもの
であり、Cの創作小物についてのそれまでの経験が豊富ともいえないことからすれば、
創作小物品の小売への業務の転換を主な目的として代表者を交代し、
それに伴ってA及びBが原告を実質的に退職したとは考え難い。
むしろ、本件事業年度には、保険金等の雑収入があり、
本件金員の支払がない場合には、本件事業年度の法人税額は多額になるのに対し、
本件金員の支払がされ、それが損金として認められた場合には、
法人税額は0円となること、原告の主張によっても、A及びBに対する
退職金の支給が本件事業年度の最終日の株主総会及び取締役会で決議されたと
されていることを考慮すると、上記の雑収入があったことに伴う法人税額の増額を
避けるために、A及びBが原告を退職したものとして、
本件金員の支払をしたという疑いも生じる。
と判示され、退職金の損金性を否認されているのである。
高裁では、もう少し詳しい事実認定が行われているが、
判示内容に全く変わりはない。
従来の判例はこのようなものであったことを念頭において、
次回以降、損金性が認められた事例を紹介することにしたい。