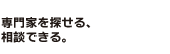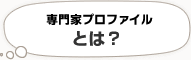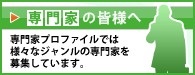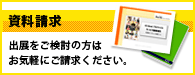- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過労によるくも膜下出血について労働者災害補償保険法の業務災害と認められた事例
最高裁判決平成12年7月17日、休業補償不支給決定取消請求事件
訟務月報47巻10号3044頁、最高裁判所裁判集民事198号461頁、判例タイムズ1041号145頁
【判示事項】 支店長付きの運転手が自動車運転の業務中に発症したくも膜下出血が業務上の疾病に当たるとされた事例
【判決要旨】 支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた者が早朝支店長を迎えに行くため運転中くも膜下出血を発症した場合において、同人が右発症に至るまで相当長期間にわたり従事していた右業務は精神的緊張を伴う不規則なものであり、その労働密度は決して低くはなく、右発症の約半年前以降は1日平均の時間外労働時間が7時間を上回り、1日平均の走行距離も長く、右発症の前日から当日にかけての勤務も、前日の午前5時50分に出庫し、午後11時ころまで掛かってオイル漏れの修理をして午前1時ころ就寝し、わずか3時間30分程度の睡眠の後、午前4時30分ころ起床し、午前5時の少し前に当日の業務を開始したというものであり、それまでの長期間にわたる過重な業務の継続と相まって、同人にかなりの精神的、身体的負荷を与えたものとみるべきであって、他方では、同人は、くも膜下出血の発症の基礎となり得る疾患を有していた蓋然性が高い上、くも膜下出血の危険因子として挙げられている高血圧症が進行していたが、治療の必要のない程度のものであったなど判示の事情の下においては、同人の発症したくも膜下出血は業務上の疾病に当たる。
【参照条文】 労働者災害補償保険法7条1項
労働者災害補償保険法(平7法35号改正前)12条の8第1項
労働者災害補償保険法(平7法35号改正前)12条2項
労働基準法75条、76条1項
労働基準法施行規則35
第七条1項 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
第十二条の八第1項 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
第十二条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
○2 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
1 本件は、支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた当時54歳の労働者Xが、早朝、支店長を迎えに行くため自動車を運転して走行中くも膜下出血を発症したことにつき、右発症が業務上の疾病に当たるか否かが争われた事案である。
2 Xの業務は、支店長の乗車する自動車の運転という業務の性質からして精神的緊張を伴うものであった上、支店長の業務の都合に合わせて行われる不規則なものであり、その時間は早朝から深夜に及ぶ場合があって拘束時間が極めて長かった。Xはくも膜下出血の発症に至るまで相当長期間にわたり右のような業務に従事してきたのであり、とりわけ、右発症の約半年前以降は、1日平均の時間外労働時間が7時間を上回る非常に長いもので、1日平均の走行距離も長く、右発症の前月は1日平均の走行距離も最高であった。
その後右発症の前月(4月)下旬から当月(5月)初旬にかけては断続的に6日間の休日があったものの、右発症の前日から当日にかけてのXの勤務は、前日の午前5時50分に出庫し、午後7時30分ころ車庫に帰った後、午後11時ころまで掛かってオイル漏れの修理をして午前1時ころ就寝し、わずか3時間30分程度の睡眠の後、午前4時30分ころ起床し、午前5時の少し前に当日の業務を開始したというものであった。
Xは、くも膜下出血の発症の基礎となり得る疾患(脳動脈りゅう)を有していた蓋然性が高い上、くも膜下出血の危険因子として挙げられている高血圧症が進行していたが、治療の必要のない程度のものであった。
3 第1審(判例タイムズ824号163頁)は、Xの発症したくも膜下出血は業務上の疾病に当たるとしてXの請求を認容すべきものとしたが、控訴審(労働判例683号73頁)は、Xの右発症は業務上の疾病に当たると認めることができないとしてXの請求を棄却すべきものとした。
Xからの上告に対し、最高裁判決は、Xのくも膜下出血の発症は業務上の疾病に当たるとして、原判決を破棄し、控訴棄却の自判をした。
4 労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険給付は、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関して行われるものであり(7条)、本件で問題となっている休業補償給付は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合に支給される(労災保険法12条の8第2項、労働基準法76条1項、75条)。
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合とは、労働者が業務に起因して負傷し又は疾病にかかった場合をいい、業務起因性が肯定されるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要であるとするのが、判例の立場である(最2小判昭51・11・12裁判集民事119号189頁等)。
なお、労働基準法75条2項は、業務上の疾病の範囲は命令で定める旨規定し、労働基準法施行規則35条、別表第1の2がこれを定めているところ、Xが発症したくも膜下出血のような非外傷性脳血管疾患は、別表第1の2の9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するか否かということになる。同号は、「明らかな」という文言を用いているものの、因果関係の明白性を要求する趣旨のものではないと解するのが通説であり、行政解釈でもある。
ところで、非外傷性の脳血管疾患は、一般に、高血圧症や脳動脈りゅう等の基礎疾患が加齢や日常生活の様々な要因と影響しあって悪化し、発症に至るものであるため、どのような場合に業務と疾病との間に相当因果関係を認めることができるかが問題となる。
このように、複数の原因が競合して結果(疾病、死亡等)を発生させた場合の業務起因性の判断基準について、相対的有力原因説、共働原因説などが唱えられている。
労働省の行政解釈は相対的有力原因説を採っており、相対的に有力な原因であるとは、業務が当該事案(当該被災労働者)にとって有力原因であるだけでは足りず、客観的に他の事案(一般的な労働者)に当てはめても発症の原因となるようなものであることを要し、この意味での普遍的妥当性が必要であるとしている。そして、この見地から、平成7年2月1日付け基発第38号労働省労働基準局長通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(7年通達)が出されている。この7年通達は、昭和62年10月26日付け基発第620号労働省労働基準局長通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(62年通達)を一部改定したものであって、脳血管疾患等の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが医学経験則上認められる負荷を「過重負荷」とし、業務による過重負荷の類型を、(1)発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと、(2)日常業務に比較して特に過重な業務に就労したこと、の2つに限定した上、これらのいずれかの業務による明らかな過重負荷を発症前に受けたことが認められること、及び過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が医学上妥当なものであること、を業務起因性認定の要件としている。
(2)については、「日常業務」とは通常の所定労働時間内の所定業務内容をいうものであるとし、また、「特に過重な業務」とは日常業務に比較して特に過重な精神的、身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、客観的とは、当該労働者のみならず、同僚労働者又は同種労働者にとっても特に過重な精神的、身体的負荷と判断されることをいうものであるとしている。
そして、発症に最も密接な関連を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず第1にこの間の業務が特に過重であるかを判断し、発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前1週間以内に過重な業務が継続している場合にはこの間の業務が特に過重であるか否かを判断し、発症前1週間より前の業務については、この業務だけで血管病変等の急激で著しい増悪に関連したとは判断し難いが、発症前1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合には、発症前1週間より前の業務を含めて総合的に判断することとしていた。
労働者災害補償制度は、使用者が労働者を自己の支配下において労務を提供させるという労働関係の特質にかんがみ、業務に内在ないし随伴している危険が現実化して労働者に傷病等を負わせた以上、使用者に無過失の補償責任を負担させるのが相当であるとする危険責任の法理に基づくものであると解するのが通説である。
したがって、業務と疾病との間の相当因果関係の有無は、経験則、科学的知識に照らし、その疾病等が当該業務に内在又は随伴する危険の現実化したものであるか否かによってこれを決すべきものと解されよう(労働省労働基準局編『労災保険・業務災害及び通勤災害認定の理論と実際上』96頁~97頁)。
相対的有力原因であるというのも、共働原因であるというのも、結局のところ、説明の仕方の違いに過ぎない面があるということもでき、最高裁判決においても、こうした一般論を説示した例はない。
このような観点から前記7年通達をみると、「日常業務に比較して特に過重な業務」については、直前や発症前1週間以内の業務さらには発症前1週間より前の業務の内容、程度に特段の変化がなくても、恒常的な時間外労働が行われていたり、恒常的に大きな精神的、身体的負荷のかかった業務に従事しているなど、当該労働者の通常の業務内容自体が既に過重なものであった場合には、その疾病の発症が当該業務に内在又は随伴する危険の現実化したものであると評価すべき場合もあり得るところであろう。
下級審裁判例においても、発症前1週間に限らず、比較的長期にわたって業務の過重性を検討しているのが大勢である。また、「自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが医学経験則上認められる」との点についても、当該負荷が血管病変等をその自然経過を超えて有意に増悪させたと(通常人の)経験則上認められれば足りるというべきであり、それ以上に右増悪が「急激」なものであることや「著しい」ものであることまで要するものではないというべきように思われる。問題は、いかなる事実関係が認められる場合に当該負荷が当該労働者の血管病変等をその自然の経過を超えて有意に増悪させたと(通常人の)経験則上認められるか否かであるが、業務起因性の判断は、法的判断であるとはいえ、基本的に事実認定と事実に対する評価によって決せられる部分の多い判断であり、個別具体的事実関係を捨象して一般的基準を定立することはできないものといえよう。
5 本判決は、原審の確定したXのくも膜下出血発症前の業務の内容、態様、遂行状況等に基づき、Xの業務は待機時間の存在を考慮してもその労働密度は決して低くはなく、所定の休日が全部確保されていたとはいえ、精神的緊張を伴い、不規則で、拘束時間が極めて長い業務に相当長期間にわたり従事したことが、Xにとって精神的、身体的にかなりの負荷となり慢性的な疲労をもたらしたことは否定し難いとし、前日から当日にかけての業務もそれ自体Xの従前の業務と比較して決して負担の軽いものであったとはいえず、前日から当日にかけての業務がそれまでの長期間にわたる過重な業務の継続と相まってXにかなりの精神的、身体的負荷を与えたものとみるべきであるとした。
そして、原審の確定したXの基礎疾患の内容、程度に加えて、脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧症、動脈硬化により増悪するものと考えられており、慢性の疲労や過度のストレスの持続が慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の1つとなり得るものであることを併せ考えれば、Xの右基礎疾患が右発症当時その自然の経過によって一過性の血圧上昇があれば直ちに破裂を来す程度にまで増悪していたとみることは困難というべきであり、他に確たる増悪要因を見いだせない本件においては、Xが右発症前に従事した業務による過重な精神的、身体的負荷がXの右基礎疾患をその自然の経過を超えて増悪させ、右発症に至ったものとみるのが相当であって、その間に相当因果関係の存在を肯定することができると判示した。
6 本判決は、これまでの最高裁判決と同様に、業務起因性の判断基準についての一般論に触れるものではなく、あくまでも事例判断を示したにすぎないものであるが、本判決が示した判断手法は、最3小判平9・4・25裁判集民事183号293頁、判例タイムズ944号93頁と並んで、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の業務起因性(公務起因性)の認定にとって有力な指針となるものと思われ、今後の実務に与える影響は大きい。
なお、本最高裁判決後に、労働省は過重な業務による脳血管疾患等の認定基準(前記7年通達)を改定した。