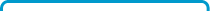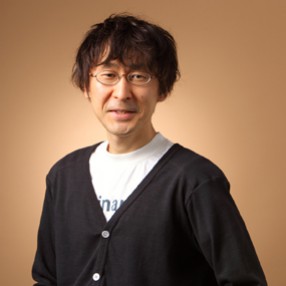
田尻 健二
タジリ ケンジマクドナルドのボリビア撤退の事例から見えてくる、主体性の大切さ
-
![]()
ボリビアからのマクドナルド撤退の事例を元に、私の研究テーマの中心の一つである「主体性」について書かせていただきます。
なお事例について詳しくは次のページをご覧ください。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449156718506037&set=a.308856822536028.74424.303781663043544&type=1&theater
主体性とは?
最初に主体性について簡単に説明させていただきます。
ここでの主体性とは、自らの意思で物事を考えたり判断して選択・実行することを指します。
そしてそれができれば主体性がある、できなければ主体性がない状態となります。
マクドナルドの件は「選択」の違いに過ぎない:
リ ンク先の記事によれば(恐らく他国では大きな成果を挙げたと思われる)様々な戦略をマクドナルドが駆使したにも関わらず、ボリビアでは赤字続きで撤退せざ るを得なかった、そしてその理由はボリビアの国民が自国の伝統料理を支持し、マクドナルドのハンバーガーを買わなかった、つまり自国の伝統料理を食べ続け ることを「選択した」ということです。
対して日本をはじめとした他の国々でマクドナルドが多くの売り上げを上げているということは、それだけ多くの人々がマクドナルドのハンバーガーを買った、つまりボリビアの人とは異なる「選択をした」ということです。
企業のマーケティング活動は消費者に「影響」を与えられるに過ぎない:
確かにマクドナルドはじめとした大企業は莫大な予算を使い、心理学の研究成果までをも駆使しながら、私たち消費者に自社の商品をできだけ多く買わせるようなマーケティング活動を行っています。
しかしそのような活動は人々の消費行動に影響を与えることはできても、完全にコントロールすることなどできません。
つまり洗脳することなどできません。
ただし、このことには例外がありまして、冒頭の主体性がない状態では、自らの意思で物事を考えたり判断して選択・実行することが難しくなるため、外からの情報の影響を非常に受けやすくなります。
で すからボリビア以外の国では、多くの人がマクドナルドのハンバーガーを自ら好んで購入したか、あるいは主体性が欠けてるためにマーケティング活動などの影 響をダイレクトに受けて、特に明確な理由もなく、ただ何となく、頻繁にマクドナルドのハンバーガーを購入しているのかのいずれかだと思われます。
主体的に生きることが幸福な人生に繋がる:
以上のような理由から、もし多くの人が、自らの判断に基づく明確な意思によりマクドナルドのハンバーガーを購入しているのでしたら、それはその人にとって満足な食生活となっているはずです。
しかし、もし満足には程遠い状態なのでしたら、それは主体性が欠如した状態により、外部からの影響をあまり大きく受け過ぎた結果と思われます。
また今回の考察からも言えることですが、その人にとって幸福な人生とは、外から与えられることを待つよりも、自らの判断で選択する行為を通じて培っていくものと考えられます。
最 後に恐らく人によっては、マクドナルドのハンバーガーを「選択せざるを得ない」理由をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、それらを一つ一つ検証致しま すと非常に大部となってしまいますので、今回の考察ではそれらの検証を一切省略し、突き詰めて考えれば「たとえどのような状況でも人間には選択の自由がある」という考えを示して、今回の考察の結びとさせていただきます。
 「社会問題」のコラム
「社会問題」のコラム
東京MXテレビ「5時に夢中!」に再び出演させていただきます!(2014/08/19 13:08)
憎しみの連鎖を断ち切る「公共外交」の可能性(2013/06/28 00:06)
企業が求める人材が大きく変化して来ているのでは?(2013/06/26 20:06)
最近、マズローの欲求段階説を誤用したような労務管理手法が注目され気になっています…(2013/06/25 13:06)
アメリカの銃社会と日本の右傾化への考察(2013/05/09 21:05)
 このコラムに関連するサービス
このコラムに関連するサービス
- 料金
- 4,000円
カウンセリングの実務経験5年以上の産業カウンセラーによる、低料金の電話カウンセリングです。