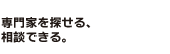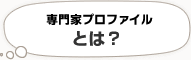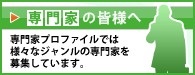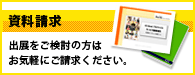- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
blog201403、会社法
・證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件(最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、民集54巻6号1767頁)
・弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ)
・笹山幸嗣『MBO 経営陣による上場企業の戦略的非公開化』
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件
最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、取締役損失補填責任追及事件
民集54巻6号1767頁
【判示事項】
一 旧商法266条1項5号にいう「法令」の意義
二 会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に会社をして違反させることとなる取締役の行為と旧商法266条1項5号にいう法令違反行為
三 複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において共同訴訟人の一部の者が上訴をした場合に上訴をしなかった者の上訴審における地位
【判決要旨】
一 旧商法266条1項5号にいう「法令」には、取締役を名あて人とし、取締役の受任者としての義務を一般的に定める旧商法254条3項(民法644条)、旧商法254条ノ3の規定及び取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定のほか、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定が含まれる。
二 取締役が会社をして会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に違反させることとなる行為をしたときは、右行為が取締役の受任者としての業務を一般的に定める規定に違反することになるか否かを問うまでもなく、旧商法266条1項5号にいう法令に違反する行為をしたときに該当する。
三 複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において、共同訴訟人である株主の一部の者が上訴をした場合、上訴をしなかった者は、上訴人にならない。
【参照条文】 旧商法266条1項(現行の会社法423条)、旧商法267条(会社法847条)、民事訴訟法40条1項
一 本件は、大手証券会社Aが大一口顧客である訴外会社Bに対して損失補填を行ったことによりAに補填相当額の損害を生じたとして、Aの株主であるXらが、その決定・実施に関わった当時のAの代表取締役であるYらに対し、旧商法266条1項5号に基づき損害賠償を求める株主代表訴訟である。
二 本件の事実関係及び訴訟経過の概要は次のとおりである。
1 Aは、大口顧客であるBと有価証券の売買等による資金運用取引を継続してきており、Bの証券発行に際しては主幹事証券会社の地位にあった。
2 Bは、訴外信託銀行との間で一〇億円の特定金銭信託契約を締結し、同銀行がAに開設した取引口座を通じて有価証券の売買を行う特金勘定取引を開始したが、実際にはAがBに代わって同銀行に取引の指図をすることによって運用されるいわゆる営業特金による取引であった。
ところが、右取引により平成元年末には約二億七〇〇〇万円の損失が生じ、平成二年に入ってからの株式市況の急激な悪化により損失が更に拡大し、Bが期間満了を待たずに右取引を終了させた同年二月末には損失は約三億六〇〇〇万円に上っていた。
3 平成元年一一月ころから証券会社の大口顧客に対する損失補填が社会問題となり、大蔵省は、同年一二月二六日、「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」と題する証券局長通達(本件通達)を発し、証券会社において法令上の禁止行為である損失保証等による勧誘に限らず、事後的な損失補填等も厳にこれを慎むとともに、特金勘定取引についても顧客と投資顧問業者との間に投資顧問契約を締結させるべきものとした。日本証券業協会も、本件通達を受けて、同協会の内部規則である公正慣習規則第九号(本件規則)を改正し、事後的な損失補填等をも厳に慎むものとする旨の定めを置いた。
Aを始めとする証券会社においては、本件通達等の主眼が営業特金の早期解消にあると理解し、株式市況が急激に悪化する中で顧客との関係を良好に維持しつつ営業特金の解消を進めていくためには、損失補填を行うこともやむを得ないとする考え方が大勢を占めていた。
4 Aでは本件通達の直後からBと営業特金の解消に向けて交渉したが解決に至らず、Bとの円満な取引関係を維持するために損失補填を実施する必要があるとして、平成二年三月、Yらが出席したAの専務会においてBに対する損失補填が決定され、AがBに売却した外貨建てワラントを即日買い戻すという相対取引により実施された(本件損失補填)。この結果、Bは三億六〇〇〇万円強の利益を得て、営業特金も解消された。
その後、AとBとの取引関係は良好に維持され、AはBとの取引により相応の利益を得ている。
5 Xらは、本件損失補填が(1)平成三年法律第九六号による改正前の証券取引法(旧証取法)50条1項等に違反する、(2)昭和五七年公取委告示第15号の9項(不当な利益による顧客誘引)に該当し、独禁法19条に違反する、(3)取締役の善管注意義務・忠実義務に違反するなどとして、Yらに対し、旧商法266条1項5号に基づく損害賠償として損害金内金一億円の支払を請求している。
6 一、二審とも本件損失補填の独禁法19条違反性のみを肯認したが、一審は、本件損失補填によりその後得られる利益を考慮すれば損害があるとはいえないとしたのに対し、原審は、独禁法19条が競争者の利益を保護することを意図した規定であることを理由に、同条違反は旧商法266条1項5号にいう法令違反には含まれないとして、Xらの請求を棄却すべきものとした。これに対してXらのうち二名から上告がされたところ、最高裁は、旧商法266条1項5号にいう法令には、取締役を名あて人とし取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を定める規定のほか、会社を名あて人とし会社がその業務を行うに際して遵守すベき義務を定める規定も含まれるとした上で、Yらにおいて独禁法19条違反の認識を欠いた点につき過失があったとはいえないとして、Yらの責任を否定した原審の判断を結論的に維持したものである。
二 取締役の任務は、会社の業務執行に関する意思決定に参画し、同時に他の取締役等の業務執行を監視するほか、取締役会からの委託等を受けて具体的な業務執行に携わるなど多岐に及ぶものであるところ、旧商法266条1項5号は、取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせるすべての場合を包含する債務不履行責任であって、無過失責任であるとされる1号~4号とは異なり、取締役の故意又は過失(帰責事由)を要すると解するのが通説・判例(最三小判昭51・3・23裁判集民事一一七号二三一頁)である。
そこでいう法令については、自己株式取得禁止(旧商法210条。平成13年商法改正により廃止)や競業避止義務(旧商法264条、会社法356条)等を定める旧商法中の具体的規定だけでなく、取締役の一般的な善管義務や忠実義務を定める規定(旧商法254条3項、254条ノ3。現行の会社法330条、335条)をも含むとするのが判例(最三小判昭47・4・25裁判集民事一〇5号八四三頁)であり、従来の通説であった。
本件一審判決等を契機として、会社の財産・利益の保護を目的とする実質的意義の会社法に属する規定等に限定されるべきであるとする限定説が有力に唱えられる一方、これに対して、従来の通説とは異なる非限定説が主張されるようになり、その中にも、法令違反行為があったからといって直ちに取締役の履行不完全と評価すべきではなく、法令違反の事実が主張立証されると、注意義務違反が事実上推定されるにとどまるとする見解や、取締役の法令遵守義務は、会社との間の委任契約に基づく善管注意義務とは別個の会社に対する義務であり、当該行為の決定に際して法令違反に当たることを知り得べき場合には、取締役に過失ありとして、損害賠償責任を負うとする見解が見受けられるなど、学説上議論が活発化し、下級審裁判例も分かれていた。
三 本判決は、旧商法266条1項5号にいう「法令」の意義について、取締役を名あて人とし、取締役の受任者としての義務を一般的に定める旧商法254条3項(民法644条)、旧商法254条ノ3の規定及びこれを具体化する形で取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定のほか、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定も含まれると解するのが相当であると判示して(判決要旨一)、非限定説を採ることを明らかにしている。営利法人である会社は会社ないしその所有者である株主の利益の極大化という目的を追求するものであるが、法で認められた社会的存在として、会社を名あて人とするあらゆる法令を遵守すべきは当然であり、取締役は、右の法令の直接の名あて人ではないが、受任者として会社に法令を遵守させるという義務を負い、その違反は取締役の責任原因となるものである。換言すれば、会社の意思決定に関与する機関たる取締役に対して、会社として法令を遵守するか否かに関して、これを否定する裁量権を認めることはできないというべきであろう。
取締役の会社に対する債務不履行責任は、いわゆる不完全履行の類型に属するものであるから、取締役の責任を追及する側で、問題とされている取締役の行為が取締役の受任者としての会社に対する義務に反するもの(受任者としての債務の本旨に従わざる履行)であることを主張立証しなければならない。旧商法266条1項は、各号で責任原因となるべき取締役の行為を列挙する形をとっており、5号にいう法令違反行為とは、不完全履行における履行不完全に相当する要件を規定しているものと解される。本判決は、取締役が会社をして会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に違反させることとなる行為をしたときは、右行為が取締役の善管義務・忠実義務に違反することになるか否かを改めて問うまでもなく、旧商法266条1項5号にいう法令に違反する行為をしたときに該当する旨判示して(判決要旨二)、取締役の責任を追及する側において、取締役の行為が同号にいう法令(善管義務・忠実義務を定める規定を除く。)に違反するものであることを主張立証すれば、それにより直ちに履行不完全の要件を充足し、取締役側において、帰責事由(故意過失)の不存在又は違法性・責任阻却事由の存在を主張立証しなければならないことを明らかにした。
本判決は、右の旧商法266条1項5号の解釈及び判断枠組みを前提とした上で、本件損失補填が独禁法19条に違反するものであり、旧商法266条1項5号にいう法令違反に該当することを肯定しながら、Yらが本件当時において、その行為が独禁法に違反するとの認識を有するに至らなかったことにはやむを得ない事情があったというべきであって、右認識を欠いたことにつき過失があったとすることはできないとして、Yらの損害賠償責任を否定した原審の判断を結論において是認している。
具体的法令違反が問題となっている場合に法令違反の認識を欠いたことにつき過失がなかったとして取締役の賠償責任が否定された先例として、前掲最三小判昭51・3・23がある。本件では、Yらが本件損失補填の決定実施に当たって法律専門家の意見を聴くこともしていないにもかかわらず、法令違反の認識を欠いたことに過失がないとされるのは、本判決が指摘しているような本件当時の特殊な状況が存在していればこそであり、こうした形での免責が認められるのは例外的なものであろう。
ただし、大規模会社で職務分掌している場合に、担当でない取締役には認識可能性がないとして、損害賠償責任の減免を認めた裁判例がある。
また、本件損失補填の決定実施がYらの取締役としての善管義務・忠実義務に違反するか否かに関しては、本判決は、右義務違反を否定した原審の判断を是認し得るとしている。
四 最大判平9・4・2民集五一巻四号一六七三頁(玉串料大法廷判決)は、類似必要的共同訴訟である地方自治法二四二条の二に規定する住民訴訟においては、自ら上訴をしなかった共同訴訟人は、上訴人の地位には就かない旨判示して、類似必要的共同訴訟における上訴審での審判対象の問題と当事者の地位の問題が、従来考えられていたように分離不能なものではないことを明らかにした。
株主代表訴訟は、個々の株主が共益権に基づいて、実質的には他の株主全体を代表して、形式的には第三者の法定訴訟担当として提起追行する類似必要的共同訴訟であって、訴訟の構造ないし形式の点では住民訴訟のうちいわゆる四号訴訟に最も類似しているところ、個々の株主にとっての個別的具体的利益が直接問題となるものではなく、原告株主の数が提訴後に減少しても、審判の範囲、審理の態様、判決の効力(損害賠償金は勝訴株主ではなく会社に支払われる。)には格別差違を生じない点や、株主全体の代表として訴訟を追行する意思を失った者に対して上訴人の地位に就き続けることを求めることが相当でないという点では、住民訴訟と基本的に変わるところはないことから、本判決は、大法廷判決の趣旨を推し及ぼして、複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟においても、共同訴訟人である株主の一部の者のみが上訴した場合には、自ら上訴しなかった者は上訴人にはならないと判示した(判決要旨三)。
五 取締役の責任が問題となるケースには、具体的法令違反が問題となるもの、経営判断の当否(善管注意義務)が問題となるもの、監視義務違反が問題となるものの3類型があるところ、本判決は、旧商法266条1項5号にいう法令の意義及び取締役の善管義務・忠実義務違反以外の具体的法令違反が問題となっている場合における判断枠組みに関して、最高裁として初めて明確な判断を示したものである。
弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ)
初版は2006年刊行。第2版が2010年刊行。
法学教室連載の単行本化。会社法の制定にいち早く対応した学者による演習書
旧商法での判例・学説との違いを重点的に論じている。これは司法試験での出題可能性が高いことによるものであろう。ただし、旧商法を勉強した実務家にとっても有意義である。 そして、会社法での解釈は未だ定まっているとはいえない。会社法の立法担当者とは違う説が学説上の多数説になったり、最高裁判例になっているからである。
上記書籍(初版)のうち、以下の部分を読みました。
設問2 株主代表訴訟
設問3 財産引受、開業準備行為
設問4 見せ金、出資の有効・無効
立法担当者は見せ金は出資として有効と考えていたようだが、最高裁は無効と解している。それが、その後の会社法改正につながった。
設問17 競業取引に対する会社の介入権の規定が廃止されたことの意義・効果
設問18 取締役の報酬等(取締役会設置会社、委員会設置会社)
設問26 子会社と親会社との取引、子会社株主の救済手段
設問27 債務超過会社との合併などの可否
弥永教授は実質債務超過会社の株式の価値は通常プラスであると解しているが、その理由付けは不明である。実質債務超過会社の株式であれば、株式の時価はゼロ以下のはずである。そして、実質評価がプラスの会社と実質評価がマイナスの会社が合併すれば、実質評価がプラスの会社から見れば、資産が減少するはずである。
設問28 会社分割の分割比率が不公正な場合の株主の救済方法
笹山幸嗣『MBO 経営陣による上場企業の戦略的非公開化』
日本経済新聞出版社、2011年、約198頁。
銀行出身のMBA保有者、弁護士による共著である。
なお、資料として、経済産業省のMBO指針(インターネットでも無料でダウンロードできる)がついているので、こちらは精読する価値がある。MBO指針は、実務的には非常に重要だからである。
上記書籍を読み終えました。
MBOは経営陣による企業買収である。買収の主体が従業員の場合には、EBOという。
上場廃止するため「非公開化(ゴーイング・プライベート)」の類型に含まれる。
PE(プライベート・エクィティ)ファンド・投資ファンドにより買収資金を調達せずに、自己資金で行う場合を「純粋MBO」という。
投資ファンドからの買収資金の調達の比率が高いと、議決権の過半数以上を保有されてしまい、MBOというより、投資ファンドへの売却というほうが実態に近い。
第1章 MBOとは何か
MBOを実施する企業は成熟段階にあることが多い。成熟段階にあることは、会社の業歴が長く、上場企業として十分な信用・実績もあり、手元に資産もある。
経営陣に大株主であるオーナー一族が含まれていることが多い。議決権が集中していることが多い。TOBで9割を握りやすい。
なお、本書で議決権の100%が上場廃止基準としているのは、誤りである。現在では、特定少数株主に株式が集中していること自体が上場廃止基準である。議決権の9割を支配している場合には、産活法により少数株主に現金対価を与えて排除すること(スクィーズアウト)ができる。なお、会社法改正により、同様の規定が設けられる予定である。ただし、税務面では、株式以外の現金等を対価とする場合は、非適格組織再編として課税されるので、株式併合・減資などにより、少数株主の株式を1株未満とする手法、全部取得条項付種類株式を活用する手法により、適格組織再編として課税されないようにするのが通常である。
PER(当該企業の市場での株価の総額である時価総額を会社の純資産総額で割った指標)が1倍を下回る企業が多い。PERが1倍以下ということは、会社や事業を買うより、株式を取得したほうが、買収資金が安上がりということを意味する。
自己株式の取得を実施して金庫株(議決権がない)のある企業が多い。自己株式は議決権がないため、MBOを決定する株主総会で、相対的に特別決議をしやすい。
MBO実施前の株価に比べてMBO実施後の株価の下落率が、TOPIX平均下落率よりも、大きい企業が多いのは、意外に感じた(ここで下落率を比較したのは、一般的な株価が下落しているため)。本稿では指摘されていないが、理論的には、MBOの前後で同一の資産・負債の構成であれば、経営が効率化した分、株価が上昇すべきことになる。しかし、MBOの買収資金による負債が増加したり、借入金利子によってキャッシュが社外に流出した場合には、株価が下落する。もっとも、資産を時価で処分しただけで現金等に形を変えただけならば、株価が下落することはないはずである。そうすると、経営効率化・リストラ目的にせよ、MBOは、MBOを行う経営陣よりも、MBOに投資する投資ファンド・買収者側にとって、メリットがより大きいのではなかろうか。
逆に、MBO後に再上場して、MBO前より株価が高くなる場合には、効率化等に成功したことを意味する。
会社の業歴が長く、低成長であるにせよ、業績が安定していて、資産があり、かつ借入金が少なく、それ以上の経営資源を特に必要としないということは、逆に、投資ファンドから資金調達しやすいことを意味する。本稿では指摘されていないが、そのような企業であれば、金利の安い銀行などの金融機関からの借り入れを選択しやすいのではないであろうか。
もっとも、本稿では指摘されていないが、そういう属性の企業であれば、オーナーが自己資金で純粋MBOするであろうし、または、創業家が保有株式を他へ処分してハッピー・リタイヤメントする場合以外には、あえて投資ファンドから資金調達までしてMBOをする必要がないのではないかという疑問を感じた。
第2章 経営者はMBOをどのように進めるか
本稿ではMBOを考える契機として、
(1) 事業や企業組織の改革を目指す
(2) 親会社からの売却
(3) 事業承継
(4) 上場維持の負担感、
があると指摘されている。
上記(1)の事業・企業改革だけでMBOを考えるかについては、MBOのコスト的に見て疑問がある。むしろ、経営の自由度を高め、上場維持費用を節約する場合のほうが多いのではないかと推測される。逆にいうと、上場のメリット・デメリットを比較して、経済合理性の観点から、上場しているメリットが少ないと感じる場合であろう。
上記(2)のオーナーが親会社の場合には、MBOの対象企業が子会社という地位を脱して、独立した会社になる。親会社が競業他社への売却を避けたい、MBOを選択するメリットがあると本稿では指摘されているが、私見では疑問がある。現在のような不況・国際化(競業会社が国外の会社である場合)では、単独の小規模の会社での生き残りよりも、同業他社との事業統合(合併など)により、市場でのシェアをある程度握り、スケールメリットを生かしたほうが得策であるし、現に上場企業でも実例が多い。スケールメリットにこだわらない会社としては、特殊な技術・知的財産、得意先などがある場合であろう。
上記(3)について。事業承継の場合、後継者が創業家にいない場合が考えられる。MBOのうち、オーナー(創業家)一族以外の取締役が会社を買収したい場合、雇われサラリーマンの取締役では頬有株式が少なく買収資金がないので、投資ファンドに資金調達を頼ることになる。オーナー一族から取締役が株式を買い取り、親族以外への事業承継ということになる。サラリーマン重役から見れば、会社の買取りということになるが、投資ファンドから資金調達しているため、支配株主が創業家から投資ファンドに変わっただけということになりかねない。
また、支配株主が金融投資家などの場合、エグジット(出口)として、MBOが選択される場合がある。他社へ売却されるくらいなら、MBOをして経営を続けていきたいと考える場合である。もっとも、投資ファンドのデグジットの場合、MBOではなく、他の投資ファンドへの売却、競業他社へのM&Aという選択肢もある。
MBOを検討する場合、税務面で公認会計士・税理士、法律面で弁護士が必要である。財務面では、財務アドバイザーが必要である。
本稿では指摘されていないが、実は一番難しいのは、財務アドバイザーであろう。金融機関・投資ファンドから資金調達しつつ、それでいて、MBOする側の立場に立って助言してくれるというのは難しい。一番無難なのは、中立的な税理士・公認会計士に助言してもらいながら、金融機関と交渉する方法であろうか。金融機関といっても、大規模企業の場合には政府系の公庫や銀行でもよいであろうが、中小企業であれば、地方銀行・信用金庫・信用組合(業種により、農協など)のほうが親身になってくれることが多い。
過去の実例でも、M&Aの財務アドバイザーの巨額の報酬が問題となったことがある。
また、上場株式、集団投資スキームなど金融商品取引法が適用される場合には、助言・媒介などのアドバイザーには金融商品取引法上の免許が必要である。
また、本書では、経営者がMBOのメリットをよく理解することが大切であるとの記載があるが、私見では前記の疑問点があるとおり、本書を読んだだけでは、MBOのメリットとデメリットの比較、MBOの目的、M&Aの他の手段と比較した場合の特徴がよく理解できるようにならないのではないかと感じた。
第3章 MBOの実務
MBOのファイナンスを説明している。
しかし、専門用語を多用しているため、かえって説明になっていない部分も多い。
第4章 MBOにおけるM&A法務
主に会社法と金融商品取引法について書かれているが、法律の根拠条文を掲げていない部分が多く、ハウツー本という性格を免れない。
実務的に問題となる細かい論点についても触れているが、金融庁などの見解が公になっていなかったり、裁判例がない場合には、結論について明言を避けている。なお、裁判例についても、明確な引用を避けているようである。
第5章 MBOにおけるファイナンスの法務
投資ファンドが経営者をコントロールする融資条件やコベナンツ(財務制限条項)などが説明されている。
優先・無議決権株式を普通株式にできるように取得請求権付株式の条項は、投資ファンドに有利である。
また、金銭を対価とする取得請求権付株式は、株式を最終的に貸付にすることである。または、社債を対価とする取得請求権付株式は、株式を社債とする手法である。
いずれも、投資が順調にいかなかったり、投資の出口(エグジット)として、投資ファンドに有利になるように用意されるものである。
投資を受ける側としては、返済義務のない株式出資をしてもらったつもりが、借入金になってしまう危険性があり、MBO、投資ファンドを用いたベンチャービジネスなどについて、経営者としては、あらかじめ注意が必要である。