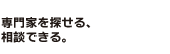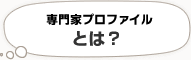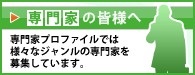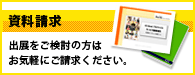- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
知的財産権法の読んだ本(その2-2)
[実務書]
第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』、商事法務、2010年、本文430頁。
複数の講師(裁判官・弁護士・弁理士などの実務家)による講演録のまとめである。
ブランドに関する法律として、商標法、不正競争防止法、独占禁止法を取り上げている。
「2 ブランドと独占禁止法」
独占禁止法に関する一般的説明は、独占禁止法を勉強したことのある人にとっては、やや長いです。
独占禁止法21条に基づく知的財産ガイドラインは商標権には適用されない。
独占禁止法は、供給される商品・役務について、市場画定をおこない、市場に対する悪影響つまり競争制限的効果を考える仕組みである。そして、市場画定の際には、ブランド間競争(異なるブランド間での競争)・ブランド内競争(同じブランド内での競争)にわけて考えるから、指定商品・指定役務に対する商標権を独占禁止法の適用除外とするわけにはいかない。なお、商品・役務の需要側の場合の市場画定も同様である。
講師は上記のようには説明していないが、私の説明のほうが簡潔・端的で分かりやすいと思われる。
また、流通ガイドラインでは、再販売価格維持はブランド内競争でも違法であるという立場と理解するのが通例であろう。
また、化粧品会社に対する公正取引委員会の審決と、資生堂・富士喜屋の民事訴訟とでは、結論が逆になっているのは周知のとおり。
なお、講師は、いろいろな事例を引き合いに出しているが、結論を明示していない箇所が少なくない。
「5 立体商標 商標法3条1項3号、3条2項の判断基準」
立体商標の定義は、商標法2条1項、5条2項に規定されている。
(定義等)
第2条1項 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
(商標登録出願)
第5条2項 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
立体商標の商標登録について特に問題(登録拒絶・無効など)となるのは、以下の条文である。
(商標登録の要件)
第3条 自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品・役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格・生産・使用の方法・時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏・名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標
2 前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
(注)商標法4条1項18号とも関係するが、商標法3条2項の特別識別力を獲得したかどうかが問題となる典型例として、以下の事例が考えられる。
飲料が入ったビンなどの容器は、ありふれた形状、あるいは動物・植物の形状、または、機能的に必要な形状として、商標権として独占権を設定することは適当ではないから、立体商標を登録することは難しい。
・コカコーラのガラス製のビンの形状(肯定例)
・乳飲料製品ヤクルトのプラスチックのビンの形状(否定例)
・ウィスキーのサントリー角瓶(否定例)
一見すると個性的だが、ありふれた形状、あるいは動物・植物の形状は、商標権として独占権を設定することは適当ではないから、立体商標を登録することは難しい。
・ケンタッキーフライドチキンの創業者カーネルサンダースの人形(人間の人物像そのものは普遍的である。)
・バラの形をしたチョコレート(否定例)
・お菓子「ひよこ」(否定例)
(商標登録を受けることができない商標)
第4条1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十八号 商品・商品の包装の形状であって、その商品・商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
商標権の「使用」とは、以下のとおりである。立体商標においては、商品形態が立体商標そのものである場合だけではなく、特に、立体商標以外の商品・役務について、立体商標を包装、表示、展示などして使用することが関連する。
第2条3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品・商品の包装に標章を付する行為
二 商品・商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品・役務に関する広告、価格表・取引書類に標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品・役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
「6 商標法上の混同概念の時間的の拡張と限界」
・購買前の混同に該当するかが問題となる例
インターネットのメタタグ
インターネットの検索型連動広告(スポンサー・リンク)
商標として使用していないので、侵害否定すべきかが問題となる。特にメタタグは、目に見えない。
ただし、インターネットの使用者の目に見える形で使用(映像面に表示、「使用」の定義に関する商標法2条3項8号。典型例はアイコン、商標そのものの表示)していれば、商標権の侵害、または、不正競争防止法2条1項1号・2号違反となる。
・商標機能論
最高裁判例フレッドペリー事件は、出所保証機能、品質保証機能を挙げている。また下級審裁判例・学説には、これらに加えて、宣伝広告機能を挙げるものがある。
宣伝広告機能は、不正競争防止法で保護されるという裁判例もある。
・田村善之教授の提唱する「購買後の混同」に該当するかが問題となる。
アメリカの判例での考え方
日本の裁判例では認められていない。詰め替えインクのリソグラフ事件
私見だが、詰め替え自体が商標権の「使用」に該当するから、あえて購買後という必要がないと思われる。(特許法に関するキャノンの詰め替えインク・カートリッジ事件参照)
処方薬で、患者が「購買後の混同」するかどうかに該当するかが問題となる。しかし、指定商品は「薬剤」であり、「処方薬」ではない。
ジーンズのリーバイスのスティッチ501事件では、購買後の混同かどうかに触れずに、商標権侵害を肯定している。なお、スティッチとはジーンズの後ろの部分のポケットの形状である。「501」は同社が名づけたシリーズ商品のサイズ・名称であり、著名性が肯定されているが、「503」では著名性が否定されている。もっとも、数字の3つの組み合わせでは、ありふれているとして、通常は侵害が否定されるであろう。
また、エール事件では、フランスの国旗と同じ3つの色と配色の順序と「ELLE」という文字で、商標権登録が認められ、商標権侵害を肯定した裁判例もある。しかし、通常は3つの色彩の組み合わせでは、よほど著名な商標でない限り、商標権登録・不正競争防止法も難しいと解されている。
「7 海外ブランドの日本における展開」
日本の最高裁判決で、「商品化事業」に初めて言及したのは、最高裁判決昭和59年5月29日NFL事件である。
日本のブランド品の典型は、洋服・カバン・財布・小物・化粧品など、ファッション、アパレル(洋服)業界での海外ブランドのライセンス生産である。
ディズニーは多数の指定商品・指定役務に商標権登録している。
コカコーラは多額の広告費用をかけている。
ライセンス契約のひな型についての解説がある。
ライセンス契約での「割引販売」については、独占禁止法の再販売価格維持に該当するかが問題となる。
「8 最近の商標権紛争の問題」
商標権無効の抗弁(商標法39条による特許法104条の3準用)について規定を設けたことは、商標権侵害訴訟を提起することをためらわせる動機付けになるのではないかという問題となる。ただし、登録していない標章については不正競争防止法・民法しか対策がない。著名・周知な商標については、不正競争防止法のほうが、判断が緩やかになるのではないかと推測される。
商標法特有の規定(例えば、商標法47条の5年の除斥期間、商標法50条・51条等の取消制度、商標法3条2項の特別識別力による登録など)との関係
特許法(創作法)と比較して、標識法である商標権独自の法理との関係
・商標機能論による真正品やライセンス品の並行輸入、
・小分け・再包装は違法。
・商標的使用論として商標権として使用しない場合は違法ではない余地がある。ただし、比較広告については問題がある。
商標権無効の抗弁と従来の判例法理の権利濫用の抗弁との関係
・代理人等による商標権の無断登録は商標法4条1項16号・19号(なお、商標法47条の除斥期間にかからない。)、不正競争防止法2条1項15項などで対処できる。
・団体や会社などが分割や相続、内紛で分裂した場合に、対立する当事者同士で、商標権承継者以外の者の権利保護をどうすべきかという問題がある。
・商標の類否判断
商標の類否判断に用いられる「称呼、外観、観念」の3つの基準について、「このうち1つでも非類似であれば商標は非類似である」という考えは判例では否定されている。
また、商標権登録の際の基準で重視されている称呼が最も優先という考えは、判例では採用されていない。
そして、取引の実情も考慮すべきとの判例の考えは、未だ使用されていない商標権登録の段階では、商標権登録の指針には必ずしもならない。
「9 商品形態模倣」
自社の商品形態を模倣する他社の商品に対抗する法的手段として、以下のものがある。
1、 商標法による商標権(ことに立体商標権)
2、 不正競争防止法2条1項1号(周知商品等表示)
肯定例、黒烏龍茶事件(東京地判平成21年12月26日、判例タイムズ1293号254頁)
否定例、正露丸事件(大阪地判平成18年7月27日、控訴審である大阪高判平成19年10月11日)
否定例、ワンカップ大関事件(神戸地判平成9年7月16日、控訴審である大阪高判平成10年5月22日)
否定例、永谷園ふりかけパッケージ事件(東京地判平成13年6月15日)
3、 不正競争防止法2条1項2号(著名商品等表示)
4、 不正競争防止法2条1項3号(発売後3年以内の商品等形態模倣禁止)
否定例、香酷事件(大阪地判平成16年12月16日)
否定例、アトシステム事件(大阪地判平成21年6月9日)
5、 意匠法による意匠権
6、 著作権法に基づく著作権(応用美術の論点)
なお、商標法や不正競争防止法における「混同のおそれ」「周知性」「著名性」などの要件を立証するためのアンケート調査は、調査の対象、調査の手法(特に誘導的な質問のしかた)などが恣意的なことが多く、裁判所では、余り重視されていないようである。
「10 めしや食堂事件」
トレードドレスは、アメリカの特許商標法で登録すれば、認められる。
トレードドレスとは、店舗の構造、外観、内装、色彩、配置、雰囲気などを指す。
しかし、日本では、認められていない。
トレードドレスと類似の考えを主張された事件として、「めしや食堂」事件があるが、ありふれた表示として、不正競争防止法侵害が否定されている。
通信販売カタログ事件は、カタログの外観・掲載商品がほとんど模倣されており、不正競争防止法違反を肯定した裁判例である。
全国共通図書券事件は、加盟店ではないブックオフについて、不正競争防止法違反が否定された。
もっとも、本稿には掲載されていないが、私の知る限り、コンピューターのアップル社がMac製品に酷似しているとして、不正競争防止法違反で他社メーカーを訴えた事例では、アップル社が勝訴している。
コンビニエンス・ストアで、ファミリーマート(現在は緑色)とローソン(現在は青色)の外観・色彩が酷似しているとして、不正競争防止法違反かが問題となった事例では、色彩を変えるという和解がされている。
また、喫茶店のエクシオールカフェがマイクロソフトの「エクセル」について、不正競争防止法が問題となった事例では、同カフェが店舗の色彩を緑色から青色に変更した事例がある。
なお、マイクロソフトは、日本のワープロソフト「一太郎」について、特許権侵害などで訴え、勝訴している。
また、日本のメーカーが電動髭剃り機に関して、アメリカで特許権侵害などを理由として訴えられ、勝訴はしたものの、大量の書類提出が必要なディスカバリー手続や陪審員裁判で、多額の弁護士費用・訴訟費用がかかったという事例もある。
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』、判例タイムズ社、2012年
上記書籍のうち、知的財産法に関して、以下の部分を読みました。
「8 共同研究開発契約」
本稿は、民法上の組合、有限責任事業組合契約に関する法律の有限責任事業組合契約に関して検討している。
しかし、共同研究開発契約には、合弁会社、委託契約、商法上の匿名組合、事業者団体、中小企業等協同組合法に基づく協同組合、ライセンス契約、出資や資金貸与などを行う形式などのさまざまな法的形式が考え得る。これらの論点について、本稿は検討していない。
なお、本稿では「ライセンス」を独占的実施権のみを指す用語に理解しているが、適切ではない。また、実施権がある場合、特許権の準共有者に対して影響を与えないかのごとき記述があったが、大きな誤解であろう。
特許法改正により、特許権が移転等した場合にも、移転前に設定された通常実施権は、登録なくして、特許権の譲受人に対して対抗できる(特許法99条)点の指摘が抜けている。
また、職務発明(特許法35条)について、対価の点の検討が抜けていた。職務発明の対価についての分担などをどのようにするかは1つの問題である。
また、本稿では、独占禁止法上の取扱いの検討がされていない。
一方的に知的財産の成果物を委託者に帰属させるのは、優越的地位の濫用に該当する(優越的地位濫用ガイドライン)。
また、公正取引委員会によれば、下請代金支払遅延等防止法にも違反する場合があると解されている。
また、情報交換が独占禁止法(不当な取引制限または、不公正な取引方法)に該当するかが問題となる場合がある。
有限責任事業組合契約に関する法律についての記述は、おおむね妥当であろう。
本稿では検討されていないが、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律も問題となる。
「10 OEM契約」
OEM契約に含まれる契約類型と関連する法律が列挙されている。
民法(売買、請負)
商法(商事売買、商行為法)
独占禁止法
下請代金支払遅延等防止法
製造物責任法(なお、OEM契約当事者間では債務不履行・契約責任も問題となる)
保険法(生産物責任保険と免責特約)
知的財産法として、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法(営業秘密)
外為法
租税法
仲裁法(商事仲裁)
「12 合弁事業者の法形態選択」
合弁事業の形態として、株式会社、合同会社、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合(LLP)、組合を比較している。
1、 合弁事業の契約を会社などにどう反映させるか(株主間契約、定款など。なお、株主間契約の契約当事者は株主であって、会社ではないから、株主間契約に会社は拘束されないと解されている。)
2、 出資比率
3、 事業形態の設立の費用・登記
4、 不動産の登記
5、 知的財産権の登録
6、 業務執行者
7、 機関設計・権限分配
8、 重要事項の決定(議決権行使)
9、 損益分配・損失負担
10、 資金調達
11、 合弁事業の終了
12、 出資持分の譲渡制限(好ましくない第三者が加入することの防止)
13、 出資持分の譲渡・払い戻し、先買権、買取請求権(プットオプション)、譲渡価格・清算の際の価格の取り決め
14、 構成員の脱退の防止(有効な対策はない。)
15、 金融機関・取引先からの評価(本稿では指摘されていないが、金融機関に対しては融資の際に定款を提出する必要があり、定款に構成員の権利義務が詳細に規定されていれば、金融機関がどう評価するかは問題である。)
16、 第三者に対する損害賠償責任(本稿では指摘されていないが、どの事業形態を選択しても、会社そのもの、あるいは、業務執行の担当者の所属する会社に対して、使用者責任などが追及される可能性がある。)
17、 構成員の倒産リスク(本稿では指摘されていないが、上場企業どうしの建設事業の共同事業で、組合の構成員企業が法的倒産し、他の構成員企業が損失を負担した事例が過去にあった)
18、 合弁事業や構成員に対する課税
なお、本稿では指摘されていないが、株式会社以外の法律請負形態であれば会計監査人設置会社とする必要がないのがメリットであるとの指摘があったが、私見では、逆に会計・監査の面でのデメリットになると思われる。上場企業の場合、連結対象であれば、監査の対象になる。また、法人税法上、連結対象とされていなくとも、税務調査の対象となる。
組合は、特定の商品・役務、建設事業の共同受注に向いているとされている。また、本稿では触れられていないが、映画の「製作委員会」方式も該当すると解される。
「15 企業間提携契約としての技術ライセンス契約とその条項」
特許権等侵害訴訟で和解した場合のライセンス条項が不抗争条項であるとの記述には疑問がある。ライセンス契約であれば、実施料(ロイヤリティ)、クロス・ライセンス契約などが定められることが多い。
「17 映画製作に関する提携契約」
映画製作について、製作委員会方式と匿名組合方式を比較している。
製作委員会方式
組合と解されている。
金融商品取引法が適用されない。
著作権が製作委員会の共有となる。しかし、本稿では指摘されていないが、契約により、著作権を1社に集中させる方策を取ることができる。ただし、出資、売上、収益分配と損失負担に応じて、あえて映画の著作権を準共有とするようである。映画の場合、ヒット作となる可能性もある反面、製作費すら回収できない場合も多いからである。
著作権の存続期間が長期間のため、構成員の変動・倒産が有り得る。
また、著作権の先買権条項を定める必要があるとされている。しかし、組合財産として、合有であれば、特に規定を設けなくとも、構成員が倒産した場合、脱退により、清算する必要がある。
また、本稿では指摘されていないが、著作権が組合財産や準共有の場合、譲渡・質入には著作権の共有者の同意が必要である。したがって、著作権の持分を処分しようとした場合、構成員の全員の同意が必要である。そのため、先買権条項を設けておかなくとも、予期しない第三者が加入してくるリスクはあまり考えられない。
本稿では指摘されていないが、譲渡価格について紛争になるケースが考えられるが、倒産の場合には清算価値である。もっとも、ヒット作品の場合、将来の収入が見込めるため、ことに対価について深刻な対立が生じることも考えられないではない。もっとも、著作権の持分には構成員全員の同意が必要となるため、反対する一部の構成員がいる場合には、対処が必要である。
製作後、新たな二次的利用が出てきた場合に著作権の持分処分に該当するため、どうすべきかについて、組合方式では難点があるとされる。しかし、本稿では指摘されていないが、二次的利用の場合、利用者に必ずしも著作権の持分の共有や支分権を譲渡する必要はなく、当該支分権に対して使用許諾を与えロイヤリティを取る方式で対処できる。例えば、商品化事業(マーチャンダイジング)の場合、商品について、非独占的な許諾を与え、生産量ないし売上に応じた使用料を取る方式である。非独占的な使用権の場合、複数の相手方に重複して許諾を与えることができるのもメリットである。有体物と異なり、著作権では使えば使うほど価値が増す特徴があるからである。また、本稿では指摘されていないが、衛星放送・インターネットが想定されていなかった時代に、衛星放送権・公衆送信権についても許諾を与えたと解している裁判例もあるが、組合方式の場合には、映画の著作権が組合財産と考えれば構成員の合有であるから、処分について構成員の同意を得ていないとして、別の考えが成り立つとも解される。実務上はむしろ、持分譲渡ではなく、許諾を与える方式が普通であろう。
原作・原画・音楽などのクラシカルオーサーの場合、当該原作等が著作権侵害した場合、第一次的には製作委員会が対処する必要がある。その場合の費用・損失分担について、本稿では指摘されていないが、あらかじめ構成間で契約で取り決めておく必要があるが、何も定めていなかった場合、組合法理ないし持分に応じた損失負担となろう。
匿名組合方式の場合、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するため(金融商品取引法2条2項5号)、金融商品取引法上の規制が適用される。また、本稿では指摘されていないが、金融商品の販売等に関する法律が適用されるかが問題となる。ただし、匿名組合の場合、著作権を集中させることができるメリットがある。
匿名組合の出資者が一般人と事業者・投資ファンドがあるとされるが、本稿では指摘されていないが、この場合の一般人は資産家・投資家などであろう。ただし、適格投資家の場合、金融商品取引法では、別の規制が適用される。
課税について、本稿では指摘されていないが、フィルム・リース事件がある。
第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』
商事法務、2005年、本文9項目、約400頁。
エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」
下請法では、親事業者の受領拒否・不当なやり直し要求が禁止されている。しかし、コンテンツの技術・技能不足により、技術・芸術水準を満たしていなければ、完成されていないことが理由であれば、正当な理由になるであろう。
また、下請法3条で、書面交付義務が定められているが、その中で役務の仕様などを記載すべきところ、放送番組などのコンテンツについては、抽象的過ぎて、ほとんど役に立たない。
「映画ビジネス」
映画を製作するのは多額の投資と労力が必要である。
そのため、現在の日本においては、映画会社、配給会社、広告会社、テレビ局などが参加する「製作委員会」方式が主流である。
監督はディレクターであり、映画の中身を「制作」する。
プロデューサーは、資金調達などの「製作」をする。
映画についての支出、すなわち、製作費・プリント費用、配給手数料、広告費などの資金の作り方について、解説している。証券化、私募、金融機関からのノンリコースローン、映画業界外からのプロジェクト・ファイナンス、個人投資家からの資金調達などの方法がある。
映画に関する収入、すなわち、劇場上映(劇場側が約半分を取る)、ビデオグラム(ビデオ、DVD)、テレビ放映権(BS、CS、地上波、インターネットなどの公衆送信)、マーチャンダイジング(小説化・玩具・グッズ・写真・絵などの商品化)などがある
「放送事業者の権利処理」
著作権法は「放送」が生放送を前提としている。放送事業者には、「放送」の許諾がある場合、放送する場合に録音・録画の時から6か月以内の一時的固定が認められる(著作権につき著作権法44条3項、実演家の著作隣接権につき92条2項)が、「録音・録画」についてまで許諾がある場合(著作権につき著作権法44条1項、実演家の著作隣接権につき93条1項)と区別しなければならない。
リピート放送するためには、「放送「録音」「録画」について、許諾を受ける必要がある。現在では、生放送が例外的なので、当初から、上記の許諾を受けておくべきである。
著作権法は、許諾につき書面によらなくてもよいとしているが、後日のビデオグラム化するためには書面によるべきである。
音楽の著作物について、放送事業者はJASRACに使用する音楽のリストを提出し、使用料を支払い、JASRACは著作権者・実演家・レコード会社などに分配する。
なお、筆者が見聞した許諾についての失敗例として、韓国テレビ番組「冬のソナタ」がある。ビデオ化しようとしたところ、まず第1話冒頭の曲の作詞家・実演家などが不明であるといった具合に、あれだけ大ヒットしたのに、当初の権利処理をきちんとしていなかったために、後日、権利処理に手間取ったのである。商品化にしても、主人公が着けていた黄色のマフラーについて、模倣類似品が出回ったといった具合である。
日本の放送事業で成功しているビジネスは、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、紀行番組などがある。
「アニメの実務」
ウォルト・ディズニーが最初作ったアニメで、制作費をもらってディズニーが映画化してヒットしたが、映画の興行収入は映画会社などに入り、著作権が原画の著作権者に留保されていたために、グッズの商品に関するロイヤリティなどがディズニーに入ってこなかった。
そのため、この失敗を教訓にして、ディズニー映画には、原作について著作権が切れている有名な童話などをアニメしたものも多い。または、オリジナルなストーリー・キャラクターに基づくアニメも多いが、オリジナルなものについては独占権を主張でき、模倣品を排除できる。
日本のアニメは、大企業の関連会社を中心とする制作プロダクションが多いが、裾野には中小零細の下請会社が多い。
「音楽の実務」
欧米では、音楽の著作物について、グランドライツ、スモールライツという分類があるが、日本の著作権法には、そのような分類は存在しない。
「パブリシティ権」
私見であるが、俳優・歌手などの写真について、ブロマイドや写真集、インターネットを含めて、被写体そのものに多大な財産的価値がある。しかし、日本では、肖像権・パブリシティ権で保護する以外になく、的確に保護する方法が必要がある。
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
商事法務、2012年、本文450頁。
著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。
本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。
以下、私が感じたなりの法的な疑問点について、多々書いたが、各業界(広告、映画、音楽など)の実情・慣習・慣行について、よくも網羅していると感心した。
『太陽風交点』に対する著者の批評については疑問がある。同事件は、明示の出版権設定がない場合、初版出版社に3年間の独占的出版権を認めなかった判決として、昭和61年当時、出版業界では、話題をよんだ。
著者は、「プロデューサー=資金出損者」という独自の観点から、同判決はプロデューサーが不当に軽んじられているとして、批判している。
また、同事件では、出版権設定契約か出版利用許諾契約かという論点もあるが、「疑わしきは契約起案者の不利益に解釈すべき」という契約解釈の一般的原則が適用されたに過ぎないと考えることもできる。
しかし、同事件が教訓となって、現在では、出版社は常に出版前に出版権設定契約を求める傾向がある。
そもそも、著作権法では、著作者を保護することから出発しているのであって、資金出損者を優位にするのは、
① 使用者が著作者・著作権者となる職務著作物、
② その性質上特別規定の多いプログラムの著作物、
③ 映画製作者を著作権者とする映画の著作物、
④ 広汎な著作隣接権を認められている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者くらいであろう。
⑤ なお、ゲームは判例上、音と映像の点から映画の著作物として、あるいは、プログラムの著作物として、取り扱われている。
これらの類型では、資金出損者は、コンテンツができる以前から、人件費・器材などの多額の経費を負担し、独自の配給・流通のシステムがあるからである。経費はかけたが回収できない「リスク・マネー」という著者独自のネーミングにも意味がありそうである(学問としての著作権法では、このような発想はあまりしない)。この著者は、上記のような特殊なビッグ・ビジネス(まさに「エンタテイメント」ビジネス)にのみ妥当しそうな考え方を、他の伝統的な著作権にまで無理に拡張・一般化しているような印象を受ける。
そして、小説・論文のような言語の著作物のコンテンツであれば、出版社が事前に多額の資金出損しているとはいえないと思われる。むしろ言語の著作物では、著作者が先行して自己投資して、コンテンツを創造するのが通例である。
なお、『太陽風交点』事件のような短編小説集であれば、タイトル及び収録されている短編小説を入れ替えるなどにより、出版権設定契約がある場合であっても、同一著者は、別の短編小説集を出版できることを指摘しておく(この点について触れている論者はいないようである。)。
疑問に感じた箇所
・「書籍の印税方式より買取り方式のほうが著作者にとって有利。」
印税と譲渡対価の金額の大小を言わずに一概には断定できない。そもそも著作権を買う側にしても、売れそうもない場合には、譲渡対価を安くするはずだから、「印税方式より買取り方式のほうが著作者にとって有利(高い)」などという経験則なるものは、最初から存在しないのである。普通のビジネスは「安く仕入れて、より高く売る」のが普遍的である。したがって、「売れた分しか印税が発生しない」印税方式のほうが、安く買い叩かれるより、著者にとっては、むしろ合理的である。
・音楽の著作物の場合
最初に著作権管理団体にコンテンツを信託的に譲渡する音楽の著作物の場合は、書籍の場合とは異なる。ただし、音楽の著作物の場合でも、買取りではなく、著作権管理を目的とする「信託的譲渡」であって、「真正売買」ではない。音楽の著作物のビジネスモデルでは、利用されるたびに、印税が支払われる。例えば、1曲ダウンロードされるたびに数円の印税が歌手(作詞家兼作曲家)に支払われるそうである。
・「譲渡対価が安いから譲渡の合意は存在しない」。
これは、売買の一般原則であって、売買代金が安いから売らないというのは当然である。あるいは極端に言えば、買い手の人柄品性が気に入らないから売らない、というのも自由である。売り手には、そもそも売る義務など、法律上、存在しないからである。
「第7章 映画業界」
映画が製作され、監督、脚本家、俳優などにギャラなどが払われるが、二次的利用(ビデオ化、テレビ放送、有線放送、航空機・ホテルなどの施設での放映、インターネット配信、海外ライセンス、商品化)に対して、俳優などの実演家には二次的利用の対価が払われないのは当然だと著者は考えているようだが、現在では、事情が違うようである。
例えば、実演家には、公衆送信権(例えばインターネット配信)・放送権・有線放送権があるから、その際には、当然、報酬請求できる。少なくとも俳優協会に加入している主な俳優について、二次利用について全くの無報酬ということは、現在ではないようである。
また、アメリカでは、俳優や歌手・録音技師などのユニオン(職業別組合)の力が強い国では、日本などより、昔から、権利意識が非常に強かったとされている。
商品化事業には、多様なものがあるが、肖像・似顔絵を無断で使われた場合には、実演家は、肖像権・パブリシティ権に基づいて、差止請求や損害賠償請求ができる。
「第8章 レコード音楽業界」
レコード会社は、タレント所属事務所に印税・出演料などを支払うが、所属事務所は何かと理由をつけてタレント本人に支払いをしようとしないし、タレントを長時間働かせるという構造になっているようにみえる。
そして、著者は、上記の構造について、何ら疑問も感じていないようである。
しかし、リスクマネーを投じるプロデューサーだからこそ、リターンを得るという著者独自の持論は、この個所では何も役に立っていないし、矛盾を感じる。
また、本書によれば、通常の意味でのプロデューサーまたはマネージメントという側面でも、所属事務所は、マネージャー・付き人をつける、運転手付きの自動車で送迎する、ヘアメイクをするといった程度であるという。
所属事務所の仕事で一番大事なのは、仕事を獲得する、スケジュールを含めて管理をするという気がするのだが、なぜか本書では、その点について、突っ込んだ検討はされていない。
「第9章 出版業界」
著者は、例えば、ある雑誌の連載漫画については、当該出版社は独占的出版権があるかのような記述をされている。
しかし、これは疑問である。出版権設定契約・利用許諾契約をしていない限り、出版社が独占権うんぬんする方法は、著作権法にはないからである。
業界慣行として、ある雑誌連載漫画を他の雑誌が掲載することが事実上ほとんどないのは、法律的な意味はなく、いわば「礼儀」としての意味合いでしかないと解される。
なお、上記のような、ある雑誌連載漫画を他の雑誌が掲載する実例は、我が国でも過去にもあった。漫画家が希望しても雑誌が掲載してくれない場合には、そのように対処するしか方法がないからである。
「第10章 ゲーム業界」
「職務著作のゲームについて、ゲームがヒットした場合、従業員に対する追加の印税が払われることがある」旨の記述がある。
しかし、職務著作の場合、著作権は使用者にあるので、従業員に対する追加報酬の支払いの法的性質は、名目はどうあれ、成果主義的な賞与やインセンティブ、対価の後払いであろうと解される。
実際のゲーム製作会社の従業員でも、ヒット作品のゲーム製作担当者と、そうではないゲーム製作担当者とでは、年収に大きく開きが出る場合があるようである。
「第12章 ライブパフォーマンス業界」
音楽、演劇について、論じている。
「第13章 テレビ業界」
著者は、テレビ番組の二次利用については、無理に拡大させなくともよいとする。
アニメと特撮番組については、近時、二次利用の需要が拡大している。
しかし、多額の費用を投下した新規の映画が興行的に失敗する場合があるのに対して、例えば、昔、高視聴率を取ったテレビ番組のビデオ化・公衆送信権・放送・有線放送などの二次利用は魅力的ではないだろうか。
「第14章 モバイルコンテンツ業界」
著者は、「作家や音楽クリエイターを育ててきた出版社やレコード会社の機能を、アップルやグーグル、携帯電話会社が担うのか」という問題提起している。
音楽業界については、確かに、アーティストを売れるように育てるという側面もあるかもしれない。
しかし、現在の出版業界では、素人をプロの作家や漫画家に育てるというシステムは存在しないと思われる。