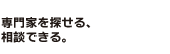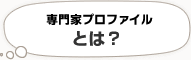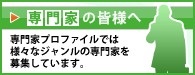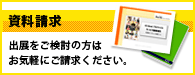- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
Blog201403、独占禁止法(最高裁判決)
・独禁法違反による課徴金の算定の対象となる「売上額」(最判平成17年9月13日、 日本機械保険カルテル課徴金事件)
・最判平成10年12月18日、資生堂東京販売(富士喜本店)事件(民集52巻9号1866頁、判例タイムズ992号94頁、地位確認等請求事件)
・最判平成10年12月18日、花王化粧品販売(江川企画)事件(裁判集民事190号1017頁、判例タイムズ992号98頁)
・独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例(最判平成22年12月17日・民集64巻8号2067頁 、審決取消請求事件)
独禁法違反による課徴金の算定の対象となる「売上額」
最判平成17年9月13日、 日本機械保険カルテル課徴金事件
民集59巻7号1950頁、審決取消請求事件
【判示事項】
1 独禁法7条の2第1項所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき独禁法8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」
【判決要旨】
1 独禁法7条の2第1項所定の「売上額」は,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値をいう。
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者である損害保険会社について,独禁法8条の3において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」は,損害保険会社が損害保険の引受けの対価として保険契約者から収受した保険料の合計額である。
【参照条文】 独禁法7条の2第1項、独禁法(平9法87号改正前)8条1項、独禁法8条の3
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)8条の3において準用する独禁法7条の2の規定によると,独禁法2条2項にいう事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限し,それが商品又は役務の対価に係るものであるときは,公正取引委員会は,事業者団体の構成事業者に対し,実行期間における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した「売上額」に100分の6を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないとされている。
本件は,損害保険会社の事業者団体が独禁法(平成9年法律第87号による改正前のもの)8条1項1号の規定に違反する営業保険料率に関するカルテル行為をしたとして,Y(公正取引委員会,被告・上告人)が同事業者団体の構成事業者である損害保険会社であるX(原告・被上告人)らに対して課徴金の納付を命じた本件審決について,XらがYに対し,本件審決のうちXら主張の金額を超えて課徴金の納付を命ずる部分の取消しを請求した事案である。
2 本件の事実関係等
(1)機械保険事業の免許を受けた者を会員とし,独禁法2条2項にいう事業者団体に該当する日本機械保険連盟は,平成5年3月7日から同8年3月6日までの間において,会員の損害保険会社が機械保険及び組立保険の引受けをする際の保険料率を同連盟が決める一定の保険料率によることとさせた。
Yは,連盟の上記行為が,機械保険等の引受けの取引分野における競争を実質的に制限し,独禁法(平成9年法律第87号による改正前のもの)8条1項1号の規定に違反する営業保険料率に関するカルテル行為であるとして,連盟の会員であるXらに対し,平成12年6月2日付けで総額54億4976万円の課徴金の納付を命ずる本件審決をした。
(2)本件審決は,機械保険等の引受けという役務の対価は損害保険会社が保険契約者から収受する営業保険料の全額であるとして,Xらが本件実行期間中に収受した保険料を合計した額を「売上額」とし,これに所定の割合を乗じて得た額の課徴金の納付を命じたものである。
(3)これに対し,Xらは,「売上額」とは,Xらが本件実行期間中に収受した営業保険料の合計額から,将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分(純保険料)の額又は実際に保険金の支払に充てられた部分の額等を控除した残額であると主張して,本件審決の一部取消しを請求した。
3 原審は,損害保険会社の役務に対する対価は損害保険会社が保険契約者から収受する保険料から支払保険金の額を控除した部分であると判断して,本件審決の一部を取り消した。原判決が取り消した部分に係る課徴金の総額は,21億4366万円であった。
4 原判決の理由の要旨は,次のとおりである。
損害保険会社は,多数の保険契約者から保険料(営業保険料)を収受し,その一部で基金を形成した上,被保険者の中で実際に事故に遭遇した者が現れた場合には,保険契約に基づき,同被保険者に対し同基金から保険金を支払うのであって,この保険金の支払も機械保険等の引受けという役務の一部を成しているのであるから,営業保険料のうち保険金の支払に充てられた部分は,経済的には保険団体内部での資金の移動とみるべきものである。したがって,営業保険料のうち保険金の支払に充てられた部分は,基金に留保され,保険団体内部での資金移動に供せられるだけのものであるから,前記役務に対する経済的な反対給付,すなわち対価とみることはできず,損害保険会社の役務に対する対価は,営業保険料から支払保険金の額を控除した部分である。
5 これに対し,本判決は,次のとおり判示して,原判決中のY敗訴部分を破棄し,Xらの請求をいずれも棄却した。
「独禁法7条の2所定の売上額の意義については,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値を意味すると解釈されるべきものであり,損害保険業においては,保険契約者に対して提供される役務すなわち損害保険の引受けの対価である営業保険料の合計額が,独禁法8条の3において準用する同法7条の2の規定にいう売上額であると解するのが相当である。」
6 課徴金制度と課徴金の額の定め方
(1)課徴金制度は,昭和52年の独禁法改正で新設されたものである。カルテルに対する制裁措置としては刑事罰の定めがあるが(独禁法89条),刑事罰の発動には立証の困難などの障害があり,カルテルによる経済利得のすべてを罰金として徴収することには法体系上の困難があり,カルテルによる損害を回復するための制度である損害賠償制度(独禁法25条)の実効性にも限界がある。そこで,カルテルによる不当な利得を徴収する制度を新たに設け,行政上の措置として機動的に発動できるようにしたのが課徴金の制度である。
(2)このように,課徴金の制度は,カルテルによる不当な利得を徴収する制度であるが,カルテルの抑止のための制度として刑事罰と損害賠償制度に加えて設けられたものであり,課徴金の額が民事上の不当利得返還請求又は損害賠償請求の対象となるべき不当利得額又は損害額と一致させられるべきものとはされておらず,画一的に算定することとされている。
(3)賦課されるべき課徴金の額の定め方について,独禁法7条の2は,カルテル行為の実行期間における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に所定の比率を乗じて得た額に相当する額としている。
そして,これを受けて,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下「独禁法施行令」という。)5条及び6条は,実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法によることとし,この合計額から控除すべきものを定めているが,この施行令の定めは,カルテルの実行期間における総売上額から,値引き,返品及びリベート(割戻し)を控除して,対象商品又は役務の純売上額を算定することとしている。
また,課徴金の額を定めるに当たって売上額に乗ずる比率については,課徴金制度に係る独禁法の規定の立法及び改正の過程において,売上高を分母とし,経常利益ないし営業利益を分子とする比率を参考にして,業種ごとに定める一定率とされている。この分母とされた売上高とは,企業会計上の概念であり,会計処理上,個別の取引による実現収益として,事業者が取引の相手方から契約に基づいて受け取る対価である代金ないし報酬の合計から費用項目を差し引く前の数値である(企業会計原則損益計算書原則―B)。
(4)以上のような法令の定めをみると,独禁法7条の2の規定にいう「売上額」の意義については,一般に公正妥当と認められる企業会計原則上の考え方に準拠して,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値を意味すると解されるべきものと考えられる。判決要旨1は,この趣旨をいうものである。
7 次に,損害保険会社についてみると,原判決と本判決の結論の相違は,機械保険等の引受けという役務のとらえ方の相違に基づくものである。
本判決は,機械保険等の引受けを,保険事故が発生したときに保険金を支払うという危険(リスク)の引受けととらえ,営業保険料はそのような危険引受けという役務に対する対価であるとするものである。
これに対し,原判決は,保険制度が団体的共同備蓄の制度であることを強調し,損害保険会社の提供する役務の実態は,多数の保険契約者と保険契約を締結し,営業保険料を集めてその一部から共同的備蓄たる基金を形成し,これを適切に運営・管理し,保険事故が発生した場合にはいつでも保険金を支払える体制を整え,実際に保険事故が発生した場合は基金から保険金を支払うことであるとする。この立場からすると,営業保険料は共同的備蓄を形成するための単なる手段にすぎず,機械保険等の引受けという役務は,共同的備蓄として集められた基金を加入者間で移動する際の仲介業務ととらえられる。
しかしながら,保険制度に原判決のいうような危険団体的性格があるとしても,それは保険制度の本来的性格を説明するものにすぎない(岸井大太郎「保険事業者団体による保険料率の決定と保険事業者に対する課徴金の算定「機械保険連盟事件刊別冊ジュリ161号87頁,和田健夫「損害保険会社に対する課徴金納付命令審決取消訴訟第一審判決」判評562号12頁(16頁))。
損害保険会社は,自己の責任と判断で保険料率を計算し,そこから引き出される営業保険料と保障される損害の内容を定め,それを一つの商品として顧客に提供することによって市場での競争が成り立っている。
また,損害保険が果たす機能は,実際に事故が生じ損害が発生したときに,損害の填補をなすだけでなく,事故が生ずる以前においても,被保険者の経済的生活の不安を軽減することにあり,この保険者の危険負担こそ,損害保険の本来的給付にほかならない(和田・前掲15頁)。損害が生じることなく保険期間が満了しても,保険者が危険を負担した限り,保険料を返還する必要がないのはそのためであると解されている。営業保険料はそのような危険引受けに対する対価と考えられる。
さらに,集められた営業保険料は,大量に蓄積されたまま保険金支払まで企業内部に留保されているわけではない。それらの資金は,利殖を目的として,産業資金として,あるいは財政資金として融資される。このような投資運用から得られる利益が損害保険会社の利潤の源泉となる。その意味では,支払保険金は,損害保険会社にとっては,保険事業を運営するための費用としての性格を持つと考えられる。
そうすると,費用を差し引く前の売上額を基準として算定すべき課徴金について,支払保険金を差し引いて計算することは認められないということになる。
本判決は,このような考え方に基づき,保険者の危険引受給付と保険契約者の営業保険料給付が経済的に対価関係にあると理解するものである。
8 以上のように,本判決は,独禁法7条の2の規定にいう売上額の意義等について,最高裁判所が初めて判断を示したものであり,公正取引委員会が独禁法に基づいて命ずる課徴金の制度の在り方自体に大きな影響を及ぼすものであって,理論的にも実務的にも重要な意義を有する。
最判平成10年12月18日、資生堂東京販売(富士喜本店)事件
民集52巻9号1866頁、判例タイムズ992号94頁
地位確認等請求事件
【判示事項】
一 卸売業者等が小売業者に対して販売方法に関する制限を課することと昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約により対面販売を義務付けることが昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付き取引に当たらないとされた事例
【判決要旨】
一 卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりに合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引に当たらない。
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約により対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(ブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、右卸売業者が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなど判示の事実関係の下においては、昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引に当たらない。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項、19条
不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)13項
一 本件判決は、資生堂東京販売事件の最高裁判決であり、花王化粧品販売事件の最高裁判決と同日に、第3小法廷によって言い渡されたものである。
本件の事案は次のとおりである。
本件の原告は化粧品の小売業者、被告は資生堂化粧品の卸売販売を行っている会社であり、両者は特約店契約を締結して取引を継続していた。
特約店契約には、特約店は販売に当たり、対面販売、すなわち顧客に対して化粧品の使用方法などを説明したり、相談に応ずることが義務付けられていた。
ところが、原告が対面販売の約定に反して、職域販売と称する一種のカタログ販売を始め、被告の是正の勧告にも従わなかったことから、被告は、特約店契約に定められた解約条項(当事者は、予告期間を置いて特約店契約を解約できるとの条項)に基づき特約店契約を解約した。
そこで、原告が、解約は権利濫用・信義則違反に当たるとして、その効力を争い、被告に対して、契約上の地位を有することの確認と化粧品の引渡を求めたのが本件訴訟である。
一審判決(東京地判平5・9・27判例タイムズ833号223頁)は、(1)本件のような継続的供給契約は、当事者の一方の意思により解約ができる定めがあっても、やむを得ない事由がない限り一方的解約は許されない、(2)対面販売等の約定は、合理的な理由なく販売方法を制限し、価格維持を図るものであり、独禁法の法意にもとる可能性も大いに存するので、右約定に従わないことを理由とする解約は許されない、として原告の請求を一部認容した。
原判決(東京高判平6・9・14判例タイムズ877号201頁)は、一審判決と同様に、(1)継続的供給契約における解約権の行使は、取引関係を継続し難いような不信行為の存在等やむを得ない事由が必要であるとの前提に立ちつつ、(2)メーカー等が小売業者との間で、商品の説明販売を指示するなどの販売方法に関する約定をすることは、商品の適切な販売のためにそれなりに合理的な理由が認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の条件が課せられている場合には、それが強行法規に反するようなものでない限り当然許されると解すべきであり、対面販売にはそれなりの合理性があるから、対面販売の約定の不履行は債務不履行に当たり、本件における原告の不履行は軽微ではなく、継続的供給契約上の信頼関係を著しく破壊するから、解約にはやむを得ない事由があると判断し、(3)信義則違反・権利濫用の主張については、〈1〉被告が対面販売を手段として小売店の販売価格を制限しているとまでは認め難いから、対面販売が独禁法の趣旨に反するとはいえないし、〈2〉本件解約が、原告の値引販売を原因とするものと認めるに足りる証拠もないとして、右主張を退け、原告の請求を棄却したのである。
そこで、原告は、〈1〉対面販売の約定及び〈2〉本件解約は、独禁法19条が禁ずる不公正な取引方法(改正後の独禁法2条9項4号)に定める「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること」のうち、公正取引委員会告示である一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法))13項に定める「拘束条件付取引」ないし一般指定12項に定める「再販売価格の拘束」に該当し、これを認めなかった原判決の判断には法令解釈の誤りがある等と主張して上告した。
二 本件判決は、(一)相手方の事業活動を拘束する条件を付けた取引は、それが公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合に、初めて相手方の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取引に当たるものというべきであり、メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきであることにかんがみると、「卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、一般指定13項に定める拘束条件付取引に当たらない。」との判断を示し、(二)本件の場合、化粧品販売の特約店契約により対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(ブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、被告が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなどの事実関係の下においては、一般指定13項に定める拘束条件付取引に当たらない、と判断したのである。
三 本判決が示した(一)の判断は、相手方の事業活動を拘束する条件を付けた取引が不公正な取引方法に該当する場合につき、オーソドツクスな理解に立った上で、対面販売の義務付けなどの販売方法に関する制限については、(1)それなりの合理的な理由及び(2)他の取引先に対する同等の適用という2要件によって、公正競争阻害性を判断すべきことを示したものである。
(1)の要件は、メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきであるとの基本的な認識に基づくものであり、(2)の要件は、販売方法の制限の恣意性を排除することを考慮したものと思われる。
右のような考え方は、すでに公正取引委員会が、平成3年7月に発表した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(ガイドライン。 NBL478号12頁以下)において示されていたところである。
そして、対面販売に合理性があるかどうかについては、一審判決と原判決とで判断が分かれ、学説上も盛んに論じられていたところであるが、本判決は、対面販売の約定にはそれなりの合理的な理由があると判断した。
従来の議論が、ともすれば対面販売が肌荒れの防止に役立つかどうかという点に傾きがちであったのに対し、本件判決は、ブランドイメージの保持という化粧品市場における競争の特性を重視して、合理性を肯定したところに特色がある。
判決要旨には取り上げられていないが、本判決が、(一)販売方法の制限を手段として、再販売価格の拘束を行っていると認められる場合には、独禁法上問題となり得るとの前提に立ち、(二)販売方法に関する制限を課した場合、販売経費の増大を招くことなどから多かれ少なかれ小売価格が安定する効果が生ずるが、そのような効果が生ずるというだけで、直ちに販売価格の自由な決定を拘束しているということはできないとの認識を示して、本件の場合に価格拘束の事実は認められないとした原審の事実認定を是認した点も注目されよう。
本件の一審判決及び花王事件の一審判決が、価格維持の効果を有する行為は直ちに再販売価格の拘束に該当するかのような、いささか短絡的な判断をしていた点に対しては批判が寄せられていた(川越憲治・NBL533号16頁、田村治朗・ジュリ1069号142頁、村上政博・NBL577号12頁など)。
本判決の右判断は右批判に沿うものといえよう。
また、本判決は、本件解約が原告の値引販売を理由とするものではないとした原判決の事実認定を是認している。
解約の真の目的が何かを判断するには、他の業者に対する対応や販売方法の制限の合理性の有無等の事情を考慮する必要があるが(実方謙二・独占禁止法〔第3版〕274頁)、この点は事実認定の問題である。
四 本判決は、花王化粧品販売事件とともに、学説においては一審判決、原判決に対する評価が分かれ、マスコミはむしろ両事件の一審判決を化粧品の値下げの実現に資するものとして肯定的に評価するなど、最高裁の判断が待たれていた事件において、最高裁が、対面販売の約定が不公正な取引方法に該当するかどうかについて初めての判断を示した判決であり、実務上重要な意義を有する。
なお、継続的供給契約を解約条項に基づき解約するための要件につき本判決は特に判断を示していない。
最判平成10年12月18日、花王化粧品販売(江川企画)事件
裁判集民事190号1017頁、判例タイムズ992号98頁
地位確認等請求本訴、契約上の地位不存在確認請求反訴事件
【判決要旨】 卸売業者が小売業者に対してカウンセリング販売を義務付ける特約店契約中の約定が独占禁止法19条に違反しない場合には、右小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することも、同条に違反しない。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項、19条
不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)12項、13項
一 本判決は、花王化粧品販売事件の最高裁判決であり、資生堂東京販売事件とほぼ同一の論点について争われ、同判決と同日に、第3小法廷によって言い渡されたものである。
本件の事案は次のとおりである。
本件の原告は化粧品の小売業者、被告は花王化粧品の卸売販売を行っている会社であり、両者は特約店契約を締結して取引を継続していた。
特約店契約には、特約店は販売に当たり、カウンセリング販売、すなわち顧客に対して化粧品の使用方法などを説明したり、化粧品について顧客からの相談に応じたりして、これを積極的に推奨販売することが義務付けられていた。
ところが、原告は、被告との取引開始後、被告から仕入れた化粧品の大部分を、資生堂事件の原告である富士喜本店(富士喜本店は、本件の被告とは特約店契約を締結していない)に卸売販売するようになった。
被告は、原告との取引高が他の特約店と比較して著しく多額になったことから、原告が商品を特約店以外に卸売販売(仲間取引)しているのではないかと疑い、販売方法を確認しようとしたが、原告は事実関係を明らかにしなかった。
被告は、原告がカウンセリング販売の義務に違反するとともに、カウンセリング販売の約定に伴う卸売販売禁止の約定にも反しているとして、特約店契約に定められた解約条項(当事者は、予告期間を置いて特約店契約を解約できるとの条項)に基づき特約店契約を解約した。
そこで、原告が、解約は権利濫用・信義則違反・公序良俗違反に当たるとしてその効力を争い、被告に対して、契約上の地位を有することの確認と化粧品の引渡を求めたのが本件訴訟である。なお、被告は、原審において原告は契約上の地位にないことの確認を求める反訴を提起した。
一審判決(東京地判平6・7・18判例タイムズ961号103頁)は、(1)本件解約条項に基づき本件特約店契約を解約するには、やむを得ない事由は必要ではない、(2)被告による解約は、再販売価格を維持する目的でされたものであり、独禁法上到底許されないものである、カウンセリング販売の義務付けは、採算面から値下げ販売を断念させようとする意図がないわけでもなく、独禁法にいう不公正な取引方法に該当しかねないなどの理由から、本件解約は権利濫用に該当するとして、原告の請求を一部認容した。
原判決(東京高判平9・7・31判例タイムズ855号111頁)も、本件解約条項に基づく解約は、信義則違反等の一般条項による制約がない限り、やむを得ない事由がなくとも許されるとの前提に立って、信義則違反・権利濫用・公序良俗違反の該当性を検討し、(1)被告による解約は、原告による契約違反を原因とするもので、原告の値引販売を止めさせるためにされたものとは認められない、(2)カウンセリング販売の約定は、一応の合理性があることなどからすると、一般指定13項にいう「拘束条件付取引」に該当しないし、販売方法に関する制限を手段として再販売価格の制限を行っていると認めることもできない、(3)卸売販売の禁止の約定も、それが独禁法に反しないカウンセリング販売という販売方法の実効性を担保する以上のものでないことから、独禁法に反しない、(4)原告の特約店契約違反の態様等からすれば両者の信頼関係は破壊されている、といった理由から、原告の主張を退け、本件解約を有効と認め、原告の請求を棄却し、被告の反訴請求を認容したのである。
そこで、原告は、カウンセリング販売、卸売禁止の約定及び本件解約は、独禁法19条が禁ずる不公正な取引方法、現行法では改正後の独禁法2条9項4号に定める「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること」のうち、一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法))13項に定める「拘束条件付取引」ないし一般指定12項に定める「再販売価格の拘束」に該当し、これを認めなかった原判決の判断には法令解釈の誤りがある等と主張して上告した。
二 本件判決は、カウンセリング販売の約定が、一般指定12項及び13項に該当しないとの判断については、資生堂東京販売事件の判断と同様の判断を示すとともに、卸売販売の禁止の約定について、被告と特約店契約を締結しておらずカウンセリング販売の義務を負わない小売店等に商品が売却されてしまうと、特約店契約を締結して販売方法を制限し、花王化粧品に対する顧客の信頼(ブランドイメージ)を保持しようとした本件特約店契約の目的を達することができなくなるから、被告と特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売の禁止は、カウンセリング販売の義務に必然的に伴う義務というべきであるとの理由から、カウンセリング販売を義務付けた約定が独禁法19条に違反しない場合には、卸売販売の禁止も、同条に反しないとの判断を示した。
三 卸売販売の禁止は、取引先の選択の自由の一形態であり、原則として事業者の自由に委ねられてはいるものの、独禁法上違法な行為の実効を確保する手段として用いられる場合には独禁法上問題となり得ると解されている。
ところで、公正取引委員会が平成3年7月に公表した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(ガイドラインは、メーカーが流通業者に対して、商品の横流しをしないよう指示すること(仲間取引の禁止)は、「安売りを行っている流通業者に対して自己の商品が販売されないようにするために行われる場合など、これによって当該商品の価格が維持されるおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当する」と定めており、右ガイドラインの規定を文字通りに読めば、あたかも、横流しの禁止をする目的の如何を問わず、横流しの禁止により客観的に価格維持の効果が生ずるおそれがある場合には、ひろく不公正な取引方法に当たると解する余地がある。
そして、そのような解釈を前提に、本件の場合にも、卸売販売の禁止によって価格維持の効果が生ずるおそれがあることを理由として、不公正な取引方法に当たるとの主張をする見解も見られた。
しかし、ガイドラインの右規定に対しては、禁止行為の基準として明確でないとの批判があり、たとえば、訪問販売、対面販売、店頭販売を義務付ける場合には、安売業者への横流し禁止は、これらの販売方法の義務付けに必然的に伴うものであるから、右販売方法が独禁法上問題にならない場合には、この点の判断が優先し、取引先の制限も許されるべきであるとの主張がされていた(村上政博『独占禁止法(第4版)』340頁など)。
また、公正取引委員会も、特約店契約によって販売方法に関する義務(例えば対面販売義務)を負う小売業者以外の者に品物を転売することを制限することは、右販売方法の制限が独禁法上問題となるものでなければ、これも独禁法上問題とならないとの解釈を採っているようである(公取委事務局・不公正な取引方法に関する相談事例集〔平成7年10月〕9頁)。
本件判決は、このような見解と同様に、本件において特約店契約によって卸売販売を禁ずることは、独禁法に反しないと判断したものと思われる。
なお、特約店契約を締結し、カウンセリング販売の義務を負っている他の小売店に対する転売さえも禁ずるような卸売販売・仲間取引の禁止は、販売方法の制限の実効性を確保するために必要なものとはいえないので、これによって価格が維持されるおそれがある場合には独禁法上問題となろう。
四 なお、継続的供給契約を解約条項(一定の猶予期間をおいて当事者のどちらからでも解約できるとの条項)に基づき解約することは、信義則違反等の一般条項による制限を除いて自由にすることができるのか、それとも解約には「やむを得ない事由」が必要なのかという問題について、資生堂事件の原判決と本件の原判決は判断を異にしている。
この問題については、上告理由にもされていないために、最高裁は全く触れていないが、仮に、本件で「やむを得ない事由」が必要との見解に立つのならば、最高裁が原判決の結論を維持する場合にも何らかの説示をすることが必要であったものと解される。 そうすると、最高裁は、両事件の事案の下において当該解約条項に基づき解約をするには「やむを得ない事由」は不要との前提で判断を行っているものと一応推測できそうである。
五 本件は、資生堂東京販売事件とともに、学説において一審判決、原判決に対する評価が分かれ、マスコミも注目していた事件において、最高裁が明確な判断を示した実務上重要な判例である。
独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
最判平成22年12月17日・民集64巻8号2067頁 、審決取消請求事件
【判示事項】 自ら設置した加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを加入者に提供している第一種電気通信事業者が,他の電気通信事業者に対して上記設備を接続させて利用させる法令上の義務を負っていた場合において,自ら提供する上記サービスの加入者から利用の対価として徴収するユーザー料金の届出に当たっては,光ファイバ1芯を複数の加入者で共用する安価な方式を用いることを前提としながら,実際の加入者への上記サービスの提供に際しては光ファイバ1芯を1人の加入者で専用する高価な方式を用いる一方で,その方式による上記設備への接続の対価として他の電気通信事業者から取得すべき接続料金については自らのユーザー料金を上回る金額の認可を受けてこれを提示し,自らのユーザー料金が当該接続料金を下回るようになるものとした行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
【判決要旨】 自ら設置した加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを加入者に提供している第一種電気通信事業者が、他の電気通信事業者に対して上記設備を接続させて利用させる法令上の義務を負っていた場合において、自ら提供する上記サービスの加入者から利用の対価として徴収するユーザー料金の届出にあたっては、光ファイバ1芯を複数の加入者で共用する安価な方式を用いることを前提としながら、実際の加入者への上記サービスの提供に際しては光ファイバ1芯を1人の加入者で専用する高価な方式を用いる一方で、その方式による上記設備への接続の対価として他の電気通信事業者から取得すべき接続料金については自らのユーザー料金を上回る金額の認可を受けてこれを提示し、自らのユーザー料金が当該接続料金を下回るようになるものとした行為は、次の(1)~(5)など判示の事情のもとにおいては、独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当する。
(1)当時東日本地区において既存の加入者光ファイバ設備に接続して上記サービスを提供しようとする電気通信事業者にとって、その接続対象は、上記第一種電気通信事業者に事実上限られていた。
(2)上記サービスは、主として事業の規模によって効率が高まり、かつ、加入者との間でいったん契約を締結すれば競業者への契約変更が生じ難いという特性を有していた。
(3)上記第一種電気通信事業者は、自らの加入者への上記サービスの提供において安価な方式を用いることを前提としてその接続料金の認可を受けることなどにより、上記第一種電気通信事業者のユーザー料金が接続料金を下回るという逆ざやの発生を防止するために行われていた行政指導を始めとする種々の行政的規制を実質的に免れていた。
(4)上記第一種電気通信事業者は、上記サービスの市場において他の電気通信事業者よりも先行していた上、その設置した加入者光ファイバ設備を自ら使用するとともに、未使用の光ファイバの所在等に関する情報も事実上独占していた。
(5)上記サービスの市場が当時急速に拡大しつつある中で、上記第一種電気通信事業者の当該行為の継続期間は1年10カ月にわたった。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)2条5項
電気通信事業法(平成15年法律第125号による改正前のもの)38条
電気通信事業法32条
1 本件は,電気通信事業者であるXが,光ファイバ設備を用いた戸建て住宅向けの通信サービス(以下「FTTHサービス」という。)の提供に際し,平成14年6月から同16年3月までの間(以下「本件行為期間」という。),自前の光ファイバ設備を保有せずに他社の設備を利用して電気通信事業を行う電気通信事業者(以下単に「競争事業者」という。)がFTTHサービス提供のためにXの光ファイバ設備に接続する際にXに支払うベき料金(以下「接続料金」という。法文上の用語は「接続料」であるが,本判決は原判決及び審決の用語例に従ったものと思われる。)を下回る金額で,Xが自己のFTTHサービスの利用者に対する料金(以下「ユーザー料金」という。)を設定したことが,独禁法2条5項にいう私的独占に該当し,同法3条の規定に違反するとの審決をY(公正取引委員会)から受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 事実関係については,判文に詳細に記載されているとおりであるが,Xは,自ら加入者光ファイバ設備を保有し,これを利用して加入者にFTTHサービスを提供しつつ,電気通信事業法により,競争事業者からXの加入者光ファイバ設備に接続させるよう請求を受けた場合には,総務大臣の認可を受けた接続条件でこれに応ずる義務を負っていた(要するに,FTTHサービス市場において小売をしつつ,競合する他の小売店に対しても求められれば卸売をしなければならなかったのであり,しかも,その卸売料金についても光ファイバ設備の構築費用や管理費用に基づいて総務省令に基づいて計算された額を超えてはならない旨の規制を受けていた。)。さらに,FTTHサービス市場における競争を促進するため,総務省は,Xのユーザー料金すなわち小売料金が,競争事業者がその加入者光ファイバ設備を使用する際にXに支払うべき接続料金すなわち卸売料金を下回ってはならない(逆ざやが生じてはならない)という行政指導をも行っていた。このため,Xは,数兆円規模の先行投資で構築した世界でも屈指の光ファイバ網を有しながら,むざむざ競争事業者にこのインフラへのただ乗りを許した上,現存する中で最も高速かつ大容量のブロードバンドサービスであり,動画配信やテレビ電話等の増加によって今後の飛躍的な発展が期待し得るFTTHサービス市場において,そのシェアを競争事業者に奪われるという可能性に直面し,強い危機感を有していた。しかも,FTTHサービス市場には,他にもXほどの規模ではないが自前の加入者光ファイバ設備を有する有力企業が既に複数参入しており,ユーザー料金で比較する限りはXにも十分に対抗し得る力を有していた。もっとも,加入者光ファイバ設備を有する企業の中で,他社にこれを貸し出す余力があったのはXのみであった。
3 このような状況下において,Xは,まず接続料金について,1芯の光ファイバを最大32人の加入者が共用する分岐方式という方式を用いることを前提に認可を得た(分岐方式は,1芯を共用する複数の加入者が同時に利用した場合には通信速度が低下する可能性があったが,加入者の人数が増加するごとに加入者1人当たりの接続料金は逓減する計算となっていた。)。次いで,Xは,この分岐方式を前提とした「ニューファミリータイプ」というFTTHサービスの提供を開始し,そのユーザー料金を月5800円と設定して総務大臣への届出を行った。この5800円という料金は,分岐方式において1芯を約19人で共用した場合における加入者1人当たりの接続料金等約4906円に営業費を上乗せした価格であって,ユーザー料金と接続料金との間の逆ざやを禁じた行政指導にも反するものではないと説明されていた。しかしながら,Xは,実際には1芯の光ファイバを1人の加入者に専用させる芯線直結方式という方式でニューファミリータイプのFTTHサービスを提供していた。本来,この方式における接続料金は月6328円であったから,Xの設定したユーザー料金はこれより安いことになり,競争事業者はXの加入者光ファイバ設備に接続してニューファミリータイプと品質面で互角となるFTTHサービスをいかに効率的に提供しようとしても,赤字を覚悟しない限り価格の上でXに対抗できないこととなった。また,競争事業者にとって,供給余力のないX以外の企業から加入者光ファイバ設備を賃借することもできず,自前の加入者光ファイバ設備を構築することも現実的ではなかった。こうした状況下で,競争事業者はFTTHサービス市場への参入が事実上不可能となった。他方,Xにとっては,たとえユーザー料金が低くても既に投下済みの資本の回収は進むことになる(光ファイバそれ自体は,銅線をはるかに上回る耐久性を有する。)上,FTTHサービス市場が未成熟なうちから圧倒的なシェアを握り,加入者宅での工事が必要なため一旦加入者と契約すると事業者の変更が生じにくいというFTTHサービスの特性も活かすことができたものと思われる。総務大臣は,上記のような状況を後に把握するに至ったが,Xに対して行政指導を行うのみで,電気通信事業法上の権限であるユーザー料金の変更命令や接続料金の変更認可申請命令を発出することはなかった。しかしながら,Yは,このようなXの行為が排除型私的独占に当たるとする審決を行い,最高裁第二小法廷も,Xからの上告受理申立てを受理したものの,判決要旨のとおり述べて,上記審決を支持した原判決の結論を是認した。
4 Xの上告理由は,概要,①ニューファミリータイプの実質は分岐方式であるから,そのユーザー料金と接続料金との間には逆ざやは生じていない,②接続料金が原価と等価である以上,Xと競争事業者との間には競争条件の同等性が担保されている,③Xの行為がなくとも競争事業者は他社のユーザー料金に対抗しなければならなかったこと,競争事業者は芯線直結方式によってニューファミリータイプとの間に差別化を図っての参入も可能であったことなどからすれば,Xの行為と競争事業者の不参入との間には因果関係が存在しない,④FTTHサービスのユーザー料金はADSL等他のブロードバンドサービスとの競争にさらされており,競争の実質的制限の状態は存在しなかった,⑤独禁法上,Xには競争事業者に自己の設備を利用させること等によりその参入を困難にしないように配慮する義務を負ってはいない,⑥Xへの認可変更申請命令や料金変更命令を発しなかった総務省の判断を尊重すべきである,などというものであった。このうち,判決要旨に直接関連するのは①及び②である。
5 上告理由①について:平成15年8月末現在のニューファミリータイプの総回線数11万8627回線中,Xが現実に分岐方式によって提供しているのは僅かに6回線にすぎず,しかもその加入者は全てX関係者であった。また,本件行為期間を通じて,FTTHサービスへの需要はなお点在していたにすぎなかったというのであるから,分岐方式を現実に導入したとしても,光ファイバ1芯当たりの加入者の収容比率が6割を超えるという(ニューファミリータイプのユーザー料金届出時にXがその算定根拠として示していた)事態はおよそ想定し難かったものと考えられる。しかも,Xは,ニューファミリータイプについてどのような状況になれば分岐方式の設備を導入するかについての具体的な基準も策定しておらず,将来的に同方式を導入することとなる場合でも,新たに利用する芯線についてのみ分岐方式でサービス提供し,それでも芯線が不足した場合に初めて芯線直結方式で既にサービス提供している回線を分岐方式に移行する予定であったというのである(しかしながら,芯線直結方式でサービスを提供している加入者につき分岐方式に変更するには,加入者が使用しているサービスを一時中断して各加入者宅内で工事を行わなければならないところ,ユーザー料金に変更がない一方で通信品質は落ちることになるのであるから,そのような工事は加入者にとって何らメリットがなく,Xが上記工事ヘの同意を得ることは容易なことではなかったものと考えられるし,仮に分岐方式への切替に同意した加入者にはユーザー料金を引き下げるというのであれば,月5800円という当初提示されていたニューファミリータイプの料金はいずれにせよ実態から乖離していたということになる。)。そうすると,分岐方式による接続料金の認可申請及びユーザー料金の届出は,接続料金がユーザー料金を上回ってはならないという行政指導(インピュテーションルールと呼ばれていた。)に抵触せずにユーザー料金を引き下げるための苦肉の方便にすぎず,少なくとも本件行為期間において,分岐方式は,現実のFTTHサービス提供方法としてはもとより,将来における芯線直結方式からの移行対象としても,その実在性すら疑わしいような状況にあったといわざるを得ない。本判決は,このような認識に立って,上告理由①をその実質において採用の余地のない認定非難にすぎないものとして排斥したのではないかと推察される。
6 上告理由②について:一般に,市場において支配的な地位を占める企業であったとしても,競業者との取引を行う義務はなく,取引の拒絶も通常は合法である。取引先を選択する自由を企業に認めなければ,企業の自主的な経営判断による経済発展は望み得ないし,競争相手との取引を勧めるのは独禁法の理念に反するともいえるからである。特に,投資リスクを負って建設した施設を競争相手に利用させることを独禁法によって義務付けることになれば,新規投資を行うインセンティブを企業から奪うことにもなりかねない。しかしながら,独禁法上も,取引拒絶を違法と評価すべき例外的な状況があることは従来から認識されており,例えば,それによって競争者の取引の機会が減少し,他の代わり得る取引先を容易に見いだすこともできない場合等がこれに当たるものとされてきた(例えば,平成3年に公正取引委員会が公表した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」)。本判決は,電気通信事業法上は原則として接続拒絶(取引拒絶)の自由がないことから,形式的には接続に応じる姿勢を取りつつ,他の電気通信事業者からは到底受け入れ難い接続条件を提示したという場合も,基本的には取引拒絶と同様の基準で独禁法上の違法性の有無を判断すれば足りると解したものと推察される(なお,本件については基本的に略奪的廉売規制の枠組みで捉えるべきであるとする有力な学説〔白石忠志『独禁法事例の勘所〔第2版〕』379頁〕もあり,本判決もその判断枠組みについては両様の考え方があるとする点に配慮しているが,上記学説も,本件においてはいずれの枠組みで検討しても実質的な差異はないとしている。)。
もっとも,Xが強調するように,FTTHサービス市場のように生成途上のネットワーク市場においては,いかに効率的な事業者であっても,需要が立ち上がるまでは参入者に赤字が生ずるのがむしろ常態であるという可能性はあろう。そうであるとすれば,Xの設定したユーザー料金が接続料金を下回るために競争事業者の赤字が必至であるという事実だけから,これが直ちに実質的な取引拒絶に当たると解することには注意が必要である。少なくとも,Xとの競争の同等性が確保されていたと解し得る限り,競争事業者が接続を行わなかったのはその自由な経営判断の結果であると解する余地があることになろう。そうすると,本件における排除行為該当性についての判断は,Xと競争事業者との間において競争の同等性が確保されていたといえるか否かによっても相当程度影響されると考えられる。
そこで検討するに,本件では,Xが加入者光ファイバ設備を先行投資によって現に建設し,保有している事実は軽視できない。Yが審決においては挙げていなかったものの原判決が補充した理由付けである「Xは設備利用部門から設備管理部門に対して計算上接続料金を移転すれば足りるのに対し,競争事業者は現実に接続料金をXに対し出捐する必要がある」という点は,Xと競争事業者との間にある競争上の差異として重大なものと考えられる。加えて,Xだけが未使用の光ファイバの位置情報を事実上独占しており,これらの情報を利用して顧客に対する訪問営業(アウトバウンド)をかけることができたというような点も重要であろう。こうしたことから,本判決は,Xと競争事業者との間に競争条件の同等性があったとは解し難いものとした上,このことも考慮してXの一連の行為が排除行為に該当するとの判断に至ったものと思われる。