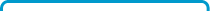約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(4)65歳までの雇用確保義務化(続き)
-
![]()
60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2007-03-20 10:53
■企業が取るべき選択
(結論)
前回お話した、2の(2)継続雇用制度(再雇用制度)が適しています。
1.の定年引上げでは、 人件費の増大になります。一律に定年年齢を引き上げますので、事業主サイドからは、人件費の増大という問題が生じます。また、勤続年数の延長となりますので各従業員の退職金額の増加という問題が生じます。
3.の定年廃止では定年制を廃止することになりますので、労働契約の期間に終わりがなくなることを意味します。従って従業員がある年齢に達したから退職させるということができなくなります。
従業員の定着率は向上できますが、人件費の増大、労働者の固定化で企業活動が停滞する可能性があります。
2.(2)は、従業員の希望に応じて、定年後も引き続き雇用する制度です。その際、定年後の労働条件は、事業主と従業員で協議して取り決めることができます。安定した雇用が確保されることが目的ですので、常用雇用でなく、短時間勤務や隔日勤務なども可能です。企業の実情に合わせて導入ができますので柔軟な対応がとれることが特徴です。
但し、注意するポイントがあります。事前に周到な準備が必要になります。・・・・・
ポイントは次の2点。
(1)労使協定で、対象労働者の選考基準を設定する(会社側と従業員側で、再雇用の対象となる者に該当する基準を作成しておくことでトラブルを避けること。法律では、希望者全員を再雇用することが原則なので、会社経営上からもこの基準作りは重要です)
(2)就業規則の整備
(就業規則に落とし込みをし、従業員に周知させることが大切です)
企業によっては、50歳代の後半期に定年後の雇用についてヒアリングをして、本人の希望を聞くところが多くなりました。雇用を継続するという大前提のもと、セカンドライフの設計の時期であるともいえるでしょう。
 「60歳以降の賃金設計」のコラム
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)