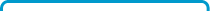約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)
-
![]()
60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2009-08-11 11:56
各種シミュレーションをすることで、各人ごとに最適賃金を設計することが可能になります。
公的給付金を最大限活用することで、賃金が減少しても本人のモチベーションの低下を防ぐことができるわけです。
今回は、連載のまとめの意味で、労働時間(勤務形態)からみた本人の収入タイプ、入社時から定年後再雇用までの賃金カーブなどのお話をさせていただきます。
●勤務形態からみた本人の収入タイプ
連載では、再雇用後は引き続きフルタイムで勤務する前提でお話をして参りましたが、実際には会社と本人とで合意した勤務形態(労働時間)は、様々な形になります。
従来同様のフルタイム勤務、またハーフタイム勤務やパートタイム勤務なども考えられますが、それらを選択した場合、公的給付金との組み合わせがどうなるかなどお話させていただきます。
1.フルタイム勤務
賃金+年金+高年齢雇用継続給付の3本立て
再雇用後も、勤務時間、勤務日数が定年前と同様である場合(概ね一般社員の4分の3以上の場合)は、厚生年金、雇用保険は両者とも引き続き継続加入になります。
従って、本人の収入源はこの3本になります。
在職老齢年金は、賃金額によって減額調整されることは既号で解説のとおりですが、引き続き保険料が天引きされますので、将来再雇用期間が終了し退職した時点で、年金額が再計算されることになりますので退職後の年金額は増加します。
継続加入のメリットといえるでしょう。定年前と同条件で働くことで、自助努力になります。
2.ハーフタイム勤務
賃金+年金 又は 賃金+年金+雇用継続給付
勤務時間、勤務日数が定年前と比較して半分程度(概ね一般社員の4分の3未満まで)
の場合は、厚生年金は加入しなくてよくなりますので保険料の負担はない上、1.のフルタイム勤務では減額調整される在職老齢年金ではなく、60歳以降に給付を受けることができる正規の年金を全額受け取ることができます。
逆に、将来の年金額のことを考えますと、保険料の負担をしませんので、再雇用期間が終了し退職した場合に年金額が増えることはありません。
また1年以上の雇用が見込まれ、週の勤務時間が20時間以上の場合は雇用保険に引き続き継続加入になりますので、雇用保険の雇用継続給付を受けることができます。
3.パートタイム勤務
賃金+年金
勤務時間、勤務日数が定年前と比較して半分未満(週勤務時間が、20時間未満)の場合は、厚生年金、雇用保険とも加入しませんので、収入源は賃金と年金(減額調整はありません)になります。
収入の減少を補うために、年金は60歳から受ける特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に本来65歳から受け取る老齢基礎年金を全部又は一部繰り上げて、併せて受給することもできます。
ただし、これを行うと請求したときの一定の減額率によって決まった年金額となり、65歳になっても年金額が引き上がることはありませんので、注意が必要です。
以上、このように職務内容を決める際に、勤務時間、日数を考慮してみてください。
役割や職務内容からみて1.のフルタイム勤務で、定年前と変わらず同様の職務を遂行する方もあることでしょう。公的給付金を最大限活用することは大事ですが、再雇用者のモチベーション低下にならないよう職務再設計(賃金額決定)をすることが何よりポイントとなります。
●入社時から定年後再雇用までの賃金カーブ
日本の賃金のあり方は、終身決済型の賃金といえます。
今回のテーマである60歳以降の賃金は、法令で求められている高年齢者雇用確保措置によって自社の賃金設計の方針を決める必要がありますが、高齢者の雇用期間が延びるわけですから、自ずと人件費の増大は避けられない問題です。
60歳以降の再雇用者の賃金減少分を、若年齢者の新規採用分にうまくまわしていくのと同時に、役割責任をより明確化し、賃金のピークをより年齢がより若い段階にしていくことも考える必要があるでしょう。
企業にとって、高齢者の処遇を制度化していくと同時に、実力のある若年齢者の貢献度合いに応じた賃金制度は欠かすことができません。
●最後に・・・
今回の連載は、これで最終回となります。
お読みいただきまして有難うございました。
企業は、「ヒト」なりだと思っております。賃金は、労働の対価です。
納得して職務を遂行するのとそうでないのでは、成果が大きく異なりますので、再雇用時の労働条件を決める際には、対象者と職務内容を詳細に話しあって決めてみてください。
会社に貢献できているからこそ賃金支給があるのだという意識をより高めていくことです。
最後に、この連載が皆様の高齢者雇用の賃金設計に少しでもお役に立つことができましたら嬉しく思います。
 「60歳以降の賃金設計」のコラム
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(30)賃金設計シミュレーション(2009/08/08 00:08)