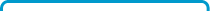真山 英二
サノヤマ エイジ住宅購入の資金その他について
マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/03/02 15:04お世話になります。
夫婦の共有名義で(結婚25年)
毎月払う賃貸料(駐車場含めて)を考えて、この度建売新築住宅2900万円(諸費用別)を購入することになりました。
資金は貯金と両親からの援助を合算した現金決済です。
私は自営業でここ10年継続して赤字申告、今年の申告も赤字です。
妻はパート勤めで90万円くらいの収入があります。
私の出す資金は貯金700万円、国債換金して500万円、計1200万円。
妻の出す資金は貯金900万円、国債換金して500万円、計1400万円。
援助は年金受給者の私の母から100万円(手持ちの現金)、
年金受給者の妻の母から200万円(手持ち現金)です。
私の資金1200万円の内訳は
独身時代の預金約200万円に、
1980年代後半から90年代バブル期に納税出来た期間においてそれなりに残した約500万円で、
当時は預け入れ金利がよく10年定期預金で約1.7倍に増えたため
元金700万円が現在の1200万円に至りました。
妻の資金¥1400万円の内訳は
独身時代の預金約300万円、親からの結婚祝い金100万円、
私の仕事の専従者期間の1980年代後半から90年代バブル期に残した約400万円で
当時は預け入れ金利がよく10年定期預金で約1.7倍に増えたため
元金800万円が現在の1400万円に至りました。
上記のような資金繰りで住宅を購入した場合、登記記載の持ち分はどういった割合になりますか?
私2分の1、妻2分の1の割合で問題ないのでしょうか?
また持ち分の割合に支援分の資金割合も加味しなくてはいけませんか?
両親からの援助を合わせると私方の合計が1300万円、妻方の合計が1600万円で300万円の差があります。
支援も私方よりも妻方のほうが100万円多くもらいます。
購入後の不動産取得に関するの税務署からのお尋ねは、どういったものなのかよく解りませんが、
真っすぐきちんと回答しようと思っていますので
それも含めてた問題点、その他アドバイスをお聞かせ頂ければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
補足
2011/03/02 15:04早速のご回答ありがとうございました。
持ち分の割合に支援分の資金割合も加味しなくてはいけませんか?
両親からの援助を合わせると私方の合計が1300万円、妻方の合計が1600万円で300万円の差があります。
支援も私方よりも妻方のほうが100万円多くもらいます。
C8PARTYさん ( 愛知県 / 男性 / 46歳 )
登記の持ち分について
- ( 5 .0)
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。
原則として、不動産の登記持ち分は、不動産の本体価格に対する
お金の出資の割合に応じて決定し、
登記持ち分の割合とお金の出資割合が異なる場合は、
その差分について贈与税の課税対象となる場合があります。
住宅ローンを使用する場合は、住宅ローン部分について
ローンの債務者が出資した金額であることが明確です。
しかし、現金出資の場合、誰が出資したのかを
厳密に分けることは難しいことがよくあります。
特に、婚姻期間が長い場合は、夫婦の共有財産として貯めた
現金をどちらが出したのか、厳密に区別はできません。
お聞きしている内容においては、夫婦ともに収入があり
かつ婚姻期間も25年と長いため、現実的な対応として、
持ち分を2分の1ずつで登記してもあまり問題にならないと思います。
ただ、今回のご相談の文面より、
まっすぐきちんと対応したいとのことなので、
原則通り、出資金の割合
C8PARTY:奥様 = 13:16
で登記するのが良いと思います。
また、奥様が支援を受ける200万円については、
贈与税の基礎控除110万円を超えているので、
贈与税の課税対象となります。
しかし、今年(2011年)については、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠が
1000万円あるので、その対象となるのであれば、贈与税はかかりません。
ただ、来年の確定申告時期に、非課税枠を使用した旨の
贈与税の申告を行う必要があります。
贈与税の特例については、下記のリンクをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
正直なところ、登記の持ち分が、1:1であろうと
13:16であろうと、夫婦で共有している限りは
大きな違いはありません。
ご相談の文面から、とても正直でまっすぐな雰囲気が伝わってきます。
原則通りの持ち分登記が良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
C8PARTY さん
2011/03/03 01:04
細かな回答ありがとうございました。ピンポイントの解説がとくに参考になり理解できました。
事前に留めておくことは理解しておきたいので
また引き続き分からない事がでましたらよろしくお願いいたします。