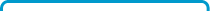相続税 小規模宅地の特例 共有名義、減額の全てを一人が受ける
マネー 税金 2015/12/21 18:40相続税 小規模宅地の特例 共同で相続した場合、減額の全てを一人が受けても良いのでしょうか?
たとえば、適応される宅地が500平米 で
同居の相続人が二名
(配偶者) 持分1/5 : (子) 持分4/5 に分割した場合、
Aパターン
配偶者→100平米→ 0平米を適用、100平米を適用外
子→400平米 →のうち330平米を適用、70平米を適用外
としても良いのでしょうか?
Bパターン
割合で計算しないとダメなんだとすると、330平米を持分比率で1対4した
配偶者→100平米 のうち、66平米を適用、34平米を適用外
子→400平米 のうち、264平米を適用、136平米を適用外
となるのでしょうか?
ここまでの結果はAパターンもBパターンも同じになると思いますが、
配偶者は「配偶者の軽減」で、かなりの金額を軽減できます。
子が小規模宅地の減額の全てを受けると、この後の子の税額が減ると思いますが、それでも良いのでしょうか?
杏冶さん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )
相続税は法定割合で計算した後、各自の相続割合で案分します
- ( 4 .0)
杏冶さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
杏冶さん、相続税のことについてかなり研究されているようです。
ただ、居住用宅を共有で取得されても、小規模宅地の課税の特例を受けようとするときの税額計算は、全体で行うことにご留意ください。
相続税の税額計算は、他の税金と少し違い、実は二段階構造となっていて、分かり辛いかもしれません。よって一般の解説書においては、少し簡素な形で紹介されています。
小規模宅地の特例の適用となる宅地を相続するのはAさん、お一人か、あるいは、A・Bさんが共有であるかの別を問いません。相続人のうち誰かがこの特例を適用するときの条件を満たしていれば、330平方メートルを上限として80%の評価減を行なうことになります。
相続税の計算は、「二段階構造」と申し上げましたが、先ず、課税対象相続財産は、相続財産から評価減できる金額、基礎控除を差し引いて求めます。そのうえで、次のような手順で計算します。
(1)課税相続財産が決まったら、法定相続分割合を乗じて相続人別の課税金額を算出します。
さらにその金額に応じた税率を乗じて各人の税額を算出します。この合計額がとりあえずの全体の相続税額です。第1段階では、あくまで法定相続分での計算です。
(2)第2段階として、具体的に納税する額は、相続人が実際に相続した財産の割合によって案分して各人の税額計算を行います。法定相続人が複数人いたとしてもAさんが1人で相続したのであれば、Aさんが全額を納税することになります。
相続した財産の割合がAさん(配偶者)5分の1、Bさん(子)5分の4であれば、税額もこの割合で納税すりことになります。
この際、配偶者の税額軽減の特例を適用した場合、配偶者の相続財産が1億6,000万円以内か、法定存続分以内であれば、納税する金額はないということになります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
杏冶 さん
2015/12/22 20:56
柴田 博壽様、早速のご回答ありがとうございます。初めての相続にあたり、勉強しながらの申告書作成で、分からない部分をピンポイントで教えていただけるのは本当に助かります。
全体で330平米の特例を受けられるのはわかりました。
減額の対象(配偶者)5分の1、(子)5分の4にしないとダメ、要するに、330平米の割り振りは、私の質問のBパターンにする必要があるということで宜しいでしょうか?
具体的に何のことかというと、相続税の申告書の「第11・11の2表の付表(別紙)」の
「 2、 一の宅地等の取得者ごとの面積及び評価額」に記載する事項の
「2左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等」書き方です。
ここに記載するのは、私の質問のBパターンの様に書かないとダメなのか
それとも、Aでも良いのか悩みました。
なぜなら、「1、持分に応じた宅地等」には、持分×面積、持分×評価額という持分に掛け算する式が載っていますが「2、左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等」の欄には計算式などは書いてないので、こちらで任意で選択しても良い項目なのかと思ったのです。
文章が下手で、質問の書き方がわかりにくく申し訳ありません。