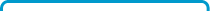松本 仁孝
マツモト ヨシタカ学生納付特例による未納と遺族年金について
マネー 年金・社会保険 2010/11/12 23:59年金の学生納付特例による未納分があることがわかりました。
夫(28)36ヶ月、妻(28)41ヶ月分です。
追納猶予期間が10年ということなので、年齢的にも微妙なところです。
しかも、併せると相当な額になり、現在新居を建設中な為に追納する余裕も
正直ありません。
ここでの過去の質問を拝見してみると、女性の方が将来貰える年金額が少ないという
ことで、妻の分から支払う方がよいとありました。
そこで、遺族年金についてですが、夫が死亡時、学生納付特例による未納分により
受け取る金額は減るのでしょうか?
子どもが2人いるため、もし遺族年金が減るようであれば、妻の方からではなく
夫の方から支払った方がよいのでしょうか?
さらに、夫・妻ともに追納できなかった場合は60歳以降も任意で国民年金に加入するか、65歳まで働き厚生年金を支払うことで、将来貰える年金額は増えるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
tetoさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )
学生納付特例制度と遺族年金の関連などについてですね。
- ( 5 .0)
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
まず、学生納付特例制度の承認を受けておられますので、
その期間は、保険料を滞納している期間にはなりません。
保険料の支払いを猶予されて、先送りにして、
その後、支払えるようになった際に、
追納していく制度であると、お考えいただきたいと思います。
妻であるあなたとお子さん2人が遺族となった場合、
夫が被保険者であることが求められます。
遺族基礎年金についての支給要件の一つである、
お子さんが18歳未満である場合には、
学生納付特例制度によって猶予されていた保険料を、
追納していないという理由で、減額されることはないと考えています。
お子さんについての加算もされると考えます。
夫が会社員である場合には、
下のお子さんが18歳に達する年度末まで、
遺族厚生年金と遺族基礎年金とが併給されることになります。
遺族厚生年金には最低保障額が設定されていることも、
留意しておいてください。(300か月のみなし規定があります)
学生納付特例制度の承認を受けていた期間の保険料を、
追納しなかった場合は、老齢基礎年金の満額支給はされません。
あなたのご指摘の通り、老齢基礎年金の支給額を増やしたい場合には、
国民年金の任意加入被保険者となることによって、
増やすことができるものと考えております。
ただ、60歳以降に厚生年金の被保険者となった場合は、
国民年金部分の老齢基礎年金の受給額には反映されないと思われます。
ご注意いただきたいと思っております。
住宅ローンやお子さんたちの教育資金など、
しっかりとしたプランづくりを行い、手元資金の状況を把握されて、
もし余裕があれば、追納されておかれたほうがいいのではないかと考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
teto さん
2010/11/13 15:40
丁寧にご回答頂きありがとうございます!
遺族年金の要件が詳しくわかりました!
おそらく60歳以降も嘱託などで厚生年金に加入になる(希望)と思うのですが、
その場合は老齢基礎年金は増額にはならないということでしょうか・・・?
どちらにせよ、今後のライフプランに併せて追納できるかどうか考えたいと思います。
松本 仁孝
2010/11/13 19:54
評価くださいまして、ありがとうございます。
60歳以降の厚生年金の加入期間が、
合算対象期間として取り扱われるのではないかと考えました。
合算対象期間とは、老齢基礎年金の支給について、
受給資格期間には合算することができますが、
支給額の計算の基礎としない期間のことをいいます。
60歳以降の国民年金第2号被保険者は、
国民年金におけるこの合算対象期間に該当するために、
老齢基礎年金の支給額を増やすことはできないと考えました。
しかし、老齢厚生年金の支給額についての計算の基礎には、
カウントされることになりますので、
結果として、老齢厚生年金の支給総額は増えることになります。
今は追納すべきかどうかについて、
日々の生活費はもちろんですが、
住宅ローンや教育費等を考慮したうえで、
お決めいただきたいと思っております。
ありがとうございます。