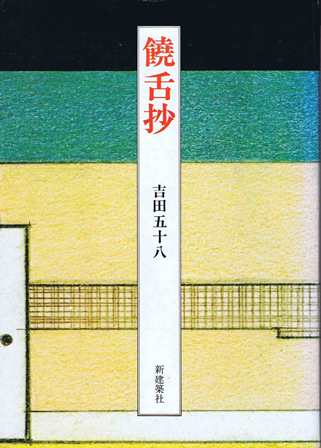- 堀 紳一朗
- 忘蹄庵一級建築士事務所 代表
- 東京都
- 一級建築士
対象:住宅設計・構造
吉田五十八(1894~1974)という昭和期に和風住宅の設計で活躍した建築家がいます。茶室の流れを汲むこれまでの数寄屋を、新素材や新工法で現代の生活に順応するような「近代数寄屋」として編み出すことで一世を風靡し、日本建築の近代化に貢献した人物です。
今でこそ伝統の部類に振り分けられ、様式として扱われる「近代数寄屋」も、当時としてはとても斬新なものでした。著書「饒舌抄」に収録された昭和9年のエッセイで吉田は理想の住宅建築について次のように述べています。
ある人がこういうことを、ある有名な建築家に尋ねた。
『住宅建築の極致とはどんなものですか。』
するとその人は、
『新築のお祝いに呼ばれて行って、特に目立って褒めるところもないし、と言ってまたけなすところもない。そしてすぐに帰りたいといった気にもならなかったので、つい良い気持ちになってズルズルと長く居たといったような建築が、これが住宅建築の極致である 。』
ど答えた。
(中略)
住宅は住む宅で、どこまでも見せる宅ではない。だから家人にとって住みいい家であり、また来る客が長く居られて家人と親しめる家であって欲しい、日本人には日本特有の雰囲気がかもし出された家が本当にいい住宅であると思う。
80年近く前に吉田の示した理想の住宅建築像が、今の私が目指す理想の住宅でもあるということは住宅の本質が普遍的だということを示しています。
「なんとなく居心地がよかったり雰囲気がよかったり」する建築はなんとなく建てれば出来るものではありません。「居住性がよい」「落ち着いた空間」を生み出す背景は建築の知識・技術・理論に裏打ちされたものですし、建築設計に必要なデザイン・法規・設備や構造・コストなども絡んできます。出来上がるまでに多くの葛藤を経ていながらそれを気取られず、「なんとなく心地よく」感じさせることが理想に思えるのです。