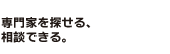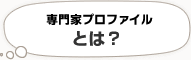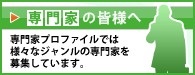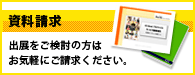- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
裁判所で勝敗が分かれたポイントはどこにあったのだろうか。
事例4は上場会社の従業員が執行役に就任するという事情によるものであるため、
役員分掌変更の場合という意味では、事例1〜3についてまず検討したい。
役員分掌変更の場合、役員退職給与の損金性を判断するための基準となるのが
法人税基本通達9−2−32であることは間違いない。その適用についても、
形式的判断ではなく、実質的に判断しなければならない。
退職金が支給される当該役員の分掌変更後の勤務実態が問題となるのである。
役員退職給与の損金性が否認された多くの事例においては、
本件通達の形式的適用がなされたために実質的に退職の事実がないのが
実情であろう。事例1においても、主要な取引先が代表者の交代を
知らなかったという事実だけみても、名目的に代表取締役を辞任していたこと
が推認できよう。この点、損金性が肯定された事例2は、Bの代表取締役退任
および会長への就任について、社内報に当該人事異動およびあいさつ文を
それぞれ掲載するとともに、取引先等にあいさつ状を送付している。
さらに、事例3においては、就業規則もしくは退職金規定に基づいて
他の従業員と同様の基準で支給された退職金であった。
また、勤務実態においても、損金性が否認された事例1は、
主要な取引先に対する実質的な対応をBが行っているが、
損金性が肯定された事例2では、(1)役職の新設や異動、給与査定など、
人事上の決定に関与していないこと、(2)取引先の選定や新規契約など、
営業上の決定に関与していないこと及び(3)設備等の取得や修繕など、
会計上の決定に関与していないことなどから、
Bの役員としての勤務実態は否定されている。
同様に、事例3は、本件学長としての職務は常勤を要するものでないだけではなく、
その多くを副学長である丁や学長補佐である戊にゆだねていたことから、
常勤から非常勤への変更として法人税基本通達9−2−32(1)にあたることになる。
さらに、分掌変更後の報酬については、事例1、2とも半減しているが
判断は分かれている。一方で、事例3は約30%(総額では約21%)の
減少にすぎないにもかかわらず、給与面にも職務の量、内容、性質の変動が
一応反映されていると判示されている。これは、本件通達に規定された
50%以上の減少という数値基準は例示であり、退職の事実を反映する金額
であれば、退職と同一に取り扱われることができるものと考えられる。
したがって、分掌変更した役員の分掌変更後の勤務実態が退職と同一に
取り扱われるべき退職の事実と実質的に判断できるかどうかが、
役員退職給与の損金性の判断基準となるのである。
役員としての職務権限を有しないこと、有するとしてもその実質を
補助者等にゆだねていることが必要であると考えられ、
形式的基準としては、就業規則の存在および他の従業員も同様の基準で
取り扱われることが必要であると考えられる。
ところが、事例4を考えてみると、就業規則等に記載されておらず、
職名も担当業務等も変わらず、給与も変わらない場合であっても、
従業員から役員への法的身分が変更されたことによって、
みなし退職金の支給が認められたのである。
このことは、何を意味するのか。
事例1〜3の検討から「勤務実態が退職と同一に扱われるべき退職の事実」を
判断基準とされた他、法的身分の変更も退職の事情と同一に扱われるのであれば、
役員が勤務を続けながらみなし退職金を受け取りたいのであれば、
法的身分の変更、つまり、役員から従業員への身分の変更も、
退職の事実とみなし得る可能性が高いと言えよう。
平成20年10月より新しい事業承継税制が遡及適用されることになっているが、
事業承継対策として株式の生前贈与とともに役員の分掌変更を行い、
みなし退職金を支給するケースは多くなることが予想される。
しかし、いわゆる平和事件最高裁判決(最高裁平成16年7月20日判決)が
判示したように、税理士は専門家としての責任において、解説書の記述を
判例等を考慮した上で検討しなければならないことを要求していると考えられ、
その上、自己の判断の根拠とリスクについて、依頼者に対する説明責任さえ
負っていることを、我々税理士は肝に銘じなければならないのである。
ロースクールでは税法が選択科目として導入され、
現在ではごく僅かである税法に強い弁護士が急増することが予想され、
アカウンティングスクールでも税法が必修科目とされていることから、
弁護士も会計士も、税法の専門家が誕生する素地が整っているこの時代、
通達のみに従うのではなく、自己のリスクを踏まえて、実質的な判断が出来なければ、
我々税理士の未来はなくなってくるかもしれない。
心して、自己研鑽をしなければならない時代になったのである。