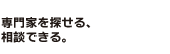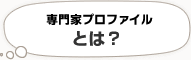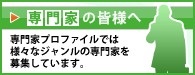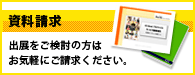- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
最高裁平成19年3月13日判決(事例1)をはじめほとんどの訴訟事件においては、退職の事実が認められず役員退職金の損金算入、退職所得性を否認されている。
しかし、平成18年11月28日裁決(事例2、確定)では、税理士と組んだ息子によるクーデターの結果、代表取締役社長を追われ取締役ではない会長に就任した前社長への役員退職金について、前社長に経営に従事している事実がないとして役員退職金の損金算入が容認されている。
また、源泉税の事件である大阪地裁平成20年2月29日判決(事例3、確定)は、学校法人の理事長が長年務めてきた高校の校長を退職し、大学の学長に就任したことに伴う退職金について、高校と大学では目的も直轄する所管官庁も異なる他、各々独立した就業規則等を有していること、高校の校長は常勤を要するが大学の学長は常勤を要さず、その勤務実態も大きく異なっている事実があること等を根拠に、その退職所得性が是認されている。
事例1のように退職金の損金算入が否認されることが多いのには、通達の文言を形式的に適用させようとするケースが多いためであるように思われる。つまり、法人税基本通達9-2-32は、
(1)常勤から非常勤への変更
(2)取締役から監査役への変更
(3)分掌変更後の給与が激減(おおむね50%以上減)
の3つのケースを例示していることから、形式的にこの通達を当てはめて、分掌変更による退職金の支出を行うケースが多いことが考えられる。
しかし、平成19年に9-2-23から改正された現行通達9-2-32は、「実質的に退職したと同様の事情にある」場合に分掌変更による退職金の損金算入特例を認めるのみであって、退職の事実がないケースでも損金算入を容認するものではないのである。
山本守之先生も次のように指摘されている通りである。(月刊税務事例39巻1号)
「法人税基本通達9-2-23の(1)、(2)、(3)は実質的な退職を判定するための通達上の要件を示しているものにすぎず、退職の事実はあくまでも実質により判定すべきである。また同通達の(1)から(3)は通達が示した例示にすぎず、役員としての地位の激変は実質的に判定すべきであり、通達に頼って税務の解釈をすることは危険である。」
また、事例3において分掌変更後の給与は総額では21%(職務分でも30%)しか減少していないが、退職所得として容認されていることも考えれば、役員退職金の損金算入・退職所得性の基準は「退職の事実」が認められるかどうかにかかっていることになる。その形式的な物証として就業規則等の存在と、それに基づいた先行事例の存在が重要になると考えるところである。
事例2について、注意が必要な主張がある。結果として納税者勝訴で終わっているが、課税庁は、顧問税理士(担当者)が作成した議事録に取締役ではない会長に就任していた前社長の名前が出席取締役として印字されていること、会社のHPからは会長が経営上の重要な地位を占めていることが窺えること等を証拠として、退職の事実がないことを主張していることである。特に、議事録については、もし本件が裁判においても従来通り否認されていたならば、税賠訴訟における税理士の勝目はあるまい。まさに専門家としての注意義務責任を自覚すべき問題である。
さらに、この問題は、平成20年10月から適用が予定されている事業承継税制の改正とも関連づけて考えることもできる。つまり、円滑な事業承継の企図するために、社長の経営の第一線を離れ、事業承継者に道を譲る場合には、実質的な退職の事実がなければならないことを忘れてはならない。事業承継税制を利用した相続対策スキームを企図する上で、安易な分掌変更の提案を行うことは、事後的にトラブル発生原因となりかねないことを我々は忘れてはならない。平和事件最高裁判決(最高裁平成16年7月20日判決)が我々税理士に突き付けた専門家責任を意識するべきであろう。