「遺産相続」を含むコラム・事例
47件が該当しました
47件中 1~47件目
- 1
60代のライフプラン作成のポイント[インタビューコラム]
60代を過ぎるとライフワークを見つけることも大切 ―――60代のライフプラン作成のポイントを教えてください。 「リタイアメント年齢の65歳から平均余命まで、男性は19.29年、女性なら24.18年の時間があります。幸せな毎日を送るため、ライフデザインを見つめ直し、ライフスタイルを考えることはもちろん、ライフワークを見つけたいものです。 また、60代に入ると世帯所得は現役世帯より少なくな...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(12)繰り上げ返済はお得?(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
繰り上げ返済とは、 毎月の返済とは別に、 住宅ローンの一部または 全額を前倒しで返済することです。 残債の一部を返済する 繰り上げ返済には、 「期間短縮型」と「返済額軽減型」の 2種類があります。 期間短縮型は、 返済期間を短くする効果があります。 定年退職後も ローンが続くなどで、少しでも 早く終わらせたい人には、 このタイプが向いています。 一方、返済額軽減型は、 返済...(続きを読む)

- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
争続にならないようにするには?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 来年1月1日から相続税の改正が行われるということもあり、新聞や雑誌では相続についての記事が多くなっていると感じます。 その相続の対策の中でもっとも一般的な方法は「遺言書」を作成しておくことではないでしょうか。 よく言われるのが「``相続``を``争続``にしないようにしっかり遺言を残しておきましょう。」という事。 相続争いが起きる、実に7...(続きを読む)

- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
新ファミリー一族:投資用不動産の保有は高いリスクに耐える運と経営力が必要
新ファミリー・一族の資産形成に関し、不動産投資をお考えの場合には、一代目と二代目のお話し合いで、下記のようなリスクをご検討ください。図は収入別に住居以外の住宅の保有割合です。新ファミリー一族は準富裕層加瀬多いので、きっとお考えになられた方も多いかと思います。私はある事情で親類のマンション3棟65室を管理・運営しておりました。そして、本人が亡くなった際に、内1棟(41室)を本人の借入金全額と共に引き...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産相続放棄と遺産分割協議
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定します。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。 ■遺産を相続しないことを何と言うのか ところで、相続による不動産登記(相続登記)の手続きを、司法書士にご依頼いただく際、「自分以外...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな相続手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな総則手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)

- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
タダなら何でも貰おうとする風潮
若い人の間で、フリーランチという言葉がよく使われるようです。ただ飯のことで、人から奢られることをいいます。わたしのように年配になりますと、ただ飯に対しては警戒心があります。特にビジネスが絡みますと、千円の食事をご馳走なったことで、心の負担を感じるようでようでは敵いません。 普段から、起業をするとき公的な補助金や助成金を貰うことに、批判的な話を書いてきました。起業準備をそっちのけで、補助金探し...(続きを読む)

- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その2)
高島司法書士事務所の最大の特徴としては、2002年の開業当初にインターネットのウェブサイト(ホームページ)を開設し、それから一貫してインターネット経由でのご依頼を中心に、事務所運営をおこなっていることです。 私が、司法書士事務所を開業するにあたり、仕事を得られるコネなどは何もありませんでした。身内には司法書士に関係するような仕事をしている人はいません。地元である千葉県松戸市の中学、高校を卒業しま...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
相続放棄、限定承認の件数
相続が開始した際に、相続人が採ることのできる選択肢として、単純承認、限定承認、相続放棄があるのは、前回のコラムで解説したとおりです(相続の3つの種類)。 被相続人の財産をすべて相続する「単純承認」が最も多いのは明らかですが、どれだけの人が、相続放棄や、限定承認を選択しているのかを、裁判所による司法統計で知ることができます。 相続放棄、限定承認の新受件数(裁判所ホームページ司法統計より) ...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記に必要な戸籍の範囲
相続登記をするときには、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。遺産分割協議による場合、法定相続による場合の相続登記では、相続人の全員が誰であるかを戸籍謄本などにより明らかにしなければならないからです。 被相続人の子供が相続人となるときには、それほど難しい調査は必要ないかもしれませんが、直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる場合には、非常にたくさんの戸籍...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(2)
2.遺産分割による相続登記 次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。 (1) 被相続人が遺言書を作成していない。 (2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。 なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。 遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割につい...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
誰が不動産を相続するのか
誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。 1.遺言書がある場合 被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。 法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得る...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人および相続分の決まり方(1)
遺産相続手続きをおこなうための基礎知識として、「誰が相続人となるのか」、また、相続人が2名以上の場合の「各相続人の相続分」についてまずはご説明します。 1.誰が相続人となるのか 誰が相続人となるのかは、次のようなルールで決まります。 まず、被相続人(亡くなられた方)に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。 そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが、次の順位により配...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
非嫡出子の相続半分の見直し
◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子) と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定して います。 本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの 論争がありました。最高裁...(続きを読む)

- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産相続をめぐる確認の訴え
【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。 しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
出口の見える“無料”相談会 IN 大田区蒲田 相続・離婚・不動産
 【私も相談員として参加します!】
◎◎◎出口の見える“無料”相談会◎◎◎
次回開催は9/29(土)
受付スタートしました!
日常生活の中で 『困ったな・・・』 『どうしよう・・・』 『納得いかない!』 などお困りごとに出会ったときに
『誰に相談しよう』 『専門家に相談したいけど高額請求されそうで怖い』 と思うこともあると思います。
そんな方達のお力になりたいっ!との志をもった専門家がボラン...(続きを読む)
【私も相談員として参加します!】
◎◎◎出口の見える“無料”相談会◎◎◎
次回開催は9/29(土)
受付スタートしました!
日常生活の中で 『困ったな・・・』 『どうしよう・・・』 『納得いかない!』 などお困りごとに出会ったときに
『誰に相談しよう』 『専門家に相談したいけど高額請求されそうで怖い』 と思うこともあると思います。
そんな方達のお力になりたいっ!との志をもった専門家がボラン...(続きを読む)

- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
遺産相続・生前贈与に関する意識と貧困率の現状
前回は、生涯現役として社会参加している方達の割合を見てきました。またもこのシリーズ初回に、高齢者の貯蓄額の大きさも確認しました。 では、最終に残る資産をどのようにしたいのかのアンケートに答えたのが下図です。 子どもになるべく多くの遺産を残したいとお考えの方は22.2%です。この数字は少ないように感じますが、私は「まだまだ子供に残したいとお考えの方が多いのだな」と感じています。 お答えの中で、...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』書籍発行のお知らせ
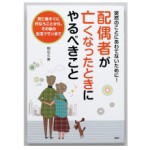 ファイナンシャルプランナーの明石久美です。
昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。
PHP研究所からの出版です。
監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。
詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。
----------------------------------------...(続きを読む)
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。
昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。
PHP研究所からの出版です。
監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。
詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。
----------------------------------------...(続きを読む)

- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税引き上げで検討(政府税調)
2011年度、相続税の引き上げが現実味を帯びて来ました。 今年4月から「小規模宅地評価減の改正」が施行され、 相続税が大幅に増税されたばかりですが、 来年からは、更なる増税をするという事で、政府税調が検討に入りました。 《参考》 過去ログ→「相続税の大増税時代に突入か!?」 税調の検討事項は次のとおり。 (1)相続税の基礎控除の縮小 (2)相続時精算課税制度の拡大 ...(続きを読む)

- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
非嫡出子相続差別は合憲も反対意見、補足意見が・・・
婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の遺産相続分を 婚姻届を提出している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1とする 規定を、最高裁第二小法廷は9月30日、これを合憲と判断した平成6年 最高裁判決を踏襲した決定をしたことが分かった。 しかし、3日12時33分asahi.com記事によると、裁判官出身の今井裁判官が 「婚姻関係から出生するかそうでないかは...(続きを読む)

- 平 仁
- (税理士)
「法律婚と事実婚」各制度での扱いの違いは?
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 人生の後半。一人でいるよりもパートナーと過ごしたい! そんな50歳以上の方の婚姻が増えているようです。 配偶者との離婚や死別の経験があるだけに、婚姻届を出さないかたちの「事実婚」カップルが少なくない。 ちなみに同棲と事実婚の違いは結婚の意志があるかどうかという点。 事実婚では夫婦の協力関係、日...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
変額年金保険の注意点
銀行窓口で10年スパンで運用を考えていますと窓口の方に相談すると、必ずといっていいほど、勧められるのが「変額年金保険」です。 FPの立場から言わせてもらうと、よほどのことがない限り買ってはいけない金融商品のひとつです。 この商品は一時金で預けたお金を「特別勘定(ファンド)」で運用して、その運用成績しだいで将来受取る年金額が変わるという商品。 死亡保障がついているので、投資信...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
47件中 1~47 件目
- 1
「相続」に関するまとめ
-
相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。






























