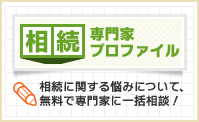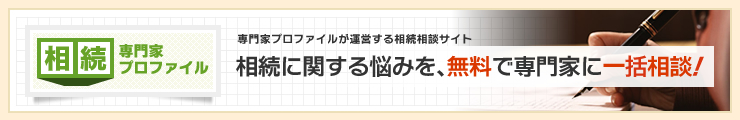対象:遺産相続
6月に土地を4500万で購入し、12月に二世帯住宅を4000万円で新築します。諸経費は700万です。
居住予定者は私、妻、子供(8歳、4歳)、妻の実母(「母」)、「母」の再婚相手(「父」)の6人です。妻は結婚前は「母」の前夫の戸籍に入っており、「父」は戸籍上は妻の他人ですが、妻が10代のころに5年程度同居もしており、事実上の養父と思われます。ここ10年は「父母」とは一緒に住んでいません。妻には「母」の前夫に育てられた兄弟が一人おり、「父」には殆ど連絡の無い兄弟が一人います。
住宅建設の費用は、私が単独の債務者の住宅ローン8000万、私の現金500万、「父」の現金700万で一旦で支払い、「父」が20年以上所有する住宅・家屋を来年1月以降に売却して、その売却代金3500万の一部1500万位を資金提供してもらう予定です。
登記ですが、今、私なりに考えているのは「父」へ一時的に1500万貸出した形として、新築時に1500+700万円分(家屋の半分程度)を「父」の名義に登記して、「父」の家が売れたら1500万を返してもらう形にしようかと考えています。名義を入れる理由のひとつは現段階での700万円に対する贈与税の課税を回避する為です。住宅ローンの融資元の銀行に問い合わせたところ、私と「父」は親族ではありませんが、土地や家屋は二人の共有名義には出来そうな感じです。
しかし、この場合は将来的な相続はどのようになるのでしょうか?「父」は「母」や妻に遺産の殆どを相続するつもりでいるようですが、兄弟の存在もありますし、妻は実の親子でないのでスムーズに相続できるのかわかりません。
または、共有名義にしないで生前贈与する、または700+1500万を借入金として扱うなど、ほかに良い方法はありますでしょうか?
Bruceさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:3件

酒井 尚土
弁護士
3
![]()
共有持分を有する「父」の相続があった場合について
「父」に子供がいない(父母も死亡している)とすれば、「父」の法定相続人は「母」(4分の3)と兄弟一人(4分の1)ですが、民法上兄弟には遺留分がありませんので、「父」が遺言で、全ての財産について「母」へ相続、「妻」へ遺贈しておけば、土地建物の共有持分など「父」の財産について兄弟から遺留分の減殺請求を受けることはありません。遺言通りに処理することができ、財産が兄弟の手に渡ることはないはずです。
なお、「父」と「妻」が養子縁組をしておけば、法定相続人は「母」(2分の1)と「妻」(2分の1)になり、「父」が死亡したときに「妻」(や「母」)が生存していれば、遺言がなくとも財産が兄弟の手に渡ることはないでしょう(念のため)。
以上は、共有名義にする場合についての回答になります。
補足
遺言書を作成される場合には必ず専門家にご相談下さい。

能瀬 敏文
弁護士
2
![]()
共有名義はお勧めできません
はじめまして!弁護士の能瀬です。
奥様の事実上の義父様(「父」)の推定相続人は弟一人ということですね。
その前提で(共有にするなら、「父」出生時点からの詳細な戸籍謄本で確認した方がよろしいですが)リスクを考えてみますと、
1 「父」と「母」が絶対に離婚しないとは言えない。
2 兄弟は遺留分が無いので、遺言書を作って奥様等に遺贈することにする方法も考えられますが、遺言 は何時でも撤回(無にする、作り変える)が可能。
また、戸籍謄本の件を上記しましたが、詳細に調べないと絶対に他に相続人がいないと断言できな い。
等がありえます。
従って、将来の相続のリスクを考えれば、「父」からの借入金にする方がよいと思われます。
ただ、その場合のデメリットは、
1 公正証書作成及び実際に分割等でも返済しないと、借入金について税務署から実質贈与として課税さ れる可能性が高い。
2 貸付残金が残った状態で「父」がお亡くなりになった場合、相続の対象となる。この点を遺言書や契 約書で対処(完全かはともかく)する必要がある。
等が考えられます。
弁護士としては主に以上の点が問題になりますが、併せて税理士さんにも相談されることをお勧めします。

樋渡 順
税理士
2
![]()
「父」ではなく「妻」と共有名義にするという考え方もあります
Bruce様
初めまして。
税理士・CFPの樋渡と申します。
マイホームを新築されるとのこと、おめでとうございます!
名義の問題は難しいですよね。
色々な観点があり、能瀬先生と酒井先生のご回答を拝見しなるほどなぁととても勉強になりました。
こちらでは税理士としての考え方をお伝えいたします。
共有名義というのは、実際のところ後々問題が生じるケースも多く、慎重に検討されることをお勧めしています。
Bruce様のご家族のケースですと、弁護士の先生方がおっしゃる通り「父」と「妻」が養子縁組されるか、「父」が遺言を作っておかないと「父」のご兄弟の方に家の名義が移転する可能性を残してしまいます。
したがって、「父」に資金の一部を出していただき名義を入れる場合は、必ずどちらかの対策を講じましょう。
また、他に検討できるとしたら、例えば「父」と「妻」が養子縁組をし、『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度』を使って700万円を贈与税ゼロで妻に贈与してもらうということも考えられます。結果的に「父」ではなく「妻」と共有名義になります。
要件に合致していれば、今年中の贈与は一般住宅であれば700万円まで非課税なのでちょうどぴったりの金額です。
☆住宅取得等資金の非課税制度→https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
追加の1,500万円の資金提供については、1.Bruce様の借入金として扱う、2.贈与税率を考えながら数年に分けてBruce様に生前贈与してもらう、3.「妻」がBruce様から1,500万円を借りた形にして700万円+1,500万円分の名義を「妻」にしておく→来年不動産が売れたら「父」から「妻」が相続時精算課税制度を使って1,500万円贈与してもらう→「妻」からBruce様が1500万円を返してもらう、といったように様々な方法が考えられます。
1は能瀬先生がおっしゃる通り、きちんと体裁を整え、返済を進めていかなければいけない&返済中に「父」の相続が発生すると「貸付金」として残ってしまうといった問題があります。
2の場合は、1,500万円をいただいて一気に繰り上げ返済を予定されているとすると、それが叶わないというデメリットがあります。(一気に贈与してもらうと半分税金で持っていかれるのでお勧めしません)
3の場合はちょっと小細工しすぎて手続きが面倒、また相続時精算課税制度は贈与するときは税金がかかりませんが、「父」の相続の時に相続財産として足し戻される&暦年贈与に戻れなくなるといったことがあるので、「父」が相続税がかかるぐらい財産をお持ちですと、実行することがいいのかしっかり検討しないといけません。
☆相続時精算課税制度→https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
いずれも一長一短でどの方法がBruce様にとってのベストアンサーは、家族の関係性や「父」の財産状況など色々考慮しないといけないことがありますので、こうしましょう!とはっきり申し上げることができません。
可能であれば税理士さんにしっかりお話を聴いていただくことをお勧めします。
お知り合いでいらっしゃらないようでしたら、よろしければご相談くださいませ。
弊所HP→http://www.hiwatashi-tax.com/
これからご新居へのお引越しの準備など、お忙しくなりますね。
新しい生活が益々楽しいものとなりますように。
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング