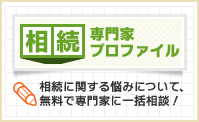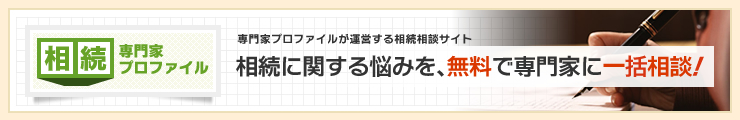対象:遺産相続
以前にも質問させていただきましたが、色々と分からないことが多く再度質問させていただきます。
相続についてですが、父が30年ほど前になくなり、母は7年前に亡くなりました。
(父が亡くなった時、母がおりましたので何もしておりません。)
相続人は長男・長女の子3人(長女は15年前に亡くなりました)・次女の5名です。
(↑合ってますでしょうか?)
母が生きていれば父の相続分のうち2分の1が母に分配され、残りが子供3人となると思うのですが、母の遺言により母の分配分は長男へと遺言状に残されています。
なので残りの2分の1は長男・長女の子3人・次女の5名で分配すればよいのでしょうか?
ややこしくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
VISTAさん ( 東京都 / 男性 / 65歳 )
回答:2件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
![]()
相続の分配について
VISTAさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『なので残りの二分の一は長男・長女の子3人・次女の5名で分配すれば良いのでしょうか。』につきまして、残りの二分の一の分配方法につきまして、各相続人が納得してもらえれば、どのように分配しても構いません。
ただし、財産の分配の割合でもめたときの目安として、法定相続を行った場合の割合を定めています。
また、既に長男さんは遺言により、お母さんの分をまるまる取得しているのですから、残りの分を改めて相続できる権利を主張した場合、他の相続人との間でもめたりすることも考えられます。
昔は長男が相続財産のほとんどを相続しましたが、今は相続人が法定相続に基づき、財産を相続することが一般的のようです。
よって、残された相続人の方々とよく話し合って決定するようにしていってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

松野 絵里子
弁護士
-
![]()
これからの手続きについて簡単に説明します
弁護士の松野絵里子です。
お父様がなくなった段階で、財産は法定相続分に応じて相続人のものとなっています。
民法は、相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになると定めているからです。
つまり、ここですでにお母様、お子さん三人のものになっていたわけです。
お母様がなくなったときには、遺言があったのでその財産がお子さん三人に相続されず長男のみになったのですが、実は、長男以外のお2人(長女についてはこ子たち)は遺留分という権利を持っていました。しかし、遺留分減殺権の行使というのをされていないのでもはやそれは行使できないでしょう。
そこで、おっしゃるようにお父様からの相続財産でお母様が相続していなかった半分は、長男3分の1、長女の子3人が各9分の1、次女が3分の1です。
遺産分割協議というものをして、すべての財産についてそういう割合で共有(みんながもっている状態)になっているものを、分ける方法を決めることになります。このとき、法定相続と異なる決め方でもいいのです。
この協議をしないでおくと、名義はなくなられた方のままで、たとえば土地についてみんなで共有していることになり、だれかが処分したくでも勝手にはできなくて不便です。その後の相続人が増えてまとまって運営できないと、実際には財産があるのに売れないしつかえないものになってしまいます。なお、預貯金はそのまま決まった法定の割合で分けられるので、各自で受け取ることも可能です(しかし、弁護士を介して判決をもらわないと払ってくれない銀行が多いです)。
遺産分割協議がまとまらないと調停を申し立てます。場所は家庭裁判所です。まず、家事調停という手続きになり相続人みんなで、調停委員が間に入って、話し合いで解決を図ります。
話がまとまらないときには、審判手続きが開始されます。これは一種の裁判のようなものです。通常の裁判と異なるのは、裁判官が職権で様々な調査ができて(通常裁判では弁護士のみが立証活動をします。)、いろいろな要素を検討してなるべく公平に最終的な決定を下すとう点です。これに不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服申立てをすることができます。この申立てがなければ、審判は裁判の確定判決と同様の効力を生じて、強制力があります。
補足
当事務所では、相続などの個人のご相談にものっております。
法律相談は随時受け付けています。http://ben5.jp/a/domain/kojin/
(現在のポイント:-pt)
![]()
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング