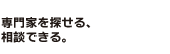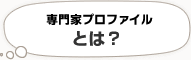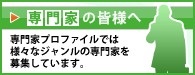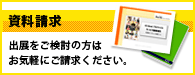- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
東京高裁平成20年12月4日判決(TAINSコードZ888-1387)を紹介する。
本件は、既に紹介済みの千葉地裁平成20年5月16日判決の控訴審判決で、
昨年8月1日から4日、10月22日の各コラムも参照して下さい。
本件は、不動産の譲渡損失の損益通算を不可とした平成16年度
税制改正法案の訴求適用を争うもので、法案は3月31日に成立したが、
その適用は1月1日に遡って適用するとした点を争うものである。
判決は以下の点の補充があったものの、いわゆる引用判決で、
地裁の事実認定が全面的に肯定され、納税者の主張が排斥されている。
第2 事案の概要
本件は、控訴人が、平成16年1月30日にした長期譲渡所得の課税対象
となる土地の譲渡について、その譲渡によって生じた損失2500万円余を
控訴人の平成16年分の給与所得等の他の所得と損益通算すると
平成16年分の所得税について還付されるべき税金136万9400円が
存在するとして、その旨の更正請求書を提出したが、処分行政庁が、
控訴人の上記更正請求には更正すべき理由がない旨の通知処分をしたため、
控訴人が、平成16年法律14号附則27条1項の規定は憲法84条が
原則として禁止する遡及立法にあたり、上記の更正請求に理由がない旨の
通知処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案である。
第3 裁判所の判断
1 当裁判所も、本件改正附則は憲法84条に違反せず、本件通知処分は
適法であり、控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。
2 当裁判所の補充の判断
(1)憲法84条の定める租税法律主義の内容の一つとしての課税要件
法定主義は、課税要件と租税の賦課・徴収の手続は法律によって規定され
なければならないとする原則であるが、遡及立法は、納税義務が成立した
時点では存在しなかった法規を遡って適用し、過去の事実や取引を
課税要件とする新たな租税を創設し、あるいは、既に成立した納税義務の
内容を納税者に不利益に変更する立法であり、法律の根拠なくして租税を
賦課することと同視し得ることから、租税法律主義に反するものとされる。
(2)所得税は、いわゆる期間税であり、歴年の終了の時に納税義務が
成立するものと規定されている。したがって、歴年の途中においては、
納税義務は未だ成立していないのであり、そうとすれば、その歴年の
途中において納税者に不利益な内容の租税法規の改正がなされ、その
改正規定が歴年の開始時に遡って適用されることとされたとしても、
このような改正は、厳密な意味では、遡及立法ではない。
(3)しかし、厳密な意味では遡及立法とはいえないとしても、本件の
ように歴年当初への遡及適用によって納税者に不利益を与える場合には、
憲法84条の趣旨からして、その歴年当初への遡及適用について合理的な
理由のあることが必要であると解するのが相当である。
ただ、歴年当初への遡及適用に合理的な理由があるか否かについては、
「租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、
所得の再配分、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、
国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般
からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を
定めるについて、極めて専門技術的判断を必要とすることも明らかである。
したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、
国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、
技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を
尊重せざるを得ないものというべきである。」(最大判S60.3.27)
と解される。
すなわち、本件においても、立法府の判断がその合理的裁量の範囲を
超えると認められる場合に初めて歴年当初への遡及適用が憲法84条の
趣旨に反するものということができるものというべきである。
(4)そこで、本件における歴年当初への遡及適用に合理的な理由があるか
否か、すなわち、歴年当初への遡及適用を行うものとしたことが立法府の
合理的裁量の範囲を超えると認められるか否かについても検討するに、
1 そもそも、分離課税の対象となる土地建物等の登記譲渡所得に対する
課税については、利益が生じた場合には税率20%の分離課税とされながら、
損失が生じた場合には総合課税の対象となる事業所得や給与所得などの
他の所得と損益通算して他の所得の額を減額することができること
については、かねてから不均衡であるとの批判が強く、長期譲渡所得
について損益通算の制度を廃止すべきことが指摘されていたこと
2 平成16年1月1項の土地建物等の長期譲渡所得について損益通算を
廃止することは、自民党の「平成16年度税制改正大綱」の中に
盛り込まれており、そして、この「平成16年度税制改正大綱」は
平成15年12月18日の日経新聞に掲載されて、納税者においても、
平成16年1月1日以降の土地建物等の譲渡について損益通算が
廃止されることを事前に予測することができたこと
3 改正措置法31条1項と同様に歴年の途中から施行されながら
その適用が1月1日に遡るものとされた改正規定は少なからず存し、
これによると、本件の歴年当初への遡及適用についても、納税者において、
歴年の途中から改正規定が施行されてもその適用が1月1日に遡るものと
されることは予め十分に認識し得たといえること
4 もし、本件改正附則を設けないものとして、改正措置法31条1項を
1月1日に遡って適用せず、3月31日までの長期譲渡と4月1日からの
長期譲渡とに区別し、前者については改正前措置法を、後者については
改正措置法を適用して別異に取り扱うものとすると、仮に前者の譲渡に
ついて損失が生じた場合、その損失をどのように損益通算するのか、
仮に、前者の譲渡について利益が生じた場合に、その利益をどのように
損益通算するのか、また、特別控除額100万円はその全額を3月31日
までの間の譲渡所得から控除していいのか、等の問題が生じるのであり、
さらに、3月31日までの譲渡と4月1日からの譲渡に区分すると、
納税者においても所得税確定申告の手続がそれだけ煩雑となり、
申告を受けた課税庁においても正しく区分されているかどうか等を
調べるために付加的な労力を要することになること
5 3月31日までの譲渡についてその損失を他の各種所得と通算できる
ものとすると、その間に譲渡損失を出すことのみを目的とした駆け込み的な
不当に廉価な土地建物等の売却を許すことになり、公正な取引を行う
他の納税者との間に不平等が生じ、不動産市場に対しても悪影響を及ぼしかねないこと
6 本件において、歴年当初への遡及適用の期間は1月1日から
3月31日までの3カ月間にとどまること
7 居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の一部については、
なお一定の要件の下に損益通算が認められていること
等の事情を総合考慮すると、本件における歴年当初への遡及適用には
合理的な理由があり、歴年当初への遡及適用を行うものとしたことに
立法府の合理的裁量の範囲を超えるところはないというべきである。
以上のような理由で、東京高裁は本件控訴を棄却した。
判決には反対意見をもっているところであるが、
実務家としては、
最高裁でも勝てなければ、我々税理士は改正大綱の段階から、
タイムリーな情報提供をすることを判例は要求していると
考えるべきであろう。
それだけに昨日の私見を言いたいのである。